1.開会
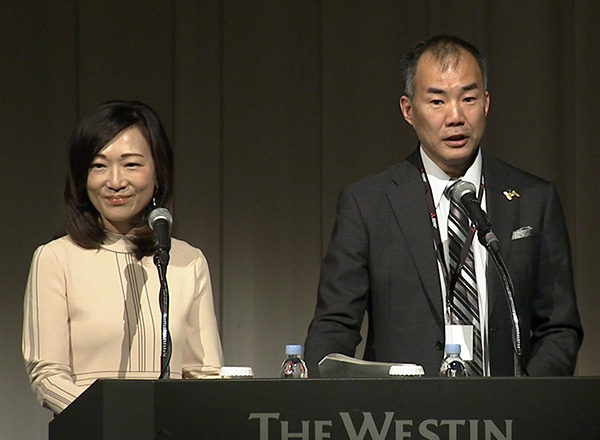
司会の野口聡一JAXA宇宙飛行士と大貫美鈴氏(スペースアクセス株式会社代表取締役)により開会が宣言された。
2.開会挨拶
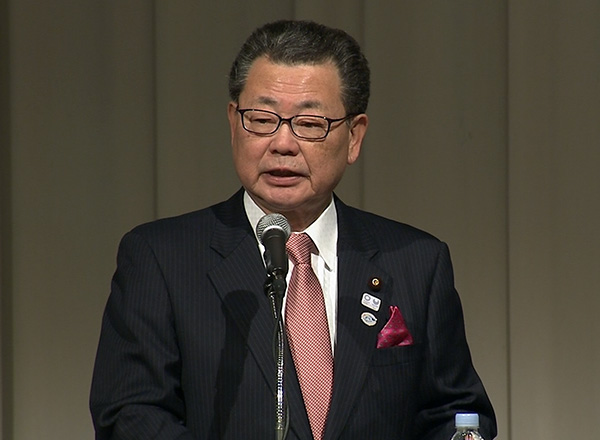
主催者である水落敏栄文部科学副大臣から挨拶が行われた。 宇宙分野での民間企業の役割はすでに重要だが、今後の宇宙産業の発展のためには、さらに柔軟な取り組み、非宇宙分野新規参入が必要であり、翌日の閣僚級会合と合わせ、このようなサイドイベントは重要との考えが示された。
3.挨拶

I-ISEF開催に寄せて、平木大作経済産業大臣政務官より挨拶が行われ、宇宙探査は政府だけの取り組みではなく国民に身近なものとなり、ビジネスの波及効果も期待されていると述べられた。また宇宙分野への進出を考える企業の方と宇宙分野に関心のある投資家マッチングさせる機会を提供するS-Matchingが紹介された。
4.ハイライトプレゼンテーション1

ボーイング社副社長James H. Chilton氏が登壇。国際宇宙ステーション(ISS)の成功は多国間協力にあると語った。また、成熟期にあるISSを、さらなる宇宙探査のためのテストベッドとして活用すること、宇宙経済開発のため政府と民間主導のプログラムの両方が必要であると述べた。
5.パネル1「2030年頃の社会経済とイノベーション」
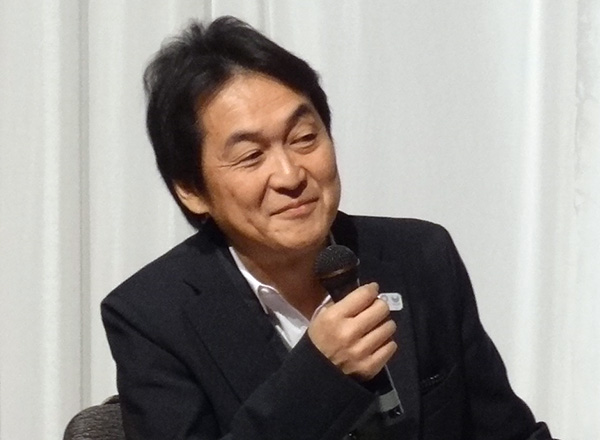
モデレータ
夏野剛
慶應義塾大学大学院政策・政策メディア研究科特別招聘教授

パネリスト(左より順に)
冨山和彦
株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO
Johann-Dietrich Woerner
欧州宇宙機関長官
茂木健一郎
ソニーコンピューターサイエンス研究所シニアリサーチャー
Peter Marquez
Andart Globalパートナー
落合陽一
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社代表取締役
Bruce B. Cahan, J.D.
Urban Logic, Inc.代表取締役、スタンフォード大学 Department of Management Science & Engineering 特任講師
(リモート参加)
産業としての宇宙探査の価値や可能性が議論された。パネリストから、宇宙は技術革新の場として有効であること、探査は目的を明確にもって取り組むべきこと、産業として発展するには協調と競争の両面が必要であるなどの意見が上げられた。
6.ハイライトプレゼンテーション2

シエラネバダ社副社長Mark N. Sirangelo氏が登壇。スペースシャトルなど過去の成果を尊重することの重要性を語った。また、同社が開発中の往還機Dream Chaserが国連に採用され、数多くの新興国が宇宙ミッションに関心を示したことが紹介された。
7.パネル2 「月面・小惑星における産業と経済効果」

モデレータ(写真左端)
Chad Anderson
CEO, Space Angels

パネリスト(左より順に)
袴田武史
ispace, 代表取締役&ファウンダー
Tom Ochinero
Senior Director, Commercial Sales, SpaceX
小笠原宏
三菱重工業株式会社防衛・宇宙ドメイン 宇宙事業部 副事業部長 兼 営業部長
Rob Chambers
Director, Human Spaceflight Strategy and Business Development, Space Systems Company, Lockheed Martin
Cesare Lobascio
Space Infrastructure Systems Innovation Lead and Expert Life Support & Habitability, Thales Alenia Space Italia
Agata Jozwicka-Perlant
Head of Prospects & International Development, Future Programmes, ArianeGroup
Mike Lewis
Chief Technology Officer, NanoRacks LLC
プレイヤーと支援者から宇宙ビジネス現場が議論された。パネリストからは、深宇宙への輸送機開発における政府の役割の重要性や、民間企業が輸送機以外のインフラ開発に取り組み需要を作りだすべきこと、法的枠組みや標準化の重要性に関する意見が述べられた。
8a.スポンサーランチセッションA
8a-1.ボーイング社講演
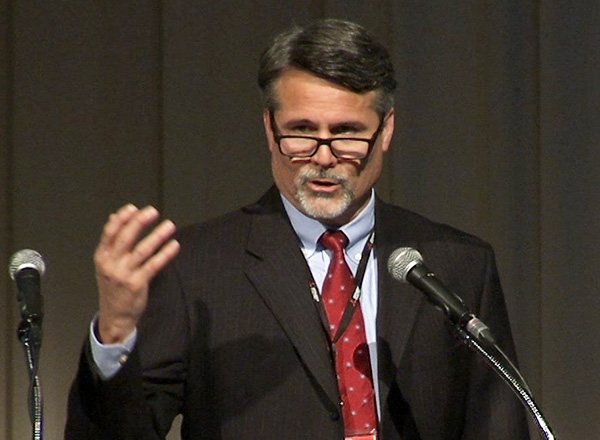
ボーイング社ISSプログラムマネージャーMark Mulqueen氏が登壇。ISSが国際協力の象徴であり、次世代をインスパイヤする存在であることを紹介した。また、ISSは今後の宇宙探査に必要な技術を実証する場として、必要とされる貢献が可能であることを強く語った。
8a-2.タレスアレニア社講演

タレスアレニアスペースCesare Lobascio氏が登壇し、ISSを技術実証の場として活用する上でも、従来の宇宙企業にだけでなく、中小を含めた非宇宙企業とも協力することで効率的な開発を目指していると語った。また、日本企業とのパートナシップにも大きな関心をもっていると語った。
8b.スポンサーランチセッションB
地球低軌道/国際宇宙ステーション(ISS)における商業利用の展望
~宇宙探査時代を見据えて~

モデレータ(写真中央)
佐藤巨光
有人宇宙システム株式会社(JAMSS)、宇宙事業革新グループ グループリーダ
登壇者(写真左より)
Carlo Mirra
Director, Space Products Sales, AIRBUS DS, Bremen – Germany
Christian Maender
Director, In-Space Manufacturing and Research, Axiom Space, LLC
登壇企業3社(Airbus社/Axiom Space社/JAMSS)で、有人LEOビジネス成功のためには、需要促進、使い易いプラットフォーム、コスト削減、国による民間サービス購入が重要であること、官民パートナーシップ・モデルを探査へ適用可能なこと等で有人LEO商業化が国際宇宙探査への貢献となり得ることと共に、以下のことを確認した。
今、有人宇宙活動のターニングポイントであり、深宇宙探査に進む上で持続可能な低軌道経済が不可欠であること。
政府による支援が行われ、民間資金も宇宙市場へ入るようになったことで、低軌道は今、ビジネスを行う最高の機会であること。我々のISSでの経験を基に、低軌道市場を開拓するというチャレンジングな道を切り開くことが可能であること。
8.Y-ISEFレポート「次世代からのメッセージ」
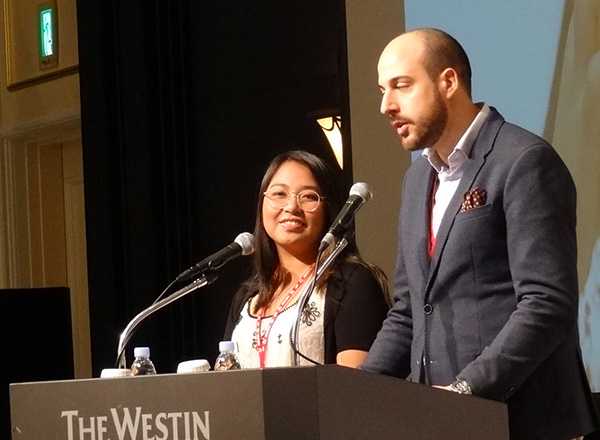
チーム代表者
Francesco Spina
SES, Luxembourg
Catherine RKP Mandigma
University of the Philippines
Y-ISEFに参加した10チームを代表し、優勝チームからMYCOMEATと呼ばれる「菌類」から「肉(タンパク質)」を軌道上で生成するアイデアについて発表がなされた。このアイデアが実現すると、宇宙での長期滞在時における食糧問題を解決するだけではなく、地上での食料問題、ゴミ・下水処理、バッテリ製造、プラスティック製造、推進薬生成などに利用できることを紹介した。
9.パネル3 「様々な産業領域から見た宇宙探査の可能性」

モデレータ
梅澤高明
A.T.カーニー日本法人会長

パネリスト(左より順に)
深堀昂
ANAホールディングス株式会社デジタルデザインラボ/アバター・プログラム・ディレクター
細井純一
資生堂グローバルイノベーションセンター マネージャー
John C. Mankins
Vice President, Moon Village Association
小野島一
株式会社大林組技術本部統括部長 兼 スマートシティ推進室長
Andrew Rush
President & CEO, Made In Space
作尾徹也
ミサワホーム株式会社取締役常務執行役員
菅原潤一
Spiber 株式会社取締役兼執行役
渡辺公貴
株式会社タカラトミー研究開発部 専門部長
非宇宙産業から見た宇宙探査ビジネスの価値と課題、宇宙探査企業との連携可能性について議論された。政府の長期投資に頼らず民主導での宇宙探査を議論すること、革新的技術を地上で示すことで公衆の認知度を上げること、標準化と大量生産により業界参入を加速すること、研究開発やビジネスに関し地上と月・火星環境の違いを明確に示すことなどが提言された。
10.パネル4 「宇宙探査ビジネス拡大に向けた政策」

モデレータ
角南篤
政策研究大学大学院教授

パネリスト(左より順に)
Mohammed Nasser Al Ahbabi
アラブ首長国連邦宇宙機関長官
Robert M. Lightfoot Jr.
アメリカ航空宇宙局(NASA)長官代行
Roberto Battiston
イタリア宇宙機関(ASI)総裁
Pascale Ehrenfreund
ドイツ宇宙機関Chair of the Executive Board
Mario Grotz
Director, General for Research, Intellectual Property and New Technologies, Ministry of the Economy, Luxembourg
P.G. Diwakar
Scientific Secretary, Indian Space Research Organization (ISRO)
山川宏
内閣府宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会長
Silvio Sandrone
Vice President, Advanced Projects and Products, Airbus Defence and Space
各パネリストより、各国の宇宙探査事業の推進・宇宙経済圏の構築に向けた政策や取組みが紹介された。また、官民の役割、産業振興上の課題と解決策について議論が行われ、以下を含む意見が出された。
・スタートアップ企業の教育や新規参入へのインセンティブ作りを行うべき。
・宇宙探査の“エコシステム”を構築する必要がある。
・官の資金だけでなく、ベンチャーキャピタルを含めた民間資金の導入、さまざまな産業の巻き込みが必要である。
・ISSでの成功に基づき、官民のパートナシップや国際協力を活用するべきであるし、先駆けとしてNASAはLEO経済開発のため民間の取組みを支援する。有人LEOランチセッションにて紹介されていたAxiom/Airbus/JAMSSが良い例である。
また、参加者からの「一般の人達に対して月面・火星の生活や経済圏の創出に意味があるか?」という質問に対し、「価値をどのように産み出すかが大切」、「次の世代へのインスピレーションを如何に創出するか」等の議論が行われた。
11.挨拶
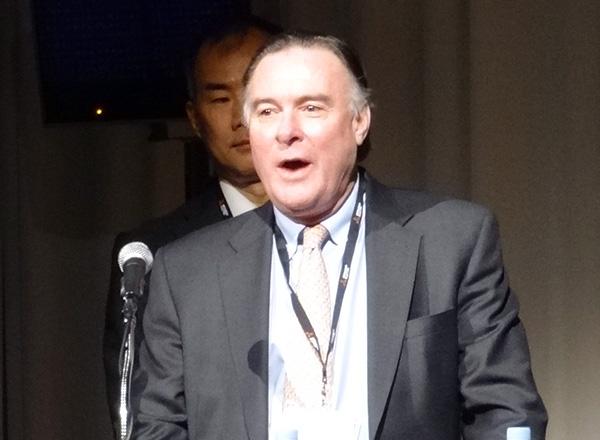
第1回ISEFをホストした米国の国務省Kenneth Hodgkins氏より第2回のホスト国である日本に賛辞が送られた。
12.挨拶

後援者であるAmerican Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)より、Daniel L. Dumbacher氏から挨拶が行われ、参加者に謝辞が述べられた。
13.閉会挨拶

主催者である、あかま二郎内閣府副大臣より閉会挨拶が行われた。本日、有意義な議論が実施されたことに感謝を述べるとともに、翌日の閣僚レベル会合での議論への期待を語った。