宇宙環境利用に関する地上研究の公募について
宇宙航空研究開発機構
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
1. 第6回までの成果及び評価
(1)目的宇宙環境利用に関する地上研究公募制度は、JEM利用初期段階の利用立ち上げを目的とした国内研究支援をはじめ、宇宙環境利用の裾野拡大、新たなる研究領域の開拓及び研究コミュニティの育成を目的とし、平成9年度に発足、これまでに毎年度1回ずつ計6回の公募を実施した(別紙1に分野別の選定件数を示す。)。
(2)これまでの実績及び主な成果-
・ これまで採択された全テーマのうち新規提案は約86%にのぼり、宇宙環境利用の裾野の拡大及び研究領域の拡大につとめてきた。また、採択された研究者を中心とした研究コミュニティ会合を開催し、そのコミュニティの活性化をはかってきた。
-
・ 研究成果の発表等も多く行われ、実績は採択数523件においてのべ講演1706回、論文等の投稿1108回、特許申請34件にのぼる。
-
・ 本制度で得られた成果を発展させた研究テーマのうち、ライフサイエンス国際公募へは49件(うち6件採択)、微小重力科学分野国際公募へは13件(うち3件採択)のテーマの応募があった。(別紙2に、これまでの成果を示す。)
地上研究公募制度の運営方針、研究テーマの選定、評価等を行う公募地上研究推進委員会において、平成15年9月から平成16年1月にかけて、これまでの地上研究公募についての評価を行った結果、本制度は「裾野拡大」、「研究領域の拡大」、「研究コミュニティの育成」に貢献しており、制度発足時の目標を達成するレベルに到達しているとの評価がなされた。
2.宇宙開発委員会利用部会での指摘
宇宙開発委員会利用部会が平成15年6月にとりまとめた「我が国の国際宇宙ステーション運用・利用の今後の進め方について(中間報告)」において、ISS計画の遅延等に伴う利用機会の不足等により、宇宙環境利用の成果創出が困難となっている状況で、戦略的に成果の創出を図る必要があるとされた。既存の利用推進制度については、次の3つの機能に留意しつつ見直しを図ることとしている。
- JEM初期利用課題を着実に実施する支援
- JEM利用開始までの間、成果の早期創出が期待される課題に対する利用機会の提供
- JEM定常運用段階での利用を目指した有望課題や国際公募候補課題の広範な発掘
3.第7回の地上研究公募について
(1)中間報告提言への対応地上研究の公募において、宇宙開発委員会の指摘を踏まえ、成果の早期創出、定常段階での有望な成果創出、初期段階の利用の補強のための募集区分の見直しを行った。また、財源の多様化への対応も考慮した。(表1参照)
(2)募集区分の変更について利用部会提言を踏まえ、以下の募集区分を設定する。
- 「きぼう」利用重点課題研究:
JEM利用初期段階の利用の補強のための実験テーマ候補となる研究提案発掘を目的とし、日本が提供する既存実験装置の利用を前提とする地上研究を募集。本研究ではフライトテーマ募集への応募を目。 - 次期宇宙利用研究:
JEM利用初期・中期段階の実験テーマ候補となる研究提案発掘を目的とし、日本が提供する既存実験装置のほか、海外の実験装置、次世代の実験装置(実験インフラ)の利用テーマの創出につながる地上研究を募集。 - 宇宙利用先駆(さきがけ)研究:
JEM利用中期以降の実験テーマ候補となる、JEM利用概念の拡大につながるアイデアレベルの提案を対象とする研究を募集。 - 落下施設・航空機利用研究:
地上の短時間微小重力実験機会である落下施設・航空機を利用して、十分な成果の早期創出が期待され、微小重力の有効性の提示が可能な研究を募集。
第7回の地上研究募集の概要を表2に示す。
(3)募集分野上記(2)の研究区分設定に伴い、各研究区分毎の募集分野が設定される。なお、きぼう船外プラットフォーム利用の進め方については別途検討を行うこととし、第7回の地上研究公募においてきぼう船外プラットフォーム(曝露部)の利用が想定される研究分野の募集は見送る。
(4)スケジュール| 応募開始日 | :平成16年2月 4日(水) |
| 応募〆切 | : 同 4月13日(火)必着 |
| 評価パネルの編成、査読者確定 | : 同 4月下旬まで |
| 査読による評価 | : 同 5月〜6月 |
| 分野毎の評価パネルによる審査(書類審査、面接審査) | : 同 6月〜7月 |
| 公募地上研究推進委員会による総合審査 | : 同 7月下旬 |
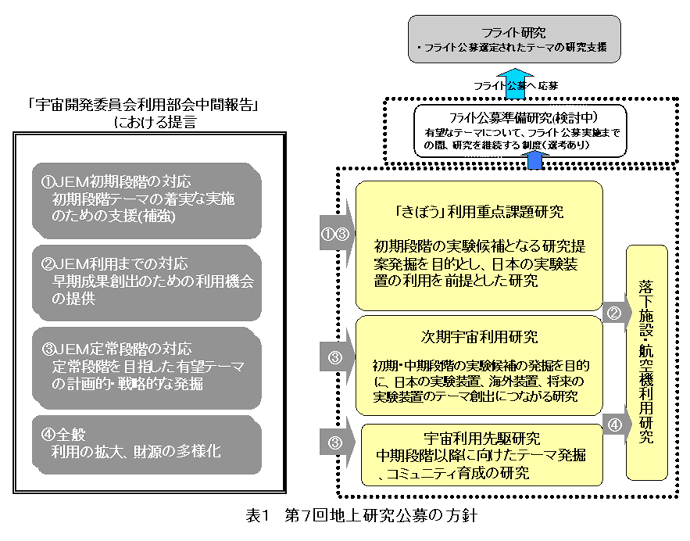
表2 第7回地上研究公募の概要
| 研究区分 |
「きぼう」等利用研究
|
落下施設・航空機利用研究 |
||
|
第1優先カテゴリ
「きぼう」利用重点課題研究 |
第2優先カテゴリ
次期宇宙利用研究 |
第3カテゴリ
宇宙利用先駆研究 |
||
| 研究目標 | ISS/JEM利用重点化の戦略を基本に、既存装置を活用して、初期段階のフライト実験テーマに発展させることが可能な地上研究。 | ISS/JEM利用重点化の戦略を基本に、初期・中期段階における有望なフライト実験テーマの創出や、宇宙環境利用を支える技術開発テーマへの発展が期待できる研究 | 独創性・新規性のある研究で、中後期段階以降において、新たな実験装置・機器の開発構想の創出や、将来の利用テーマへの発展が期待できる研究。若手研究者の育成や研究コミュニティの活性につながる研究 | 宇宙環境利用への発展が期待できる独創的で新規性のあるアイデア・発想を、短時間微小重力実験により具体化することを目標にする研究 |
| 研究内容 | ● 軌道上実験要求案の設定 ● 適合性試験、運用要求案の設定 ● 供試体開発要素試作 |
● 初期・中期段階の利用に向けて、科学的実験要求を地上実験や解析などで明確にする。 ● 例えば、検討中の次世代実験装置候補の利用を想定した研究。ただし、新規装置の提案を妨げない。 |
中後期段階に向けて、アイデア・発想を具体化する | JSF/JAXAが提供する落下施設・航空機による短時間微小重力施設利用機会を利用する研究 |
| 想定する実験装置等※ | 「きぼう」既存実験装置(船内実験室)の利用 細胞培養装置 クリーンベンチ 流体物理装置 結晶成長装置 温度勾配炉 |
以下の装置を中心とするが、新たな概念の装置やインフラによる研究も妨げない。 「きぼう」既存実験装置 「きぼう」次世代実験装置(構想中):水棲生物実験装置、浮遊炉、多目的ラックなど 海外機関開発装置 |
制限無し |
(装置は提案者が準備) |
| 募集対象分野 | ● 宇宙環境を利用した物理学・化学系研究 ● 宇宙環境を利用した生命科学系(ヒト及び脊椎動物(固体)を対象とする研究は除く)研究 |
● 宇宙環境を利用した物理学・化学系研究 ● 宇宙環境を利用した生命科学系研究 |
微小重力環境を利用した以下の研究分野、物理学・化学系、生命科学系、先端宇宙技術 | |
| 研究費 | 最大3000万円/年度 | 最大1500万円/年度 | 最大300万円/年度 | 実験機会及び旅費程度 |
| 期間 | 最大3年度 | 最大3年度 | 2年度 | 1〜2年度 |
別紙1 地上研究公募における応募、採択状況
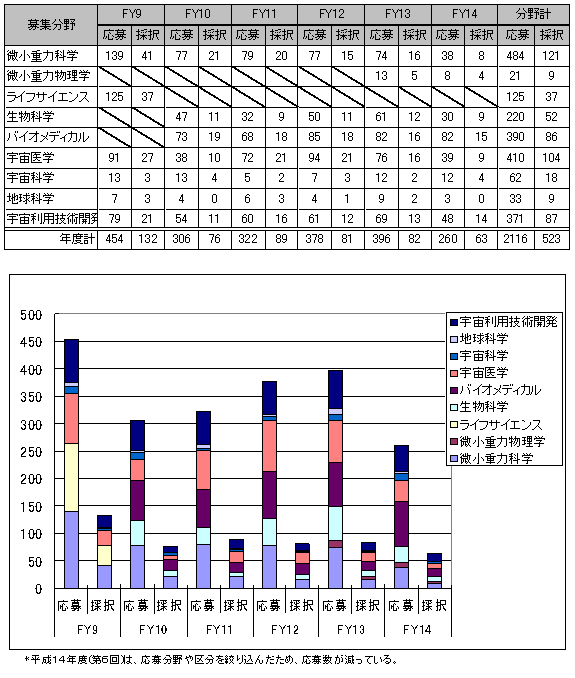
別紙2 地上研究公募のこれまでの成果
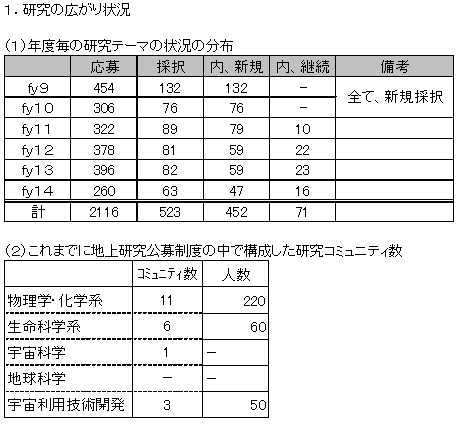
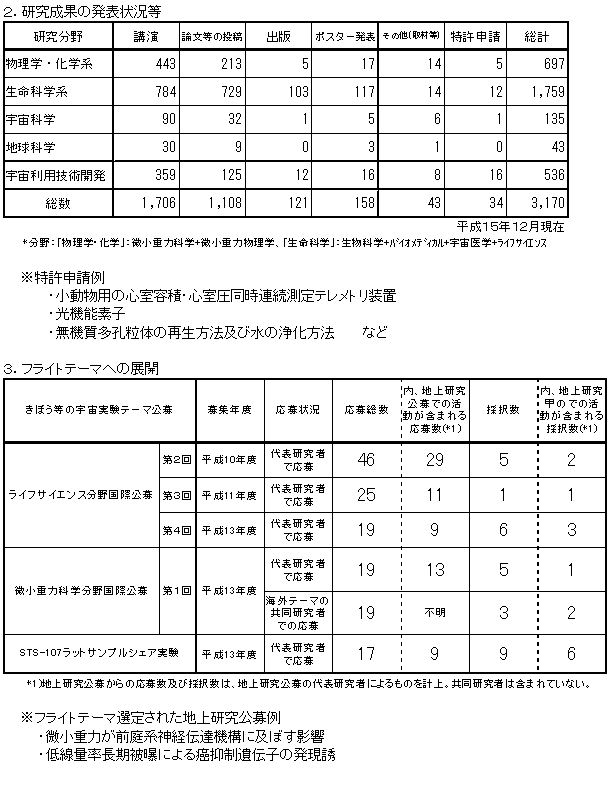
|
|
宇宙航空研究開発機構 広報部
TEL:03-6266-6413〜6417
FAX:03-6266-6910