第7回「宇宙環境利用に関する地上研究公募」のテーマ選定について
平成16年8月4日
宇宙航空研究開発機構
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
1. 第7回「宇宙環境利用に関する地上研究公募」の目的
「宇宙環境利用に関する地上研究公募(以下、「地上研究公募」)」制度は、JEMの初期段階の利用立ち上げを目的とした国内研究支援をはじめ、宇宙環境利用の裾野拡大、新たなる研究領域の開拓及び研究コミュニティの育成を目的とし、平成9年度に発足、これまでに計6回の公募を実施している。
宇宙開発委員会利用部会が平成15年6月にとりまとめた「我が国の国際宇宙ステーション運用・利用の今後の進め方について(中間報告)」(以下、「利用部会中間報告」)を踏まえ、募集方針の見直しを行い、第7回の公募を行った。
2. 第7回地上研究公募の募集概要と応募結果
(1)第7回地上研究公募は、下記の日程でテーマ募集を実施した。
・テーマ募集期間 :平成16年2月4日〜平成16年4月13日
・応募テーマ数 :184件
(2)利用部会中間報告において、利用促進制度の見直しとして、下記の提言がなされた。
- JEM利用開始までの間、成果の早期創出が期待される課題に対する利用機会の提供
- JEM初期利用課題を着実に実施する支援
- JEM定常運用段階での利用を目指した有望課題や国際公募候補課題の広範な発掘
- (a)「きぼう」利用重点課題研究:((2)の1、3に対応)
- JEM利用初期段階の利用の補強のための実験テーマ候補となる研究提案発掘を目的とし、日本が提供する既存実験装置の利用を前提とする地上研究を募集。
- (b)次期宇宙利用研究:((2)の3に対応)
- JEM利用初期・中期段階の実験テーマ候補となる研究提案発掘を目的とし、日本が提供する既存実験装置のほか、海外の実験装置、次世代の実験装置(実験インフラ)の利用テーマの創出につながる地上研究を募集。
- (c)宇宙利用先駆(さきがけ)研究:((2)の3に対応)
- JEM利用中期以降の実験テーマ候補となる、JEM利用概念の拡大につながるアイデアレベルの提案を対象とする研究を募集。
- (d)落下施設・航空機利用研究:((2)の1に対応)
- 地上の短時間微小重力実験機会である落下施設・航空機を利用して、十分な成果の早期創出が期待され、微小重力の有効性の提示が可能な研究を募集。
3.選定結果
(1)選考評価プロセス
- 分野毎の専門家による査読(1テーマ毎、複数名による査読)
- 事務局による搭載性に関する技術評価
- 分野毎の専門パネルにおける書類審査、面接審査
- 公募地上研究推進委員会における総合審査
(2)選定結果
研究区分の目的・条件を踏まえて、ISS利用に繋がる有望なテーマを以下のとおり選定した。個々の選定テーマについては別紙2に示す。
第7回地上研究公募 選定テーマ数
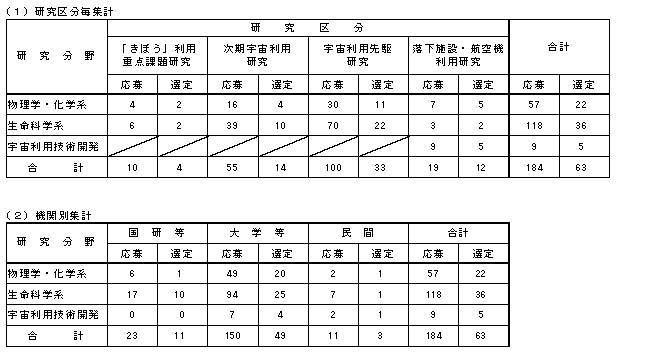
4.第7回選定テーマのマイルストン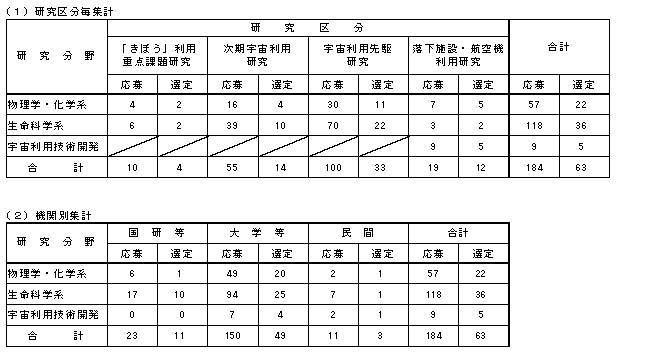
第7回地上研究公募は、テーマ選定後、以下のマイルストンで地上研究を実施する予定である。

|
|
公募地上研究推進委員会の構成
| 委員会・パネル | 氏 名 | 所 属 機 関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 推 進 委 員 会 委 員 |
委員長 |
壽榮松 宏仁 |
(財)高輝度光科学研究センター利用研究促進部門1部門長 |
|
| 副委員長 |
星 元紀 |
慶應義塾大学理工学部教授 |
||
| 推進委員 |
浅島 誠 |
東京大学大学院総合文化研究科研究科長 |
||
| 推進委員 |
尾形 悦郎 |
(財)癌研究会附属病院名誉院長 |
||
| 推進委員 |
木村 茂行 |
(社)未踏科学技術協会理事長 |
||
| 推進委員 |
小間 篤 |
高エネルギー加速器研究機構理事 |
||
| 推進委員 |
佐藤 文隆 |
甲南大学理工学部教授 |
||
| 物 理 学 ・ 化 学 専 門 パ ネ ル |
専門委員 |
神山 新一 |
秋田県立大学大学院システム科学技術研究科研究科長 |
|
| 専門委員 |
和達 三樹 |
東京大学大学院理学系研究科教授 |
||
| パネル委員 |
佐藤 武郎 |
東北大学 名誉教授 |
||
| パネル委員 |
栗林 一彦 |
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部宇宙環境利用科学研究系研究主幹・教授 |
||
| パネル委員 |
新岡 嵩 |
秋田県立大学地域共同研究センター教授 |
||
| パネル委員 |
太田 隆夫 |
京都大学基礎物理学研究所教授 |
||
| 生 命 科 学 系 専 門 パ ネ ル |
生 物 科 学 分 科 会 |
専門委員 |
大森 正之 |
埼玉大学理学部教授 |
| パネル委員 |
射場 厚 |
九州大学大学院理学研究院生物学部門教授 |
||
| パネル委員 |
漆原 秀子 |
筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 |
||
| パネル委員 |
諸橋 憲一郎 |
自然科学研究機構基礎生物学研究所教授 |
||
| バイオ メディ カル 分科 会 |
専門委員 |
矢原 一郎 |
(株)医学生物学研究所伊那研究所所長・常務取締役 |
|
| パネル委員 |
増田 康治 |
北九州病院理事長 |
||
| パネル委員 |
須田 立雄 |
埼玉医科大学ゲノム医学研究センター副所長 |
||
| 宇宙 医学 分科 会 |
専門委員 |
埜中 征哉 |
国立精神・神経センター武蔵病院名誉院長 |
|
| パネル委員 |
須田 立雄 |
埼玉医科大学ゲノム医学研究センター副所長 |
||
| パネル委員 |
盛 英三 |
国立循環器病センター研究所 心臓生理部部長 |
||
| パネル委員 |
宇佐美真一 |
信州大学医学部教授 |
||
| 宇 宙 利 用 技 術 開 発 |
専門委員 |
中丸邦男 |
(元 NEC東芝スペースシステム) |
|
| 専門委員 |
林 友直 |
千葉工業大学付属研究所教授 |
||
| パネル委員 |
佐藤 英一 |
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部宇宙構造・材料工学研究系助教授 |
||
| パネル委員 |
岩田 勉 |
宇宙航空研究開発機構参事・筑波宇宙センター所長 |
||
| パネル委員 |
松本 甲太郎 |
宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部宇宙先進技術研究グループ主任研究員 |
||
| パネル委員 |
鈴木 良昭 |
情報通信研究機構無線通信部門部門長 |
||
| 宇宙科学パネル専門委員 | 槙野 文命 |
神奈川大学工学部特任教授 |
||
| 地球科学パネル専門委員 | 木村 龍治 | 放送大学教授 |
||
【公募地上研究推進委員会】
「地上研究公募」制度の運営方針、募集方針・要領、選定方針・基準、中間評価・最終評価の方針を審議する委員会。
【専門パネル】
公募地上研究推進委員会の下に置かれる分野毎に設定されるパネル。テーマ選定及び選定後の研究活動の中間評価を行う"選定パネル"と、研究終了後の最終評価を行う"最終評価パネル"の2つから構成され、8分野2パネルの計16パネルを設定。
第7回「宇宙環境利用に関する地上研究公募」選定テーマ一覧
| 区分 | 研究 分野 | 分科会 | 研究テーマ名 | 氏 名 | 機関名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「きぼう」利用重点課題研究 | 物理学・化学系 | マクロ分子の界面吸着が関与する結晶成長機構の解明と結晶成長制御への応用 | 古川義純 | 北海道大学 | |
| タンパク質結晶の成長機構と完全性に関するその場観察による研究 | 塚本勝男 | 東北大学 | |||
| 生命科学系 | 植物の抗重力反応におけるシグナル変換・伝達機構の解明 | 保尊隆享 | 大阪市立大学 | ||
| 植物の成長を統御する重力応答分子の機能とネットワーク機構 | 高橋秀幸 | 東北大学 | |||
| 次期宇宙利用研究 | 物理学・化学系 | マルチアングル光散乱法によるタンパク質の集積機構解明 | 小沼一雄 | 産業技術総合研究所 | |
| 2次元燃料液滴群の群燃焼発現メカニズムの解明 | 三上真人 | 山口大学 | |||
| 微小重力下における粉体の非平衡ダイナミクス | 佐野雅己 | 東京大学 | |||
| 航空機実験用静電浮遊炉を用いた熱物性計測システムの確立と熱物性計測における重力の影響評価に関する研究 | 原田匡 | (株)IHIエアロスペース | |||
| 生命科学系 | 生物科学 | 宇宙放射線被曝がゼブラフィッシュ体内の突然変異発生に及ぼす影響 | 青木康展 | 国立環境研究所 | |
| 長期間の微小重力がメダカの重力感受機構の形成・発達に及ぼす影響と解析 | 井尻憲一 | 東京大学 | |||
| ホヤによる重力感受遺伝子の機能解析 | 津田基之 | 兵庫県立大学 | |||
| バイオメディカル | 骨における重力応答遺伝子の同定と遺伝子改変マウスを用いた機能解析 | 小守壽文 | 長崎大学 | ||
| 位置有感生体組織等価物質比例計数箱の開発とそれによる宇宙ステーション内での線量当量計測技術の確立 | 佐々木慎一 | 高エネルギー加速器研究機構 | |||
| ISSを用いた微小重力による骨芽細胞系譜制御の分子機構の解明に向けた基盤研究 | 中島和久 | 東京医科歯科大学 | |||
| 骨における力学的刺激応答メカニズムの解析 | 池田恭治 | 国立長寿医療センター | |||
| 微小重力空間が免疫システムの維持再生におよぼす影響 | 久保允人 | 理化学研究所 | |||
| 宇宙医学 | 多様な条件下におけるヒト脳機能変化の研究:特に脳波、脳磁図とfMRIとを用いた聴覚認知機構について | 柿木隆介 | 自然科学研究機構 | ||
| 宇宙環境における遠隔自動治療システムの基盤技術の開発 | 神谷厚範 | 国立循環器病センター | |||
| 宇宙利用先駆研究 | 物理学・化学系 | 宇宙環境下の多孔質中における物質とエネルギの連結移動 | 登尾浩助 | 岩手大学 | |
| 磁場制御による磁性流体の微小重力下における自然対流の解明 | 山口博司 | 同志社大学 | |||
| 微小重力下におけるタンパク質分子間相互作用の顕在化 | 和泉研二 | 山口大学 | |||
| MRI顕微鏡を用いた3He-4He混合液体の界面形状へのCasimir効果の検証 | 水崎隆雄 | 京都大学 | |||
| 微小重力燃焼法を用いたカーボンナノチューブ生成 | 伊東弘行 | 北海道大学 | |||
| 浮遊試料の磁気回転振動に基づく非磁性物質の磁場整列特性の検出 | 植田千秋 | 大阪大学 | |||
| 微小重力環境における無機・有機複合ナノ粒子生成プロセスの研究 | 山口周 | 東京大学 | |||
| 燃料液滴の着火挙動に及ぼす変動放射加熱の影響 | 瀬川大資 | 大阪府立大学 | |||
| 浮遊炉による大型浮遊液滴の界面大変形と内部流動に関する研究 | 阿部豊 | 筑波大学 | |||
| 微小重力環境を利用した火炎振動現象の研究 | 藤田修 | 北海道大学 | |||
| 反応拡散系および反応拡散対流系に自己組織化される散逸構造の階層性と重力効果に関する研究 | 三池秀敏 | 山口大学 | |||
| 生命科学系 | 生物科学 | 微小重力環境下におけるマウス生殖機能およびそのメカニズムの解明 | 野村昌良 | 産業医科大学 | |
| 張力反応性エレメント・トランスジェニックマウスの作出 | 新井克彦 | 東京農工大学 | |||
| シロイヌナズナの形態形成に対する磁場環境の影響-植物の磁場応答にカルシウムチャンネルは関与するか- | 唐原一郎 | 富山大学 | |||
| 宇宙環境及び擬似火星環境における微生物生態系の構築 | 太田寛行 | 茨城大学 | |||
| 網羅的解析による、宇宙でのウイルスの変異と増殖の分子機構の解明 | 押海裕之 | 大阪大学 | |||
| 重力変化に対する応答遺伝子クラスターのゲノム機構解析 | 田中利男 | 三重大学 | |||
| 重力環境に影響される棘皮動物の石灰化プロセス | 清本正人 | お茶の水女子大学 | |||
| バイオメディカル | 心筋再分裂誘導の分子機構と微小重力環境の応用に関する研究 | 北嶋繁孝 | 東京医科歯科大学 | ||
| 粒子放射線低密度照射が及ぼす遺伝的影響に関する研究 | 鈴木雅雄 | 放射線医学総合研究所 | |||
| 細胞の重力記憶の分子機構の解明に基づく微小重力骨免疫学 | 高柳広 | 東京医科歯科大学 | |||
| 無重力環境下の骨折治癒の新規メカニズム:繊維芽細胞活性化因子オステオアクチビンの役割を中心に | 安井夏生 | 徳島大学 | |||
| 重力の骨代謝共役における生理的役割の解明 | 宇田川信之 | 松本歯科大学 | |||
| 重力変化にセンシティブに応答するラット辺縁系部位の特定 | 粂井康宏 | 東京医科歯科大学 | |||
| 放射線応答の先行指標となるタンパクの網羅的解析とその制御に関する研究 | 三浦ゆり | 東京都老人総合研究所 | |||
| 宇宙環境ストレスに応答するp38/JNKシグナル伝達経路の活性制御機構の解明 | 武川睦寛 | 東京大学 | |||
| 免疫系細胞を宿主とするヘルペスウイルスの潜伏感染と再活性化様式の宇宙環境における動態の研究 | 原田志津子 | 国立感染症研究所 | |||
| 宇宙医学 | 空間識における体感覚と視覚のずれに関するfMRI研究 | 中井敏晴 | 産業技術総合研究所 | ||
| 微小重力下での自律神経による心機能制御の検討 | 石川義弘 | 横浜市立大学 | |||
| 空間識と運動制御に関与する大脳前庭野の同定とその入出力 | 篠田義一 | 東京医科歯科大学 | |||
| 生体リズムに関連した運動処方の開発とヒトへの応用 | 柴田重信 | 早稲田大学 | |||
| 静脈還流量の変化が圧受容器反射機能に及ぼす効果の量影響関係 | 岩崎賢一 | 日本大学 | |||
| 正常および遺伝的内耳障害マウスの前庭系生後発達に及ぼす重力の影響 | 松永達雄 | 国立病院機構 | |||
| 落下施設・航空機利用研究 | 物理学・化学系 | 固体試料上の火炎伝播限界に与える外部環境の影響に関する研究 | 高橋周平 | 岐阜大学 | |
| コロイド分散系の乾燥散逸構造発現に対する微小重力効果 | 土田亮 | 岐阜大学 | |||
| 密度差を伴う旋回噴流の挙動 | 植田利久 | 慶應義塾大学 | |||
| Reynolds応力を利用した熱対流の生成と数値モデル化 | 田辺光昭 | 日本大学 | |||
| 宇宙空間における気液二相流界面積濃度輸送機構解明に関する研究 | 賞雅寛而 | 東京海洋大学 | |||
| 生命科学系 | バイオメディカル | ヒト個体において微小重力に特異的に応答し細胞の核外から突然変異の発生を抑制する遺伝子とその産物の検証 | 鈴木信夫 | 千葉大学 | |
| 宇宙医学 | 放物線飛行の耳石頚反射に及ぼす影響 | 渡辺行雄 | 富山医科薬科大学 | ||
| 宇宙利用技術開発 | 濡れ性が高いマイクロストラクチャを有する沸騰伝熱促進面における気泡核生成とその離脱に関する研究 | 浅野等 | 神戸大学 | ||
| 超親水成膜処理による微小重力下の沸騰伝熱促進技術の研究開発 | 鈴木康一 | 東京理科大学 | |||
| 網構造のふろしき展開と歩行機能を有する構造エレメントによる宇宙大構造物の構築 | 賀谷信幸 | 神戸大学 | |||
| 微小重力下における超小型衛星用分離把持機構の機能評価実験 | 松永三郎 | 東京工業大学 | |||
| 衛星搭載用スピン軸方向伸展マストの伸展安定性と制振に関する実験 | 渡辺和樹 | (株)ウェルリサーチ | |||
表1 第7回募集の方針

表2 前回(第6回)と今回(第7回)の募集における変更点
| 第6回(平成14年4月募集) | 第7回(平成16年2月募集) |
|---|---|
| 課題計画研究 - これまでの研究実績に基づく、確実かつ有望な研究成果を提示できる下記の課題に限定 ・ 溶液からの結晶成長 ・ 準安定相物質研究 ・ 生物の重力応答 - 体系的な研究(チーム構成) - 採択規模:1課題 |
重点課題研究 - ISS/JEM利用重点化の戦略を基本に、既存装置を活用して、初期段階のフライト実験テーマに発展させることが可能な地上研究。 - 「きぼう」既存実験装置を利用した下記の分野 ・ 物理学・化学 ・ 生命科学(ヒト及び脊椎動物(個体)を対象とする研究は除く) - 採択規模:3-4課題 |
| 重点研究 - 下記の分野の重点領域を中心とした、個人提案の研究 ・ 物理・化学(微小重力科学・物理学) ・ 生命科学(生物、バイオメディカル、宇宙医学) ・ 宇宙科学 - 採択規模:10課題程度 |
次期宇宙利用研究 - ISS/JEM利用重点化の戦略を基本に、初期・中期段階における有望なフライト実験テーマの創出や、宇宙環境利用を支える技術開発テーマへの発展が期待できる研究 - 既存実験装置、次世代実験装置、海外機関装置を利用した下記の分野(新たな概念の装置やインフラによる研究も妨げない。) ・ 物理学・化学 ・ 生命科学 - 採択規模:15課題程度 |
| 萌芽研究 - 新規性の高いアイデア・発想が、宇宙環境利用に効果的であるかを具体化する研究 ・ 物理・化学(微小重力科学・物理学) ・ 生命科学(生物、バイオメディカル、宇宙医学) ・ 宇宙科学 ・ 地球科学 ・ 宇宙利用技術開発 - 採択規模:40課題程度 |
宇宙利用先駆研究 - 独創性・新規性のある研究で、中後期段階以降において、新たな実験装置・機器の開発構想の創出や、将来の利用テーマへの発展が期待できる研究。 - 若手研究者の育成や研究コミュニティの活性につながる研究 - 採択規模:30課題程度 |
| 落下施設・航空機利用研究 - 宇宙環境利用への発展が期待できる独創的で新規性のあるアイデア・発想を、短時間微小重力実験により具体化することを目標にする研究 - 落下施設・航空機での微小重力環境を利用した以下の研究分野 ・ 物理学・化学系 ・ 生命科学系 ・ 先端宇宙技術開発 - 採択規模:10課題程度 |
表3 第7回地上研究公募の募集概要
| 研究区分 |
「きぼう」等利用研究 | 落下施設・航空機利用研究 (科学・技術利用) |
||
| 第1優先カテゴリ 「きぼう」利用重点課題研究 |
第2優先カテゴリ 次期宇宙利用研究 |
第3カテゴリ 宇宙利用先駆研究 |
||
| 研究目標 |
ISS/JEM利用重点化の戦略を基本に、既存装置を活用して、初期段階のフライト実験テーマに発展させることが可能な地上研究。 | ISS/JEM利用重点化の戦略を基本に、初期・中期段階における有望なフライト実験テーマの創出や、宇宙環境利用を支える技術開発テーマへの発展が期待できる研究 | 独創性・新規性のある研究で、中後期段階以降において、新たな実験装置・機器の開発構想の創出や、将来の利用テーマへの発展が期待できる研究。 |
若手研究者の育成や研究コミュニティの活性につながる研究 宇宙環境利用への発展が期待できる独創的で新規性のあるアイデア・発想を、短時間微小重力実験により具体化することを目標にする研究 |
| 研究内容 |
|
|
中後期段階に向けて、アイデア・発想を具体化する | JSF/JAXAが提供する落下施設・航空機による短時間微小重力施設利用機会を利用する研究 |
| 想定する実験装置等※ |
「きぼう」既存実験装置(船内実験室)の利用 細胞培養装置 クリーンベンチ 流体物理装置 結晶成長装置 温度勾配炉 |
以下の装置を中心とするが、新たな概念の装置やインフラによる研究も妨げない。 「きぼう」既存実験装置 「きぼう」次世代実験装置(構想中):水棲生物実験装置、浮遊炉、多目的ラックなど 海外機関開発装置 |
制限無し | (装置は提案者が準備) |
| 募集対象分野 |
|
|
微小重力環境を利用した以下の研究分野、物理学・化学系、生命科学系、先端宇宙技術 | |
| 研究費 |
最大3000万円/年度 | 最大1500万円/年度 | 最大300万円/年度 | 旅費程度 |
| 期間 |
最大3年度 | 2〜3年度 | 2年度 | 1〜2年度 |
参考 これまでの応募・選定状況
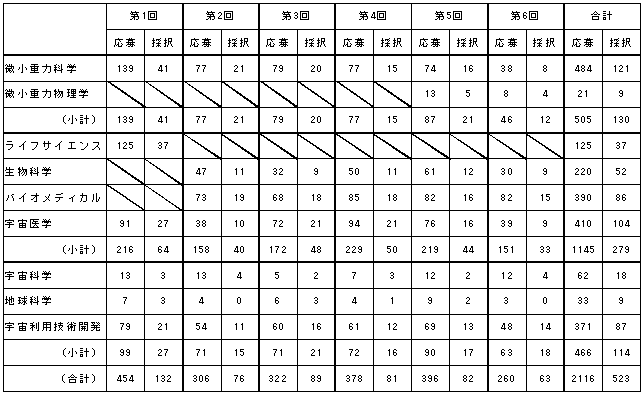
宇宙航空研究開発機構 広報部
TEL:03-6266-6413〜6417
FAX:03-6266-6910