第2回総合技術研究本部公開研究発表会の開催結果について
宇宙航空研究開発機構
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
1. 報告事項
「第2回総合技術研究本部公開研究発表会」の開催結果の概要について報告する。
2. 開催目的
本公開研究発表会は、総合技術研究本部の全体の事業と研究成果を広く一般に紹介することを目的として、1年に1回開催するもので、今回は第2回目にあたる。
3. 開催概要
(1) 日時:平成16年12月1日(水) 10:00〜17:00
(2) 場所:みらいCANホール(日本科学未来館7階)
(3) 主催:宇宙航空研究開発機構
(4) 発表内容:口頭発表 18件
展示発表 23件
(5) 来聴者:348名
4. 開催結果
(1) 特別講演
特別講演は、ノンフィクション作家の中野不二男氏により「航空宇宙と日本社会」と題して講演が行われ、概要は以下のとおりである。
- 現在、日本の社会現象において情報伝達の変化が起きている。
インターネットを使用してたくさんの情報のやりとりができている中、現状は官側(航空宇宙関係者)からの一方的な情報提供となっており、一般国民からの意見を吸い上げられていないことから、官民相互の情報交換が必要である。 - 中野氏が出演したラジオ番組の中で、平成15年11月に起きたH-IIAロケット6号機の打上失敗直後のアンケート調査(http://www.tbs.co.jp/ac/bt/2003/20031202.html)を行ったところ、 6割の人が開発を積極的に推進すべきであるという結果であった。
- 国民が日本の航空宇宙開発に何を期待するかをくみ取るため、日本の航空宇宙"技術"に対する国民の意識調査(支持を確認)を行う。
- 日本の航空宇宙開発を国民に対して積極的にアピールする。
- 我が国に適する宇宙開発のあり方を考えるための、"民"による、独立したシンクタンクを設置する。
(2) 一般講演 (添付1)
一般講演は、総合技術研究本部の事業展開について、中期計画に基づき、その概要と具体的な活動等を紹介した。
航空分野では、「社会的要請に応える航空科学技術の研究開発」に焦点を絞り研究開発の進捗を紹介した。宇宙分野では、プロジェクトの信頼性向上に資する宇宙機に共通な基盤技術の研究開発を紹介した。基礎基盤分野では、風洞試験技術とエンジン試験技術を中心に設備の整備計画等を紹介した。
(3) 研究発表(口頭) (添付2)
研究発表(口頭)は、将来宇宙輸送システムの設計・評価ツールの開発状況や宇宙エネルギー利用システムの研究内容など最新の研究成果を、航空分野3件、宇宙分野3件、基礎基盤分野3件を発表した。
一般講演と同時進行であったが、多数の来聴者があり、活発な意見交換もあった。
(4) 研究発表(展示) (添付3)
研究発表(展示)は、ポスターにより最新の研究成果を、航空分野2件、宇宙分野12件、基礎基盤分野9件について発表した。供試体の展示や実験装置によるデモンストレーションを行いながら分かりやすく紹介した。来場者との密接な質疑応答により、技術の理解を深める交流ができた。
5. 来聴者からの主なコメント
- 市民レベルでの宇宙開発への参加が必要。国民全体を巻き込んでいくような底上げ企画が必要。
- 日本社会に対する今後のJAXAの役割を理解できた。
- 日本の研究の独創性をアピールしておられるのは素晴らしい。宇宙/航空機開発の面ではアメリカに大きくあけられているが、たゆまぬ努力こそが追いつき追い越せる原動力と思います。国民の支援をうけつつ、国民に還元することを考えて下さればと思います。
- 日本の航空機開発に明るい未来が少し見えたような気がします。中野先生の話にあった、政策立案等のためのシンクタンク創立にまったく同感。
- 前回同様、若手技術者の意気込みを感じた。企業の技術者の研究者との交流を如何に図るか検討したい。
- 研究開発計画の確実となる進捗を踏まえた、JAXAの自信を感じた。
- 日本発の技術開発、情報の取得・応用に役立つ体制ができることを希望します。
- 社会の考え方、JAXAがどこに力を入れるべきなのか、参考になった。社会へのアピール・リサーチが大切と感じた。将来宇宙について必要性が本当にあるか?HOPEのように凍結にならなければ良いが。宇宙エネルギーはコスト実現性に疑問を感じた。
6. まとめ
本公開研究発表会は、各会場ともに多数の来聴者があり、研究発表会場では、来聴者と発表者との間で活発な意見交換が行なわれ、全体として充実したものとなった。当本部へのより一層の期待が高まっていることが感じられた。
特別講演や来聴者から得られた貴重な意見を参考とし、今後の事業活動に有効に反映させていく。
<参考資料>
第2回総合技術研究本部公開研究発表回プログラム (PDFファイル477KB)
特別講演「航空宇宙と日本社会」 配布資料 (PDFファイル31KB)
|
|
「宇宙用電源サブシステムの研究開発」
1.概要
衛星、ロケット等の宇宙機の運用に必要不可欠な電源について、これまで研究開発を実施している。電源サブシステムとして重要な太陽電池、バッテリ(2次電池)等についての研究開発状況について紹介するとともに、昨今の電源系の不具合に起因する衛星のトラブルを踏まえ今後の宇宙用電源サブシステムの研究開発の取り組み方について報告する。
2.まとめ
電源サブシステムは衛星の寿命を左右する重要な構成要素であるので、これまでの研究成果を踏まえつつ、近年の不具合に対応し、メーカ、大学等との連携を密にし、より一層基盤技術の底上げを行うと共に、それらを通じて信頼性の高い電源サブシステムの構築に向けた研究開発を推進する。
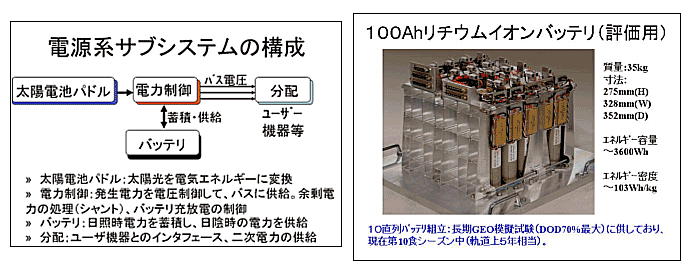
添付2 【研究発表(口頭)】
「将来宇宙輸輸送システムの設計・評価ツールの開発について」
1.概要
本ツールの目的は、将来目指すべき宇宙往還システムについて、複数のコンセプトを設計・評価することにより絞込みを行い、その技術開発の方向性や定量的な技術改善目標を設定することである。最初に本ツールの開発方針をまとめ、現在の開発状況について報告する。また、本ツールによる単段式ロケットプレーンの設計・評価結果についても述べる。
2. まとめ
開発中の設計・評価ツールについて述べ、設計結果の一例を示した。ツール開発過程で、その改善すべき点が数多く抽出されている。これらは、要素技術を統合してシステム設計に挑戦する際に重要な知見となり、各要素技術の向上に貢献するであろう。今後の課題として、設計変数の抽出、信頼性の異なるデータを用いたシステムの設計・評価技術の開発、等が挙げられる。
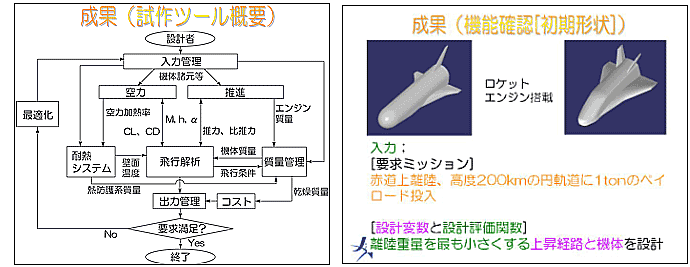
添付3 【研究発表(展示)】
「先進ロケットノズル流れの可視化技術の研究」
1.概要
将来の高性能ロケットノズルとして有望なエアロスパイクノズルの流れを可視化し、可視化結果に基づいて性能予測モデルを提示した。性能予測モデルは燃焼試験にて検証した。また、従来型ノズルの起動/停止過渡中の内部流を可視化し、横推力発生現象を解明し、LE-7Aエンジンの横推力の問題解決に貢献した。
2.今後の展望
可視化研究を進めることによって、先進ロケットノズルの性能予測式を得た。また実機ロケットエンジンで発生した問題の解決に貢献できた。今後とも試験技術の向上をめざしてより新しい可視化技術の研究を進めていく予定である。
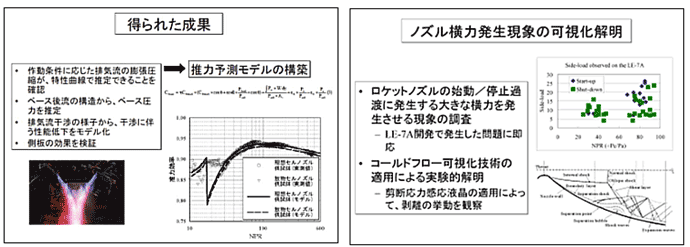
宇宙航空研究開発機構 広報部
TEL:03-6266-6413〜6417
FAX:03-6266-6910