「宇宙利用シンポジウム2005 防災と宇宙」
〜その日のために、できること。〜
の開催について
平成17年10月17日
宇宙航空研究開発機構
平成17年11月7日(月)に、学術総合センター一橋記念講堂(東京都千代田区一ツ橋)において、下記のとおり「宇宙利用シンポジウム2005 防災と宇宙」〜その日のために、できること。〜を開催します。
シンポジウムの概要
| (1) | 日時:平成17年11月7日(月)10:00〜17:00(懇親会:17:00〜18:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 場所:学術総合センター一橋記念講堂(東京都千代田区一ツ橋2-1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 目的:当機構は、今春発表した「JAXA長期ビジョン2025」で、今後の宇宙活動の重点分野のひとつとして、安全で豊かな社会をつくるため、防災・危機管理分野における宇宙航空技術の活用を提唱しました。地震、火山災害、津波、豪雨などの災害発生時に、被害状況を観測衛星で把握し、危険を防止するための警報や防災情報などを、通信衛星を介して国内のみならずアジア・太平洋諸国の個人の携帯端末まで、直接通報できるシステム構築を謳いました。本シンポジウムでは、企業、大学、研究機関及び行政分野の防災専門家に、構想実現のための必要条件や課題について討議していただき、防災分野における今後の宇宙利用の可能性を探ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 内容:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | プログラム構成:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 後援:内閣府、文部科学省、総務省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 参加費:シンポジウムの参加費は無料。(懇親会は有料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 参加者:全国の宇宙および防災関係の専門家と、「防災と宇宙」に関心のある一般の方々を想定しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | シンポジウムに関する問合せ先: (電話)株式会社プライムインターナショナル:03-5467-5539(10:00〜17:00) (インターネット)http://i-space.jaxa.jp/symposium2005/ |
(参考資料)衛星を利用した防災関係のこれまでのJAXAの取り組みです。
・ 平成13年度「応急危険度遠隔判定(有珠山)」
・ 平成14年度「応急危険度遠隔判定(御前崎)」
被災建造物や河川の状況を、ヒトが装着した超小型カメラで撮影し、衛星中継を通じて危険度を判定するシステムの開発を行なっています。
・ 平成14年度「早期被災エリア判定」
広域災害を想定して航空機による被災地状況早期把握システムの開発を目指しています。
(問い合わせ先)
宇宙航空研究開発機構 宇宙利用推進本部 通信・測位利用推進センター
参事 松原彰士(まつばら しょうじ)
東京都千代田区丸の内1-6-5丸の内北口ビルディング
TEL:03-6266-6300
|
|
参考資料
【平成13年度】
応急危険度遠隔判定(有珠山)
被災地(北海道有珠山)と現地自治体(虻田町)や内閣府を可搬型地球局で結び、被災建造物・河川等の「応急危険度遠隔判定」を実施しました。(平成14年3月)
 |
 |
| ▲ 想定被災地に設置した中継車 | ▲ 中継先の内閣府 |
【平成14年度】
応急危険度遠隔判定(御前崎)
東海地震を想定した政府の広域防災訓練に参加し、静岡県御前崎において各種防災訓練の状況をリアルタイムに政府や静岡県の対策本部に伝送するとともに、インターネットのウェブページを通じて動画及び静止画の配信を行いました。(平成14年9月1日)
 |
 |
| ▲ ウェアラブルカメラによる応急危険度判定 | ▲ カメラの撮影画像と撮影位置表示画面 |
早期被災エリア判定
近い将来発生する可能性が高い東海地震、東南海地震、南海地震などの広域災害を想定し、航空機による被災状況早期把握を行いました。「映像解像度」及び「時間的制約からの解放」の観点から発展させ、より効果的な被災情報の収集に努めるため、ハイビジョンカメラ、赤外線カメラ等による航空機からの伝送を目指した調査を実施しました。(平成15年1月)
 |
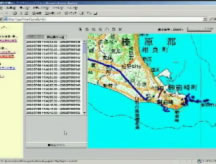 |
| ▲ 航空機からの撮影風景 | ▲ 撮影画像検索画面 |
● 上記実験の詳細はこちらをご覧下さい
http://i-space.jaxa.jp/pilot_experiments/disaster/index.htm
宇宙航空研究開発機構 広報部
TEL:03-6266-6413〜6417
FAX:03-6266-6910