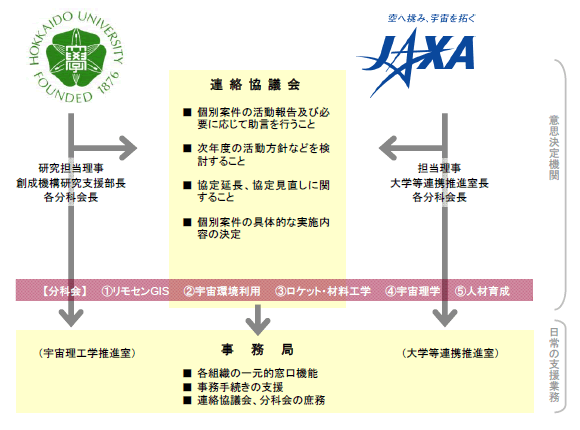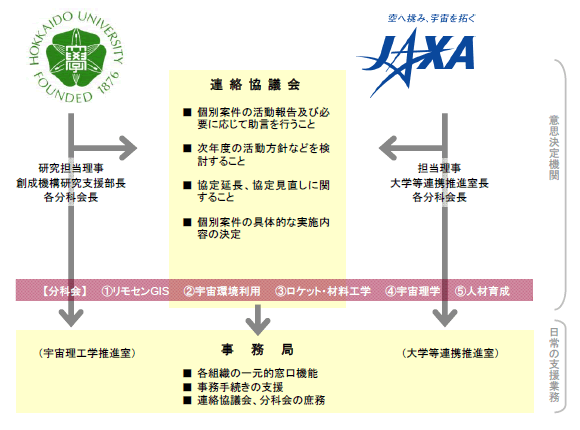北海道大学と宇宙航空研究開発機構との連携協力協定の締結について
平成20年10月31日
北海道大学
宇宙航空研究開発機構
北海道大学(札幌市北区、総長/佐伯浩)と宇宙航空研究開発機構(東京都調布市、理事長/立川敬二、以下「JAXA」)は、平成20年10月31日、両機関の連携・協力を推進し、相互の研究開発能力及び人材を生かして総合力を発揮することにより、学術研究と教育の発展、宇宙及び航空に関する科学技術の向上、並びに宇宙開発利用の促進等に、新たな重要な役割を果たすことを目的とし、連携協力協定を締結いたしました。
1.主な連携協力の内容(詳細は別紙参照)
(1)共同研究の推進
(2)教育・若手研究者育成
(3)研究者・技術者交流
2.連携協力の運営形態- 1)北海道大学独自の宇宙工学研究ツールとJAXAの基盤研究との有機的な連携による共同研究の推進
- 2)地域自治体・企業等との連携による北海道のフィールドを活用した研究の推進、宇宙関連研究拠点およびネットワークの整備
- 3)北海道大学の宇宙観測基礎データセンターを拠点とした宇宙科学技術開発の推進
- 4)衛星・探査機の機器開発およびデータ解析
- 1)連携講座の実施
- 2)インターンシップ制度の拡充
- 3)研究者・技術者交流を通じた若手研究者の育成
- 1)共同セミナーの実施
- 2)フォーラムの実施
- 3)研究ネットワークの構築
- 4)エクスチェンジプログラム制度の構築
北海道大学及びJAXAは、連携協力を円滑にかつ効果的に推進するため、両機関の代表者で構成する「連絡協議会」を設置します。さらに、連携協力のテーマごとに「分科会」を設置し、連携協力事業の具体的案件の検討を行います。北海道大学では宇宙理工学に関する研究および人材育成を支援推進する部局横断的な組織として創成科学共同研究機構に宇宙理工学推進室を新設します。連絡協議会ならびに日常の連携支援を円滑に行うため、北海道大学宇宙理工学推進室とJAXA大学等連携推進室が連携して事務局業務を担当します。
|
|
別紙
北海道大学と宇宙航空研究開発機構との連携協力協定の締結について
(参考資料)
1.協定の背景と経緯北海道大学とJAXAは、これまでも宇宙理学分野、宇宙工学分野、宇宙環境利用分野及び地球環境観測分野を中心に多岐に渡る交流を積み重ね、そこで生まれた知見と技術は、人類の宇宙への進出と学術の拡大深化に貢献しつつ、次世代を担う研究者や学生へ脈々と引き継がれています。
宇宙のフロンティアを目指すJAXAと「フロンティア精神」を基本理念のひとつとする北海道大学は、これらの交流の一層の推進と展開を図ることによって世界をリードする宇宙の先端科学技術の創出に挑むと同時に、それらを推進し支えることのできる多様な人材の育成を図ります。そのために、JAXAと北海道大学は、地域企業・自治体とも連携し、北海道というフィールドを活用した広範な研究協力と研究者・技術者交流を展開します。
2.北海道大学の対応と関連する具体的な連携協力
北海道大学では本協定締結にあたり、北海道大学における宇宙理工学の展開を支援する全学的な組織として宇宙理工学推進室を創成科学共同研究機構に設置します。
宇宙理工学推進室は、次の4センターの連携と分野・組織横断的な事業の支援促進を図り、さらに本協定に関する北海道大学側の窓口となり、JAXAとの連携協力を推進していきます。
1.4つのセンターとその活動例
- (I)宇宙工学研究センター(開設予定)
- 代表:永田晴紀教授
〜エンジンの開発や国際宇宙ステーション日本実験モジュール「きぼう」の利用〜
北海道大学独自の技術で開発が進められてきた無火薬式小型ロケット「CAMUI」を活用し、JAXAが研究を進めている機器の弾道飛行試験を検討しています。具体的にはロケット/航空機エンジンの飛行環境試験、アボート飛行技術、自律帰還飛行、着陸技術等の基盤技術開発への応用が期待されます。また、今年11月末ごろには、北海道大学低温科学研究所の古川義純教授とJAXAとの共同実験『氷結晶成長におけるパターン形成』が、国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」で行われる予定です。
これまでも特に宇宙工学の分野に関しては、北海道のフィールドを活用した実験が活発に行われてきました。大樹町でのCAMUIロケットによる弾道飛行実験、赤平市の50m級落下塔を用いた無重力実験などを通して、地方自治体、および地域企業の研究者、技術者等との交流も活発であり、道内外の宇宙科学技術に対する関心と理解の促進に貢献します。
※ p1「1.主な連携協力の内容 (1)共同研究の推進」のうち、主に1)、2)に該当します。
- (II)宇宙観測基礎データセンター
- 代表:渡部重十教授
〜惑星探査教育研究ネットワークの構築〜
北海道内外の惑星探査に関する教育研究機関との連携を推進し、宇宙理学に関する研究の展開と人材の育成を図ります(具体的には北海道宇宙観測ネットワーク(苫小牧北大電波望遠鏡・名寄木原天文台・陸別銀河の森天文台)の構築、宇宙科学基礎データ・知見公開アーカイブの整備、JAXAを含む関連教育研究機関間連携の推進等)。
特にJAXAが2010(平成22)年の打上げを目指している金星探査機PLANET-Cでは、紫外線観測装置の研究開発を実施しています。
さらに今年度採択された、神戸大学と北海道大学との連携によるグローバルCOEプログラム「惑星科学国際教育研究拠点の構築」(惑星科学に関する国際ネットワークのアジア地域における拠点構築)からもサポートを受けて活動を推進しています。
※ p1「1.主な連携協力の内容 (1)共同研究の推進」のうち、主に2)、3)、4)に該当します。
- (III)同位元素イメージングセンター(開設予定)
- 代表:圦本尚義教授
〜宇宙物質と宇宙材料の分析〜
北海道大学が所有する同位体顕微鏡(同位元素の3次元分布をイメージングにより可視化できる世界唯一の装置)を用い、宇宙物質と宇宙材料の分析研究の促進を図り、宇宙科学技術開発の推進を行います。北大、JAXA研究者・技術者が有効利用する他、企業または海外研究者の利用促進も図ります。
※ p1「1.主な連携協力の内容 (1)共同研究の推進」のうち、主に3)に該当します。
- (IV)衛星データ・衛星画像利用研究拠点センター(開設予定)
- 代表:本間利久教授
〜グローバルな自然・人工環境の観測・保全・予測に関する衛星データ・衛星画像の高度な利用研究開発〜
本年9月「地球規模課題対応国際科学技術協力事業(JST/JICA)」に北大・JAXAの共同事業が採択されたことに伴い(*)、国際的な研究活動と同時に、北海道のフィールドを活用した地域との連携を強化して、衛星画像利用を推進します。センターにはデータ収集・管理のための環境を整備します。
(*) 採択された研究課題は「インドネシアの泥炭における火災と炭素管理」。日本の年間排出量に相当するほどの膨大な量の二酸化炭素の放出源となりつつあるインドネシアの熱帯泥炭を対象として、JAXAの人工衛星を利用した統合的炭素管理システムを構築し、気候変動緩和への貢献を目指します(研究担当者:北海道大学大学院農学研究院 大崎 満教授)。
※ p1「1.主な連携協力の内容 (1)共同研究の推進」のうち、主に2)、4)に該当します。
2.4つのセンターの研究教育活動の支援
- 共同研究の促進
- 教育・若手研究者育成
北海道大学とJAXAはすでに同大学工学研究科と情報科学研究科で連携講座を実施しておりますが、次年度より新たに理学院に連携講座を開設する見込みです。
また、双方の機関における既存のインターンシップの門戸を拡充し、学生が実習体験をする事業の構築を目指します。 - 研究者・技術者交流
特に、新たに北海道大学教員とJAXA研究者の短期相互派遣を行う「エクスチェンジプログラム」制度の構築を目指します。
この連携協力を円滑にかつ効果的に推進するため、両機関の代表者で構成する「連絡協議会」を設置します。さらに、連携協力のテーマ毎に5つの「分科会」を設置し、連携協力事業の具体的案件の検討を行います(図)。
| 分科会 | 関連する宇宙理工学推進室のセンター |
|---|---|
| (1)ロケット・材料工学分科会 | (I) |
| (2)宇宙環境利用分科会 | (I) |
| (3)宇宙理学分科会 | (II),(III) |
| (4)リモートセンシング・GIS分科会 | (IV) |
| (5)人材育成分科会 | 4センターの活動における人材育成・交流の支援 |
※表中ローマ数字は上述「2.」における各センターを示す
図:連絡協議会ならびに分科会の位置づけ