インド洋のダイポールモード現象をモデルで再現に成功
〜気候変動予測の実現に向けて〜
宇宙開発事業団
防災科学技術研究所
海洋科学技術センター
地球フロンティア研究システム(海洋科学技術センター・宇宙開発事業団)の山形俊男領域長(東大教授)および、防災科学技術研究所の飯塚聡研究員・松浦知徳室長らは、高解像度大気海洋結合モデルを用いたシミュレーション計算によりインド洋におけるダイポールモード現象を再現することに初めて成功し(図1)、日本を含むアジアの気候変動予測の実現に向けて大きく前進した。
この成果はGeophysical Research Letters(GRL)10月15日号に重要なハイライト研究として掲載される予定です。
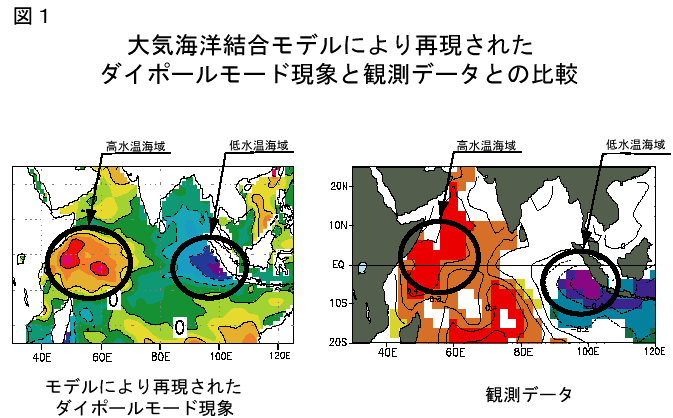
背景
平成11年9月に、地球フロンティア研究システムの山形俊男領域長(東大教授)とサジ.N.ハミード研究員らがダイポールモード現象を発見し、ネイチャー誌に論文が掲載された。(9月22日発表)
ダイポールモード現象は東部熱帯インド洋(スマトラ側)の海面水温の異常低下と西部熱帯インド洋(アフリカ側)の海面水温の異常上昇で特徴づけられる大気海洋相互作用現象で、インド洋沿岸諸国、オーストラリア、我が国を含む極東アジアの気候に大きな影響を及ぼすため、この現象が予測可能となることは洪水や干ばつ・猛暑への事前対策を講じる上での重要な情報を与えることとなり、人口稠密なこの地域の社会経済へのインパクトが極めて大きい。
成果及び考察
今回の高解像度大気海洋結合モデルを用いた研究では、ダイポールモード現象をシミュレーションにより再現することに成功し、現象の発生、成長、減衰過程の詳細(図2)が明らかになった。また、ダイポールモード現象は太平洋のエルニーニョとは独立したインド洋の大気海洋現象(図3)であり、その発達過程では海上風により励起されるインド洋の赤道海流が重要な役割を果たすことも明らかになった。
今回のモデル再現実験の成功により、海洋科学技術センターにより進められているインド洋のTRITONブイ計画や宇宙開発事業団による海上風の衛星観測計画(ADEOSII衛星のセンサーSeaWindsによる)を統合的に展開することで、日本を含むアジア及びインド洋の気候変動予測の実現可能性が大いに高まったといえる。
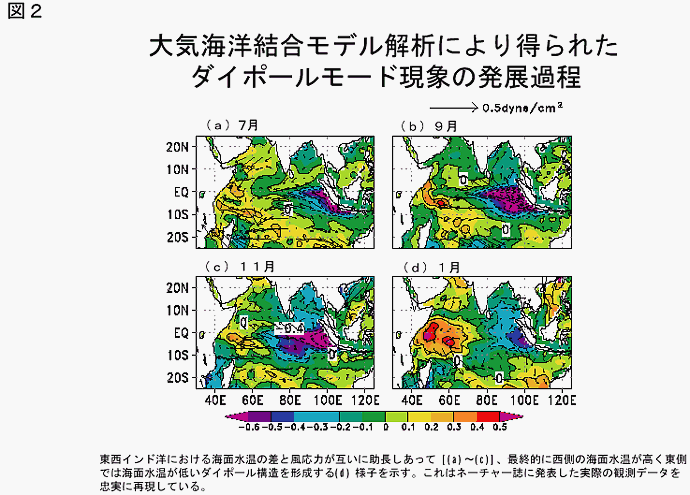
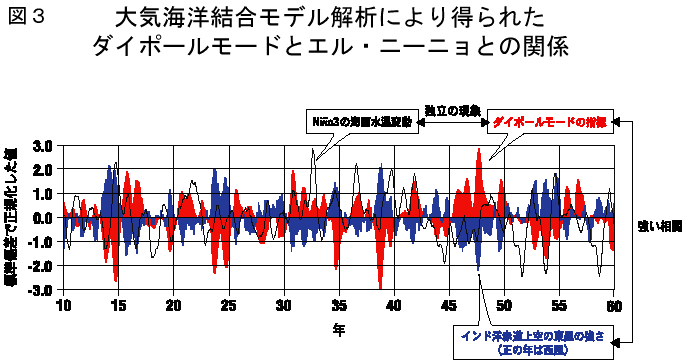
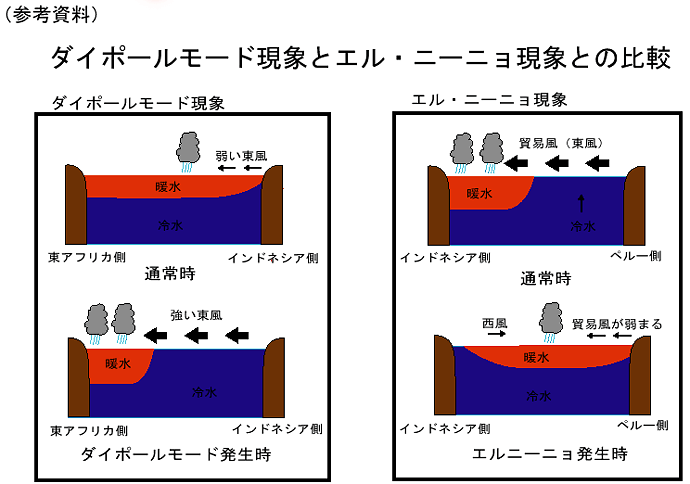
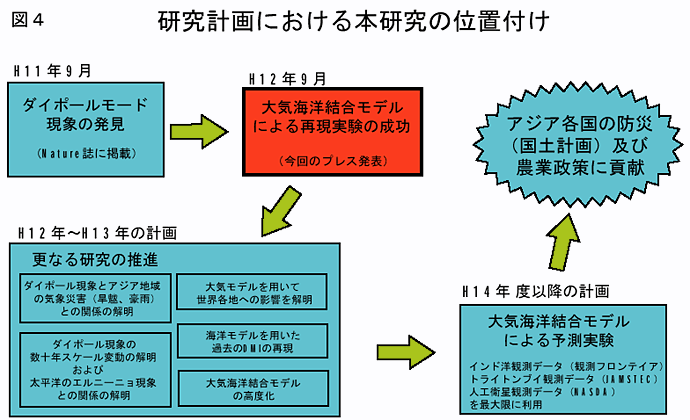
ダイポールモードと周辺諸国の気候変動との関係
ダイポールモード現象はインドネシアなどインド洋東部では干ばつを、インドからアフリカ大陸東岸などにかけては洪水をもたらし、インド洋沿岸諸国、オーストラリア、我が国を含む極東アジアの気候に大きな影響を及ぼす。
最近では、1994年と1997年に発生しており、この影響で特に1997年の秋から1998年の春にかけて東アフリカ沿岸諸国では激しい洪水に見舞われた。(下表参照)
また、1994年の夏には、日本は記録的な猛暑となるなど、ダイポールモードは日本にも異常気象をもたらしている。
(情報提供:外務省国際緊急援助室)
|
Geophysical Research Letters ( GRL )について
GRLは地球物理学関係の世界第一級の学術誌(発行国:米国、発行回数:毎月1日と15日の2回発行)であり、これに掲載されることは研究者として非常に高い評価を受けたことを意味する。また、本誌は常に最新の情報を提供する速報性という点において、関係内外からの注目度も高い。
使用計算機および今回の計算結果
主に防災科学技術研究所のスーパーコンピュータ(Cray T9:32CPU)を使用。
今回の高解像度大気海洋結合モデルを用いた研究では50年のシミュレーション期間内に太平洋のエルニーニョ現象とは無関係にダイポールモード現象(指標の値1.5以上のもの)が8回出現した。
- 問い合わせ先:
- 海洋科学技術センター/宇宙開発事業団
地球フロンティア研究推進システム合同推進事務局 担当:菱田
TEL 03-5404-7852(菱田) - 科学技術庁 防災科学技術研究所 企画課 担当:小島
TEL 0298-58-1773
|
|