標準型H-IIAロケット 地上試験機/射場システム試験の結果概要
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
1. 報告事項
平成12年7月5日(水)に、標準型H-IIAロケット 地上試験機/射場システム試験(以下「GTV-1」)について、3回目の試験(極低温点検及び第1段ステージ燃焼試験)を実施した。エンジンの燃焼は計画通り100秒行われたが、エンジンの燃焼停止後に後燃えが発生した。それら試験結果の概要について報告する。
2. 経緯
| (1) | GTV-1については、種子島宇宙センター大型ロケット発射場において平成11年4月より準備作業を開始し、同6月1日に1回目の試験を行った。(燃焼時間:約16秒【緊急停止】。原因:緊急停止装置のパッチボードの誤配線) |
| (2) | H-IIロケット8号機の打上げ失敗で中断されていたが、平成12年6月20日に2回目の試験を実施。予定通りのデータ取得を行った。(燃焼時間:10秒【計画通り】) |
| (3) | 同7月5日に3回目の試験を実施した。(燃焼時間:100秒【計画通り】) |
3. 3回目の試験結果概要
(1)作業経緯
| 7月5日(水) | |||
| 5時14分 | : | 総員退避(1600m立ち入り規制)完了(推進薬充填作業開始) | |
| 10時00分 | : | 極低温点検(F-0)#3実施 | |
| 17時00分 | : | 燃焼試験(T-0)#3実施(試験後に後燃えが生じた) | |
| 18時頃 | : | 液体酸素排出完了(タンク内の液位がゼロとなった) | |
| 19時15分 | : | 総員退避(1600m立ち入り規制)解除 | |
| 22時30分頃 | : | 液体水素排出完了(タンク内の液位がゼロとなった) | |
(2)データ取得状況
GTV-1における主要なデータ取得項目とその取得結果概要を表1に示す。25の主要確認項目全てについて、計画通りにデータを取得した。 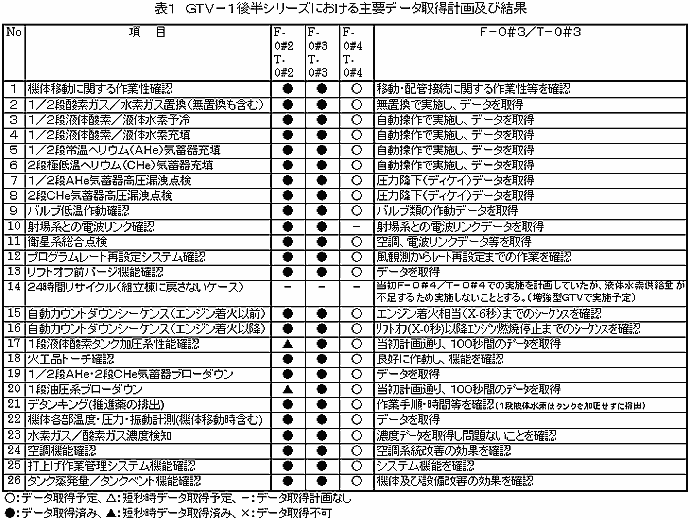
(3)燃焼試験結果
第1段ステージ燃焼試験を行い、ほぼ目標通りの結果が得られた(表2)。
| 項目 | 単位 | 目標値 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 燃焼秒時 | 秒 | 100 | 100 |
| メイン燃焼圧力 | MPa{[kgf/cm2]} | 12.3{125} | 12.2{123} |
| 液体酸素インタフェース圧力 | MPa{[kgf/cm2]} | 0.63{6.4} | 0.61{6.2} |
| 液体水素インタフェース圧力 | MPa{[kgf/cm2]} | 0.31{3.2} | 0.32{3.3} |
| (注) | メイン燃焼圧力及びインターフェース圧力は、燃焼開始後95、100秒時点のデータの平均値を示す。 |
| (注) | 1[kgf/cm2]=9.80665×10-2[MPa](圧力の単位) |
4. 試験の特記事項(燃焼試験後の後燃えについて)
(1)状況
エンジン燃焼停止後、エンジン付近に炎らしきものが確認された。このため、液体窒素を数回放出して消火作業を実施した結果、17時30分頃には付近の炎が消えたことがTVカメラにて確認された。しかし、水素ガス漏洩の可能性があることから、液体水素はタンクを加圧せずに液のヘッド(水頭)のみで排出した。なお、液体酸素は問題がないため通常の手順に従い、タンクを加圧して排出した。
(2)原因
エンジン停止後に液体水素ターボポンプ(FTP)のタービン出口温度のみが低下していたことから、FTPのポンプ側からタービン側への低温水素の漏洩の可能性が考えられる(図1)。
なお、大型ロケット組立棟にて、常温の状態でリフトオフシールの漏洩点検を実施したが、漏洩は認められなかったことから、低温水素の漏洩の原因はリフトオフシールの動作が緩慢だったためと推定される。
リフトオフシールの動作緩慢については、混入した水分の氷結、コンタミ(異物)等の影響が考えられる。
| (注) | リフトオフシールは、エンジン作動中はポンプ吐出圧力の上昇によりバネを縮めてシールを開口させる機構を有しており(図2)、これにより水素ガスをタービン側に流し、タービンを冷却する働きを行う。エンジン停止後は、ポンプ吐出圧力が低下することによりシールが閉まり、水素が漏洩しない仕組みとなっている。(なお、実際のフライトにおける燃焼停止時に、この漏洩が発生したとしてもその後の飛行に支障はない) |
(3)今後の作業
エンジンからFTPを取り外し、製造メーカにてFTPの詳細な分解点検を実施する。原因が現在想定している範囲であれば、大きな設計変更にいたることはなく、次回のGTV-1が当初計画より遅れるが、GTV-1終了後の種子島における打上げに向けた準備作業には余裕があるため、試験機1号機の打上げに影響は無いと考えられる。(図3)
5. まとめ
GTV-1シリーズにおいて3回目の極低温点検及び燃焼試験を実施し、必要なデータを取得した。次回試験の試験日程詳細については、4項の特記事項に示す原因究明作業状況を踏まえて設定する。
|
|