平成12年宇宙開発事業団評価委員会の報告について
宇宙開発事業団
本年3月から8月にかけて行われました宇宙開発事業団評価委員会の各部会における評価の結果について、下記の通り報告します。
|
|
宇宙開発事業団評価委員会
第3回軌道上技術部会評価報告書
軌道上技術部会
軌道上技術部会共同部会長 署名
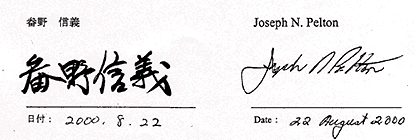
1. 経緯
平成11年秋のH-IIロケット打ち上げ失敗により、宇宙開発事業団の全ての計画が見直されることになった。平成12年度の宇宙開発見直しには、新たな衛星計画の要望が提出される予定が無くなったため、軌道上技術部会の開催は行わないこととしていた。しかしながら、衆議院選挙、沖縄サミット等にも関連して、IT関連の特別プロジェクトが急に浮上し、宇宙開発事業団においても、衛星通信分野において「i-space」と名付けた計画を推進するための要望を提出するべく作業を開始した。このため、8月に予定される宇宙開発委員会計画調整部会以前に、その計画の評価を行う軌道上技術部会を急遽開催することが必要になった。
このような状況のため、全委員出席の部会を開くことが物理的に不可能であると判断し、国内委員のみの会合を開催し、海外評価委員については提示資料を送付すると共に、ペルトン共同部会長には意見を求め、他の海外評価委員には電話、E-mail等による説明及び意見を求め、それらを集約した上で、報告をまとめることとした。
2. 軌道上技術部会 会合
日時:7月21日(金) 10:00-17:30
場所:NASDA 本社28階 第1・2会議室
議事次第:付録1に示す。
委員への資料送付、コンタクトの状況の記録:
| 7月17日 | 国内評価委員へ「i-Space構想」に関する提示資料を送付 |
| 7月18日 | 海外評価委員へ「i-Space構想」に関する提示資料を送付 |
| 7月21日 | 国内評価委員会合にむけて共同部会長ペルトン氏とNASDA事務局でテレコンを実施 |
| 7月21日 | 国内評価委員会合を開催 |
| 8月7日 | 国内評価委員へ評価報告書(案)和文版を送付 |
| 8月11日 | 海外評価委員へ評価報告書(案)英訳版を送付 |
| 8月22日 | 評価報告書完成 |
3. 「i-space」の評価
3.1 計画の全体評価
- 「i-space」という、利用を含めた構想を中心に衛星計画を立てるということは評価出来る。「従来のNASDAは打ち上げ後の利用については、積極的でなかった。そのため、NASDAの評価は、打ち上げの成否のみに集中し勝ちであった。特に衛星通信実験計画は、技術試験衛星(ETS)シリーズで行われることが多く、その傾向が強かった。衛星計画そのものも、先端技術の実証に重点が置かれ勝ちであった。情報通信の世界は、今大きく動いており、良い技術が必ずしも生き残るとは限らないような状況になっている。衛星通信の技術開発といえども、どのような実用的な利用価値があるかを忘れることは許されなくなっている。」
- しかしながら、計画の詳細については、今後その内容を充実させ、シナリオに明確なイメージを打ち出す必要がある。「計画の目的、特徴、開発する技術、存在するニーズ、期待される利用、国際協力、経済的効果、コスト(本計画全体及び提供されるサービスの)、全体のシステム構成、タイムスケジュール、将来への展開のビジョン等、幅広い要素について詳細に検討し、全体構想を必要性、実現性、必然性、妥当性、将来性などの観点から、説得力あるものに練り上げる必要がある。また、これら実験に必要な設備、インフラ等についても検討すべきである」
3.2 指摘事項
- 教育、医療については先行例が多く、一部には実用が始まっている。過去の実績と現状を正確に把握し、その上に立って技術とサービスの両面から新規性、必要性を示すべきである。例えば、伝送レートを高めることによるサービス面でのメリットを明瞭に説明するべきである。また、この分野では国際協力・貢献の意義に、特に注意を払って計画するべきである。
- 衛星通信の特徴を生かしたサービス形態を考えることが重要である。
衛星通信の持つ面的な特性(同報性)とインターネットの持つ線的な特性(一対一通信)を統合的に利用できないか。
蓄積放送については現在までには実現されていないが、そのパイロット実験はやる意味がある。 - 利用も含んだ計画を立てる以上、従来の通信衛星計画とは大きく異なる幅広い検討が求められる。
既存の技術・サービスについて、地上のファイバー系、地上移動体系等を含めて調査する必要がある。
その上で、i-spaceの計画策定には、ビジネスプランを頭において行うことが出来る人材を含めるべきである。実験の計画・実施には民間のユーザも含めた幅広い組織・人材の参加が必要である。
実験の成果が将来の実用に繋がるためには、プロトコルやインターフェイスにおいて、世界的に受け入れられるものとならなければならない。計画の最初から、国際協力、国際協調で進めることを忘れてはならない。また、これらは通信のセキュリティとプライバシーの保護に十分考慮したものにする必要がある。
最も重要なのはコストである。衛星を含む全システムの計画、設計には経済的視点を忘れてはならない。システムのコスト、サービスのコスト、将来のユーザ(政府のサービス、企業を含む一般の利用)のニーズに対するコスト・パフォーマンス等についての真剣な検討に基づいて行うべきである。
一方視野を広げて、自由に使える新しい利用や実証の場(高精細度のサイバースペース)を提供し、幅広い参加を可能とすることも意義がある。 - i-space構想は、NASDAが利用分野に踏み込もうとするものであると認識される。そのためには、それに相応しい覚悟と、努力が必要である。
各利用分野毎のコミュニティとしっかり連携・協力しなければ、十分な成果を期待できず、その後の利用にも発展しないであろう。このプロジェクトの成否の大きな鍵である。 - 衛星通信の持つ広い意味でのナショナル・セキュリティの重要性について検討し、織り込むべきである。防災・地球環境等国民の生活に直接関係する安全の他に、経済的発展、科学技術的実力の涵養等、広い意味でのナショナル・セキュリティのへの役割と効果についての検討は、今後このトピックスについての論点の整理、認識の統一のためにも必要である。
- 衛星通信は、通信インフラの整備が進んでいない地域に対する、所謂ディジタル・ディバイドの解決に有効である。i-space計画では、国際協力・貢献、特にアジア・太平洋地域との連携を重視するべきである。
4. 高速インターネット衛星について
4.1 意見
- i-spaceという利用を含めた構想を中心に、衛星計画を考える方向は評価出来る。
その中での高速インターネット衛星の具体的な内容については、今後i-spaceのシナリオの練り上げの進展、ETS-VIIIの結果等に基づいて柔軟に対応して行けるものでなければならない。従って高速インターネット衛星の具体的な仕様・設計については、本評価報告書に沿って、今後更に慎重に検討することを期待する。その内容については、今後の適切な時期に、本部会に於いて改めて検討を行う。 - 高速インターネット衛星の内容の具体的計画に当たっては、前年度、前々年度の軌道上技術部会評価報告に示した「ひとつの衛星が、致命的な結果をもたらし得るリスクを、複数持つ計画は行うべきでない。」という意見に十分留意して進める必要があることを指摘しておく。
- ETS-VIIIについては、評価委員会発足(前々年度)以前に既に計画が進展しており、変更・見直しは無理であったが、前年度、前々年度の報告に意見を述べて来た。それに基づきNASDAの対応が行われているものと期待するので、今回は評価の対象としない。しかしながら、ETS-VIIIの結果は、高速インターネット衛星計画、更にはi-space計画そのものに大きな影響を与えるものであることを認識する必要がある。
4.2 指摘事項
- 既存の衛星プロジェクト(ETS-VIII)を、i-space構想に統合していくのであれば、今後i-space構想を改良して行く過程で、そのストーリーに従って、高速インターネット衛星はもとより、既存の衛星計画の中身(少なくとも実験計画)にもフィードバックを掛けて行く必要がある。
- i-space構想を進めるに当たって、計画の範囲と規模、従って衛星の構成と大きさの妥当性に関して十分な検討と評価が行われなければならない。
例えば、衛星のサイズを決める絶対的前提条件にH-IIAがあるのではないか。何故、4.6トン衛星なのか。何故、実証実験に4ビーム、3ビームが必要なのか、2ビームではどうして駄目なのか。何故、3種類のデータレート、アンテナサイズが必要なのか。ユーザ端末がi-spaceの計画やスケジュールに対応して商業的に可能なのか。等々の疑問が委員から指摘されている。
先ず、超高速通信の実験・実証をどこまでするか、ディジタル・ディバイドにどう対応するのか等という目的やニーズを明確に検討するべきである。それに基づき必要なサービスやシステム、更に衛星の設計についての比較・評価(Competitive Design,Comparative Evaluation)を行うべきである。 - 同時に、i-space計画が、衛星通信における先端技術の開発に於いて、当面我が国にとって唯一の機会であり、国際的貢献の視点からも重要であることを十分認識し、新しい周波数分野の開拓、先進的モデムの開発等、実用・商用的見地と共に、長期的視点に立った技術開発についても、十分に目配りしたものとすることが期待されている。
- i-space計画の将来への展開、更には通信衛星計画の今後について本質的な議論を行うべきである。
5. 準天頂衛星(8の字衛星)
本衛星については、部会において一通りの説明がなされたが、今後どのように進めるべきかについて、柔軟に検討を進める必要がある。以下に、委員の意見の中から主要なものを示す。
- 本衛星システム実現には、一部産業界も参加に積極的と伝えられている。明確なニーズと確実な利用計画を踏まえた衛星計画を、産業界の参加を得て共同で進めることも、ひとつの選択肢として真剣に検討する価値があると思われる。将来の宇宙開発において、国と産業界が名実ともにイコール・パートナーとして協力するための、初めての雛型とするには最適である。
- 衛星としては、出来るだけ小型・単純で、安価なものとして、このような方式の実用システムとしての有用性のデモンストレーションに集中してはどうか。
- 利用では、GPSの補間・補正情報や補足・更新データ等の提供、地図配信等の測位サービスやエンターテインメント、アミューズメントを中心とした移動体放送サービスとして有効と思われる。
GPSは軍用の目的のために開発・展開されたシステムであるが、民間の利用にも限定的に開放・運用されて来た。各種衛星システムの中では、通信衛星以上に多くのユーザにより、幅広く・多様に、活発に・有効に利用されている。しかし、導入以来約20年が経過し、次期システム導入の必要性が視野に入って来ている。軍用を目的とするものであることから、民間利用者の不便・不満も多く、ヨーロッパでは独自システムの導入を計画しており、我が国においても種々の検討が行われてきた。米国ではGPS後継システムを世界の標準システムとして維持するため、政治的働きかけを強力に進める一方、SA(民用の精度を意図的に劣化させるために周波数を揺する)の廃止等の改善を行って来ている。
国際的協調・協力、コスト・パフォーマンス等の見地から見れば、今後我が国が独自で同等システムを保持・運用するメリットは必ずしも大きくなく、そのような可能性は薄いが、幅広い調査・研究、先端的技術の開発、精度や利用の便宜性の向上のための各種改善・改良やそのための支援システムの整備・運用等は必要であり、有用である。特に我が国は世界的に見ても、カーナビから地震予知まで、幅広く高度な利用が最も活発に行われており、ニーズも大きく、システム導入には高い効果が期待できる。更に、アジア・太平洋地域への貢献も可能である。
6. まとめ
頭書の経緯に述べた通り、本評価は突然必要となったことから、国内委員のみで開催するという正常でない形をとることになった。
しかしながら、逆風と様々な環境の急激な変化から出てきた「i-space」構想は、計画の詳細は更に検討・充実すべきであるが、今後の我が国における衛星通信の開発の新しい方向を示唆するものと期待されるため、「i-space」計画は積極的に進められるべきであると評価する。
衛星通信は、宇宙開発・宇宙利用の中で、唯一商業化が実現し、今後も可能な分野である。「i-space」構想が、我が国の宇宙開発の改革の糸口になることを期待したい。そのためにも、開発・利用に係わる産・学・官の幅広い全てのコミュニティの、前向きで積極的な参加が成功の鍵であり、NASDAは、世話役として貢献することを期待する。
付録1 平成12年度 宇宙開発事業団評価委員会 軌道上技術評価部会 国内評価委員会合 議事次第
開催日程:平成12年7月21日(金) 10:00〜17:30
開催場所:宇宙開発事業団 本社28階 第1・2会議室
| 10:00〜10:10 | 開会挨拶、議事確認等 |
| 10:10〜11:00 | (1)NASDAの現状 |
| 10:10〜10:40 | i H-II8号機失敗の原因究明結果 (H-IIAへの反映含む) |
| 10:40〜11:00 | ii 改革推進委員会の開催について (特別会合報告書を受けたNASDAの対応) |
| 11:00〜11:10 | 休 憩 |
| 11:10〜12:00 | (2)衛星システム本部の現状 |
| 11:10〜11:35 | i 衛星システム本部の業務状況報告 |
| 11:35〜12:00 | ii 各衛星プロジェクトの計画変更と進捗状況 |
| 12:00〜13:30 | 昼 食・休 憩 |
| 13:30〜15:00 | (3)新規計画について ・「i-Space計画」について |
| 15:00〜15:15 | 休 憩 |
| 15:15〜17:30 | (4)全体審議 (報告書の作成方向について等) |
| 17:30 | 閉会挨拶 |
| ※18:00〜19:30 | 懇親会(第3会議室) |
付録2 軌道上技術評価部会 メンバー表
| 共同部会長 |
畚野 信義
ジョセフ ペルトン |
| 委員 |
原島 文雄
安田 靖彦
木田 隆
林 理三雄
橋本 和彦
ビノッド モディ
スティーブン ガンター
ジェームス ハミルトン
ニールス ジャンセン |
| 主事 | 木村 真一 郵政省通信総合研究所宇宙通信部宇宙技術研究室 主任研究官 |
宇宙開発事業団評価委員会
第3回技術評価部会評価報告書
技術評価部会
まえがき
宇宙開発事業団評価委員会技術研究部会は、2000年5月26日、宇宙開発事業団芝分室において開かれた。部会は私ども2人が共同部会長を務めた。
SELENE月探査ミッションプロジェクトは、リスク低減と確実なミッションの成功のために見直しの検討がなされており、本部会ではその計画と方向性が評価された。同時に前年度の部会の提言に対する技術研究本部の対応及びこの一年間の同本部の改革の状況についても報告された。認識事項と提言はこの評価報告書に含まれている。
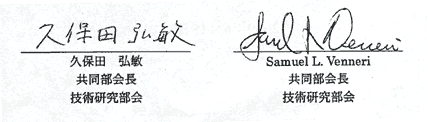
1.はじめに
宇宙開発事業団評価委員会 技術研究部会は2000年5月26日、宇宙開発事業団芝分室においてSELENEプロジェクトの計画見直し案の評価を行うとともに、技術研究本部の改革に関わる進捗状況を確認した。技術研究本部の改革は、21世紀の宇宙開発計画に向けて技術基盤の確立を目的として、外部機関との協力のもと、先端技術の開発を行うものである。本部会は、評価を実施する過程での技術本部からの誠意ある支援に感謝している。
本部会における提言(Recommendation)と認識事項(Findings)を以下に述べる。
2.SELENEプロジェクトに対する提言
- SELENEプロジェクトについては、過去の本部会にて、総合的なリスク管理システムの確立と実行を提言してきた。SELENEプロジェクトの見直し、および宇宙開発事業団、ISAS、NALの3機関共同による計画の実施は妥当であると考える。H-IIロケット8号機の打上げ失敗に伴い、設計上の不確定要素に対してリスク管理を実施し、ミッションを確実に遂行する過程を確立する必要があると本部会は認識している。
- 従来のSELENE計画は統合設計された2つの機体を同時に打ち上げるものであったが、見直しでは2つの機体を別々の打上げ時期とする計画案とした。この変更は、従来のSELENE計画に対して、本部会が総合的なリスク管理を実行するよう求めた提言に宇宙開発事業団が対応した結果である。見直し後のプロジェクトは、SELENE-AとSELENE-Bの2つで構成される。SELENE-Aは2004年に打上げ予定で、周回軌道からの月観測と障害物検知実験を行う。また、SELENE-Bは現在のところ2006年に打上げ予定で、機体を月面に着陸させるものである。本部会は、SELENE-AおよびSELENE-B計画を確実に遂行するための重要な技術開発も含め、この見直し計画およびリスク低減への取り組みは妥当であると考える。この取り組みには、FEMA (Failure Effects and Mode Analysis)やFTA (Fault Tree Analysis)などの手法を取り入れることも含むものとする。こうした手法を取り込むことにより、リスクを全ライフサイクル設計過程の要素の一部としてとらえ、SELENE-AおよびSELENE-Bで必要な技術活動を位置付けることに活用できる。
- SELENE-A計画では、当初行われる予定だった月の秤動計測が削除されたが、VLBI機能を搭載した小型衛星(VRAD)が月周回軌道に投入され宇宙空間でのVLBI観測を実施する。この変更により、従来のSELENE計画に比べて2〜3倍の高精度な月の重力場計測が可能となる。1年間の観測ミッションにおける目的は達成されると考えられる。重量余裕に伴う推薬増分を利用してミッション期間を延長し、より多くの知見を得ることも検討しているが、これも可能と考えられる。また、設計変更された機体では、障害物検知の基礎的実験が可能である。本部会では、SELENE-Aで実施される障害物検知・回避機能実験を、SELENE-B開発のリスク低減化戦略に含むよう提言する。
- SELENE-B計画における月着陸ミッションでは、障害物検知・回避、転倒防止などの技術開発を達成できるよう努力が必要である。本部会は、このプロジェクトを通じて得られる技術成果の重要性を認識している。地上からの介入なく、自律的に着陸することがもっとも挑戦的なミッションリスクとされる。現在までのプロジェクト計画ではハードウェア開発および検証に重点が置かれ、難度の高い軟着陸フェーズ用ソフトウェア開発および検証作業の重要性についてはまだ十分に示されていない。
- SELENE-B計画にNALが参加したことで、日本の3主要宇宙機関が協力してプロジェクトを推進することとなった。本部会は、各機関により文化的土壌が違うことを認識しており、タイムリーな意思決定ができる統一のとれたプロジェクト体制を構築することが必要であると再度強調しておく。
- 本部会は、SELENEプロジェクトは、日本の将来の宇宙技術の可能性に大きな影響力を持ち、その技術成果から将来宇宙開発事業団がより複雑な宇宙ミッションを計画・実行していく能力を修得することに寄与すると認識している。
3.認識事項
- 技術研究本部は、1999年6月の部会提言に対応して、内部改革を計画し、具体化してきたと認識している。
- 技術研究本部が今日までに取り組んできた改革の計画および成果を確認した。
- 宇宙開発事業団の全体方針の見直しに伴い、技術研究本部は1999年に策定した2つの基本方針(技術研究本部は宇宙開発事業団の技術の創造、蓄積、継承の中核組織であること、および高度な技術を有する専門集団となること)を堅持しつつ、その改革を進めている。全体的に、改革は着実に進められている。
- 技術研究本部の改革方針は、研究総監と各専門グループの意見交換会、および主任調整会における研究目標や予算配分に関する議論を通して次第に各技研職員に浸透しつつある。
- 研究構想、概念設計の実施体制、および関係諸機関との連携を通じて、研究およびプロジェクト計画の立案が強化されつつある。
- 専門家の育成、および先端的なプロジェクト連携研究を通して、プロジェクトの確実な実施に貢献しつつある。
- 試験技術室の業務を、試験運用から解析・検証に重点を移し、またシステム解析ソフトウェア研究開発センターの設立により、試験検証の過程が強化されると考えられる。また宇宙開発事業団は、IV&&V (Independent Verification && Validation)を計画し、各結果を専門家の立場から独立評価するシステムを確立し、ソフトウェアの確実な開発と信頼性向上を図る計画である。
- 外部研究者に開かれた研究体制が強化されている。
- 本部会は、現在までに達成された成果は認めるが、現在進めている改革をさらに推進し、技術的専門能力を高め、研究の人的資源を増加させる努力が必要であると認識する。
- 技術研究本部は、研究開発資金や新しい技術成果が日常生活にどのような影響を与え、今後どのような利益を提供できるかを社会に明確に示すような展開過程を本部の計画に加えるよう提言する。
4.要約
本部会は、SELENEプロジェクトの見直し計画を評価し、リスク低減を図るためにSELENE-AとSELENE-Bシステムの2つのフェーズ分割し、それぞれ独立して打ち上げるとしたことは妥当であると考える。また、ミッションサクセスの観点から各フェーズの技術活動を位置付けることの重要性と、開発サイクルの全フェーズにおいてリスク評価ツールを正規に取り入れ、実行する必要性をここで再度強調する。本部会は、この評価にあたり報告された技術研究本部の活動は、全体的に満足すべきものと認識している。
技術研究部会 委員名簿
| 共同部会長 | 久保田 弘敏 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻 教授
サミュエル・L.ヴェンネリ |
| 部会委員 | 畚野 信義(財)テレコム先端技術研究支援センター 専務理事
木田 隆
高木 幹雄
武田 峻
戸田 勧 |
| 主事 | 新城 淳史 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻 |
部会スケジュール
平成12年5月26日(金)
| 09:30 | 挨拶(宇宙開発事業団 五代理事長代行) |
| 09:40 | 事務連絡等 |
| 09:45 | 提示資料等説明(質疑応答を含む) |
| -H-IIロケット8号機の失敗関係 | |
| -SELENEリスク低減策関係 | |
| -技術研究本部の改革関係 | |
| 12:20 | 昼食 |
| 13:30 | 評価部会審議、報告書作成(クローズド・ミーティング) |
| 17:45 | 宇宙開発事業団への評価結果の通知 |
| 18:20 | 部会終了 |
宇宙開発事業団評価委員会
第3回技術評価部会評価報告書
技術評価部会
まえがき
宇宙開発事業団評価委員会技術研究部会は、2000年5月26日、宇宙開発事業団芝分室において開かれた。部会は私ども2人が共同部会長を務めた。
SELENE月探査ミッションプロジェクトは、リスク低減と確実なミッションの成功のために見直しの検討がなされており、本部会ではその計画と方向性が評価された。同時に前年度の部会の提言に対する技術研究本部の対応及びこの一年間の同本部の改革の状況についても報告された。認識事項と提言はこの評価報告書に含まれている。
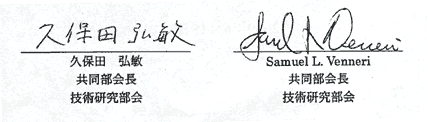
1.はじめに
宇宙開発事業団評価委員会 技術研究部会は2000年5月26日、宇宙開発事業団芝分室においてSELENEプロジェクトの計画見直し案の評価を行うとともに、技術研究本部の改革に関わる進捗状況を確認した。技術研究本部の改革は、21世紀の宇宙開発計画に向けて技術基盤の確立を目的として、外部機関との協力のもと、先端技術の開発を行うものである。本部会は、評価を実施する過程での技術本部からの誠意ある支援に感謝している。
本部会における提言(Recommendation)と認識事項(Findings)を以下に述べる。
2.SELENEプロジェクトに対する提言
- SELENEプロジェクトについては、過去の本部会にて、総合的なリスク管理システムの確立と実行を提言してきた。SELENEプロジェクトの見直し、および宇宙開発事業団、ISAS、NALの3機関共同による計画の実施は妥当であると考える。H-IIロケット8号機の打上げ失敗に伴い、設計上の不確定要素に対してリスク管理を実施し、ミッションを確実に遂行する過程を確立する必要があると本部会は認識している。
- 従来のSELENE計画は統合設計された2つの機体を同時に打ち上げるものであったが、見直しでは2つの機体を別々の打上げ時期とする計画案とした。この変更は、従来のSELENE計画に対して、本部会が総合的なリスク管理を実行するよう求めた提言に宇宙開発事業団が対応した結果である。見直し後のプロジェクトは、SELENE-AとSELENE-Bの2つで構成される。SELENE-Aは2004年に打上げ予定で、周回軌道からの月観測と障害物検知実験を行う。また、SELENE-Bは現在のところ2006年に打上げ予定で、機体を月面に着陸させるものである。本部会は、SELENE-AおよびSELENE-B計画を確実に遂行するための重要な技術開発も含め、この見直し計画およびリスク低減への取り組みは妥当であると考える。この取り組みには、FEMA (Failure Effects and Mode Analysis)やFTA (Fault Tree Analysis)などの手法を取り入れることも含むものとする。こうした手法を取り込むことにより、リスクを全ライフサイクル設計過程の要素の一部としてとらえ、SELENE-AおよびSELENE-Bで必要な技術活動を位置付けることに活用できる。
- SELENE-A計画では、当初行われる予定だった月の秤動計測が削除されたが、VLBI機能を搭載した小型衛星(VRAD)が月周回軌道に投入され宇宙空間でのVLBI観測を実施する。この変更により、従来のSELENE計画に比べて2〜3倍の高精度な月の重力場計測が可能となる。1年間の観測ミッションにおける目的は達成されると考えられる。重量余裕に伴う推薬増分を利用してミッション期間を延長し、より多くの知見を得ることも検討しているが、これも可能と考えられる。また、設計変更された機体では、障害物検知の基礎的実験が可能である。本部会では、SELENE-Aで実施される障害物検知・回避機能実験を、SELENE-B開発のリスク低減化戦略に含むよう提言する。
- SELENE-B計画における月着陸ミッションでは、障害物検知・回避、転倒防止などの技術開発を達成できるよう努力が必要である。本部会は、このプロジェクトを通じて得られる技術成果の重要性を認識している。地上からの介入なく、自律的に着陸することがもっとも挑戦的なミッションリスクとされる。現在までのプロジェクト計画ではハードウェア開発および検証に重点が置かれ、難度の高い軟着陸フェーズ用ソフトウェア開発および検証作業の重要性についてはまだ十分に示されていない。
- SELENE-B計画にNALが参加したことで、日本の3主要宇宙機関が協力してプロジェクトを推進することとなった。本部会は、各機関により文化的土壌が違うことを認識しており、タイムリーな意思決定ができる統一のとれたプロジェクト体制を構築することが必要であると再度強調しておく。
- 本部会は、SELENEプロジェクトは、日本の将来の宇宙技術の可能性に大きな影響力を持ち、その技術成果から将来宇宙開発事業団がより複雑な宇宙ミッションを計画・実行していく能力を修得することに寄与すると認識している。
3.認識事項
- 技術研究本部は、1999年6月の部会提言に対応して、内部改革を計画し、具体化してきたと認識している。
- 技術研究本部が今日までに取り組んできた改革の計画および成果を確認した。
- 宇宙開発事業団の全体方針の見直しに伴い、技術研究本部は1999年に策定した2つの基本方針(技術研究本部は宇宙開発事業団の技術の創造、蓄積、継承の中核組織であること、および高度な技術を有する専門集団となること)を堅持しつつ、その改革を進めている。全体的に、改革は着実に進められている。
- 技術研究本部の改革方針は、研究総監と各専門グループの意見交換会、および主任調整会における研究目標や予算配分に関する議論を通して次第に各技研職員に浸透しつつある。
- 研究構想、概念設計の実施体制、および関係諸機関との連携を通じて、研究およびプロジェクト計画の立案が強化されつつある。
- 専門家の育成、および先端的なプロジェクト連携研究を通して、プロジェクトの確実な実施に貢献しつつある。
- 試験技術室の業務を、試験運用から解析・検証に重点を移し、またシステム解析ソフトウェア研究開発センターの設立により、試験検証の過程が強化されると考えられる。また宇宙開発事業団は、IV&&V (Independent Verification && Validation)を計画し、各結果を専門家の立場から独立評価するシステムを確立し、ソフトウェアの確実な開発と信頼性向上を図る計画である。
- 外部研究者に開かれた研究体制が強化されている。
- 本部会は、現在までに達成された成果は認めるが、現在進めている改革をさらに推進し、技術的専門能力を高め、研究の人的資源を増加させる努力が必要であると認識する。
- 技術研究本部は、研究開発資金や新しい技術成果が日常生活にどのような影響を与え、今後どのような利益を提供できるかを社会に明確に示すような展開過程を本部の計画に加えるよう提言する。
4.要約
本部会は、SELENEプロジェクトの見直し計画を評価し、リスク低減を図るためにSELENE-AとSELENE-Bシステムの2つのフェーズ分割し、それぞれ独立して打ち上げるとしたことは妥当であると考える。また、ミッションサクセスの観点から各フェーズの技術活動を位置付けることの重要性と、開発サイクルの全フェーズにおいてリスク評価ツールを正規に取り入れ、実行する必要性をここで再度強調する。本部会は、この評価にあたり報告された技術研究本部の活動は、全体的に満足すべきものと認識している。
技術研究部会 委員名簿
| 共同部会長 | 久保田 弘敏 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻 教授
サミュエル・L.ヴェンネリ |
| 部会委員 | 畚野 信義(財)テレコム先端技術研究支援センター 専務理事
木田 隆
高木 幹雄
武田 峻
戸田 勧 |
| 主事 | 新城 淳史 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻 |
部会スケジュール
平成12年5月26日(金)
| 09:30 | 挨拶(宇宙開発事業団 五代理事長代行) |
| 09:40 | 事務連絡等 |
| 09:45 | 提示資料等説明(質疑応答を含む) |
| -H-IIロケット8号機の失敗関係 | |
| -SELENEリスク低減策関係 | |
| -技術研究本部の改革関係 | |
| 12:20 | 昼食 |
| 13:30 | 評価部会審議、報告書作成(クローズド・ミーティング) |
| 17:45 | 宇宙開発事業団への評価結果の通知 |
| 18:20 | 部会終了 |
宇宙開発事業団評価委員会
第3回地球観測部会評価報告書
地球観測部会
地球観測部会共同部会長 署名
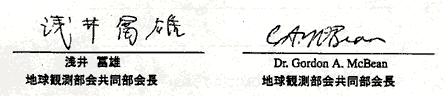
概要
地球観測部会は、地球観測分野の研究開発課題を評価し、宇宙開発事業団(NASDA)が平成13年度に実施するプロジェクトへの助言をするために、平成12年3月21日〜23日にNASDAの地球観測データ解析研究センター(EORC:東京)で開催された。部会は、地球環境変動観測ミッション(GCOM)プログラム、特にGCOM-A1衛星プロジェクトの検討、及び国際的な全球降雨観測ミッションへ搭載する二周波降雨レーダの研究についての検討を依頼された。
部会は、GCOM全体の目標を支持するとともに、これを率先して行うことは、地球環境変動を観測し、理解し、予測するための世界的努力に大きく貢献すると考える。GCOMは、観測の継続性や効率的な科学利用を技術的、制度的に約束した15年にわたる枠組みと見るべきであり、部会は、その実施にあたって、科学コミュニティを幅広く取り込んだ新しい組織的な進め方を行うべきとの提言をした。また、研究開発機関であるNASDAと、関係する定常利用者及び政府の政策決定機関との、業務上の連携を強化する事が重要であると考える。国際的には、NASDAは、他の地球観測プログラムや統合地球観測戦略(IGOS)との関係において、GCOMプログラムの所定の役割を明確に示す必要がある。NASDAは、どの分野でイニシアティブを取り、国際的なコミュニティを先導していきたいのか、またどの分野では、他機関の活動を補完する、あるいは強化することを目的にしたいのかを明確に示すべきである。
部会は、GCOM-A1ミッションが、時宜を得たかつ潜在的にとても重要な観測、特にオゾン層破壊に関する観測を実現すると考えるとともに、オゾン層破壊や気候変動の研究に対するエアロソルデータの重要性を強調した。GCOM-A1は、京都議定書及びモントリオール議定書に関連した重要な過程の理解をすることに貢献するであろう。温室効果ガスについては、そのデータ利用についての明確で詳細かつ一貫した科学的戦略が策定されるべきである。部会は、SOFISから得られる情報が、大気物理化学システムの研究に効果的に使うことができるであろうと考え、可能な測定方法とのバランス及び他のミッションとの可能な連携を検討することを提案する。また、NASDAと環境庁は、プログラムの成果を最大限に引き出すために、別々の処理からのデータを後で統合するための措置をとるよう提言する。
部会は、熱帯降雨観測衛星(TRMM)の成功を認めるとともに、二周波降雨レーダ(DPR)の研究という新しい提案を強く支持する。TRMMプログラムにおいて、NASDAは、気候変動研究及び地球環境変動研究の重要な領域において、真の科学的リーダシップを発揮してきた。
また、平成10年7月の第1回会合における部会からの提言に対してNASDAが対応し、さらに提言に関する見直しを進展させるつもりであることに、全般的に満足している。
はじめに
地球観測部会は、平成12年3月21日〜23日に宇宙開発事業団(NASDA)の地球観測データ解析研究センター(EORC:東京)で開催され、NASDAから資料説明を、また環境庁環境研究所(NIES)及び郵政省通信総合研究所(CRL)から補完的な説明を受けた。部会会合中のNASDAスタッフの優れた対応ぶりと事務局サポートに感謝したい。また、部会委員のうち数名は、3月24日に筑波宇宙センターを訪問した。
地球観測部会は、地球観測分野の研究開発課題を評価し、NASDAが平成13年度に実施するプロジェクトへの助言をすることを目的として開催された。部会会合の議事次第と出席者リストを添付する。
部会は、地球環境変動観測ミッション(GCOM)プログラム、特にGCOM-A1衛星プロジェクトの開始、及び熱帯から亜寒帯までの降雨構造を観測するTRMM後継ミッションとしての国際的な全球降雨観測ミッションへ搭載する二周波降雨レーダ(DPR)の研究についての検討を依頼された。GCOMの全般的な目的は、地球温暖化、気候変動、オゾン層破壊等を理解するため、地球物理量を観測することにあり、最初の衛星ミッションであるGCOM-A1の具体的な目的は、オゾン層と温室効果ガスの観測にある。評価の目的は、平成13年度にGCOM-A1及びDPRの開発を進める決定をするにあたって、科学的な情報を提供し支援することにある。
部会は、以下の項目についての評価を行うことを依頼された。
- プロジェクトの目標
- プロジェクトの意義
- プロジェクトの企画立案プロセス
- 調達方針
- 技術開発及びその利用
- 信頼性品質管理
- 計画のトータルコストとスケジュール
- 失敗から学んだこと及びリスク管理
しかしながら、時間的制約、部会委員の専門性、提示された資料から、結果的に1、2、3、5、8の項目の評価が中心となった。また、NASDAが共同議長の助言を得て、GCOM-A1ハードウェアに関する4、5、7の項目を中心とした評価のために分科会を設置したことは、時宜を得たものと考える。
地球環境変動観測ミッション(GCOM)プログラム
部会は、設定された15年間にわたって、全球システムの変動を系統的に観測するという包括的なプログラムとして、GCOMの打ち上げを決定することは戦略的に重要であると認識する。また、GCOM全体の目標を支持するとともに、これを率先して行うことは、地球環境変動を観測し、理解し、予測するための世界的努力に大きく貢献すると考える。GCOMは、日本が宇宙からの地球環境変動研究への継続的な貢献を約束するにあたり、踏むべき段階であり、そのミッションは、衛星プロジェクトの一貫したシリーズとしてのみならず、観測の継続性や効果的な科学利用を技術的、制度的に約束する枠組みと見るべきである。このためには、校正、検証、データ管理に必要不可欠な要求はもとより、科学の発達やデータ利用、そして政策決定の支援に必要な新しい制度的関係を構築するところにまで範囲を広げる必要がある。
GCOMは、15年間継続されることを前提とすると、必要とされる制度的関係は長期的視野で構築されるべきである。日本政府が大きく再編されるこの時期に、新しい組織的な手続きが開始しやすいと考えられることから、部会は、今NASDAがこれを実行することを提言する。この観点から、間もなく行われる科学技術庁と文部省の合併は、きわめて重要である。
観測機器サイエンスチームへの科学者の参加
特に問題として考えられるのは、主に国立研究所やNASDA自身の研究者から成る中心的な専門家集団の外にいる科学者は、NASDAの衛星に搭載する主な観測機器の検討や開発への積極的な参加が限られていることである。大学その他で地球観測の専門技術を育てることで、これらのプロジェクトに従事する科学者を増やすことは、NASDAにとって利益となることを強調したい。このための資金提供は、NASDAと関係の深い宇宙技術や管理の問題に有能で役立つ科学者グループを形成するであろう。センサ開発チームに参加する科学者は、NASDAのプロジェクトを実施する際に、あらゆる場面で活躍するであろう。
機関間協力
研究開発機関であるNASDAと、関係する定常利用者及び政府の政策決定機関との業務上の連携を強化する事が重要であると考える。地球環境変動問題は、非常に学際的な問題であり、様々な分野の科学技術を支援する機関間の業務上の連携を促進するとともに、科学者間の学際的な協力奨励していくことが必要である。NASDAにとっての挑戦は、a)地球科学研究への貢献、b)データ応用・利用の促進、c)技術開発の推進という、NASDAの使命の中で同じように重要な3つの側面の間の適切なバランスを維持することである。
NASDAと他機関の連携を強化することは必要であり、特に情報の最適な利用を促進するために(例えば、対流圏オゾンの推定値といったより進んだ要求の成果物を導くために、SOFISとODUSのデータの複合利用を進めるということ)、データ処理を分担すること及びデータの標準を統合することの調整が必要である。この領域においては、気象庁や環境庁といった機関との協力は必須である。
国際的な状況の中でのGCOMの役割
GCOMは、地球システムを全球的に観測することにより、気候や地球環境の理解を深める世界的取り組みの一端を担うこととなる。NASDAは、世界中の他の宇宙機関が計画している地球観測プログラムとの関係において、GCOMプログラムの所定の役割を明確に示し、統合地球観測戦略(IGOS)へのGCOM独自の貢献を見極める必要がある。この時、GCOMの包括的な目的と、実際に行われる具体的な観測との間の関係を解析することが必要であると考える。それぞれの観測センサの科学的な役割は、一般的な科学的優先順位及び国際的な協力の機会もしくは約束との関係でまとめられるべきである。
NASDAは、どの分野でイニシアティブを取り、国際的なコミュニティを先導していきたいのか、またどの分野では、他機関の活動を補完するあるいは強化することを目的にしたいのかを明確に示すべきである。TRMMの実現において、NASDAとCRLが先駆的努力をしたことは、前者の良い例である。降雨レーダの開発を引き受けたことは、宇宙からの気候観測を大きく前進させることにつながった。これが世界から広く成功と認められたことで、NASDAはさらに開発を進められる上に、全球水循環の観測で長期的に先導的役割を果たすこととなった。
GCOMプログラムのそれぞれの観測項目により、求められる具体的な目的は以下のとおりであろう。
- リーダシップ
最先端をさらに越えて進み、新しい世界標準を構築するような(国際的地球観測システムの規模を広げつつ)、新たなまたは高度化した観測手法や成果物を開発する可能性を探ること。 - 補完的貢献
相互バックアップの協力及び不慮の事故のリスク緩和(国際的な地球観測システムを増強して)を最適化する観点で、GCOMデータの成果物を他の宇宙機関の既存もしくは計画中のプログラムと適合性を取ること。 - 協力
他機関や研究者グループと協力して努力する機会を見つけるとともに、GCOMサイエンスチーム及びNASDAのプログラムマネージャの役割として機関間/国際的な協力活動を組織的に行うためのガイドラインをとりまとめること。
部会は、この問題について大きく注目し、GCOM開発計画をレビューした結果、以下のような例をあげた。
- 次世代グローバルイメージャ(SGLI)システムは、他に類を見ない海洋観測センサであり、海色チャネルとティルトビーム機能(太陽反射光問題を最小にするため)が完全に整っており、午前軌道に打ち上げられる予定である(将来、米国のNPOESSという定常運用衛星が、決して最適ではない夜明けの薄暮時と午後の早い時間の軌道に投入される予定である)。この開発において、NASDAは、海色観測と系統だった海洋基礎生産量の観測の分野を先導する機会を得る。
- SGLIの陸域及び大気の観測能力は、NASAのEOS-TerraやAquaといった同世代の観測システムと遜色は無いし、EOSからNPOESSにいたるミッションと整合が取れるであろう。この場合、中分解能の陸域観測(これに適合したデータの流れも提供することにより)について観測範囲を広げ、長期間にわたって継続することを、第一の目標にすべきことである。
- 米国のジェット推進研究所(JPL)との協力により、ADEOSからGCOM-Bにわたるシリーズ衛星は、能動型マイクロ波センサ(NSCAT、SeaWinds、そして将来の風観測散乱計であるAlphaScatのような)により、高精度の海上風観測を行う比類のない能力を持つ。この分野において、当然にとるべき道は、NASAとの協力である。
NASDAの長期シナリオの策定は、注意深い検討を要する。従来、宇宙機関は、それぞれ他に依存することなく、全ての範囲の地球観測システムを開発する努力をしてきた。あるひとつの機関が、その機関自身の要求及び他の機関の要求に合ったある特定の観測に責任を持つような、機関間の提携に向けた展開を提言したい。これは、機関間のみならず、世界中の科学者のコミュニティとの間において、観測のある分野における(共通の観測目的を確認し、観測戦略を決定し、成果について議論する等のために)関係を徐々に効率的なものとするために主体的な役割を果たすことを意味する。このような目的をまとめる上で重要なのは、観測目的を最初から明確にすること(例えば、一度だけの「プロセス研究」なのか、長期にわたる気候変動研究のための期間を限定しない観測なのか)と、他の観測センサや他の観測方法との可能な連携を検討することである。
国際的なシステムによってデータ成果物の継続性を保つことは重要である。NASDA及び他の宇宙機関は、観測データを交換及び複合利用することでデータセットの品質を最大限に高めることを協力して行うべきである。NASDAは、ある分野に責任を持ち、その分野においてNASDAのみならず他機関の観測センサをも用いて、国際的なデータセット作成の努力をするために、協力機関の支持を得ることができるであろう。
GCOM衛星コンフィギュレーション
GCOMプログラムの最初の2つのフライトミッションは、2つのかなり異なる衛星を使用する点が注目される。すなわち、J-2ロケットで打ち上げられる1トンクラスの衛星(GCOM-A1)と、より大きなH-IIAロケットで打ち上げられる2トンクラスの衛星(GCOM-B1)である。部会は、可能ならば3つの1トンクラスの衛星に観測センサを搭載することで、最初のGCOMミッション間の共通性をより高めようとすることが適当ではないかと考える。これにより、システムの複雑さが低減され、開発が早くなるとともに、新しい技術を積極的に導入するための柔軟性が付加されることとなろうが、一方で、GCOM-Bシリーズでの異なった観測センサ間の連携が失われることとなる。
部会は、1つの衛星に2つのマイクロ波センサ(AMSRと海上風散乱計)を搭載することは、重要な利点であると判断する。一方で、これらのセンサと他の観測方法との連携の有効性も検討する必要がある。
資源配分(人員及び予算)
部会からの質問に対して、GCOM-A1とGCOM-B1の開発スケジュール(約6ヶ月間隔)は、NASDAのプログラム全体から見て、過度な負担とはならないとの説明があった。部会は、NASDAが、予算的、人的リソースの観点からGCOM-A1とGCOM-B1の最適なスケジュールを検討すべきことを提案する。
GCOM地上システム運用の最適化
部会は、2つの異なる軌道に打ち上げられる2つのGCOM衛星を運用する地上システムを最適化するためのさらなる検討を提言する。
GCOM-A1
部会は、GCOM-A1全体の目的から、以下の科学的価値や社会的重要性をおおよそ理解した。
「CO2、CH4等の温室効果ガスやオゾン層の観測により、温室効果ガスの輸送メカニズム、オゾンの輸送プロセス、オゾン層破壊のメカニズム、地球温暖化及びオゾン層変動の研究及びその予測についての解明に寄与すること」
GCOM-A1のミッションは、時宜を得たかつ潜在的にとても重要な観測であり、特にオゾン層破壊の問題に関する観測を実現すると考える。成層圏オゾン破壊と回復の問題には、さらなる観測と研究が必要であり、部会は、ディレクター及びGCOMプログラムサイエンティストがEORCに加わったことは、オゾン研究を強化する求心力ができたものと考える。オゾン全量観測にはギャップが生じるが(TOMSの追加ミッション、ヨーロッパのENVISATやアメリカのEOS-Aquaに搭載されるオゾン観測センサを含む他の宇宙からのオゾン観測システムが、近い将来打ち上げられるとしても)、GCOM-A1は平成22年(2010年)以前の期間に生じるそのギャップを埋めることとなろう。部会は、オゾン層破壊及び気候変動研究に対してエアロソルの観測が重要であること、特に周辺とはっきり区別できるようなバイオマス燃焼によるエアロソルの情報が重要であることを強調した。オゾン観測センサ(ODUS)のような分光計は、2つもしくは3つの重要なチャネルを持つ多分光放射計よりも、この点に関してかなりよいものである。GCOM-A1は、上で述べた問題を全て解決するように設計されたものではないが、京都議定書及びモントリオール議定書に関連した重要な過程の理解に貢献するであろう。
SOFISは、広範な化学物質、主として長期間存在する温室効果ガスを測定する予定である。部会は、SOFISが大気物理化学システムの研究に効果的に使われるであろうと考える。ILAS及びILAS-IIの後継センサとして、SOFISは、成層圏オゾン破壊の原因となる広範な化学物質を測定する潜在的能力がある。SOFISの機器(フーリエ変換分光計)としての感度及び広い分光幅によって、5km以上の上空で観測されるオゾン化学に影響を与える広範な活性化学物質の検知が原理的に可能になる。現状のSOFISの設計は、そのトレードオフにおいて、鍵となる多数の分子もしくは前駆体を検知できるであろう高い分光分解能を犠牲にして、垂直分解能を優先している。高い垂直分解能は、成層圏及び/もしくは対流圏の交換プロセスの物理化学研究を実施する上で必須であると認識されている。部会は、機器設計者(環境庁サイエンスチーム)が、可能な測定手法とのバランスを検討し、国際宇宙ステーション及び他のミッションで計画されている大気化学測定との可能な連携も考慮することを提案する。
部会は、成層圏及び対流圏上部の温室効果ガスの分布について得られた情報からは、地球表面の発生源と吸収源を測定するという主要な科学的疑問を解決するには至らないと考える。後者の目的のために、対流圏下部が観測できる直下視の観測センサが必要であろう。
ODUSとSOFISの組み合わせ及び連携は、刺激的な結果を生み出すであろう。しかしながら、NASDA(ODUS)と環境庁(SOFIS)が別々に生成する2つのデータの流れを1つにしようとする努力は、少ししかはらわれていないと思われる。データのアクセス性は重要な問題である。部会は、プログラムの成果を最大限に引き出すために、別々の処理からのデータを後で統合するための措置をとるよう提言する。
GCOM-A1ミッションが、現状の計画では、必ずしもGCOMプログラム全体の広範な目標のすべてを満足させるものではないが、特にオゾン破壊と回復に影響を及ぼすプロセスについて、現状の成層圏化学についての理解と知識をかなり深める可能性がある。
この点について、部会は以下を提言する。
(a)ODUSとSOFISからの科学的利益を十分引き出すために、別々のデータの流れ(そして、もちろん、国内外のデータソースからの適当なデータの流れとも)の統合を促進するため、対策を明確にとるべきである。
(b)成層圏オゾン破壊と回復に影響を及ぼす化学物質を特定するため、SOFISの設計において、より広範な化学物質を測定する可能性があるか検討すること。
実行スケジュール
ミッションパラメータの決定に必要な、科学的情報を集める広範で包括的な概念設計フェーズに価値があり、同様にミッションを科学的に完全な状態にするために、実質的な観測センサの校正/システム試験フェーズも重要である。ADEOS-II後の観測の継続性を確保するために、早期打上げは科学的に必要であることも認識している。それでも、部会としては、NASDAの最優先の目標はミッションの信頼性を確保することであり、現在計画されているスケジュールに合わせるために、確立された技術的経験(例えば、適切なエンジニアリングモデルを用いた開発及び試験)からかけ離れ、軌道上での成功に悪い影響を与えることはすべきではないと考える。GCOM-A1は、NASDAが設計する初めての太陽非同期軌道の地球観測衛星であり、特に熱設計についての懸念がある。
二周波降雨レーダ(DPR)
部会は、熱帯降雨観測衛星(TRMM)が成功し、3次元降雨レーダと受動マイクロ波センサがとてもうまく組み合わさって、赤道±35°の降雨推定が実証できていると考える。この結果に基づき、部会は、新しく提案された同様の原理の二周波降雨レーダ(DPR)の研究を強く支援する。DPRは、70°まで降雨観測を拡大する衛星編隊の中心衛星に搭載される予定であり、降雪も含んだ全球降雨プロセスの理解に貢献するであろう。TRMMプログラムに関して、NASDAは、気候変動研究及び環境変動研究の重要な領域において、真の科学的リーダシップを発揮してきた。
さらに、TRMM搭載降雨レーダ(PR)の測定品質は、TRMMマイクロ波観測装置(TMI)の受動放射計データから推定された降雨をかなり改良してきた。これらの進歩は、主に受動型マイクロ波リモートセンシングを基にした将来の定常的な全球降雨観測への道筋をつけるものである。次の段階は、NASAとNASDAが提案している全球降雨観測ミッション(GPM)であり、これはマイクロ波センサのアルゴリズム校正を二周波降雨レーダに依存している。降雨データが天気予報、水文予測及び気候科学応用に重要であることから、GPMが技術的に成功すると定常的な観測プログラムがすぐに必要となるであろう。このため、GPMは「定常観測の先駆的ミッション」として取り扱う必要がある。
少なくとも2つのマイクロ波(雨滴もしくは氷粒子の密度及び大きさの間の不確定さを取り除くため、及び降雪測定の範囲を広げるために)による天気システムの3次元構造の探査ができることが、降雨リモートセンシングのさらなる進展の中心となる。二周波による測定という手法によって、この地球観測センサがGPM編隊及びおそらく地上気象レーダにも、校正装置として扱われるまでの高い能力を持つことになる。この中核センサの中心的機能を考えれば、部会は、DPRの開発を直ちに進めるべきと確信する。
部会では、2つの周波数の観測幅が低い方(220km)に対して、一方がほんの少し(40km)しかない現在の設計の正当性についても議論した。この比較的狭い方の観測幅は、凝結した雲システムの直線横断面が本質的に得られ、他の(観測幅の広い)観測センサと比較のために適切な校正データベースを蓄積する上で十分であると思われる。一方、比較的観測幅の広い方の周波数は、中規模の気象システムの構造及びそれと大気大循環の変動との関係の科学的研究に非常に貴重なデータを提供し続けることになる。
NASDAアクションプランのレビュー
平成10年7月の第1回会合における部会からの提言に対してNASDAが対応し、アクションプランに関するさらなる進展の見直しを継続するつもりであることに、全般的に満足している。
NASDAは、第1回会合における10の提言に対する回答の分析を行い、以下の4つの全般的なトピックとしてまとめた。
(1)全般
(1-1)資源の確保及びバランスの見直し
(1-2)観測の相互協力
部会は、NASDAがGCOMプロジェクトの全体経費のうち、地上システム及び引き続く研究への資源の割り当てを約10%から20%に増やしたことに満足している。また、EORCに割り当てられた資源の増加も重要である。これらは、とても意義深いようにみえるが、今が他の機関や大学によって行われている研究活動へのNASDAの支援をさらに拡大する時であり、NASDAが将来の地球システム科学でイニシアティブを取るため、科学的知見の基礎を広げる投資となる。
この鍵となる考え方は、提言の「他機関との協力及び国際協力」にも述べられている。GCOM-A1及びTRMM後継機の計画段階の最初から、このような協力がSOFISでは環境庁と、DPRでは通信総合研究所との間で始まっている。他の機関、例えば気象庁、大学、国際的な地球科学コミュニティとのさらなる協力の計画は、あまり明確でない。航空機及び衛星観測センサの開発において、専門的技術を持つ日本の学術研究者を巻き込むことは、重要な利益を生み出すし、新しいアイディア、学生、資源をNASDAのプロジェクトにもたらすことになろう。また、外部機関からの専門家を巻き込むことによって、NASDAの関連プロジェクトにこれらの外部専門家を参加させる約束が明確になるし、彼らが広範な仲間のコミュニティと意欲的に交流し、外に対してNASDAの代表として働くこととなる。
NASDAの専門家が統合地球観測戦略(IGOS)の戦略実施チーム(SIT)に参加することについては、部会として実行状況をはっきりと理解し、この活動がどこに向かおうとしているのか、将来像を知りたい。また、部会は、GCOM-B及びTRMM後継機における国際パートナーとの協力においては、GPMの中核衛星及びAlphaSCAT機器等についてのより明確な説明が必要であるとの懸念がある。
ADEOS-IIの打上げ遅延については、そのプロジェクトに割り当てられた資源が、プロジェクトチームを維持し、打上げ準備を支援するに十分であると思われる。ADEOS-II、研究、ALOSデータ利用促進、GCOMプログラムの開始という将来計画については、平成13年度のNASDAの予算要求に含まれているが、これらと同様にとても重要である二周波降雨レーダ(DPR)の予算は明示されていないことが懸念される。
(2)地球科学研究への貢献
(2-1)EORCの強化
(2-2)科学者の参加促進
(2-3)ADEOS解析研究の継続
部会は、追加のスタッフがEORC、NASDAが支援している地球フロンティア研究及びADEOS-IIプロジェクトの代表研究者(PI)に割り当てられたことに満足している。これらの対策は、必要不可欠な科学的任務を遂行するために、EORCの能力を大幅に強化することとなるが、将来にわたる長期計画を立てるべきである。ユーザコミュニティの取り込みについては、ワークショップを計画するという考え方を認めるとともに、これらの科学者をプロジェクトの促進に巻き込むことも重要であると提案する。
上述のコメントのとおり、NASDA外部からの科学者の取り込みには、ワークショップ及び委員会への参加だけでなく、「実質的な」参加を押し進める必要がある。日本の省庁が再編される(特に科学技術庁と文部省)ことから、地球観測研究及び開発を支援するための、NASDA外部の実体のある制度的な枠組みを作り上げるために、ここ数年の間に重要な機会があると考える。
部会は、ADEOSデータの解析研究について繰り返し提言する。
(3)実利用の促進
(3-1)EOCの強化
(3-2)ALOSデータ利用促進
(3-3)データ利用推進センター
部会は、地球観測センター(EOC)の改善がなされたことに満足している。ALOSに関しては、観測を継続することは、長期間のデータ利用プロジェクトを実現するには必須であることから、ALOS後継ミッションの計画を今立ち上げることが重要である。データの利用応用については、日本がアジア太平洋地域の高分解能リモートセンシングの利用応用のために、先導的な役割を果たすべきとの部会提言に関して、日本以外の研究者が参加するための対策がとられたのか、あるいは計画があるのかはっきりしなかった。
(4)技術開発の推進
(4-1)中小型衛星システムの研究
(4-2)ADEOS-II品質評価強化
小型衛星の実現に向けて(3トンのADEOSから2トンのGCOM-Bへ)作業を進めてきたことは認めるが、同じサイズの小型衛星ミッション、すなわち実質的には単一観測ミッションの利点と限界についての検討をさらに進めるべきである。将来計画に関しては、欧州宇宙機関(ESA)と協力して行う雲放射ミッションの研究提案については、NASA、カナダ宇宙庁(CSA)、フランスの宇宙機関(CNES)が計画しているCloudSat-PICASSO/CENAミッションと類似していることから、部会として確信が持てない。NASDAが、上述の先駆的なミッションで予想される新しい科学的成果を越えるような、重要な成果を実際にこのミッションで得ることができるかという懸念がある。
地球観測部会 委員名簿
- 浅井冨雄
科学技術振興事業団「地球変動のメカニズム」研究事務所 研究統括 -
Gordon A. MCBEAN(マクビーン)
カナダ環境庁 次官補Charles F. KENNEL(ケンネル)
カリフォルニア大学サンディエゴ校 スクリプス海洋研究所長真鍋 淑郎
地球フロンティア研究システム 地球温暖化予測研究領域長Pierre MOREL(モレル)
NASA地球科学局 科学顧問高木 幹雄
東京理科大学 基礎工学部 教授竹田 厚
東北文化学園大学 科学技術学部 教授Vibulsresth SUVIT(スービット)
タイ国科学技術環境省次官補
<主事>
本多 嘉明
千葉大学環境リモートセンシング研究センター 助教授<オブザーバ>
久保田 弘敏
東京大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻 教授 (宇宙開発事業団評価委員会幹事) - 印:共同部会長
E2評価スケジュール
- 開催日程 平成12年3月21日(火)〜23日(木)
- 開催場所 地球観測データ解析センター(EORC)
- スケジュール
3月21日(火)
- 9:30-10:00
- 開会挨拶
出席者の紹介
資料確認、ロジ確認等 - 10:00-12:00
- アジェンダ採択
NASDAからの資料説明 - (1) H-IIロケット打上げ失敗に伴うNASDAのプログラム変更
(2) 地球観測システム本部の業務
(3) アクションプランの進捗状況
NASDAからの資料説明と質疑応答 - (1)地球環境変動観測ミッション(GCOM)の研究
- 昼食
- 13:30-15:45
- (2) GCOM-A1の研究
- GCOM-A1科学的要求
- GCOM-A1衛星システム
- GCOM-A1地上システム
- GCOM-A1データ解析
- 休憩
- 16:00-17:30
- (3)TRMM搭載降雨レーダ(PR)の解析研究
- (4)二周波降雨レーダ(DPR)の研究
- 18:00-20:00
- レセプション
3月22日(水)
- 9:30-10:30
- 前日の質問に対するNASDA側の回答
- 10:30-12:00
- 各評価項目についてディスカッション
- GCOM
- GCOM-A1
- PR
- DPR
- アクションプラン活動のレビュー
- 昼食
- 13:30-15:00
- 各評価項目についてディスカッション(続き)
- 休憩
- 15:30-17:00
- 各評価項目についてディスカッション(続き)
- 17:30-19:30
- 夕食
3月23日(木)
- 9:30-10:00
- 前日の質問に対するNASDA側の回答
- 10:00-12:00
- 評価部会報告書のドラフティング
- 昼食
- 13:30-15:00
- 評価部会報告書(案)の作成
- 休憩
- 15:30-16:30
- 評価部会報告書(案)の採択
評価部会報告書策定までの調整 - 16:30-17:00
- NASDAへの部会結果通知
- 閉会