「ヒューマンファクタ分析ハンドブック」について
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
1. 経緯
- ETS-VIの静止軌道投入失敗及びHYFLEXの回収失敗を機に、宇宙開発における不具合発生の過程についての調査分析法の検討を早稲田大学への委託研究により平成7年度から平成10年度まで行い、平成11年度には関連企業の品質保証担当者および関連研究者による検討委員会にて審議し「ヒューマンファクタ分析ハンドブック(案)」を作成した。
- H-II8号機の打上げ失敗をうけた宇宙開発委員会特別会合の報告をふまえ、平成12年6月「ヒューマンファクタ分析ハンドブック」を制定し、事業団各本部、関連メーカに配布するとともに、内容について説明会を実施した。また、製造・試験工程における品質保証の管理基準を定める「品質保証プログラム標準」において、不具合背後要因分析の実施要求を追加し、その中でこのハンドブックを参考とすることとした。
2. ハンドブックの概要
1. ヒューマンファクタ(HF)の概念
このハンドブックでは、ヒューマンファクタとは「機械やシステムを安全にしかも有効に機能させるために必要とされる、人間の能力や限界、特性などに関する知識の集合体」(参考文献.1)としている。
ヒューマンファクタの捉え方としては、M-SHELLモデル(参考文献.2)を説明モデルに用いており、人間(L)の周囲の凸凹は人間の限界を示し、その凸凹とそれを取り巻く要素(S,H,E,L)の凸凹が合致しないと不具合が生じるという考え方である。

2. ヒューマンエラーの発生
このハンドブックでは、ヒューマンエラーとは「達成しようとした目標から、意図せずに逸脱することになった、期待に反した人間の行動」(参考文献.1)としている。エラーは人間と外界との関連性で発生する心理学上では正常な心理現象である。
また、エラーの発生には、エラーに至る過程にも種々の問題があり、さらに種々の問題が連鎖的に結びついて鎖のようになった時にエラーとして表出するものと考えられる(「事象のチェーン」(参考文献.3))。
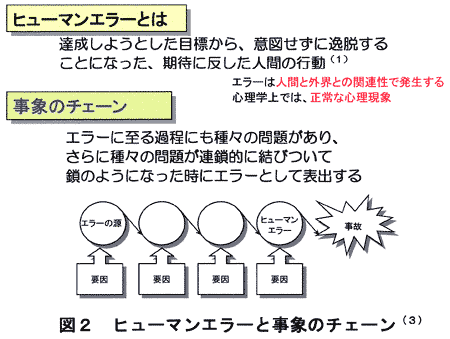
3. ヒューマンエラー防止の考え方
よって、エラーを表出させるのは作業当事者であるが、その病原は組織であることが多く、エラーの上流に存在するエラー要因を断つことが必要であると考えられる。
このため、ヒューマンエラーを末端とする事象の流れを鮮明にすることで、エラーの源は何かを突き止め、恒久的な対策を導くことを主眼においた分析法として、バリエーションツリー分析(参考文献.4)を用いることとしている。
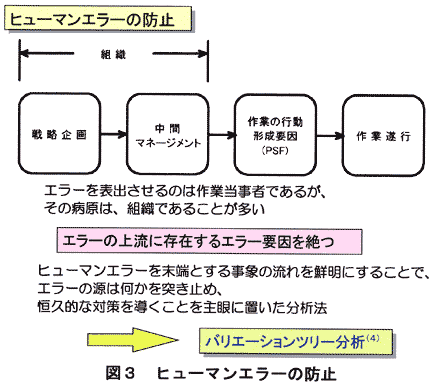
4. ヒューマンファクタの分析
このように従来の不具合調査では、不具合原因の1つに何かしらのミスがあっても、なぜミスが発生したのかという観点での掘り下げは十分でなく、エラーの発生メカニズムや動機的原因は不明なままに終わっていた可能性があるのに対し、ヒューマンファクタ分析ではミスが発生するに至る背後要因までをも探索し対策をたてようとするものである。(図5)
本ハンドブックで解説しているヒューマンファクタ分析要領は図6の通りである。
また、図4に対応する背後要因分析事例を図7に示す。
3. むすび
- 今後は研修やシンポジウム、説明会等にて「ヒューマンファクタ分析ハンドブック」についての教育活動を行い、分析活動の定着を図っていく。
- 特に重大品質問題(事故、トラブル)についてはこの手法を適用し再発防止に役立てる。
4. 参考文献
- 黒田勲 : 「今なぜヒューマンファクタが重要か」 「働く人の安全と健康」 付録「ヒューマンファクタ〜災害ゼロに向けて新たな展開を〜」 中央労働災害防止協会 1999年 p3〜8
- 河野龍太郎 : 「ヒューマンエラー低減技法の発想手順:エラープルーフの考え方」 日本プラント・ヒューマンファクタ学会誌 Vol.4 No.2 1999 p121〜130
- ICAO事故防止マニュアル
- Leplat, J. and Rasmussen, J. : Analysis of Human Errors in Industrial Incidents and Accidents for Improvement of Work Safety, in Rasmussen, et al. (Eds.) : New Technology and Human Error, John Wiley & Sons, 1987.
|
|