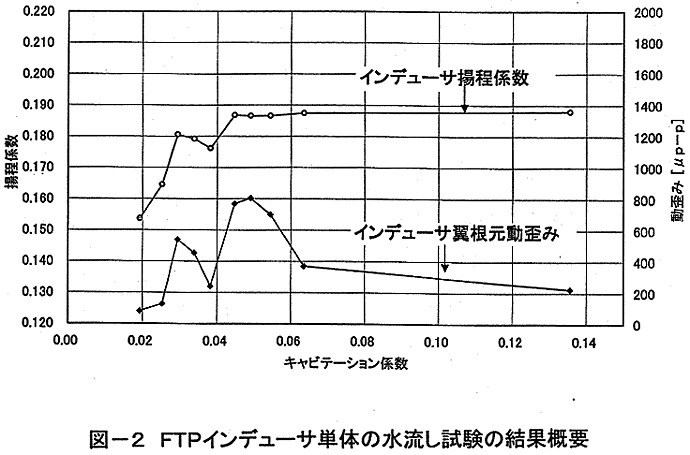H-IIAロケット LE-7A認定型エンジン種子島燃焼試験の状況と
インデューサの水流し試験状況について
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
<LE-7A認定型エンジン種子島燃焼試験の状況>
1. 経緯
| (1) | LE-7A認定型エンジン(3号機)については、平成12年6月6日より種子島宇宙センターにおいて燃焼試験を開始した。 |
| (2) | 長秒時耐久性確認試験(約350秒)2回を含む8回計1,085秒の試験を実施した。 |
| (3) | 7月11日に行われた燃焼試験後の点検において液体水素ターボポンプ(FTP)の一部部品(ガイドプレート及びタービン動翼ストッパ)に損傷が認められ、FTPの分解点検を行った。 |
2. 試験結果概要
試験結果概要を下表および図1に示す。
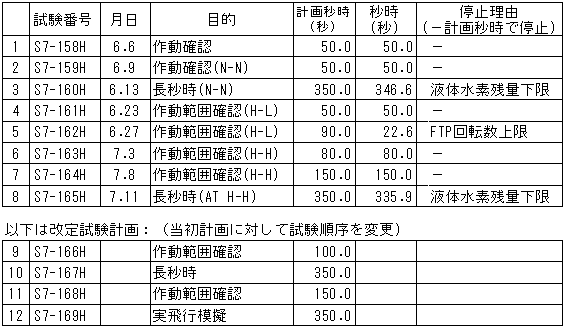
H-H:推力-混合比のレベルを表す。 H:高、L:低、N:ノミナル
AT:領収燃焼範囲を示す
初回、2回目と領収燃焼試験相当の試験を行って作動点をノミナル付近に設定し、その状態で長秒時試験を行った。
4回目以降、認定範囲での確認試験を行った。(なお、この認定範囲については、実運用段階で領収燃焼範囲内に調整されたエンジンが飛行時に遭遇し得る作動点について、各コンポーネントのばらつきを考慮した重要コンポーネントの作動範囲から求められている。)
また、6回目以降は、H-IIロケット8号機の事故原因究明の反映として、表面仕上げを改良したインデユーサを装着したFTPに交換して試験を行った。
3. 特記事項
長秒時燃焼試験後には、ターボポンプをエンジンより取り外して点検することとしており、この点検においてFTPのタービン部(図2、図3)を目視検査したところ、以下の損傷が発見された。
| (1) | タ一ビン動翼ストッパ(コバルト基合金製):58個のうち、タービン下流側において、1個に欠損、3個に亀裂が発生していた。 |
| (2) | ガイドプレート(ニッケル基合金製):外周部分から内径側に1〜8mmのクラックが27ヶ所入っていた。 |
FTPについては、エンジンより取外し、工場に発送し、分解を実施し、原因調査中である。
分解点検の状況、推定原因等については、下記「液体水素ターボポンプの故障解析結果について」に示す。
4. 今後の予定
推定した原因に対する試験や解析の結果を踏まえ、必要な対策の後、種子島宇宙センターでのエンジン燃焼試験を再開し、上記対策の妥当性の確認を行うとともに、引き続き認定試験データの蓄積を図る。
|
|
液体水素ターボポンプの故障解析結果について
1. 不具合状況
7月11日に実施した350秒認定エンジン試験(試験番号S7-165H)後の点検で、液体水素ターボポンプの動翼ストッパーに一部欠損と割れが、ガイドプレートCに割れが発見された
このため、液体水素ターボポンプを工場へ持ち帰り分解点検を実施し原因調査中である。
2. 分解点検状況
工場での分解点検の結果は、以下の通りであり、下記の部分を除いて異常なし。
(1)ガイドプレートC
破面は疲労破面であった。ノズル内輪との接触痕があった。
クラックは、タービン温度の高い方向に多く発生していた。
(2)動翼ストッパー
破面は疲労破面であった。
3. 推定原因等
(1)ガイドプレートC
エンジン定常運転中にリフトオフシールの傾きによる金属Oリングの漏れが発生すると、ガイドプレートCに液体水素がかかる可能性がある。この時の熱応力及びタービンノズル内輪との接触から、ガイドプレートCに高い引張力が発生し、これにエンジン燃焼環境下の振動が加わり疲労破壊に至ったと推定される。
リフトオフシールの傾きの原因としては、熱変形によりガイドプレートCとタービンノズルが干渉し、位相によって干渉の状態が異なるために、ガイドプレートCがリフトオフシールを引っ張り、傾けていた可能性が考えられる。
現時点では、対策としては、組み立て時にガイドプレートCとタービンノズルの隙間が一定値以上で均等となるように調整し、干渉の発生を防止することが考えられる。
(2) 動翼ストッパー
エンジン停止後にリフトオフシールまわりに漏れが発生すると、動翼ストッパーに液体水素がかかり、この時の熱応力のために、動翼ストッパーに残留応力が残ったと推定される。この残留応力のために疲労強度が低下し、エンジン燃焼環境下で疲労破壊に至った可能性がある。今後さらに上記で確認した原因について試験・解析を進める。
現時点では、対策としては、ガイドプレートでの対策に加え、エンジン停止後にリフトオフシールまわりの漏洩を防止するための以下の対策が考えられる。
a)水分対策
認定試験においてもリフトオフシール部に漏洩が発生したが、水分除去パージを入念に行った後の試験では、同シール部の漏洩に改善が見られたことから、不具合が水分に起因する可能性がある。
現時点では、対策としては、認定試験で採用したリフトオフシール部のパージ強化を行うことが考えられる。
b)バネ力の強化
GTV用と認定試験用のリフトオフシールは、同一のロットで製作されており、両方ともバネ力はやや弱めに調整されていた。
現時点では、対策としては、閉作動の確実性を増すために、バネ力を実績範囲内で強めに調整したものを使用することが考えられる。
LE-7Aエンジン インデューサの水流し試験>
H-IIロケット8号機事故原因究明において、LE-7エンジンの水素ターボポンプ(FTP)のインデューサが疲労破壊したことが事故の1次原因であると結論付けられた。
これを受けて、LE-7Aエンジンの開発の一環として、インデューサの単体水流し試験及びインデューサと入口配管を組み合わせた水流し試験を行い、データを取得したのでその概要を報告する。
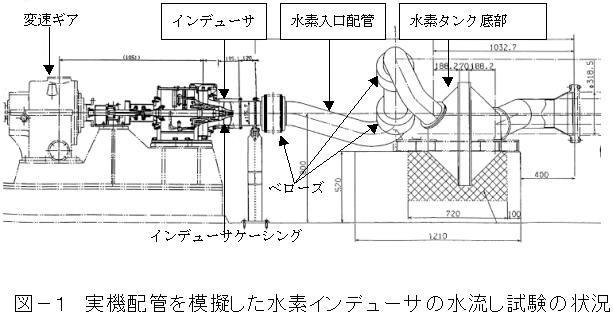
(1)IHI横浜における水素インデューサの単体水流し試験
平成12年4月に石川島播磨重工業(横浜)においてLE-7AエンジンのFTPインデューサの単体水流し試験(水を作動流体に用いた回転試験)を実施した。この試験では、インデューサ入口の流量と圧力をパラメータとして変化させて、キャビテーションの発生状況、インデューサ周りの変動圧力データ、インデューサの羽根に発生する応力データを取得した。
この試験で得られたデータをもとに、8号機の事故原因究明と同様の方式で評価したところ、LE-7AのFTPインデューサは、羽根に発生する変動応力は半減する結果を得たものの、疲労に対する余裕を確保する改善策を採用するものとし、流体研磨等により表面粗さを向上させること、レプリカによりインデューサ羽根の根元に加工痕がないことの確認を行うこととした。
(2)大阪大学における酸素インデューサの単体水流し試験
FTPと同様に、液体酸素ターボポンプ(OTP)用インデューサについても、大阪大学の辻本研究室において、4月末から5月にかけてインデューサの単体水流し試験を実施し、キャビテーションに関するデータを取得した。
8号機の事故原因究明と同様の解析により、データを評価した結果、OTPインデューサについてもFTPインデューサと同様に疲労に対する余裕を確保するものとし、レプリカによりインデューサ羽根の根元に加工痕がないことの確認を行うこととした。
(3)航空宇宙技術研究所における入口配管と水素インデューサの組合せ試験
H-IIロケット8号機の事故原因が、液体水素ポンプ入口配管のガイドベーンとインデューサの流体干渉に起因する可能性が大きいことから、H-IIAロケットには水素入口配管にガイドベーンはないものの、実機の配管系(水素タンクのサンプ部、水素入口配管)を模擬して水素インデューサの水流し試験を行い、インデューサの吸い込み性能、インデューサ翼に発生する応力、ケーシング壁変動圧力、流れの可視化・流速分布等についてデータを取得した。試験状況とこれまでの試験結果を、図-2に示す。
実機の配管系の影響を確認するために、ポンプ上流を直流管に置き換えた試験も実施したが、旋回キャビテーション発生時に増加する動歪みは、実機配管の結果とほぼ同等であり、入口配管とポンプに段差を設けた試験においても特異な差は見られなかった。
今後は、実機配管系とインデューサの組合せた状態で、エンジンのジンバル状態を模擬した試験の実施について、必要に応じて試験で確認する。