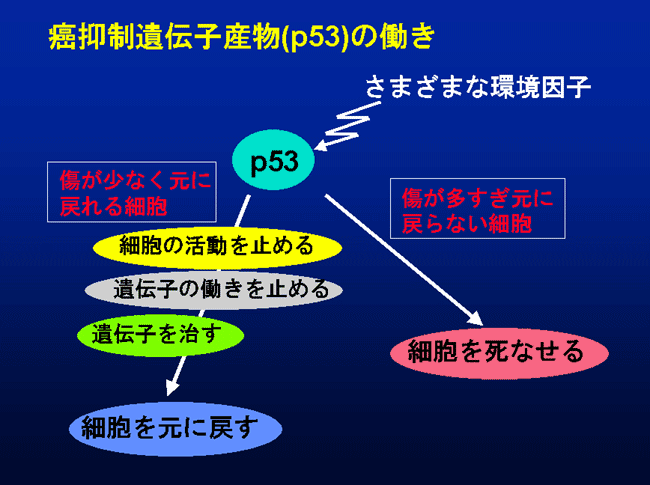ライフサイエンス国際公募の宇宙実験候補テーマ選定結果について
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
1. 報告事項
平成11年に募集を行った第3回ライフサイエンス(生物学・医学研究分野)国際公募について、平成12年4月26日に国際ライフサイエンステーマ選定委員会がドイツで開催され宇宙実験候補テーマが選定された。
2. ライフサイエンス国際公募について
2.1 公募の目的等
ライフサイエンス国際公募は、日・米・欧・加が国際宇宙ステーション等における科学的研究に係るフライトテーマを国際的に選定するものであり、限られた実験装置及びリソースを効率的に利用し、最大限の科学的成果を得ることを目的としている。
今回の公募は平成15年(2003年)から平成16年(2004年)の国際宇宙ステーションの初期利用段階を対象として募集を行った。ただし、げっし類(ラット、マウス)を飼育する実験装置を使用するテーマについては、既に選定され準備中の実験が多く、今後追加の飛行実験機会の確保が困難であることから、今回は募集しないことが、参加各機関で取り決められた。
2.2 参加の条件
| (1) | 参加機関による実験装置の提供(国際公募で選定された利用研究テーマに使用させるもの) |
| (2) | 利用研究テーマの各機関経由による募集 |
| (3) | 国際科学評価パネルへのパネリスト(当該分野の研究者)派遣、国際技術評価への参加 |
| (4) | 参加機関の独自の宇宙環境利用政策による再評価 |
| (5) | 国際ライフサイエンステーマ選定委員会への参加 |
| (6) | 各機関経由で提案され、選定されたテーマへのフライト準備・フライト・フライト後解析に亘る各機関によるサポート |
2.3 作業経緯
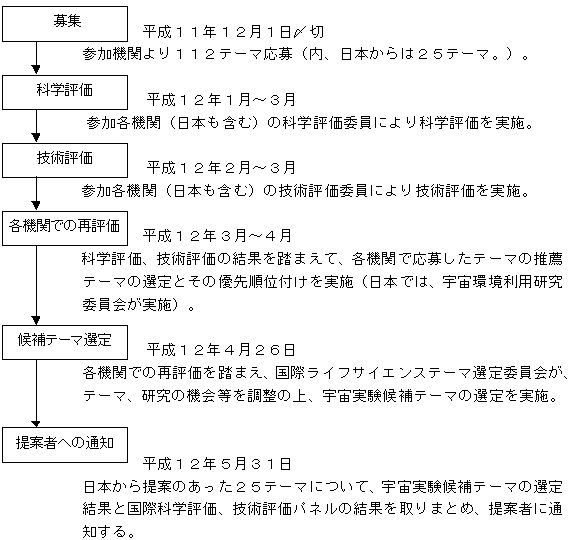
3. 宇宙実験候補テーマ選定結果
日本からは以下の1テーマが宇宙実験候補テーマとして選定された。
| テーマ名称 | 提案者 | 試料 | 主な使用装置 |
|---|---|---|---|
| 哺乳類培養細胞における宇宙環境曝露後のp53調節遺伝子群の遺伝子発現 | 大西武雄* 奈良県立医科大学 |
ヒト細胞 マウス細胞 |
細胞培養装置 (NASDA) |
| *: | 本研究者は、平成11年度宇宙環境利用に関する地上研究公募の代表研究者として以下のテーマで参加している。 |
「低線量率長期被曝による癌抑制遺伝子p53の発現誘導」
各国の選定テーマ数/応募総数を以下に示す。
| 日本 | 米国 | 欧州 | カナダ | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1/25 | 7/40 | 3/39 | 1/8 | 12/112 |
また、参考に昨年度の各国の選定テーマ数/応募総数を以下に示す。
| 日本 | 米国 | 欧州 | カナダ | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5/46 | 17/57 | 13/49 | 4/13 | 39/165 |
なお、日本の実験装置を利用する海外の研究者からの提案テーマは、前回同様選定されていない。
4. 今後の予定
宇宙実験候補テーマについては、今後約1年間の実験計画設定作業を経た後、実験の実現性、リソースや準備計画等を評価し、フライトテーマとしての最終選定を行う。
|
|
「哺乳動物培養細胞における宇宙環境曝露後の
p53調節遺伝子群の遺伝子発現」
(1)テーマ提案者の紹介とテーマのバックグランド
大西武雄氏(奈良県立医科大学生物学教室 教授)は大学院時代から約30年間放射線生物学を研究してきた。はじめの頃は紫外線や化学物質が遺伝子DNAにけがをもたらすしくみとそれによる生物影響(分化異常・細胞死・突然変異・DNA修復)の研究を行っていた。ここ10年来、放射線特にX線やガンマー線を用いて、ヒトが生まれながらに持っている癌になることを防ごうとする癌抑制遺伝子p53のはたらきの研究をしている。その研究を癌治療や放射線の生物影響の研究に役立てたいと願っている。放射線と同様に温熱などの各種ストレスが癌抑制遺伝子p53のはたらきを促進することを見つけている。
向井千秋さんがはじめてスペースシャトルで宇宙実験を行った国際宇宙実験(1994年)において、細胞性粘菌を用いて微小重力環境での発生・増殖・分化・形態形成や宇宙放射線による突然変異誘発研究を行った。その後もスペースシャトルやロシアの宇宙ステーションで、宇宙放射線による遺伝子DNAの損傷の同定・突然変異誘発の実験をヒト細胞・酵母・枯草菌・大腸菌・プラスミドDNAなどを用いて行ってきた。また損傷DNAの修復やDNA合成過程での突然変異誘発に微小重力が影響を与えるかを調べてきた。さらに宇宙飛行したラットの皮膚や筋肉では癌抑制遺伝子p53遺伝子産物が蓄積していることを発見した。宇宙飛行した金魚ではストレスタンパク質が皮膚・筋肉・肝臓で誘発しているしていることを見出している。宇宙環境は動物にとって地上とは異なる空間であることを分子レベルで明らかにしようとしている。今まで宇宙実験を21回行い、そのうちの10回が実験テーマの代表者であった。
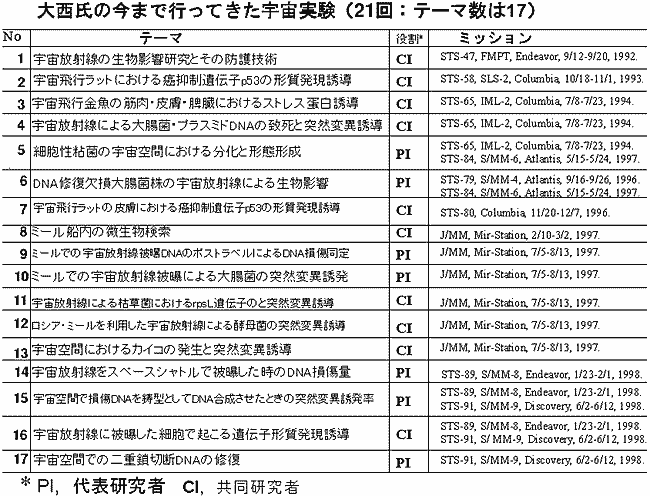
(2)提案テーマの概要
癌抑制遺伝子p53は我々の体が癌になることを抑えようとするはたらきがある。さまざまな環境因子によって遺伝子DNAに傷が生じても、積極的に元に戻そうとするはたらきがある。下図に示すように、傷が多すぎるとその細胞だけに選択的な細胞死をもたらそうとする。そして傷が体に残らないように監視するはたらきをするし、傷が少ない場合は、元通りに戻そうとするはたらきをすすめる。そして結果的には遺伝子DNAの傷が体に残らないように監視するはたらきがある。本テーマは宇宙空間でこの癌抑制遺伝子p53が調節している遺伝子群の形質発現の変化を解析することを目的としている。宇宙ステーションでは地上では経験のない微小重力環境で、人体に影響を与える高エネルギー粒子線を低線量ながら被曝することになる。そのような宇宙環境ではこの癌抑制遺伝子p53がまともにはたらくことができるのか、ヒトの細胞は宇宙環境に適応することができるのかを明らかにしようとしている。またどのようなことを工夫することで、ヒトが長期間宇宙環境に滞在し安全な生活をしていけるかを求めている。