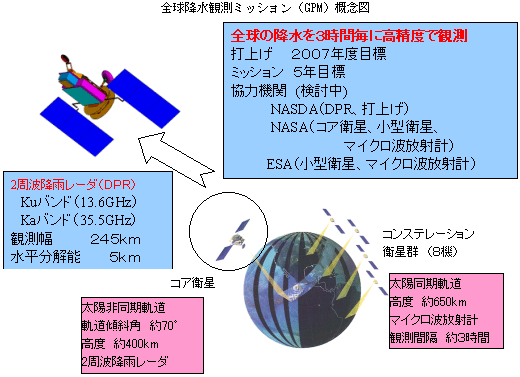全球降水観測ミッション(GPM)日米合同作業部会/ワークショップの結果について
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
1. 経緯
平成12年11月の科学協力に係るNASDA・NASA共同声明 に基づき、平成13年5月15日にNASAゴダード宇宙飛行センター (米国メリーランド州グリーンベルト市)において第1回全球降水観測ミッション (GPM、下記参照) の日米合同作業部会が開催された。またこれに引き続き翌16日から18日までメリーランド大学 (米国メリーランド州カレッジパーク市) においてNASAとNASDAの共催でGPM ワークショップが開催されたので、これら2つの会議の概要について報告する。
2. 会議概要
(1)第1回日米合同GPM作業部会
日米の作業部会メンバー他が集まり、GPM計画の考え方と当面の進め方についてNASA側との調整を行った。日本側からは、NASDAから古濱理事を含めて6名、地球観測委員会のTRMM後継ミッション検討チーム(ATMOS-A1サイエンスチーム)より2名(名大 中村教授、東大 小池教授)、通信総合研究所(CRL)より2名、気象庁より2名が参加した。米国側は、NASAから、NASA本部地球科学局のCleave副局長、 TRMM(熱帯降雨観測衛星)及びGPMのプログラムサイエンティストのKakar博士を含む11名、さらにコロラド州立大のKummerow教授、プリンストン大のSteiner教授等が出席した。
(2)GPM ワークショップ
世界の各国、各機関がGPMに寄せる期待ならびに計画への貢献の可能性を発表、討論し、協力の形態を模索した。参加者の国、機関は、米国(NOAA、NRL、USDA、USGSなど)、カナダ、日本(NASDA、CRL、気象庁)、韓国、インド、欧州(ヨーロッパ宇宙機関、イタリア、フランス、ドイツ、ヨーロッパ中期予報センター)など16カ国24機関から200名を超える参加があった。
- 注)
- NOAA:National Oceanic and Atmospheric Administration, 米国海洋大気庁
- NRL:Naval Research Laboratory, 米国海軍研究所
- USDA:U.S. Department of Agriculture, 米国農務省
- USGS:US Geological Survey, 米国地質調査所
3. 会議結果
(1)第1回日米合同GPM作業部会
- NASA側から、2001年度にGPMのミッション定義とプロジェクト化準備を行うこと、このための予算は議会の留保予算から支出することが認可されたこと、また2002年度予算についてはプロジェクト化のための予算を政府が議会に対して要求中であること、NASAの地球科学観測事業(Earth Science Enterprise)の新規計画の中ではGPMを最も優先度の高いものとしていること、について報告があった。また当面のスケジュール案、日米の分担案、当面作成する必要のある文書、TRMMマイクロ波放射計(TMI)後継センサであるTMI+等の技術検討状況、日米の技術インターフェース検討状況等について説明があった。
- 日本側は、NASDAの地球観測将来計画の概要、NASDA及びCRLにおける2周波降雨レーダ(DPR)検討状況、TRMM後継ミッションの検討概要、日本及び東南アジアにおける水資源管理研究計画の概要、気象庁の衛星データ利用将来計画概要等について説明を行った。
- 本会合において、NASDAが現在検討しているTRMM後継ミッション計画と米国のGPMコア衛星計画を統合して共同の計画とする可能性や、共同のサイエンス要求及びサイエンス実施計画、並びにインターフェース文書を今後作成する可能性等について、意見交換を行った。
(2)GPMワークショップ
各国の各機関が、GPM への期待ならびに計画への貢献の可能性を発表した。宇宙機関は、2007年頃のそれぞれの衛星計画とGPMとの関わり、特にマイクロ波放射計センサの提供可能性などについて報告した。気象機関からはデータ同化等GPMデータ利用の可能性について説明があった。その中でのトピックは以下の通りである。
- GPM全体構想の中で、コア衛星は日米の共同ミッションとして実現する可能性のある計画として、ワークショップの中で広く認識された。
- GPM全体計画における2周波降雨レーダ(DPR)の重要性が強調され、GPMのコアセンサとしてDPRが強く要望された。
- 各国が提供するスペックの異なるマイクロ波放射計データのデータフロー、校正方法、3時間毎のリアルタイムデータ作成・配信方法がGPM成功のための重要検討課題であることが認識された。
- NASAはスーパーサイトと称する検証サイトを2箇所ほどサポートする構想を持っている。
- 降水観測ミッションと関連の強い、CloudSAT(2003年頃打上げ予定の、米国/カナダによる雲レーダ、マイクロ波放射計による雲・放射観測ミッション)やEarthCARE(ESAとNASDAが協力して2007年以降2010年頃までの実現に向けて検討している雲レーダ、ライダー等による雲・放射観測ミッション)との連携の必要性が指摘された。
- 2002年以降の極軌道上のマイクロ波放射計としては2ないしは3機のSSM/I(Special Sensor for Microwave Imager)と、ADEOS-II搭載のAMSR(Advanced Microwave Scanning Radiometer, 高性能マイクロ波放射計), NASAのEOS-PM1(Aqua)搭載のAMSR-E(Advanced Microwave Scanning Radiometer-E, 改良型高性能マイクロ波放射計)が揃うことになり、日本の提供するセンサがGPM関係者の大きな注目を集めていた。
4. 今後の予定
- 次回の作業部会開催は11月頃に予定
- 来年度のGPMワークショップの開催
|
|
全球降水観測ミッション(Global Precipitation Mission: GPM)の概要
| (1) | 1機の熱帯降雨観測衛星(TRMM)タイプのコア衛星と8機のマイクロ波放射計を搭載した衛星群(コンステレーション)から構成される。
|
||||
| (2) | コア衛星は、2周波降雨レーダを用いて降水の3次元高精度・高感度観測を行うほか、マイクロ波放射計の校正源となる中心的衛星である。2周波降雨レーダについては、現在、NASDAとCRLの間で共同研究を行っている。 | ||||
| (3) | コンステレーション衛星群は、8機のマイクロ波放射計衛星により、3時間毎の全球降水観測達成を目的としている。既存の衛星計画(NOAA/NPOESS等)を含めて8機の観測とし、NASA、ESA等が提供する衛星により観測ギャップを埋める。 | ||||
| (4) | 3時間毎の降水データは、数値気象予報の改善、短期天気予報に大きく貢献できるほか、気候変動に大きな影響を与える全球水循環の実体の把握、世界の水資源管理、農業計画等への貢献も期待されている。 |