地球資源衛星1号(JERS-1)の大気圏再突入について
平成13年11月14日
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
1. 地球資源衛星1号(JERS-1:ふよう1号)の概要
| 【目的】 | 資源探査・国土調査・農林漁業・環境保全等を目的とし地球全般(陸域中心)の観測を実施 |
| 【搭載センサ】 | ・合成開口レーダ(SAR):能動型の電波センサ ・光学センサ(OPS):可視光/近赤外/短波長赤外による(地表からの)反射光を観測 |
| 【軌道】 | 高度約570km、軌道傾斜角約98°の太陽同期準回帰軌道 |
| 【打上げ日】 | 平成4年2月11日 |
| 【経緯】 | 2年間の定常運用。その後は後期運用段階の運用。 平成10年10月12日運用終了。 (太陽電池パドルとパドル駆動機構との間の電線の寿命のため) |
| 【主な成果】 | ミッション期間は2年間であったが、約6年半に渡り資源、災害、環境監視等の地球観測データを取得。 これらのデータを通し、中国トルファ ン盆地における石油賦存地域の抽出、アマゾン熱帯雨林の森林伐採の実態や、岩手山火山活動による地殻変動等に関する成果が得られた。 |
2. JERS-1:ふよう1号の外観図と質量/大きさ
 |
|
3. 落下予測
【11月12日現在の状況】
落下予測日:平成13年11月30日〜12月10日 (ノミナル12月4日)
近地点高度:約335km、 遠地点高度:約342km
- 太陽活動の変動により大気抵抗が衛星落下に及ぼす影響に予測誤差があり、上記の様な幅が生ずる。再突入1週間前で±1.5日、1日前でも±5時間程度の誤差が残る。
- NASA経由で入手する米国の2ライン要素を中心に、美星スペースガードセンターの取得データ等も用いて軌道状態のモニタを行い、NASDAで落下予測日の推定を行っている。
4. 落下安全性について
【落下の解析】
落下溶融解析の結果では、ほとんどは落下途中に溶融消失。
チタン合金製の推薬タンク2個(各直径約55cm、質量約7kg)が地上まで到達する可能性がある。
【落下の危険性】
上記タンクがまるごと燃えずに落下した場合
「全世界で破片に接触する一人当たりの確率」=3.8×10-15
となっており、これは、JERS-1の大気圏再突入に係る危険性が、米国で定められている基準に比べて十分小さいことを示している。
今回のような宇宙機体の大気圏再突入は、全世界で、年間約150回発生しているが、国連の報告書によれば、「これまで重大な被害はもたらされていない」とのこと。なお、今回と同様な事象に対しては、各国とも特段の対応はとられていないのが現状。
5. 今後の対応
- 最新の軌道データ基づく落下予測を行い、情報をNASDAホームページ( http://www.nasda.go.jp)に適宜公開予定。
- 落下が確認された場合、速やかに関係方面に連絡予定。
【対応体制】
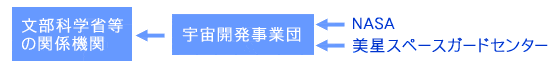
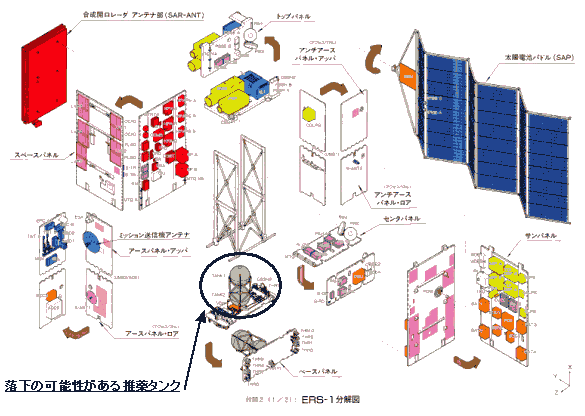
|
|