第5回宇宙開発事業団改革推進委員会の開催結果について
宇宙開発事業団
以下のとおり第5回宇宙開発事業団改革推進委員会が開催されました。
1. 日時
平成13年3月27日(火) 9:30〜12:00
2. 場所
宇宙開発事業団 本社第1〜4会議室
3. 出席委員
久保田委員長、坂内委員、土居委員、鳥井委員、中原委員、畚野委員
4. 議題
| (1) | 品質保証の強化に対する取り組み(その4) -企業における取り組みの強化状況等- |
| (2) | 高度情報化の推進に対する取り組み |
| (3) | 専門的人材の育成活用に対する取り組み |
5. 配布資料
5-1 品質保証の強化に対する取り組み(その4)
- 品質保証の強化に対するこれまでの論点の整理 ( 1 , 2 )
- (1)NASDAと企業との役割分担の明確化の検討状況 ( 1 , 2 )
- (2)NASDA-企業間の一体となった取り組み
-H-IIAロケット開発における取り組み例- ( 1 , 2 )
5-2 H-IIAロケット試験機1号機打ち上げ成功への取り組み(三菱重工業(株))
- 三菱重工全社体制での取り組み
- 品質確保活動への取り組み ( 1 , 2 , 3 )
5-3 LE-7Aエンジン開発における品質保証の強化への取り組み(石川島播磨重工業(株))
5-4 宇宙開発高度情報化戦略概要
はじめに5-5 高度情報化の推進に対する取り組み
- 高度情報化の目的
- 背景・経緯
- 遂行方針
- IT化に当たっての考え方
- ITによる開発の高度化 ( 1 , 2 )
- 開発業務IT化に当たってのシステム構成 ( 1 , 2 , 3 )
- 情報の知識化、活用
- 業務運営の改革
- 革新的な情報技術の研究の推進
5-6 専門的人材の育成活用に対する取り組み
|
|
LE-7Aエンジン開発における品質保証の強化への取り組み
石川島播磨重工業(株)
宇宙開発事業部
(1)設計品質の向上:
| ・ | 基礎試験/基礎データの充実 | 疲労強度、吸込み性能、加工残留応力、LOS低温作動 |
| ・ | 解析の強化/充実 | ポンプ系CFD解析、インデューサ疲労強度、 詳細3次元モデル解析 |
| ・ | 特性値トレンド管理強化 | 特性値の選別とトレンド管理(性能、軸系振動、各部クリアランス、軸系バランス量 等) |
| ・ | その他…コンフィギュレーション管理/評価の充実、リスクマネジメントの充実 | |
(2)製造品質の向上:
| ・ | 納入前点検の充実 | 現物確認の強化 中間工程検査/製造完了レビューのチェック強化 |
||
| ・ | 工程設計内容の充実 | 工程解析、製造工程審査 | ||
| ・ | 画像による記録の強化 | ディジタルカメラ、ファイバースコープ等による記録の充実 | ||
| ・ | 不適合事例に対するヒューマンファクタ分析とそれに基づく教育 | |||
| ・ |
|
|||
(3)末端に至るまでの開発成功への意識の徹底
不適合再発防止、信頼性再確認、緊張感の維持
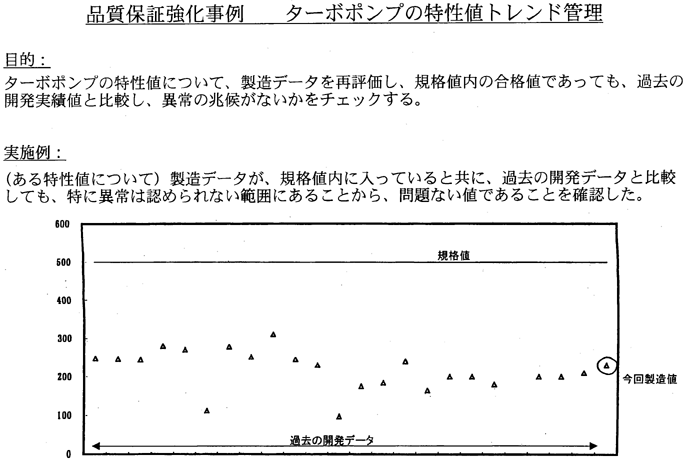
宇宙開発高度情報化戦略(要約版)
宇宙開発高度情報化推進委員会
はじめに
宇宙開発高度情報化推進委員会は、宇宙開発事業団(NASDA)の業務の推進に当たって、高度情報化技術を活用することにより、より確実で、効率的かつ迅速な開発活動および効果的な開発成果の利用を促進するための戦略、ならびにそれらを推進するための体制について調査審議し、必要に応じて理事長に意見を述べることを目的とし、平成11年12月に発足した。委員会、分科会、ワークショップ等において審議するとともに、NASDA職員との意見交換を重ね、NASDAの情報化推進の指針として高度情報化戦略を策定した。
本戦略策定に当たっては、宇宙開発情報化の観点から意識、体制、ITに関して、重点的に審議した。戦略の中心をなすものは、NASDAにおける意識の改革であり、また、次世紀においてNASDAが宇宙開発のフロントランナーとして留まるための経営陣に直結した情報化推進体制の確立である。
現在、政府はITによる産業・社会構造の変革(IT革命)に取り組み、国際的に競争力ある「IT立国」を目指している。NASDAはその一翼を担うべく、宇宙開発事業の効率的かつ確実な実施のみならず、情報技術革新においても、宇宙開発産業界さらには我が国を先導する自覚を持って戦略の実現にあたり、国民の支持を得て国益を確保した上で人類の叡智に貢献することを期待する。
宇宙開発高度情報化推進委員会委員長
石井 威望
1. 高度情報化戦略
1.1 方針
NASDAの宇宙開発事業は、高度情報化推進の立場から、次の考え方に基づいて行うこと。
(1) 開発思想「仮想から現実へ、現実から仮想へ」
仮想モデルの構築、実験データによる検証等への取組みと共に、サイバー空間における開発設計とその現物化、実用化を推進
(2) 開発目的
広く科学技術上の探検と発見を可能とする極限の基盤技術の開発
(3) 開発目標
宇宙機の抱える諸問題・障害をブレークスルーするための小型・高機能化、軽量化、および、宇宙機の管制・支援基盤への先端的情報・通信・制御技術の開発・導入
(4) 開発分担
国家主導によるサイバー空間での開発・設計及び検証と確認のための実物製作、ならびに民間主導による獲得技術の民生事業展開
1.2 高度情報化基本戦略
NASDAが21世紀における高度技術産業への脱皮を図る中核として機能するために、ITの持つ特性を活かして、次の戦略に基づいて宇宙機開発環境を整備すべき。
(1) 開発の効率化
国内外の叡智、技術を集めて、開発コスト・期間・マンパワーについて定量的な目標を掲げ、合理的な改善を目指すこと
(2) 開発のライフサイクル化
開発支援システムは、宇宙機の機能、性能、信頼性等の実現をめざす設計・開発・維持に利用するだけでなく、そのままで研究者及び技術者教育、運用者教育等にも利用できるようにすること
(3) 情報の一元化
開発に関する情報は、統一した概念のもとで一元的にかつ永続的に蓄積・管理し、情報間の時間的・空間的不一致をなくすこと
(4) ディジタル化
開発に必要な、またはそれによって得られた技術情報は、可能な限りディジタル化し、保存・加工・利用が容易に行えるようにすること
(ア) 可視化
開発成果等は、理解しやすい動画像、3D画像で表現し、設計検証や工程点検の質的向上、および技術の蓄積・伝承を図る
(5) 開発プロジェクトにおける情報共有化
(ア) 時間的・空間的制約の緩和
あらゆる現象が時間的・空間的制約から解放され、局所的あるいは大局的に理解できるようにする
(イ) システムの安全・信頼化
開発支援システムの信頼性保証と共に、それへの破壊攻撃、開発情報の悪用を許さない
上記の開発環境の構築は、以下の基本的観点から出発することが必要である。
(1) 技術移転の容易化
我が国の産業発展の牽引車になる最先端技術を開発し、その技術が国益になり、人類の幸福に容易に利用できるようにすること
(2) 原則公開化
成果を原則公開するとともに、宇宙開発に関心のある国民が、開発状況を評価でき、新しい技術提案ができるようにすること
(3) ITによる開発支援の強化
経営層トップが率先してIT化戦略を推進し、高度な専門指導者及び強力な情報技術者集団を配置すること
(4) 開かれた組織への移行
広く一般国民の審判に耐えうる規範の下で、最先端の情報技術を利用した開発支援体制を確立すること
1.3 高度情報化実行体制
(1) 高度情報化推進体制
NASDAが技術競争の場において生き残り、最先端技術集団として他を先導するITを発信するために、組織の最高責任者が主導権を持った情報化推進体制を構築。
| (ア) | 理事長直結の組織として情報支援グループ(両三年で100人程度)を設置し、理事長指名のCIOにより実務遂行 |
| (イ) | 大学等への先進ITの研究開発委託、情報化専門業者による先進的開発支援システムの導入等、外部情報専門集団の活用 |
| (ウ) | 危険分散を考慮した上での情報の一元管理 (筑波宇宙センターへの集中化) |
| (エ) | 外部専門家による常設委員会の設置 (先端情報の提供、情報化のフォローアップ等) |
(2) 情報セキュリティポリシー
政府情報セキュリティ対策推進会議の「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(平成12年7月策定)」に準拠した情報セキュリティポリシーを策定し、これに基づく総合的・体系的な対策を推進
(3) 教育・訓練
業務情報を処理し、業務情報の持つ意味を理解して活動に活かす能力を技術者が習得するために、技術情報を管理するデータベース、技術情報を「知識」として容易に蓄積できる環境、および、豊かな経験と技術を持つ技術者のネットワークを構築
2. 情報技術基盤の構築
2.1 高度情報化指針
企業、外部ネットワーク、そして人間を含めたNASDA全体の情報システムと、全体システムの統合制御下で様々な目的を担当する複数のサブシステムを構築する。
実現のためには、まず次の点を念頭に進める。
| (1) | 現状で電子化されていない情報を早急に電子化 |
| (2) | 情報形式と図面の標準化 |
| (3) | 現状システムの改善から目指すターゲットシステムの構築までのロードマップの明示 |
また、情報システムの構築にあたっては、NASDA主導の下、コンピュータ画面上でものづくりを実施する3次元ディジタル設計、シミュレーション、モデリングおよび製作をベースとした新しい生産方式(バーチャルエンジニアリング)をプロジェクトへ適用する仕組み作りを推進する。
2.2 具備すべき技術
(1) ネットワーク技術
NASDAと関連機関・企業間でマルチメディア仮想空間における共同作業を実現する高度なネットワーク環境の設備充実と、安全性、安定性の確保
(2) 情報管理技術
データ操作・交換、セキュリティ等に関する一貫した情報管理ポリシーの策定、および、これに則った各情報管理システムの構築
(3) ヒューマンインタフェース
仮想現実やマルチメディア表示等のインタフェース技術を利用し、高度化、大量化する情報処理の内容をユーザに効率的に伝えるシステムを構築
(4) プロジェクトの記録・再現・分析
プロジェクトの記録・再現・分析を支援する環境を構築し、開発プロセスの解明および失敗の評価・予測・改善のための定量的システムを構築
(5) 信頼性保証技術
開発で得られたノウハウ情報(ナレッジ)を伝承維持する技術、開発品の信頼性を保証するための品質保証技術、調達部品類を評価する技術、ソフトウェアの信頼性を独立して検証する技術(IV&V)等の整備および保持
(6) ディペンダビリティ(Dependability)技術
宇宙機のライフサイクルを通した安全性、耐久性、維持・補修の容易さ、機能変更に対する柔軟さ等をも視野に入れた広義の信頼性(Dependability)を実現
第4回宇宙開発事業団改革推進委員会議事録
宇宙開発事業団
|
- 山之内理事長
- 今まで様々なご指摘を受けましたが、本日は主として品質保証や企業との関係で過去に様々なご指摘を受けましたことにつきまして、私どもなりの考え方、これからの方針をお出しして、ご議論、ご指摘を賜りたいと思います。かなり重要な問題でございますので、たぶん次回を含めてこの議論はしていただいた方がいいかと思いますので、是非、忌憚のないご叱責を賜ればありがたいと思います。
- 久保田委員長
- ありがとうございました。
少し役職の変更等もございますので、紹介を先にさせていただきたいと思います。
委員の方では、桑原委員が1月から発足した総合科学技術会議の議員になられましたので、委員を辞退させていただきたいと申し出られました。それから宇宙開発事業団の方では役員の異動がございました。三浦理事がお辞めになって、その後任に池田理事が就任されておりますので、一言ご挨拶をお願いします。
- 池田理事
- 先週、事業団の理事になりました池田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。昨年、この委員会につきましては、科学技術庁におりまして、むしろ事業団を監督する立場から、その設置について注文として働きかけた経緯がございます。今回、事業団の経営に参加させていただくことになりましたけれども、本件につきましては極めて大事な問題だと思っておりますので、しっかり取り組ませていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
- 久保田委員長
- ありがとうございました。
それから内藤特任参事が就任されまして、信頼性管理総括官という役職に就かれておりますので、一言ご挨拶をお願いします。
- 内藤特任参事
- 今月から信頼性管理、品質管理について、担当することになりました内藤です。横から見て様々指導するということになると思います。よろしくお願いいたします。
私はここに来る前は、アスファルト事件の後、動燃に行きまして、業務システムの改善の指導をかなりやっておりましたので、今回もまた似たようなことになるかと思いますが、畑がずいぶん違いますので、いろいろ戸惑うことも多いのですが、ご指導の程よろしくお願いします。
- 久保田委員長
- それでは議題に入りたいと思います。今日の議題は4つございますが、その経緯をご説明したいと思います。
前回、11月29日に第3回の委員会を筑波宇宙センターで行いました。そのときには午前中会議をしまして、午後は技術研究本部と衛星システム本部の見学をさせていただきました。
その午前中の会議で議題として出ましたのが、「品質保証の強化に対する取り組み」、それから「衛星の開発強化の取り組み」、「技術基盤の強化に対する取り組み」、「アクションプランの階層別及び期間別整理」です。そして衛星の開発強化、技術基盤の強化につきましてもご意見、ご指摘をいただきましたが、最大の議論の対象になりましたのは品質保証の強化に対するものでした。
そこで様々提案も出ました。品質強化につきまして、この議事録にもございますように、そのときに出た指摘事項を今日まとめて、それに対する議論をするということになりました。その品質保証の強化に関して大きく分けて5つの議論がありました。
1つ目は、中原委員からご指摘のあったことですが、製造メーカーから見た品質保証という問題。いってみればNASDAからのトップダウンの指示とメーカーからのボトムアップの提案がうまくかみ合っているかどうか、そしてかみ合うことが重要だろうという指摘でした。これにつきましては、整理の都合もありまして、次回の第5回で報告をしてもらおうかと事務局と協議しております。
2番目のNASDAとメーカーの間で目的意識を共有する必要がある、つまり一体感を持って開発を進める必要があるというような指摘が桑原委員、蛇川委員、中原委員から出ました。これについても第5回で「宇宙開発全般に対する取り組み」というような議題で報告したいということになっております。
3つ目は独立評価をする必要がある。これの内容としては、桑原委員からの指摘でしたが、あまり細分化し過ぎると大きな点が抜けてしまう、それから現場に監督員を派遣しても、同化しないようにする必要があるだろうというような指摘がありました。これも独立評価の活動というのを具体的に第5回で報告したいということでございます。
4番目は対策の実現性ということで、それぞれの対策案というNASDAから報告された対策案は、それぞれ評価はするけれども、実際に効力を持つかどうかにはまだ疑問があるということが、桑原委員、蛇川委員、立花委員、畚野委員からそれぞれのニュアンスで指摘されまして、これも具体的な実行状況を第5回以降の会合で報告したいと思います。
5番目は背景要因分析ということで、事故、不具合が起こったときに、その背景要因をきちんと分析する必要がある。立花委員も指摘されていたのですが、アメリカのスペースシャトル事故のときのファインマンレポートとか、東大の畑村教授の失敗学とか、そういう実例を挙げて、徹底的に背景要因分析をする必要があるだろう。これからの問題を克服していって初めてNASDAが日本の宇宙開発を担っていく方向が見えてくるのではないか。そういうことによって世界一のものを目指すという気持ちでやっていただきたいというような指摘がありました。
従いまして、前のH-IIロケットもそうですが、H-IIAロケットの事故、不具合の背景要因分析を今日の会議で出していただいて、NASDAとしてはどう考えていて、その対策をどうとっているかということを今日ご議論いただきたい。
この5つが前回の品質保証の強化ということに関連して出て来たご指摘と、それの対策になるかと思います。それを受けまして、第5回以降、先ほど理事長もおっしゃいましたが、品質保証の問題は非常に重要で、前回畚野委員もこの委員会の主要なミッションはこの品質保証の強化ではないかというご発言もございました。従って1回、2回で終わるものではないという認識を持っており、ずっと続けていく必要があるだろうと思います。
いつまでやるかというのは最後にご相談したいと思っておりますが、少なくとも品質保証の強化に関しては継続してやっていく必要があるということでございます。
そういう意味で、今日の議題は、品質保証の強化に対する取り組み、特に事故、不具合の背景要因分析をやります。そのイントロになるわけですが、H-IIAロケットの打上げを延期したという事情もございまして、それは単に延期したのではなく、開発のやり方自体も再検討してみようという意味で延期されたのだろうと思っております。そういう思想から、現在の開発状況をまず報告していただいて、その後、議題の2番目で背景要因分析をした結果を出していただいてご議論いただきます。
更に、今までこういう議題もやりましょうと言っておりましたものを2つつけ加えております。特別会合で提案されている「企業との役割・責任関係の見直し」ということ、それからこの委員会で出てきたことで「アクションプランの階層別及び期間別整理」、この2つの議題です。4番目の議題につきましては、前回の第3回の最後に内容だけをご紹介いただき、議論はしていないので、これも継続して議論をします。それではまず1番目の議題、H-IIAロケットの開発状況について、柴藤理事からお願いします。
- 柴藤理事
- H-IIAロケットの開発状況です。試験機1号機は、より万全を期すために、当初計画では今年の2月に打上げる予定でしたが、13年度の夏期に延期するというご提案をして、12月8日の宇宙開発委員会で了承されております。
試験機1号機の機体製作状況です。試験機1号機については、ここに書いてあるLE-7A以外のサブシステムは製造が順調に進んでおりましたが、LE-7Aエンジンの領収燃焼試験でここに書いてある2点の現象が発見されております。
それからLE-7Aエンジンノズルスカートを新しく製作しておりましたが、冷却管の侵食が認められて、その原因究明と対策を実施いたしました。
3ページです。試験機1号機の領収試験を、10月18日に3回目の試験をしました。これは1回目で性能を調整して、 2回目で領収試験範囲の中にオリフィスで調整します。それで3回目でそれの再現性を確認する目的で試験を実施いたしました。試験そのものはうまくいったのですが、その後の点検でメッキの剥がれたものが付着していることがわかりました。
どういうところかといいますと、こちらから液体水素が流れて来ますが、ここがターボポンプのインデューサ、それからインペラになります。ケーシングAのところを10μぐらい削り過ぎたのをメッキ補修して、それでインデューサライナというのを差し込んでおりますが、ここのメッキが剥がれてしまった。
分解してみますと、ベアリングAの影響もありました。それでベアリング全交換、それからケーシングAのメッキを剥がして、インデューサライナをつくりかえて、逆にこれを膨らまして、つくり直すという処置をとっております。
どうしてこうなったかについては、4-2の資料で後ほど詳細にご説明いたします。
4ページです。もう1つの不具合は、これは水素の配管ですが、タンクのほうに戻して加圧用に戻すところのベローズの谷の部分に亀裂が生じて、水素漏れが発生しました。これも同じ試験のときです。
原因については、今までずっと試験をやっていたものは、この曲がりがずっと均一になっていたのですが、試験機1号機で良かれと思って直した治具のせいで、ここのアールが急になり、疲労で破壊したということがわかりました。
これの対策は、形状についての規定を細部にわたり設定、製造工程の安定性を向上するために定期的に抜き取り切断検査を行う。同時に、ここの荷重を緩和するために、ベローズの変形を小さくし、そのために3層構造に変更しております。これについても、後ほどどうしてこうなったかということを詳細にご報告いたします。
5ページです。もう1つの不具合実証ですが、2号機以降の機械製作をやっておりまして、検査した結果、再生冷却といって中に水素を通して冷却しておりますが、それのろう付けの工程中に、配管は大体0.5mmの厚さですが、大体半分の0.2mmぐらいのピッティングというか、中に侵食が起こっております。
その原因は何かと様々試験した結果、ろう付け後の漏れ試験を、今まではただ単にヘリウムを吹きつけて、内側から見てろう付けの具合を確認するということでしたが、その検査をもっと確実にしようということで、治具をつくって、外から加圧して漏れ検査を確実化するという工程に切り換えております。
ただそのときに、ここのところのオーリングを密着させるために、フッ素系の潤滑剤を塗っており、その後ちゃんと除去してきれいに洗ったつもりでしたが、そういうものが残っている可能性があるということと、ろう剤のバインダの炭素が影響したのではないか。そういうことが起こらないように、フッ素系の樹脂の塗布をやめるということと、バインダの量をできるだけ少なくするということと、ろう付けする前処置でバインダを十分揮発させるという処置をとって、妥当性を確認しております。次機に対してはそういうことが起こらないような対策をとっております。
ただ、これがどうして起こるのかという詳細な原因のメカニズムがはっきりしておりませんので、今後ろう付け関係も含めた材料の専門家の先生方と連携して研究を進めて、信頼性向上を図ることを計画しております。
2ページに戻ります。試験機1号機、2号機の機体製作状況はこういうことになりまして、確実性、万全を期すためにということで、夏期への延期をお願いしております。それから試験機1号機の確実な打上げに向けた措置として、4つの措置をとっております。
その1つ目が6ページにあります。特殊工程により製造する部位に対する措置ということで、1号機製造時の下請けメーカーも含む特殊工程製造データの再評価をやっております。それからLE-7A、LE-5Bエンジン開発供試体の特殊工程部位の切断検査、これは今まで試験に供したエンジンですが、それの切断検査の実施をしております。
2つめは大きな振動や衝撃が発生する可能性のある部位の措置ということで、LE-7Aエンジンの大きな振動が発生する部位について、最新の材料試験データを利用をした応力解析の再実施をしております。それからLE-7Aエンジンの燃焼試験での振動データの追加取得をやりました。これはエンジンの試験を追加してやりましたが、それで追加取得して、現在評価をしております。
3つめは品質確保に対する措置です。下請けメーカーも含めた補修工程、工程変更の妥当性の再評価をやっております。それから高圧配管破壊試験等ということで、これは高圧になる部分の配管ですが、この配管の破壊試験をして、それの余裕等を見るためにやっております。それからLE-7Aエンジンの品質向上のための試験の実施もやっております。
4つめは試験機1号機の確実性の向上/検査の充実ということで、領収試験で不具合のあった試験機1号機用エンジンについては、実際のフライトに供しないということで、新規に再製作をしております。それから試験機1号機用の射場運用用要求文書及び手順書等の再点検を実施中です。この試験機1号機用のエンジンについては、確認試験用の供試体に回す予定です。以上でございます。
- 久保田委員長
- ありがとうございました。
この議題は2番目のH-II及びH-IIAロケットの事故・不具合の背景要因分析、品質保証の強化についても関連が深いと思われますので、2番目の議題をやっていただいて、その後の議論を両方まとめてするということでいかがでしょうか。
それでは議題2の方を、内藤特任参事と原部長のお2人からお願いします。
- 内藤特任参事
- 品質保証の強化の取り組みのうち、背景要因分析の状況についてご説明申し上げます。
資料の4ページです。ロケットで4つ、人工衛星で3つ不具合の事例を挙げております。例えば1番目のH-II5号機でいいますと、燃焼ガスの漏洩ということで、これは2段目のノズルのチューブ管のニッケルろう付けのところで漏れが出ました。この背景を整理していくと、ニッケルのろう付けのところは、高温部では弱くなるという、そこの基礎知識が不十分であった。2つ目は、X線で検査したデータを参考扱いにしていたところが問題だ。それから地上試験のときに、めくら蓋をしたまま燃やした。これは単純な作業ミスということになります。
こいうふうに中身の内、特に重要なものを整理していきますと、3ページにあるように大きく5つの項目に整理されます。
1番目は技術基盤整備と計画設定上の要因です。中身は、特に材料特性データの方に不十分なものが結構多いという問題があります。それから設計検証のときにそういうものを踏まえた、もう少し検証項目を増やすべきだという問題が出てきます。もう1つは、メーカーの製造部門と研究開発部門の情報共有をもっときちんとやってもらいたいという問題が出てきます。そういったものも含めて1番目の項目になります。先ほど内容的には9つのケースを挙げておりますが、9つのうち5つがこれに該当します。
2番目は製造時の技術判定基準上の要因です。ここに製造工程解析の不備と書いてありますが、背後要因も含めて考えると、一番問題なのは、昔のベテラン技術者では常識と思って、基準なりマニュアルに書いてないというところで、様々問題が起きるケースが最近増えていますので、検討範囲、あるいは各範囲を広げることが必要になってきます。そういう問題が工程解析で特に大きい問題になります。それから関連部門の連携不備のところは、後で説明しますが、気がかり事項が出て来たとき、引継ぎのときによく問題を起こすということ、それから特に作業指示などで、目的とか背景も含めてどういう指示を出させるかという問題なども含みますが、関連部門の間の連携不備という問題が出てきます。以上が2番目で、これも9つのケースのうち5つが該当します。
3番目は信頼性・品質の向上計画の継続性の問題です。これは、ロケットについては過去6回うまくいって油断したということから出てくる諸問題と考えていただければいいと思います。これは、うまくいった部分についても、データ的なフォローとか注意力をどう維持していくかというのが基本的な問題になります。
4番目は異常/不具合処理手順等の管理上の要因というのがあります。特に連携やコミュニケーションのあり方ということで、これも後ろに出てきますが、トラブルではないけれども一応ホールドはした、だけど「まあいいか」と思って次の工程に進んだ。そういうところで様々問題が起きる確率が高いということで、関係部門とどうやって協議を義務づけるというか、ちゃんとやらせるようにするか、そういう問題が重要になってきます。それから工程変更を連絡しなかったとかいう問題もこの項目に入って来ます。
5番目は単純ミス発生防止に対する考慮面での要因というのがあります。これは、最近特に作業の効率化のために工具とか様々なものを揃えることが増えておりますので、識別管理をどう確保するかとかいうものが内容になってきます。
この5つの項目が基本的に重要なファクターになってくるということがいえようかと思います。
次に、この結論を出すまでの分析のツールですが、これは5ページです。8号機以降は事業団は「バリエーションツリー」と「なぜなぜ分析」の2つのツールを加えております。バリエーションツリーの方式は、全体の作業を時間軸に沿って並べてみて、原因と結果の因果関係の上で非常に需要な意味を持つものを特定していって、因果関係を切ることによって再発防止を強化する、そのためのツールになります。これは縦に時間軸を取って、横に組織で、座標上に何をやったというのを順番に書いていく。そういうことで評価していくことになります。
なぜなぜ分析の方は、事故・トラブルというのは、直接的な原因を除いたときには、同じことは起きにくくなるけれども類似のものは防げないというのがあります。従って、間接原因まで探して除くと、類似の事項は抑えられる。更に基盤的な原因まで抑え込むともっと広い範囲でトラブルを抑えられるという原理がありますので、背後要因について間接とか基盤の要因まで含めて分析していくという方法です。これは基本的には5段階ぐらいに割って、なぜこれが起きたかというのを詰めていく方法になります。
その適用の事例を7ページに、主にメッキ剥離のケースについての事例を挙げております。因果関係を切るというところで、切るチャンスがあったというところで重要な作業の工程部分は、I〜Vまで番号が振ってありますが、この5段階がその因果律を切るチャンスがあったということになります。
1番目の加工時の削りすぎというのは、通常はこういうことはなかったらしいのですが、これは作業ミス管理の問題になります。これが1つのチャンス。
2番目はメッキで補修しようと決めたというところがあります。メッキがのりやすい部分については、一般的なこういうやり方をとっていたらしいのですが、メッキ作業そのものが簡易メッキ装置みたいなことでやっていますし、様々ありますから、結果論として見れば、ここで慎重に詰めて決定をすべきであった。ここも因果律を切るチャンスがあったということになります。
3番目はメッキ不良発生ということで、メッキしようと思って狙った補正面そのものは目的を達成したのですが、その両脇の面のところで密着性不十分な部分ができてしまったということになります。ここも切るチャンスがあったということです。
4番目は密着性不足のまま使用したということです。スコークというのは不具合そのものではなくて、ちょっとおかしいなというものをスコークといいますが、それを見つけて、作業は一応ホールド状態にした。だけど、これはオプショナルエリアだから「まあいいか」ということで、ホールドを解除して作業を進めてしまった。ここはこの5つの中でも一番重要かと思いますが、もっと周りに相談するとか、そこの部分を緩和できる措置を考える必要がある部分になります。
最後の5番目は、中間工程検査とか総点検のときには、スコープの記録があるので、論理的には見つけるチャンスがあったということで、これは全体の状況の中で変わることもありますが、ここでも切るチャンスがあった。そのどこかで因果関係を切っていればこれは起きなかったろうということになります。
次の8ページのなぜなぜ分析のほうです。先ほどの4番目の密着性不足のまま使用したというところは、なぜなのだろうということで、その事例を挙げております。
まず行為面については、左上に技術判断不要と判断した。なぜなのだろうというのは、スコーク判定の不明確さ、基準に解釈の余地があったからと書いています。作業班に作業してもらった表ではこうなっております。ただ実際上は、これは工程中作業なので、判断基準を書くのは難しい部位だと思いますので、対策としてはたぶん知恵を動員できる関係者を集めて協議するシステムを入れていくというのが正解なのかもしれませんが、そういう部分が背景として重要になってきます。
それから判断面については、右のオプショナル範囲なのでそのまま使用と判断した。なぜなのかというのは、一番左にオプショナル部について検査規格の不明確さと書いてありますが、これは先ほど言いましたように、最近一般の潮流みたいなところがありまして、ベテランなら書かなくてもいいところを若い人向けには書かなければいけないということで、その判断事項を拡充する必要があるという部分になります。
それから中ほどの他製品の一部でも同じ判断の事例ありというのは、他でもやっているので、「まあいいか」という、そこの意識のところが問題になります。
それから右のほうは、剥げると思わなかったし、それが影響すると思わなかったというのがありますので、エンジンへの影響評価不十分というふうに分析ではなります。
更にもっと根っこのほうにいきますと、現場技術者とか検査員への製品に対する教育不十分。これも最近の一般論でいいますと、手順とかを教えるだけではなくて、それぞれの基準の意味を教えるというところまで踏み込んでやっていただかないと、ちゃんと作業ができないということがあります。
それから基盤的なデータが不足する。それからFMEA(故障モード影響解析)にメッキ工程も追加する必要があったと思います。こういうふうにだんだん下げていく。
ただ、さらにベースになる経営方針、管理方針とか、そういうところで調べた範囲では、これが問題だったのではないかというのはまだ結局出てこなかったということになります。もう1つ、9ページに酸素タンク加圧配管漏洩についてのバリエーションツリーの例を入れてあります。ここで特に重要な作業工程は、1番目がベローズ仕様検討というのがありますが、これはロケットダインの手法を使って、それらのモードで大体知っている範囲のスキルでやって、事件が起きたということで、この仕様検討のところをもう少し慎重にやっていれば、因果関係は切れただろう。
そのもとになるのが、右のベローズ要求仕様決定、ここでこういうところを気つけろというのをきちんと出していれば、そこでも切れた。
左上の専用治具製作提案のところですが、これは担当メーカーが汎用治具からフライト製作専用の治具に切り換えて、それを周りの人に連絡もしなかったという問題があります。ここでもしそういう情報共有ができていれば、あるいは気がついて因果律を切れたかもしれないということがあります。
(3)は手続き不十分ということで、お互いに連絡する、あるいはチェックするチャンスを逃したということになります。
(4)が専用治具製作/検査不十分ということで、評価試験をやらなかったのは結果論として見れば問題であった。外形はきれいにできているけれども、断面にしてみると問題が発見できたというようなケースではありますが、やはり評価試験というのは重要だということになろうかと思います。
それから酸素タンクの背景分析、なぜなぜ分析のほうは、項目と判断でまだ議論が割れておりまして、今日お出しできなくて申しわけないですが、以上、実例をということでありましたので、ご紹介申し上げました。
- 久保田委員長
- ありがとうございました。
それでは1番目の議題、H-IIAロケットの開発状況と、いまの品質保証の取り組みで、関連しているところがたくさんありますので、両方一緒にやっていただきました。ご意見をいただければと思います。
- 畚野委員
- 私は機械のことはあまりよくわからないので、それだけ余計にお先真っ暗と言ったら言い過ぎかな、これから何が出てくるかわからないなという、非常に暗い気持ちになってしまいました。これはよくわからないのですが、後のほうの説明にもありましたが、削り過ぎをメッキでごまかすというのは、そんなことは私たち素人から見ると常識では考えられないと思います。
それから治具を良かれと思って直したと、悪かれと思って直すやつはいないので、そんな程度の考え方でいいのかと。一体何で直したんだというのがここに出てこないのはおかしいのではないかと思います。
こういうのが今ここの時点で出てきたのは、たぶん今まではこんなにきちんとやっていなくて、さっきのちょっと怪しい何とかいうのがありましたが、ああいうのがあっても、エイヤッとやっていたのですね。それでとにかく何とかやってきたと思います。だから、こういう最初からやっておかなければいけないことを、いま始めたということで、これからはいくのかなという気はしますけれども、我々が聞いていて、非常に意外というか、驚くようなことが多いですね。
最後に言おうかと思っていましたが、これはみんな製造現場の問題です。桑原さんがおられなくなって、我々みたいな評論家みたいな者ばかりが増えたのではしようがないので、やっぱりちゃんと現場のそれも現役の委員をもっと補充してやってもらわないといけないのではないかという気がします。
実際に委員会でこれからやっていく検討の中身は、こういうのが増えてくると思います。この委員会はNASDAの経営の委員会ではなくて、羊頭狗肉で、実は業務改善の委員会なので、そういうことをもっと様々経験しておられる方とか、実際に現場で現役でまだおられるような方とかを増やしていかないと、私がいま思いついたような、こういうことを聞いていてエッと思うようなことが出て来て、そのままスーッと通り過ぎていくのでは、直らないような気がします。
この後の解析のプロセスというのは、私はよくわかりますし、やっぱりこういうことをやらなければいけないだろうと思いますが、これは後から言ってもしようがない。これでは電波で地震の予知をやるというのと同じです。電波で地震を予知するという研究があって、後からデータを見直しあそこに何か出ていたと、こればかりです。そんなものは研究じゃないと言っていますが、それと似たようなものです。ただし、これはロケットです。
- 山之内理事長
- 畚野さんと同じように、ともかくこの件だけの問題ではない。まさしく製造現場だけではありませんけれども、個々のテーマについては直る方法はあるけれども、これはもう少し本質的な、全体の技術体制、現場を含めた責任体制、価値観の問題だと思ったものですから、今回は打上げを延期しました。この件については答えは全部見つかったけれども、もう1ぺん全体を考え直せと、はっきりいうと、メーカーの方ももうちょっときちんとものの考え方を変えろという意味で延ばしたのです。後ほどまた専門家に追加してもらえばいいです。
私も畚野さん以上の素人ですから、どういう印象を持ったかというと、まず、「何でこんなところにメッキを使っているんだ。」という反応をしたら、「いや、こんなことはしょっちゅうやっています。」という反応であって、良いか悪いかは抜きにして、こういうミクロン程度の加工上の違いというものに対して、メッキ処置で過去やっていた。
先ほどの問題提起に答えますが、いいか悪いかは議論があるかもしれませんが、現実問題としては、ロケットの歴史の中でこれはかなりやっていましたというのが私の受けている話です。良し悪しは別ですが、今回だけ特にいいかげんにやったというわけではなくて、この程度のことはロケットの加工では過去では当たり前でありました。
ただ問題点が2つ出て来たのは、1つは、今回の場所は本来メッキでやるべきところではなかった。あちこちやっておりまして、この場所は本来はメッキで直すべきではない場所までやってしまった。しかも本来直すべきポイント以外のところまでメッキがガタガタいって、そこの仕上がりがまた悪くて、それで剥げたということのようです。これは製造現場ではよくあります。私は昔しょっちゅう経験しておりますが、そこのやり方がだんだんひどくなってきたり、レベルが落ちてくる。それが起きると、ピャッと直るという繰り返しで、私は何度経験したかわかりません。
そういう意味でいうと、私の経験の世界では、極めてよくあった問題ですし、今回の経験として、これをどう品質管理するか、もっと踏み込んで、メッキはいけないというところまでいくかどうか、これはまたちょっと議論があります。
それからベローズについて、いま説明不足のところを言うと、皆さんはベローズがここではじけると思っていなかった。そういうことはあることはあると思いますが、ただ、聞いてややびっくりしたのは、ベローズというのは他にもありますが、ほかのところはほとんど全部三重系にしてありましたけど、ここはしていなかった。起きてみて、あれというようなことがあって、その辺はちょっと抜けがあったのです。
それと同時に、認定エンジンで4台やっていて、ここは全然はじけていない。何でいよいよ主要エンジンになってはじけたかということを突き詰めていくと、実は製造過程でさっき言った治具の変更があった。何で変更があったかというと、下請けのまたその下請けで治具を直して、このほうが仕事がしやすくなったということで換えたらしいのです。それにNASDAはもちろんのこと、キーコントラクターのほうも全然気がついていない。
ところが、これは例のJCOもそうですし、私が以前いた会社もそうですが、現場の末端というのはついこうやったほうが仕事がやりやすくなるというので勝手に直すことは、一般論としては決して珍しいケースではない。
したがって、そういう意味でいうと、メッキの面についても、蛇川さんのトヨタみたいな立派なところは恐らくないかもしれませんが、私がいたような企業では、現場のパフォーマンスとしてはきわめて普遍的な現象で、よくはないですけれども。従ってこれはきわめて本質的な問題提起であるという感じを持ちました。
ただ教訓とすれば、ベローズでもそうですが、末端といえども治具をちょっと簡単に換えることについて、もっときちんとチェックできる、あるいは判断できる体制が抜けたということは、本質的な問題提起です。
それから振動問題というのはエンジンで一番怖いところですから、やっぱりここで出たかと。そういうふうに見ますと、現場でつい手を抜くと品質管理が落ちていくということが、典型的な例がメッキで起きた。
だからこの振動問題という本質的なところで、そういう現場の品質管理も含めて問題が起きたことは、この2件に限らず、ロケット全体の品質管理、あるいは技術に対するきわめて本質的な問題提起と私は考えたので、へたするとここだけの問題ではない、全体の製造カルチャーに係わるということも含めて、延期もしたし、改めて全部の点検なり、あるいは製造工程の再検討をしていただくというふうに考えたわけであります。
- 生駒委員
- 私は外資系の製造業におりますので、おっしゃったことは非常にその通りだと思います。
申し上げたいのは、アメリカもアジアも含めて製造業の品質というのは非常に向上してきました。ところが、私は外資系におりましてアジア、アメリカ、日本で全部同じ製造をやっておりますけれども、品質保証の考え方が全然違います。
日本は、まさにおっしゃったように、現場で臨機応変に作業手続きを変更する自由度というのを持たせて、いわゆる現場の改善運動が日本の品質を保証してきたという風土がずうっとあります。アメリカやアジアで同じ品質を保証するためには、逆にその自由度を減らして、マニュアルどおりにやらせることで品質を保証するということが成功してきたわけです。
まさに日本の作業員が非常にナレッジブルで優秀な場合には、現場の自由度を増やしたほうがいいということで、日本は伝統的にいまだにそれをいっていますが、JCOの事故を見ても、現状は全くそうではない状態だと思います。現場にどこまで任せて、マニュアルどおりにどこまでやらせるかという、そのボーダーラインの変更が日本の現場の人の質の違いによって変わってきております。
我々の場合には、全く同じ工場をヨーロッパを含めて作りますと、全部マニュアルどおりにやらせるということで、現場の自由度をどんどん減らす方向でいま品質保証をしております。だから日本の作業員は非常に不満がございます。提案がある場合、「こうやったほうがいいのじゃないか」ということで。
ですから品質保証の管理の仕方を、日本のワーカーの質が違っている、あるいは現場の意識の違いによって変えていかなくてはいけないのに、いまだに現場にずいぶん自由度を持たせているので、私は実はびっくりしました。
これは、単に畚野さんがおっしゃったような話より、もっと経営層の問題だと私は認識しておりまして、現場の問題よりも、経営管理の問題が非常に効いてきまして、「この経営のところがちょっとわからない」になっているのが非常に不満でして、これはやっぱりトップがどういう姿勢で現場に臨むかという問題に非常に関連していると思います。ですからそこの部分をよく考えて、切り分ける必要がある。
それから経営層の部分で、ちょっと離れたことですけれども、私が大学から企業に移ってつくづく感じたのは、大学の場合には皆さんかなり自由度にやっていてよろしい。これは官庁もどちらかというとそうですが。何千人、何万人を束ねていく一つの手法というのが、いわゆる日本が得意な方針管理と展開というか、トップがアテンションをかけると、現場がその通りに動くのです。これも私は実際に経験して非常に不思議に思うのですが、まあ事業団の場合は実際携わっている人が何人か知りませんが、何千人の人を一つにするというのは、やはり経営者の非常に大きな責任で、そこの部分がこの報告書で見えていないような気がします。
ですから事業団の理事の方と受注したメーカーのトップの人が本当に一つの方針を出して、それを共有するような姿勢が大変重要ではないかという気がしておりまして、その辺もぜひお考えいただけたらと思います。
- 鳥井委員
- 私も今までの中のご意見に全くそういうことだなと感じます。
現場から一つ提案があったら、それを正式の場に上げるということがすごく大事だろうと思います。現場からの提案を切る必要はないので、正式の場できちんとした判断をすることが大切だと思います。
例えばものすごく大量生産をしているものは、トータルとして使用する経験時間というのは非常に長いわけです。それがどんどんフィードバックされてくるメカニズムというのも、放っておいてもある程度フィードバックされてくる可能性がありますけれども、単品だと使用時間がものすごく短いです。それは経験から何か判断できないものです。技術に裏打ちされていないと判断できないものです。現場での判断というのは経験からの判断ですから、やっぱり大量生産品とこういう単発製品というのは品質管理のあり方が全く違うべきだろうと思います。
何故それが違うのか。単品生産の場合にはどういう品質管理をしなければいけないのかというのが、やっぱりNASDAのほうできちんと方針が出ていないといけない。メーカーの方は大量生産をやっている部門も持っているし、様々なものを持っているので、普通の品質管理をやってしまうという可能性があるだろうという気がするわけです。
ですから、そういうのはどこからのものはこういう管理をしろとか、どこどこのものはこういう管理をしろとか、そういうことを指示して、それは何故かということまで含めて、現場まできちんと浸透させることがすごく大事なような気がいたしまして、それはまさに経営の問題ということでもあります。
- 中原委員
- まず、前回のメーカーとの関係を重視しなければいけないというのは、様々なことが起こったときに、恐らく大部分のことはメーカーの中で起こっている可能性が強いので申し上げました。
この事例を見ますと、NASDAがいくらスペックをつくって検査をしても、メーカー自体の問題をボトムアップ的に解決していかなくてはいけないという一つの例だと思います。
それで様々な方がおっしゃったことに対して、私はメーカーを少し弁護するような言い方をしてみますと、まず、現場の人はあまり信用できないから、エンジニアが標準をきちっと決めて、それを増やすという場合には、エンジニアは現場の人以上に現場のことを知らなければいけないのですが、それがそうなっていないのが現実だということがあるように思います。
やはり現場とエンジニアの両方が歩み寄ってベターなシステムを作るということは、トータルQCは日本でもアメリカでも同じ考えでやっているわけです。ですから、今の場合は現実的に考えて、現場の人も改善するし、技術者の人ももっと現場に入り込んで標準を改善していくという、両面からアプローチが必要ではないかというのが1点です。
2番目に、経営でも、技術でも、工学でもそうですが、有限な、与えられた条件の中でデシジョンしていかなければいけないというのが現実だと思います。例えば時間が限られている、費用が限られている、その中でベストを尽くしてチョイスをする、その繰り返しが現実だと思います。
そうしますと、この打上げを延ばされたというのは、もう時間がなかったからしようがなかったという言い訳はちょっと除かれたということで、賢明だった面があると思います。同じようなことが、費用とか、人の数とか、工場の施設とか、様々現実的な制限の中で選択していかなくてはいけないというのが実態だと思います。
しかし、やはり故障につながるようなもの、こういうことは絶対にいけないんだという経験がまだ十分ではなかったということはいえるのではないか。現実的に選択するのだけれども、「これだけは絶対やってはいけない」というのはどこなのかということです。
ですからどんどん追究していくと、パーフェクトを望むようになりますが、完全なものは世の中に存在しないという面がありますので、実際的に考えていく必要があるのではないかと思います。以上です。
- 蛇川委員
- 多少現場に近い仕事をしておりますが、今日伺いまして、確かに硬質メッキで手直しするというのは、昔の高技能者も絶えずやっておりましたが、最近はそんなことをやれる人もきわめて少ない状態だと思います。
従って、伺いたいし、また意見を述べさせていただくと、まず、こういうトラブルが起きたときに、求償制度というのがあるのかないのかです。要するに原因が特定されたと。全額を払えというわけではないです。
我々の場合でも、事実は事実としてまず被害総額を出す。それに対して、原因系で大体四分六分だとか、二・三だとか、設計、あるいはどの部署の責任割合はこれ位だと。それでもまだ全額を下請けメーカーというか外注メーカーに要求するわけではないのですが、そういう被害があって、責任はこれくらいだよということをしながら、相手さんの再発防止で減免処置をするということを繰り返しているわけです。ですから一生懸命になって再発防止をし、少しでも被害を減らそうということがある意味では表に出る。その行動を監査することによって減額をしていくということをやっております。倒産してはいけないわけですから。
そのときにいつも問題になるのは、「では正直に申し上げれば逃げ手があったのか」です。例えば、「不良品を出した。」「その手直しではない方法があった。」のかと、現場の実態を見ますと、例えば代わりの素形材がない、納期は迫られるという中で、適正な判断ができるのかということを絶えず訴えられます。
我々はこういうすごい状態というのはめったにないのです。従って我々が今やっているのは、レース用エンジンと飛行機用エンジンぐらいです。それは、今日現在は必ず1つはダミーを与える。それを使わずに済んで、次のプロジェクトに使えたら、ボーナスを払う。我々が再度買い上げた格好になるわけです。ですから1つはダミーで、我々の責任で払う。そして買い戻す。
そのように彼らにペナルティーとボーナスということで、熾烈なことを一応やっているわけです。何かそういう形がないと、逃げ場がない。そうすると必ず巧妙なる手直しが行われる、あるいは何らかの工作が行われるというのは、もうこれは避けられないと思います。
例えば我々が入っても、同情してしまいます。あるいは「何とかしよう」というふうになります。そのときに、昔はよくて、「まかしとけ!」という人がいたけれども、いまは技術者が口を出したぐらいでは、とてもとても、実態としてはそれが実現できないというふうに私たちはほぼ諦めていました。
しかし、それではだめなものですから、このレース用とか飛行機用のエンジンは、もちろん全工程監査して認定して、人と工程を認定しているわけです。それをいじる場合には届けろということを明確にしていますが、そういうことが行われているのかどうかですね。それが唯一、人がいるか、工程を安定させるかという、そういう血みどろの繰り返しをやっております。
参考になればというか、何かそういったことでもしないと、末端の実態を吸い上げること、あるいはそれが正しいかどうかを議論することが、末端ではなかなか難しいのではないかというような気がしますので。ご質問やら意見です。
- 土居委員
- 私も製造ということに関しては全くの素人ですので、何か勘違いというか、違うことを申し上げることになる可能性は多々あるわけですが。
ただ、そういいましても、ソフトウェアというようなことの物づくりということ、あるいは製造現場でのアプリケーションのソフトを作るということに関してはタッチしてきたことから申し上げます。
ご説明の中でも、メーカーとの間の情報共有とか、あるいはベテランの時代には常識であって明記する必要がないのを、明記しなければいけない。あるいは背景・要因分析のときもそうです。
要は、先ほど生駒委員のお話もありましたが、欧米各国は経験知を形式知にしているようなことがかなりうまくできております。
ところが我が国は、経験知といいますか、ベテランに任せておけば大丈夫だということなものですから、それを形式化するということが今まであまり行われていない。こちらの高度情報化委員会で様々なお話を伺っておりましても、その経験知が集約されていない、あるいは形式化もされていないということで、びっくりした面があります。特段デジタライズしなくても、紙でもよろしいですけれども、何がどこにある、要するにどのロッカーのどの棚に何があるかということであってもよろしいですが、そういうことを含めて、やはり経験を蓄積し、様々なところで過去の経験を役立たせるようなことを、こういう時代になりますとますます早急にお進めになっていただく必要があるのではないかと思います。
従って、いずれこの場でもご説明があるかと思いますが、短期間ですから十分ではないとはいえ、我々がまとめた高度情報化推進委員会の報告書、提案がございますが、そういうところにも、言葉足らずかもしれませんが、こういうことに関して盛ったつもりですので、是非そういうことを踏まえてお進めいただくのがよろしいのではないかと思いました。
- 馬場委員
- 私ももちろん物作りは素人で、評論家の域を出ないわけですが、一言感想だけ申し上げます。
前回の委員会で立花さんが盛んに言っておりましたが、東大の機械工学の畑村洋太郎教授がご専門になっている失敗学のことです。今日の分析例を見ますと、まさにあの本に書かれている失敗の依って来るところを追跡していって、分析をして、究極の失敗を突きとめて、それを次に役立てるということをおやりになっているのだろうと思いました。先ほどのメッキの問題で、スコークを解除した「なぜなぜ」についてのフローチャートを見ますと、最後へいくと、製品に対する教育不十分とか、管理要因の追究不十分というようなところに落とし込んでいっているわけです。
そうすると、こういう追究不十分、教育不十分というものを解消、解決するためにはどうしたらいいかということを考えて、もちろん考えているのでしょうけれども、それに対する問題提起、課題提起を是非挙げていただけないかと思います。
それからノズルスカートの腐蝕のことでちょっと感じたのは、この腐蝕が発生したから、これからはフッ素系潤滑剤を除去するというだけですけれども、こういうフッ素系潤滑剤を使用すると腐蝕をするという科学的な知見は今までなかったのでしょうか。これは全く未知との遭遇だったのでしょうか。そういうことが触れられていないのですが、そういう知見を誰かがどこかで調べるか、知っておく必要があったのではないか。そこまでいかないと、失敗の本来の追究のところまでいかないのではないか。単にこの潤滑剤を使うと腐蝕するのだということで終わるのではなく、そういうことを知るべき立場の人がなぜ知らなかったのかというところまでいかないと、畑村教授の失敗学の学問は完結しないと私は理解しているので、是非そういう視点まで踏み込んでいかれたらいいかと思いました。
それから、今回のこれを見ていると、やっぱり物づくりの基本が非常に重要であるということを感じたわけです。先ほども出ていましたが、ロケットは大量生産とは全く違って、単品でつくっていくわけで、この品質管理ですけれども、作る人の愛着とか、責任というものと、大量生産の品質管理とはずいぶん違うのではないかという感じを非常に持ちました。
例えば蒲田の金属加工機械に取り組んでいる職人の話を聞いたことがありますが、やはりあそこでもH-IIロケットに使うような単品をつくっている職人さんたちが大勢いまして、ロケットが打上がるときには、我が事のように祈って打上がるのをテレビで観ている。非常に愛着と誇りを持っているわけです。ロケットを作っていくというのは、そういうものだろうと思います。
ですから、大量生産の品質管理の考え方から発想して物づくりの現場の体制を作り上げていくというものだけではなくて、やはり単品に取り組んでいくような誇りと、職人気質、愛着、そういうような非常に情緒的なものが何かありはしないかということをちょっと感じました。
- 鳥井委員
- 1つ質問があります。7ページの背景要因分析のところで、スコークが起草されると、その後はどういうプロセスになりますか。
- 原部長
- スコークはとりあえず紙に書いておきます。それで検査の人間がもう一度見直して、これは技術的な判断が必要であるとか、オーケーという、このままにしようかとか、そういう判断を下して処理されます。
8ページのスコーク判断の不明確さというところで、基準と書いておりますが、スコークを判断した結果をどうするかという条件の解釈がやや甘かったということでございます。ものによっては不具合と判定され、不具合処理の一連の処置がとられます。
- 鳥井委員
- その判定は、どういう人たちが何人ぐらいでやるのですか。
- 原部長
- 今回はそこが反省の一つになっておりまして、検査員が1人か2人でやったと聞いております。
- 畚野委員
- 私はさっきエイヤッとやっていると言いましたが、蛇川さんが言われたように、工期は迫っている、スペアがないというのでは、エイヤッとやってしまうよりしようがないというわけです。だから本当に妥当な判断ができるのかどうか。妥当な判断ができるような仕組みも必要です。さっき理長長が言われたメッキの問題は、私たちは昔子供の頃から、化けの皮が剥げるのと同じで、「メッキが剥げる」というのは日本のイディオムであります。だから始終あったのだろうと思いますけれども、ロケットにこういうことをやっているというのに私は驚いたということです。
- 原部長
- 先ほどから、単品物ということと、それからエイヤッでいいかげんにやられているのではないかというお話が出ておりますが、宇宙開発は少量生産であるということから、30年前から一つこういう思想があると感じております。それは、まず、NASDAスペース用スタンダードとして、いま持っている品質プログラム標準の中にありますが、 MRB(不具合品処理制度)ということをちゃんと規定しております。これがISO9000に比べても、ちゃんとボード(委員会)をつくって判断しなさい。言い換えますと、これはやたらと物を捨ててはいけない、それが合理的ですよという思想だと思います。それから最近は、製作予備品をメーカーの方から見積りを出して来ても、ほとんど認められないという状況でございます。その辺と相まって、MRBの判定がやや甘くなってきたという感じはしております。
- 大橋委員
- 開発で一番大切なのは開発の基本シナリオの書き方ではないかと私は思っております。その書き方が悪いと、せっかくの国費を使った研究でも、結局役に立たなかったというケースが様々ありまして、私自身も主に原子力のほうでそういう経験があります。今回のシナリオの一番大きい変わり目は、 LE-7の8号機の失敗で、急遽LE-7を捨ててLE-7Aに移るという大きなシナリオの書き換えがあったときに、これは宇宙開発委員会の特別会合でも議題になったと思いますが、最初はかなり楽観的な、要するにLE-7Aに変わることによって、LE-7が抱えている様々な問題点がほとんどなくなるというようなご説明でした。
様々なご忠言があって、それをもう少し慎重に、試験機の数を増やすとかして対応することになりましたが、そういうシナリオを書き換えるときに、LE-7からLE-7Aへの移行はやっぱり相当大きいチャレンジがあると私は思います。それは何かというと、コストダウンでありまして、わざわざLE-7Aにするのはコストダウンが大きな目標だったと思います。
そうすると、コストダウンというミッションを抱えたままLE-7Aに移ると、恐らく実証されていない様々なバグが入って来るだろうというのは予想されることでありますし、現に様々出てきているわけです。
ですから例えばLE-7Aに移るにしても、技術の凍結令といいますか、技術というのは実証の裏付けがなければ、後で「しまった」と思うケースが多くて、実証に優る価値はないと思いますので、LE-7で実証されたことは凍結するというぐらいの基本的方針をきちんと貫くというのが、シナリオの書き方の一番重要なことだと思います。
そういう点において、シナリオとして十分その思想が行き渡っていなかったのではないかという感じがします。
- 久保田委員長
- 私も最初、これを伺いましたとき、NASDAとしても言いにくいことをかなり分析したという評価ができると思いましたが、こういうことをやっていたのかという、先ほど畚野委員がおっしゃられたことと同じような感じがいたしました。それはそれとして、ここまでやっておられるので、ではこれからどうするかというところで、馬場委員がおっしゃられたことは私も非常に共感するのですけれども、技術的な知見が出たら、その要因を挙げるだけではなくて、今後にどうやって反映させていくか。口で言うと簡単で、その辺が一番難しいだろうと思います。その辺をもっと突っ込んでご検討いただければという気がいたしました。
それから、現場でのそういうことと同時に、もう1つ、問題になっておりましたのは、NASDAでのチェックと同時に、 NASDAと企業との関係がその背後にあるのだろうということです。
今日の後の議題で、「企業との役割・責任関係の見直し」という議題がありますが、これはかなり上のほうの話で、現場ではどうするかということにたぶんあまり立ち入っておられないのではないかと思います。今日議論があったようなことをもう少し深めていただいて、次回、次々回ぐらい、さらに続けていくことにしたいと思います。
それから、畚野委員がさっきおっしゃられた、現場を知っておられるメーカーの委員を増やすというお話もございます。この辺については、事務局とも検討させていただきたいと思います。
- 生駒委員
- 特にメッキに関してですけれども、ここに「業者」とありますけれども、実際にやられたところは受注の下請けだと思いますが、その会社にとってはどのくらい大事な位置づけの仕事なのですか。それによって経営者の姿勢がすごく違って、経営の問題と関係してずいぶんあると思いますけれども、この会社にとっては具体的にどのくらいのプライオリティーを置いた仕事なのでしょうか。
- 原部長
- このメッキは、下請けに出したのではなくて、たまたまエンジンのターボポンプを作っているメーカーで、工場がちょっと違うだけです。
- 生駒委員
- そうすると、そこの業者というのは会社の中でも高いプライオリティーの仕事としてやられて、こういう結果になったわけですか。
- 原部長
- はい。航空・宇宙に対して高いものを持っております。
- 中原委員
- 1つは、6ページに時間軸に沿ってこういうことが起こったというバリエーションツリー分析をなさっています。この「時間」というのが、リーズナブルなペースで動いているのか、あるいは納期等に迫られて、かなり無理のある時間軸で動いているのかということの調査も併せてやられたら、もっと原因が分かるように思います。それから、様々な不具合があって、現場とか、技術的な標準とか、やり方が改められて、今度はこうするというのが決まっていると思いますが、「それで十分か」という評価が要ると思います。
今、悪かったということを一生懸命言っておられるわけですけれども、これを今度はこういうやり方で解決しますという案が十分かどうか、そういう分析をやると現実的になってくるように思います。
- 山之内理事長
- 多少、今の議論の纏めと、私どもの現象から、これからのことについて申し上げます。
幾つか本質的なお話を承って、今日時点、完全に100%、こうしようとか、あるいはややどこか違うなというのが残っている部分がありますので、あえて率直に申し上げます。生駒先生、土居先生がおっしゃった、要するに昔の日本と違う、欧米と違う、暗黙知を明快な知の方に持っていったほうがいいと。テンデンシーとしては同感ですけれども、やはりストンと落ちないのは、では本当にそうやっていれば今回の事故は両方とも防げたかというと、私などは必ずしもそういうふうにならないわけです。ではメッキを全部やめてしまうかというと、そうもいかない。メッキでここからここまでいけなかったということは、やっぱりそういう失敗の経験があって初めて、ある部分はいけない。そういうことを全部積み重ねないと、本当の意味のマニュアルも、明快な知としてのデータベースもできない。
そういう意味でいうと、まあ言い訳ではありませんが、ロケットの世界や宇宙の世界というのは、決定的なデータ不足、経験不足という、その前提で物を作っていかないといけない。これは何百台つくって同じ手法だというわけにはいかないので、そこを一体どうするかというのが、頭の中ではまだ混乱していますのと、方向でそちらへ何とか持っていきたいと思いますが、それで全部片づくかというと、なかなかそういうふうにならないのかもしれない。
もう1つ本質的なのは、ともかくこれは単品生産に近いものですから、ただそれでいいというのではなくて、単品生産に近いもののクォリティーをどうやって上げていくかというのを、大量生産とは違った手法で私どもにちょっと考えさせて欲しいと思います。
それから馬場先生がおっしゃった、ともかく今度のことを活かしていくというのは本質論ですから、そういった意味で今回は、私どもができる範囲で、欠陥はありますけれども、様々な分析をさせていただいた。それから私自身も明日からメーカーに乗り込んで行って、この議論をもうちょっと深めていきたいと思います。
もう1つは、日本がこれまで50年作り上げてきた現場主導、改善主義というのが100%だめで、全部データベース管理、マニュアル管理にいくかというと、なかなかそうもいかない。その辺は、単品生産という特徴、それから日本が持っていたいい面もある。しかもそれがいきなり今日か明日というわけにはいかないので、どういう答えを持って来るかということは、メーカーを含めてもう一ぺん考えさせていただかないと、観念論での考察になってはまずいものです。次回を含めてぜひ勉強させていただきたいと思います。
- 鳥井委員
- 1つだけ考えておいていただきたいのは、たとえばQCとか、そういうことを通すと、現場が「自分で解決することはいいことだ」ということが営々と続いてきた。今でもいいことだと。今おっしゃられた通りですけれども。それはしっかり意識して対処しないと、何か変なフリクションを起こすことになりかねないと思います。
- 久保田委員長
- ありがとうございました。NASDAの考えを理事長にまとめていただきまして、失敗を失敗で終わらせないようにお願いしたいと思います。この問題はまた折に触れて議題にしたいと思いますので、いったん議題2を終わりにしまして、関連する議題3の企業との役割・責任関係の見直しに移りたいと思います。これについては斎藤理事からお願いします。
- 斎藤理事
- これまで一連の失敗が続きまして、様々なご指摘をいただいており、参考資料9〜11ページに書いてあります。細かい説明は省略します。宇宙開発事業団の評価委員会の報告書は平成10年11月に出されておりますが、ご審議していただいているときに、H-II5号機の失敗があり、それらも踏まえてご指摘をいただいたものです。その中で、企業との役割分担ということで、言われておりますのは、事業団が技術面ですべての責任を負っている、また契約者の品質管理等が曖昧になっているのではないか、もう少し産業界がより主体的にできるように関係を発展させて、それぞれの役割を見直したほうがいいのではないかというご指摘でございます。
10ページは、5号機の失敗を踏まえ宇宙開発委員会に設置された基本問題懇談会の中で、企業と事業団との係わりの問題に触れている部分です。ここでも適切な役割分担が必要だということで、やはり企業の能力が活用できるところはより多くという、基本的にそういう考え方の方向でご指摘をいただいております。
11ページは8号機の失敗を踏まえて宇宙開発委員会に設置された特別会合でのご指摘です。この会合ではもう少しフォーカスされており、失敗の原因になった個所のインターフェース問題についての議論がここからスタートを切りまして、プライム契約を含めて、企業の責任をもう少しはっきりさせた方向にいく必要があるのではないかという指摘等が書かれております。
2ページに戻りまして、これらを踏まえつつ、宇宙開発事業団としての問題認識の点が中ほどに書いてあります。宇宙開発事業団におけるロケット、衛星開発については、技術導入から始まり、キャッチアップを目指し、独自の技術に切り換えるべく努力をしてきたわけです。それが次第にフロントランナーに近づくに当たって、先端的な技術とミッションを開拓するフェーズへ近づいてきました。それに対応するための開発の進め方とか、体制とか、そういうものが十分できていなかったのではないかというのが総論です。
一方、世界的に見ますと、国内も一部そのようになってきておりますが、宇宙の実用化と産業化が進んでおりまして、企業の自立化と産業化のための基盤の強化も並行して必要になっています。
これらを踏まえて宇宙開発事業団としては、下に書いてありますように、それぞれ企業と事業団がどういう形で役割を分担していくべきか、それぞれの間でどう係わるべきか。その係わり方の問題として、契約と監督・検査のあり方はどうあるべきか。また、これは比率の面からいいますとモチベーションとも関係しますけれども、企業の自立のためにNASDAがすべきことは何なのか。そういう点を意識しながら改革を推進しています。
3ページ以降、もう少し具体的な説明をさせていただきます。役割分担の考え方ですが、NASDAの限られたリソースを有効に活用しつつ、新しいミッションと技術を開拓し、かつ確実なプロジェクトを実施し、そして企業の自立を促進することが望まれるわけです。そのために以下のように役割をはっきりさせていこうとしております。
まずNASDAの役割ですが、ここに4つ挙げております。1つは新しい事業の企画立案と推進です。中身は資料に記載させていただきます。
次の先端的技術の研究開発も、技術の動向とニーズを踏まえつつ、それに基づく戦略的な方向性を定めて研究開発をしていくということです。
3番目は、様々起きている現象の中に、やはり基盤技術が十分でないという点がかなりありますので、必要となる共通的基盤的な部品、機器、サブシステムレベル等の研究開発、更に様々な検証をしていく、設計をしていくためのシミュレーションの技術とか、解析評価の技術、それから先ほど様々議論がありますが、信頼性とか、品質管理の技術としてどういうものがあるか、品質を向上させるための技術にどういうものがあるという点の研究開発を行います。
4番目は、先ほど情報化の話もありましたが、これまでの経験、成果をどういうふうに蓄積、体系化して、活用できるようにしていくかという取り組みです。データベース化とか、情報インフラの整備・運用などです。情報システムの高度化に関する取り組みについては、次回以降、もう少し具体的に説明させていただきますが、ここではこういう取り組みをしております。
更に、これはいわずもがなですけれども、様々な設備とか、施設の整備という共通的なものは当然これからも進めていくことになろうと思います。
4ページは、企業のほうの役割です。企業においてもNASDAと協力して国の宇宙開発事業を推進していただくと同時に、独自の技術革新を図りつつ、我が国の宇宙産業の発展に貢献していただくことが期待されているわけです。
もう少し具体的にいいますと、当然我々だけで技術開発ができるわけではありませんので、宇宙開発に関する基礎技術と製造技術に関する研究開発については、是非やっていただきたいと思います。それから宇宙開発の事業化。それからフライト品の製造に代表されるように、製造については分担していただく必要があります。それから品質向上とコストダウンのための活動というのは期待されるところです。
それでは事業団と企業との係わりを関連してもう少し整理します。技術開発については、全く初めて、新しいものに挑戦するという活動と、例えばある程度フライトでデータが取れて、更にそれを技術的に安定させる活動にここでは大きく分けて整理をしております。
それぞれに対して事業団が関与する範囲とか、それぞれ区分けしていく必要があるわけですが、それらの区分に当たっては、当然ながら技術の成熟度、戦略性に基づいて仕分けをしていかなければいけない。
先ほど申し上げたような役割分担にふさわしい関係を構築していくために、以下に申し上げるような形をとっていこうとしております。
まず新規技術の開発の分野ですが、事業団としては当然のことながら技術動向やニーズ等の把握をして、戦略計画を立てて、研究開発を推進する。それから開発に入る前にリソースの投入を十分行って、その過程の中で様々な設計作業、試作作業、これがいけるかどうかの評価を行って、先ほどのご指摘にもありました計画の設定の仕方が後々様々影響してきますので、実現性のある仕様と計画を設定することが非常に重要だと認識しております。開発段階に移行した後は、企業と協力して行う設計活動、それから製造については基本的に企業にお願いします。後は仕様の管理とか、フライト品の検証と評価、それぞれの立場をできるだけはっきり分けるようにして、事業団としての立場を分けていくような形にしていきたい。
この新規技術について企業に期待するところは、まず開発に移行する前の段階としては、企業から先端技術の提案を受けて、研究開発に係わる活動にも参加していただきたいし、特に実際に物が作れるかどうかの検討と研究、それから試作などがこのフェーズの代表的なものかと思います。それから開発段階に移行した後は、設計は協働で行うわけですが、フライト品の製作と品質保証については企業の方でお願いしたい。
ロケットとか人工衛星は、先ほど申し上げましたようにある程度試験フライトなどで実績があって、これがさらに技術的に安定して、最終的には競争力のあるものを目指して、信頼性と品質がより向上するための活動が必要になるわけです。このフェーズにおいて事業団がやるべきことと企業でやっていただくことを分けてあります。
まず事業団としてやるべきことは、フライトデータの蓄積と解析、それを踏まえた改良。品質とか信頼性については、様々な企業が参加しますし、それぞれが役に立つことは非常にあるわけで、それらの蓄積と、それらを知識化して提供するという活動。それぞれの企業で使われるような部品とか材料の研究開発と試験データの提供。最近様々起きているクリティカルな部分の個体のバラツキによる影響ということで、繰り返し製造していく過程において、一品生産ということもあって、これらの影響がかなり出ておりますので、これらの影響を確認するための試験、さらに、バラツキが出ても、検査とか、解析とか、そういうもので検出できないかと、そういうための研究。これら全体を含めて、蓄積された情報とか知識を集約して、それを実際に活用していただくための作業として、情報インフラ、そのソフトウェアも含めたインフラの整備。それから技術移転がこのフェーズにおけるNASDAの作業かと思います。
企業においては、フライト品の製造と品質を責任を持って実施していただくと同時に、製造に関する品質データの収集と分析、更に工程の安定化のための活動は当然お願いしたいことです。
以上申し上げました役割分担とそれぞれの関係の中で、どういう形で契約と監督・検査制度を変えていったらいいかというポイントについてです。契約の問題ですが、事業団が主体として活動する部分で、企業の支援をいただくことが当然必要になるわけです。事業団の中における制度としては、委託の制度。これは基本的には事業団が責任を持って企業でやっていただいた結果を出していただくという契約です。次に、フライト品等の製造に関して、企業の責任をはっきりさせる契約としては、製造請負契約というのがありますが、これにおいて、それぞれのケースに応じて責任関係をできるだけはっきりさせていくという切り分けをできるだけしていきたい。プライム契約の推進ということが指摘されたりしております。事業団としても認識しております。メーカー間インターフェースというのはどうしても出てきますので、それらのトラブルとか、NASDAの調整作業の改善をする、責任関係の明確化、企業のほうで最終的に技術が安定していくと、自立していただくことが必要になりますので、そういう自立化の促進、それから技術移転の促進のためには、こういう方向が必要かと思っております。こういう方向を採るに当たっては、個々にはそれぞれの技術の成熟度、プロジェクトの性格とか規模に応じてプライム化ということを検討していっております。
資料の8ページですが、監督・検査制度の改革です。問題認識と見直しの考え方ですが、最初に書いてある監督・検査制度というのは、どちらかというと会計制度からきておりまして、契約で要求したものに対する適合性を確認するということです。その中には品質を保証するということも含まれておりますが、基本的に仕様が確定しているものについては非常に適した制度になっております。しかしながら、事業団で行っている様々な研究開発の行為は、企業と事業団が協働で行わなければいけない行為は非常に多いということで、現在、様々な契約については、監督員としてこれらの共同研究開発行為が行われているわけですが、これらがそういう意味では一体として少しまぎらわしくなってきているということもあります。そこの識別を、協働開発者として関与するという部分と、契約が適切に履行されているということとをできるだけ切り分けていきたいというのが趣旨です。
それから宇宙開発事業団におけるリソースを有効に活用するためには、先ほど言いました1と2の項目の分担の考え方に沿ったような形で、監督とか検査の具体的な細部を含めて見直す必要があるのではないかと考えております。
それでは今どういう方向でしているかというのが2に書いてあります。先ほど言いましたように、開発担当者の業務と監督員の業務を分けていく。技術問題の解決には、監督員ではなくて、プロジェクト開発担当者が企業の開発担当者と協働で当たることを徹底する。次に企業が中心になって行う活動とか、品質管理活動の主体的・自立的方向を促すため、監督行為とか、承認する文書の範囲とかについては、縮小する一方で、役割としては、NASDAとしてはその製品が受け入れられるかどうか、機能するかどうかという検証とか評価の活動に重点を移すということです。
それから品質確保と検証評価をきちっとしていくためには、技術とか、情報の基盤を充実する。これは事業団が使うのみならず、企業も一緒に使っていただく基盤整備を充実していくというのが方向です。
- 久保田委員長
- この問題は、外部評価とか、特別会合でも指摘されていた問題でして、その問題点と、改革の方向をNASDAがどう考えているかということを説明していただきました。
- 畚野委員
- 1(役割分担の考え方)と2(NASDAと企業の関係)の部分は仕事の役割分担ですけれども、こんなのは当たり前の話なので、いまさら出て来るのはおかしいとも言えますが、ここで整理されたことに意義があるかと思います。こんなのは当然のことで、これからも、今までもそうなので、ちゃんとやっていないとおかしい。お互いに両者が共通認識を持つ意味で整理されたという程度のものだと私は思います。3(契約形態と監督・検査制度)は、今までの議論も様々踏まえて、なかなかいい方向だと私は思いますが、まだ精神訓話でして、これを本当にちゃんとやる、具体的にどうするかというのをそのうちに聞かせてもらわないといけないと思います。
- 鳥井委員
- 最近、技術者倫理という本を2冊ほど読みましたが、2冊とも例のチャレンジャー号の話が出ていまして、あのとき低温になるとシールがだめになるということを見つけたのは、実はメーカーでもNASAでもなくて、その間に立っていたコンサルティング会社なのです。そのやりとりを見ていますと、NASAといえどもそのコンサルティング会社のオーケーが出ないと打上げを決断できない状況にあって、コンサルティング会社そのものはNASAの意向を反映してオーケーを出すわけですが、その何とかという技術屋さんはそれに対してずうっと抵抗するという仕掛になっています。監督員を別途設けるといっても、それをNASDAが持つのか、コンサルティング会社みたいなものを育てて、そこに委託をして、業務としてきちんと監督をするというのか、そこは、一品生産の品質管理のプロフェッショナルというのを日本の産業の中に育ててもいいような気がします。NASDAが抱え込んでやると、NASDAの人事権の範囲内だし、NASDAの制度の範囲内で何かをやるわけだし、メーカーがやるといっても、メーカーの人事権の範囲内でやるわけです。
そうすると、これは本当か嘘か知りませんけれども、NASDAだと何とかスケジュールを守りたいというような意向が働いた中で何かやるかもしれませんし、メーカーのほうは何とか利益を上げたいというモチベーションの中でやるかもしれない。しかし、技術の健全性を守ることが利益に結びつくという集団があれば、業務としてそこをきちんとやって、それはNASDAにいてやるより、メーカーにいてやるよりはるかにちゃんとやるかもしれないという感じがしたわけです。だからそういうところがさっきのスコークの処理なんていうのをやってもいいかもしれないという気がします。だからやはり立場が違う人が参加している必要があるのではないかという感じがします。
- 中原委員
- 前半のところは、試験装置などメーカーになくNASDAが持っているものがいっぱいあります。こういうものは、メーカーから何か改良したいと思って提案があったときに、それを評価することはごく普通だと思いますが、そのようなことは現在行われているのでしょうか。メーカーが中途の段階でこれを改良してみたいが、評価してみてくださいと、依頼が来て、NASDAがチェックするようなことが開発のプロセスの中でしょっちゅう行われているかという質問です。宇宙センターにしかないような設備がいっぱいありますよね。メーカーでは自分で設備を持っていなくて、こうしたらどうかと思っても。
- 富田技術研究副本部長
- 部品関係とか、技術評価する装置は筑波宇宙センターのほうで前回見ていただきました。それの治工具、それと併せたインターフェース部分がだいぶありますが、そういうものについては、やはりメーカーさんの提案もありますが、我々も協力し合って、インターフェースを調整しながら改善しております。それが現状でございます。
- 中原委員
- そういうことがもっと頻繁に行われるといいと思いました。それから、後半の契約形態と監督・検査制度というのは、これはいい方向だと思いますけれども、現行の様々な規制によってできないようなことがあるかどうか。この通りやろうと思っても、何か別の法律があって難しいとか、そういうことがありますか。全部この通りやれるということでしょうか。
- 斎藤理事
- 細かいところは当然様々と詰めないといけない部分はありますが、方向としては、この方向で大きな矛盾はないと思っております。ただ、個々のところ、例えば監督員と協働開発の関係者を切り分けるかどうかとかについてはもう少し具体的に詰めるとか。個々のケースになってきます。
- 石井副理事長
- 今のことで言いますと、例えばプライム契約とかは、法律上の規制があるわけではないですが、プライム契約をやれば、当然それに伴う責任ということを相当詰めてやっていかなければならない。責任を追及すればするほど、先ほど蛇川先生がおっしゃったボーナスとか、逆のことが必要になってきます。そうなると、公的資金の世界でやっているということで、財政当局とのからみとか、会計検査院とか、そういうところにも十分理解されるようなシステムを作っていかないと、だから規制ではないですが、公的資金を使っていることによる一般的規制を国民に理解されるような形態でこれを実現していかなければならない。単にプライムだといってやるだけでもいけないのであって、そのプライムに伴う責任、あるいはその責任を十分果たしうるような何らかの措置を別途講じてやる、これのかみ合わせが非常に難しい。そういう意味で、ここも即やるといわずに、「検討している」という表現になっておりますが、今後十分検討しながらそちらの方向で様々とやっていきたいと考えております。
- 中原委員
- 今お伺いしたかったのは、そういうことなのです。保険の問題とか、様々ありますね。
- 畚野委員
- 今言われたのは、確かに一番難しい問題です。古くさい会計制度のままで、明治時代以来の考え方でやっているのです。だから理解を得ないといけない。だめと書いてないけれども、実はやるのはものすごく大変ですね。後からグズグズ言われたり、次のときに金をくれなかったりするわけです。だからこれはNASDAだけでなしに、応援する意味で、周りがやっぱりそういう声を出さないとだめだ。そうしないと、新しいこういうやり方に入っていくのは、とても抵抗があるというか、難しいと思います。また、さっきの開発担当者と監督員の問題ですけれども、開発担当者はいいですが、私はさっきこれからどういうふうに固めていかれるのか言ってもらわなければいけないと言いました。前に桑原さんが言われましたが、監督員というのは別のほうがいいような気がします。今はNASDAがやっている。だから監督員のオーケーを取れば、結局NASDAに責任を全部持たせる感じで、後は野となれ山となれと言ったら言い過ぎかもしれませんが、そういう精神構造があるのです。とにかく認めてもらうことだけが大事であって、認められたらもうこっちの勝ちと。きつい言い方ですけれども、やっぱりそういうことがあり得るので、この監督員制度を一体どうするのか、どこまでやるのか。これは責任問題と直結しています。
それから、この資料の企業との役割のところで、技術的な部分だけしか出て来ていないと思います。この後の問題、さっき蛇川さんが言われたようなものも含めて、金の払い方も含めて、責任の問題も含めて、トータルとして一体どういうふうに構築するかというのが大事だと思います。
- 久保田委員長
- おっしゃるように、独立評価というのが必要だということと、監督員をどうするかということですね。鳥井委員も具体的に提案されておりましたけれども、そういうのは今後検討することかと思います。法制度のことは私もよくわかりませんが、畚野委員がおっしゃったように、一番難しいことかもしれませんので、この改革委員会でこういうところが問題だというのをやっぱり声を大にして言っておくことが必要かと思います。最後にどういうふうにまとめるかということですが、そういうところで強く出したいと思います。
- 馬場委員
- これを見て私の非常に感じたことは、いま製造業の現場でEMS(Electronic Manufacturing Service)という形態が出て来て、昨年の10月にソニーがEMSの世界最大のソレクトロンという企業に工場を売却しました。このEMSというのはなかなか日本語に直りませんが、「製造業請負専門会社」というような言い方が一番いいだろうと思います。企画・開発・研究というような部分はNASDAがやって、実際に物を製造する、この場合はロケットですが、これは企業がやるというのは、形態としてはこのEMSと非常によく似ています。もちろん製造現場にこのEMSというような一つの形態が出て来たのは、ITという技術革新があって、物づくりが効率化できる、あるいはしてきた。それは品質の信頼性とコストという2つの面で大きな貢献ができるということから、製造物の部分は特化させようということです。大量生産で安くていいものをマーケットに供給していくというものとロケット製造とは一緒にはできないわけです。しかし経営のあり方としては非常に似ている部分がある。当然物づくりの一端ですから、そういえるわけです。ですから、そのEMSのあり方について、NASDAでもやはり参考に一度見ておく必要があるのではないかと私は感じました。
- 土居委員
- 8ページで「NASDAは検証・評価活動に重点を置く」というのは、それはそれで大変結構なことだと思います。要するにソフトウェアに関しては、ソースコード及び関連文書は納品の一部として受け取られるのですか。今まではどうも違っていたようですが。
- 斎藤理事
- なっているものと、なっていないものがあって、個々の契約の条件の中で設定されております。
- 土居委員
- その「なっていない」と言われるのは、要するに製造を担当している企業固有の、知的所有権を含めたものに係わる部分ですか。
- 斎藤理事
- 結局そういうことが交渉のターゲットになりますので、経費との関係とか、先ほど言いました、どっちの責任とか、そういうことが全部議論になりますので、事業団としては基本的にたくさん蓄積して、レビューできるように、評価するようにしたいのですが、個々の問題としては必ずしもそうならない場合もございます。
- 土居委員
- その辺がかなり難しい面があって、国費を使う場合には、「フタをしちゃって」ということをやらせることもあるわけですが、必ずしもそれがいいとはいえません。要するにノウハウを蓄積していくことが重要なわけです。但し、検証するときには、ブラックボックスを検証するというだけでは済まない、ホワイトボックス化しなければいけないというのが多々あるわけです。従来とは違って、ソースコードは関連文書を含めてとにかく徹底的に手に入れられるという方向で動かれるのがよろしいのではないかと思います。
- 久保田委員長
- それでは、様々ご意見をいただきましたので、最後のまとめに残しておくことにし、この議題をいったん終わりにしたいと思います。
4番目の議題で、アクションプランの階層別及び期間別整理ということに移りたいと思います。これについては、外部評価、基本問題懇、特別会合から様々指摘事項がありまして、それに対してNASDAがどういうアクションをとるかという、アクションプランを作ったわけでございます。これも、あまり漠然としたものではなくて、階層別及び期間別に整理した方が取り組みやすいのではないかというご意見が第1回、第2回の委員会でございました。それを受けて、いま言った2つの分け方で整理したというものでございます。第3回の続きでございます。
- 斎藤理事
- アクションプランをご説明したときに、階層別になっていなくて非常に分かりづらいというご指摘をいただき、前回、我々としてはこういうふうに理解していますということと、更に細かいところについては整理の上、最後はまとめてお出ししますが、考え方として、2ページの左のほうに書いてあるように、経営レベル、実施レベル、現場レベルという形としました。これは通常の、ISO9000を含めたマネージメントシステムの中で、経営レベルがやるべきこと、それぞれのプロジェクトがやるべきこと、現場がやるべきことというふうに当然のことながら分かれてくるわけです。
アクションプランの中で書かれているのは、H-IIA初号機の打上げまでと、それからすでに走っている既存の衛星計画等までと、それから長期については、このアクションプランからははずれておりますので、初号機の打上げまでと、それ以降既存の計画に対してというふうに大きく分けられると思っております。
3ページですが、経営レベルが本来やるべきことは、基本的には目標の設定、ここでは表現としては「事業の重点化」と書いてありますが、事業の目標をきちっと重点を定めてはっきりさせるということです。課題になるのは、リソースの問題、それから組織と役割分担の問題というのが当然問題になります。その他に、情報化というものを使って、全体が確実で効率的な運営ができるような形に持っていくというのが、もう1つの大きな柱になっております。それぞれの実施レベルにおいて、技術の開発、ミッションの開拓、それから開発段階に入っているプロジェクトの確実な遂行、そして得られた成果の還元という形になってくると考えております。
4ページでは、章立てから見ますと、4章に初号機打上げまでにやるべきことと、残りの部分と、フェーズとしては分けられます。
5ページに、例として、実施レベルと現場レベルでアクションを切り分けている例があります。ちなみに、ここではアクションプランですから事業団の行為が書いてありますが、この「現場」という中に、必ずしも事業団と企業との関係が入ってなく、実際の製造を担当している企業のほうのアクションというのがわかりづらくなっており、前回、少し中途半端な資料という格好になっていたきらいもありました。もう一度次回に各企業におけるアクション、こういう改善・改革の取り組みの現状について説明をさせていただきたいと思っております。
- 久保田委員長
- 参考資料の宇宙開発委員会が昨年12月に作った「我が国の宇宙開発の中長期戦略」という資料をお手元につけております。16ページのあたりにこれに関することがありましたので申し上げておきます。
- 馬場委員
- 省庁再編、行政改革がスタートを切ったわけですけれども、宇宙開発委員会とNASDAとの関係で、今回変わった点をご説明してください。
- 斎藤理事
- 新しい宇宙開発委員会は「宇宙開発事業団に関すること」という形に特化されております。その内容は何かといいますと、宇宙開発事業団の基本計画に関する部分、それでは基本計画というのは何かという話に次になるわけです。それから事業団の切り分けについては、現在宇宙開発委員会の委員の先生方と事業団の間で議論をしております。我々が伺っておりますのは、宇宙開発委員会が作成された基本戦略部会の中で、宇宙開発事業団が今後目標とすべき内容についてまとめられて、それに基づいて宇宙開発事業団がそれをどういうふうに実施するかというのをパッケージで切り分けようと。どこで切り分けるかについては、現在調整中でございます。
- 山之内理事長
- この経緯は馬場さんもよくご存じで、強い問題意識をお持ちだということは基本戦略部会でも度々伺いました。先日、今度新しく宇宙開発委員長に井口前東大教授がご就任になりまして、私ども幹部が招かれまして、これからどうするかという打ち合わせをやったところですので、その辺のご報告を若干したいと思います。
議論になっているのは、宇宙開発委員会は新しいフレームワークの中で何をすべきか。もう1つは、その下に具体的にどういう部会をつくるべきかということを議論をしております。と同時に、そういう状況ですから、宇宙開発事業団と宇宙開発委員会でこういう議論を月に2回ぐらい精力的に進めていこうということになっております。そこで議論になりましたのは、いま斎藤から申し上げましたように、宇宙開発事業団を中心として、これからの宇宙のあり方、あるいは基本計画は当然事業団の分野の宇宙開発委員会としてやるべきことである。
私のほうから申し上げたのは、宇宙の開発に対して、単なる当事者の事業団ではなくて、やや中立かつ公平的な立場から、様々な事象についてものを言っていただく組織というのがあった方がむしろありがたいし、そういう役目をお願いしたい。
2番目は、様々な技術問題、あるいはトラブルが起きたときに調査、それに対する公平的な判断については、やはりお願いする必要があるのではないか。これを技術部会なり事故調査部会に幾つか分けるかどうか、その辺は別として、一つ大きなドメインとして、そういうテクニカルな問題があるだろう。
それからもう1つは、宇宙利用といいますか、これから宇宙事業をやっていくについて、今のただ単に狭い範囲ではなくて、それこそメディアから、いま話題のITSから、宇宙というものがもっともっと様々な産業界で使っていただける可能性があるのではないか。それはむしろ宇宙開発事業団という次元をこえて、宇宙開発委員会というフレームワークの中でやっていくべきではないかという議論を行っております。
同時に、新法では宇宙開発委員会は宇宙開発事業団だけの監督となっていますが、昨日も、三機関をどうしていくかという議論がありまして、航空宇宙科学研究所、宇宙科学研究所をどうするかということが、ホットな事業となりつつあります。
先程お話もありましたように、「文部科学省になってくると、宇宙開発事業団だけと言っておれなくて、少なくとも文部科学省のレベルにおける宇宙開発部門をここでやらざるを得なくなるんじゃないの?」と言ったら、「そうですかね」「そんな気がしますね」という話になってきました。
今後もし何らかの時点で国家レベルで宇宙政策をどうするかという議論になった場合には、当然内閣調査室から、環境庁から、産業経済省から、全部係わってきますので、どこでそれをやるかといったら、「これはまたここで受けなければならないことになるかもしれないよ」という議論もあったということだけはご紹介しておきます。
- 久保田委員長
- それと関連してたぶん馬場委員がおっしゃりたかったのは、今年の1月から総合科学技術会議が発足して、そこで日本全体の科学技術政策を議論する際に、その中で宇宙開発がどういう位置づけになるのかと、そういうところで議論が忘れ去られてしまうと何にもならないという危惧感がおありで、その関係と宇宙開発委員会はどうなのだろうかということもおっしゃりたかったのだろうと思います。私自身が現にそう考えております。
- 山之内理事長
- これは極めて偶然、2、3日前に、笹川大臣に呼ばれまして、興統括官もご一緒で、これは個人の問題もあると思いますが、「俺は宇宙が好きだから、絶対頑張れ。」とのことでした。率直にいうと、私どもと文部科学省の担当局長、課長が呼ばれて、「本当に大丈夫か」ということで、1時間以上やってまいりました。大臣が「俺は絶対にサポートする。これをやらなきゃだめだぞ。その代わり逆に、今度落としたらタダでおかんぞ」と、そういう話もありました。
まず1つご指摘があったのは「今までやっていたトラブルの原因を極めてきちんと掴まえて生かしているか」。次は「H-IIが5回連続して成功したのに、何で2発落っこったんだ。そこの本質的な原因を突きとめているか。そこがきわめて本質的な問題だぞ」ということですね。
今の大臣というのは、ご自身も製造業をやっていらっしゃるものですから、「これはやはり非常に難しい技術だし、個体差というものが響くということの過程から、そういう個体差というのはどうしても出て来るし、職人芸に頼るところがあるから、そこをいかに個体差というものを無くすようなシステムなり、監督体制を強化することをきちんとやっていかなければいかんぞ。」というようなご指摘もありまして、現段階では、関心がアット・モーストに強いというのが現状でございます。ただ、これは人が替わっても同様かどうかはよくわかりません。
- 畚野委員
- 今は、たまたま人のファンクションで関心が高いのかもしれませんけれども、実は総合科学技術会議で私はいままで「宇宙のウの字もない」と言っていますが、非常に軽く扱われていますね。だからやっぱりそういうのはアピールしていくよりしようがないと思います、今もう動き出した以上は。
- 久保田委員長
- まさにそうだと私も思っております。
- 生駒委員
- ちょっとはずれるかもしれませんが、さっきのNASDAと企業との関係でもありますが、衛星の打上げの部分を、私の個人的な考えでは、できるだけ早い時期に民営化する。全体の事業を民営化するというのは難しいと思いますけれども。
国際競争力の点とか、先ほど伺っていますと、様々な契約上、会計上の問題等を含めて、やはり民営化の方向が正しいのではないかというふうな個人的な考えを私は持っておりますが、全体の宇宙開発の中ではそういう議論はなされているのでしょうか。
- 斎藤理事
- 先ほど「企業の自立」ということを申し上げましたが、自分たちの認識としては、宇宙開発事業団は基本的に研究開発するための機関だと思っております。全部が例えば産業化とか自立にいくものではなくて、渡せるものはできるだけ早くそういう形になるべきだと思っております。先ほど言いました企業との役割分担で、できるだけそのようになるよう技術開発とか、渡すための方策とか、国の機関としてやるべきことと、そういうふうに整理をさせていただいておりますので、内容に応じて考えるべきではないかというのが我々の考えです。
- 柴藤理事
- 具体的には、例えばH-IIロケットの失敗でだいぶトラブっておりますけれども、H-IIAがちゃんとでき上がりますと、私たちだけではなくて、もう数年前に科学技術庁のほうで技術移転の政策を作っておられます。ですからそれにのっとって現在ロケットシステムというロケットメーカーが中心になって作っております。そちらがNASDA以外の衛星の打上げを受託するということで動いておりました。たまたま失敗したもので、いまちょっと鎮静化しておりますが、H-IIAロケットがうまくいき出すと、そっちのほうが動き出すと思っております。そうしますと、そちらはもう技術移転して、ロケットシステムがNASDA以外のミッションも取り込んでくるということで、民営化への動きを少しずつでも進めていこうという準備はしております。
- 生駒委員
- スケジュールは。
- 柴藤理事
- スケジュールもありましたが、後発機の失敗で、「いつ」ということがなかなか言えなくなりまして、できるだけ7月の打上げを万全を期してやりますので、それの成功した後、まあ2、3回成功すれば、かなり具体化していくと思いますので、慎重にやっていきたいと思っております。
- 中原委員
- この委員会の第1回で畚野委員とか、馬場委員から予算をもっと増やさなければだめだという応援演説をいただいたわけですが、きょうの山之内理事長のお話ですと、笹川担当大臣は絶対に応援するということですけれども、具体的な、予算の形でなく、そういうのが出て来ているのでしょうか。
- 山之内理事長
- 今回私は予算折衝にまいったわけではございませんので、ちょっと即答をいたしかねますし、それとこれとはちょっと私は違うと思います。そういったことで取り組んでいただけることと、いま柴藤が申しましたように、私どもは結果が出て来ればかなり様子が変わってくる可能性はあると思いますが、何分、逆にいま天下国家はそもそも財政再建という話が強くなっていますから、そこは何ともいえないというのが現実の問題だろうと思います。
- 久保田委員長
- それでは、この議題は終わりにしてよろしいでしょうか。こういう階層別と期間別に整理したということで、アクションを採るのにかなり分かり易くなっているという気がいたします。しかし、これもまさに画に描いただけではいけないので、後どうやっていくかということが最も重要なことだと思いますので、その辺はNASDA内部でもよくご検討いただければと思います。
残された時間で、今後の会合の審議事項のご相談をしたいと思います。お手元に資料4-5というのがございます。すでに3回やっておりまして、その小さな字で書いたところがすでに終わったところです。今日は第4回で、この4つを行いました。「品質保証の強化に対する取り組み」は非常に重要な問題で、継続してやりましょうということでございます。前回のときも、今度は企業とNASDAとの協働、あるいは企業においてどう取り組みが行われているかということも議題にしたらどうかという提案がございましたので、第5回では、「品質保証の強化に対する取り組み(その4)」として、企業における取り組みの強化状況を報告していただいて、意見と助言を行います。それから最初に出した議題が幾つかありまして、それも考えていきます。1つは高度情報化の推進に対する取り組みでございます。これについては、先ほど土居委員がおっしゃられた高度情報化委員会の報告ということも出ておりますので、そこでご紹介いただいて、ご議論いただくということがよろしいかと思っております。
それから宇宙開発全般に対するNASDAの考え方。先ほどアクションプランにも関連して様々出ておりました。リソース重点分野等。これについてNASDAはどう考えているかということをここで議論したいということでございます。
この3つを今度取り上げたらいかがでしょうか。そうしますと、「専門的人材の育成活用に対する取り組み」というのが議題としてまだ残っております。これを第5回に入れてしまうのは、時間的にも、議論の内容的にもちょっと無理ではなかろうかという気がいたします。
さらに、品質保証の強化を重点的にやりましょうといっておりまして、もし第5回で更にこういうところも議論したほうがいいというのが出て来れば、それを第6回に入れるというような案でございます。
最終的に、先ほどチラッと申しましたが、具体的な改革実施案、ご意見、ご助言を入れて、こういう意見、こういう助言があった、それに対してNASDAとしては具体的にこう改革していきますというのを最後に作った方がいいのではないか。それを最後にして、まとめということにしたいと思っております。
そうしますと、第1回のときに議論がありましたが、あんまりダラダラとやってもしようがない、もう今年度いっぱいで終わりにしたらいいのではないかというご意見もございました。それにのっとりますと、3月下旬の第5回で終わりになるわけですが、いま私が申しましたように、残った議題と、最後の改革実施案ということをやると、どうしてもやはり第6回までいかなければいけないのではないか。
同時に、せっかくH-IIAロケットの議論をしていただいたので、その打上げが夏期になっておりますので、その打上げ結果の報告を聞いて終わりにする。こういう原案ですが、いや、もうやっぱり第5回ぐらいで終わったほうがいい、あるいは第6回で終わったほうがいいというご意見がございましたら、出していただいて、大体の方向を決めたいと思います。
- 鳥井委員
- もう一点きちっと議論しておく必要があるという感じがします。それはどういうことかといいますと、例えば今日のフッ素とスカートの関係ですが、たぶんこういう現象が起こっているのを発見したのはわりと初めてに近いかもしれない。いや、そうじゃなくて、たくさんあるのですか。日本のこういう大きなプロジェクトというのは、その結果が学術に貢献することはあるけれども、そこのプロセスで出て来た様々な事象が学術研究に貢献することはほとんどないです。つまり、様々困った問題にぶつかったときに、例えばこの問題で言いますと、フッ素が本当に悪いのか、フッ素と金属との反応のメカニズムはどういう反応が起こるのかとか、そういうことがはっきり分かってくると、二度とばかな真似はしないで、こういう薬剤は使ってはいけないとか、学術的な知識が社会に定着するわけです。
そういうメカニズムを作っていけば、社会の知的基盤というのはずうっと上がって来て、日本がこういうプロジェクトをやることが日本の知的基盤を上げることに貢献します。ただロケットを上げて、成功しましたというだけでは、知的基盤を上げることには何にも繋がっていないです。
私はずうっと思っていますが、日本のプロジェクトは全てが、そこの裏の学術へのフィードバックが無いもので、それが知的基盤の構築にはほとんど繋がっていない。ですから、100億、150億かけてプロジェクトをやるけれども、それはみんな誰も使わないし、何の知的基盤の構築にも役に立っていないというのが現状です。
先端的なことを様々やったら、それを何とか学術の世界にフィードバックして、知的基盤を上げていくというメカニズムを作っていく。それがたぶん品質保証の一番の根本だろうと思うので、こういうところがその辺のメカニズムをどうやって構築していくかということを少し議論したほうがいいのではないかという感じがします。
- 畚野委員
- 私は今日の話を聞いて、2点引っかかるところがあります。1つは、今言われたように、品質保証は、事例、対象報告ばっかりです。今日なんか見ていると、アナリシスをかなりやっていかれるというのは分かりますけれども、やっぱりただ事例報告にしかすぎない。事例報告をベースにしてやっておられるので、別のことで同じようなヘマはやらないような検討がもうちょっとできないのかと思います。
もう1つは、今日の「企業との役割・責任関係の見直し」では、私がさっき言いましたように、第3章あたりは、あれではまだ具体的に一体どうするのか、何も見えないし、更にその後ろの、もっと広い意味での責任関係も含めて、トータルとして責任関係を一体どうするのか、その辺をもうちょっと検討して出してもらう必要があるような気がします。ただ、そのために先へ先へ延ばすのではなくて、この流れでやられるのは私はいいと思いますし、今の時点でだめというのは何も見当たりませんが、議題はこれだけに限らず、前からの宿題はきちんと入れていただきたい。
- 中原委員
- 当初、年度末というご意見が出たときには、H-IIAロケットの打上げは今年の2月の予定でした。それで我々としてもH-IIAロケットが打上がったということを見届けたいという気持ちがございます。
- 久保田委員長
- それでは、いま畚野委員がおっしゃられたように、具体的な事項、議題を考えて入れていきまして、基本的には第7回までこの案の通りやらせていただきたいと思います。それから、いま鳥井委員がおっしゃられた、単に打上げたというだけではなくて、社会の知的基盤を上げるということは、私も非常に賛成で、共感をしております。特に私どものように教育畑におりますと、こういう宇宙活動を通じて次世代の人たちの教育に使えるのではないか。こういう宇宙活動をしていると、これは大きなことを言えば将来の人類の資産になるわけで、それを教育にも生かして、単に技術ではなくて、社会への還元、貢献ということにも生かしていきたいという気がしております。
先ほどの中長期戦略の出来栄えについては、様々議論がありますが、宇宙活動をそのように捉えようと言われているのではないかと思っておりますので、鳥井委員がおっしゃったことと関連して、私も今後各方面の方にお願いしたいと思っております。
それでは、委員会は7回までで、議題は事務局と相談して入れさせていただくことにいたします。
それでは、どうも活発なご議論をいただきましてありがとうございました。本日の会合は以上で終わりたいと思います。