タイ北部の常緑林、最も乾燥する乾季後半に大量の水蒸気を大気中に放出-新しい森林モデル予測が観測結果と一致-
海洋科学技術センター
宇宙開発事業団
地球フロンティア研究システム(宇宙開発事業団と海洋科学技術センターの共同プロジェクト)の水循環予測研究領域・陸面水循環過程グループの田中克典研究員は、タイ北部の常緑林から大気への水蒸気放出が最も乾いた乾季後半に最大になることを新しく開発した森林モデル(図2)を用いて世界で初めて明らかにした。また、このモデルの予測結果は、水蒸気放出の季節変動の手がかりとなる樹液流速の観測結果と一致した(図1)。
この森林モデルは2002年1月1日発行の「Ecological Modeling」に掲載される。
背景
タイの森林には落葉林と常緑林がある。落葉林は乾季に葉を落し、葉からの蒸散がなくなる。また地表も乾いている為、地表から水蒸気が大気に放出されることはない。 一方、一年中葉をつけている常緑林も、乾季に大気・土壌ともに乾燥しているとき(資料1)、植物体内の水の損失を押さえるために気孔を閉じ、これによって水蒸気の放出が著しく低下すると考えられていた。実際、1970年にPinkerらが観測を行ったところ、蒸散は見られなかったと報告されている(Journal of Applied Meteorology 19, 1341-1350, 1980年発表)(資料2)。それ以後、この研究に対する新しい試みは行われていなかった。成果
新しく開発した森林モデルを使って、タイ北部の常緑林について水蒸気の放出量をシミュレーションしたところ、常緑林は乾季後半の蒸散によって大量の水蒸気を大気に放出した(図1)。これにより、常緑林がポンプのように土壌深くにある水分を汲み上げ、大気中にばら撒いていたことが判った。GAME熱帯プロジェクトによる、蒸散の季節変動の手がかりとなる樹液流速の季節変動における最近の観測結果もモデルが示す結果と一致し、乾季後半に常緑林からの水蒸気が大量に大気中に放出されていることが実証された。今回得た成果は、アジアモンスーン地域における水循環の予測精度の向上に役立つとともに、森林が水資源に果たす役割を考える上でも重要な資料となり得るであろう。|
|
図1 森林モデルによる森林から大気への水蒸気放出のシミュレーション結果
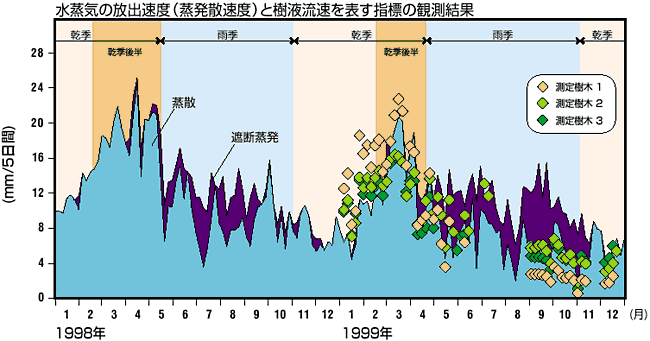
- 森林から大気への水蒸気放出の計算値は乾季後半に大きいことを示した。
- 蒸散速度の計算値と樹液流速の観測結果とが一致。
- 森林モデルによる遮断蒸発量は、全降水量の11 %。これも遮断蒸発の観測結果と一致した。
図2 新しい森林モデル(図解)
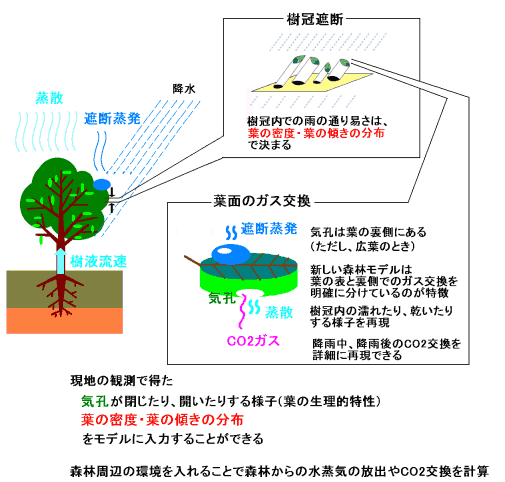
図2の解説
新モデルはタイの森林のエネルギー収支・水収支(大気への水蒸気の放出も含まれる)・CO2ガス交換をシミュレーションするために開発された。
タイの季節帯には雨季、乾季があり、雨季には、樹冠表面で捕らえられた雨が大気に蒸発する成分(遮断蒸発)が重要になると考えられていたことから、従来のモデルに降水の遮断とぬれた葉からの蒸発のメカニズムが加えられた。新しい森林モデルでは、現地調査で得られる、1)葉の生理特性、2)葉の鉛直密度分布、3)葉の傾き、4)土壌の性質をもとに、森林周辺の環境要因(日射量、大気の放射量、温度、湿度、風速、降水)から、森林内部で起こる複雑な現象を計算し、森林全体の水蒸気の放出を計算することができる。また、森林内部で、雨がふっていときの葉の濡れる様子、雨が降り終わった後の乾く様子を再現できる。
資料1 森林周辺の環境(観測結果)
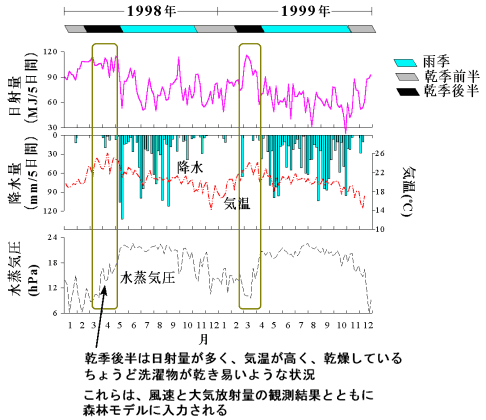
資料2 Pinkerらが行った常緑林の水蒸気放出の観測
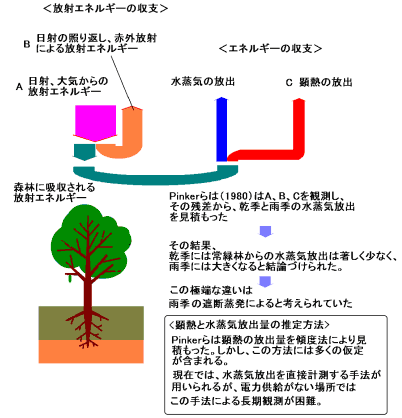 |
Pinkerらは1)傾度度法で顕熱の放出を求め、2)放射エネルギー収支と3)顕熱放出の残差から常緑林の雨季と乾季の水蒸気放出を算定した。
1)傾度法 |
資料3.用語解説
落葉林
ある時期、葉が落葉する森林。タイの場合、乾季に落葉する。
常緑林
一年を通じて、葉をつけている森林。
蒸散
植物は気孔を開いたり、閉じたりしながら植物体内からの水蒸気を出す。蒸散とはこうした現象のこと。植物は蒸散をすることにより、葉の温度が極端に高くならないように温度調整している。
樹液流速
植物は地中にある水を根から吸い上げ、葉から蒸散する(ごく一部は葉内で光合成に使われる)。樹液流とはその途中の水の流度。
遮断蒸発
森林に降った雨はすべて地面に到達せず、一部は植物表面に付着する。遮断蒸発とはその付着した水が大気中に蒸発する現象のこと。
気孔
葉にある小さな穴。この穴によって植物体内と大気とがつながって、水蒸気を大気に放出することができる。またその穴が大きいほど、大気に水蒸気を放出し易くなる。
葉の生理特性
気孔は、日射量、CO2濃度、葉の温度、湿度、土壌中の水分といった要因で刻々と、開いたり閉じたりしている。ここでいう葉の生理特性とは、こうした要因で気孔が開いたり閉じたりする性質のこと。
葉の傾き、葉の鉛直密度分布
葉の傾きは森林内部での光や雨の通り易さなどに影響する。葉の鉛直密度分布は森林内部での光(放射)の伝わり方や大気の拡散に影響する。
蒸散抑制
気孔を開いたり閉じたりして蒸散をコントロールすること。極度に乾燥している状況にさらされているときは気孔を強制的に閉じて植物体内の水分の損失を防ぐこともある。