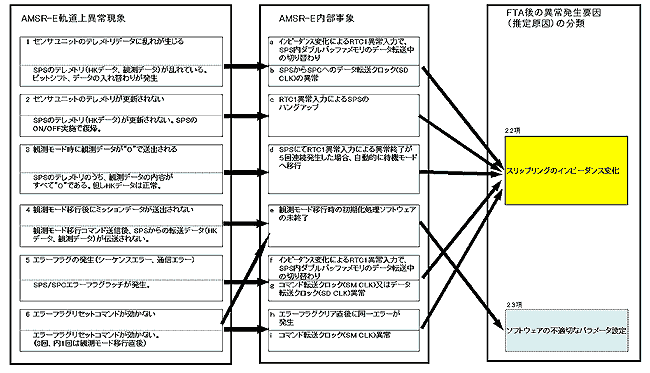改良型高性能マイクロ波放射計(AMSR-E)の
軌道上異常事象についての原因究明
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
1.事象の整理
1.1 発生の経緯
AMSR-Eにおいて発生した異常事象は、打ち上げ10日後の2002年5月15日に最初の異常が発現した。異常事象は、約2週間継続した後に発生頻度は減少し、2002年6月11日以降発生していない。
発生した異常事象は、下記6種類に分類される。
| (1)センサユニットのテレメトリデータに乱れが生じる | :多数発生 | ||
| (2)センサユニットのテレメトリが更新されない | :1回 | ||
| (3)観測モード時に観測データが“0"で送出される | :2回 | ||
| (4)観測モード移行後にミッションデータが送出されない | :3回 | ||
| (5)エラーフラグの発生(シーケンスエラー、通信エラー他) | :11回 注1 | ||
| (6)エラーフラグリセットコマンドが効かない | :7回 |
1.2 AMSR-E動作概要と異常事象の発生箇所
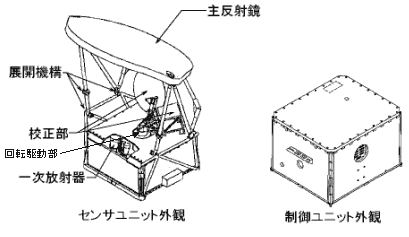 図1.2-1 AMSR-E外観図 |
AMSR-Eは、40rpmで回転するセンサユニットとそれを制御する制御ユニットの2つのユニットから構成される。 それぞれのユニットには、信号処理部(SPS及びSPC)が搭載され、その間の通信は、回転駆動部のスリップリングを介して行われる。 衛星との通信インタフェースは、制御ユニット内のSPCが行なう。 今回の異常事象は、その発生状況を考慮すると、SPC-衛星間でのI/Fにおいての問題ではなく、SPC-SPS間における問題だと推定される。 |
2.原因究明
2.1 原因の推定
AMSR-E軌道上異常事象1〜6についてFTA(fault tree analysis:故障の木解析)を実施し、異常事象発生要因の絞り込みを行った。サマリを図2.1-1に示す。
さらに、計算機による解析、EMを用いた検証、ソフトウェアのソースコードの解析を行い、異常事象のメカニズムを推定した。
| <推定原因のまとめ> 以上より、次のとおり原因を推定した。 |
|
| (1) | スリップリング部のインピーダンス値の変化 [事象1、2、3、5、6] スリップリング部のインピーダンス値が変化したため、SPS-SPC間で伝送エラーが生じ、テレメトリ等の異常事象が発生した。 |
| (2) | ソフトウェアの不適切なパラメータ設定 [事象4] SPCのソフトウェアが自己診断の終了処理をする際のパラメータ設定が不適切であったため、観測モード移行コマンド送信後、観測モードへ移行するのに長い時間を要した。この時、自己診断を継続しているため、SPSからの転送データが伝送されなかった。 |
2.2 スリップリングのインピーダンス変化
| 今回の軌道上事象の原因は、以下の2つのいずれか、または、これらが複合したメカニズムが要因であると推定される。 | |
| (1) | 地上試験および保管期間中に僅かに大気開放された時に生じたブラシの吸湿等により、軌道上初期回転時のブラシの摩耗量が多く、約10日を要して比較的厚い二硫化モリブデン皮膜を形成し高頻度ノイズを発生。水分蒸発と共にブラシの摩耗率は低く安定し、摺動継続により皮膜は除去されノイズ発生が無くなった。 |
| (2) | 打上前約3年間に生成された微量の硫化銀等や、可能性は小さいが、熱真空試験時にリング表面に微量に付着したフッ素系グリスや不良導体コンタミが、軌道上初期回転時にブラシ材と共に摩耗/転移/再付着を繰り返し、約10日を要してリング表面にむらのある皮膜を形成し高頻度ノイズを発生。その後の摺動継続による摩耗等で皮膜は徐々に除去されノイズ発生が無くなった。 |
2.3 ソフトウェアの不適切なパラメータ設定
ソフトウェアのソースコードを解析した結果、事象4の発生原因は、観測モード移行の初期化処理において実施する自己診断処理の終了判定パラメータが不適切であり、現判定条件では処理終了条件の成立は、確率的なものであり、観測モードに移行するまで時間がかかったためと判明した。
尚、本機能は、ADEOS-II AMSRにはなく、EOS衛星とのインタフェース確保のためAMSR-Eのみに追加されたものである。
また、何故上記の様な不適切なパラメータが設定されたのか、調査したところ、本機能を追加する際に用いたソフトウェア要求仕様書の記述が十分でなかったことが原因であると判明した。
3.是正対策
3.1 AMSR-Eへの対応
|
|||||||||
 |
|
||||||||
|
|||||||||
3.2 ADEOS-II AMSRへの対応
ADEOS-II AMSRに対しては、スリップリングによるテレメトリ異常(事象1〜3、5、6)に対して以下の対応を実施する。
(尚、事象4は、AMSR-E特有の処理であり、 ADEOS-II AMSRには該当しない。)
| (1) | 打ち上げ前の対応
|
||||||||
| (2) | 打ち上げ後の対応 リフレッシュ運転実施後から打上げまでの期間は、非回転状態となるため、軌道上での当該事象発生の可能性は否定できないが、発生しても初期運用期間中に沈静化すると予想される。 |
3.3 他プロジェクトへの反映
3.3.1 スリップリング部のインピーダンス変化
| (1) | スリップリングに関する信頼性技術情報を発行し、以下の事項について注意を喚起する。
|
||||||
| (2) | 過去の軌道上の衛星において類似の事象の発生の有無を調査し、知見の共有化を図る。 |
3.3.2 ソフトウェアの不適切なパラメータ設定
既開発ソフトウェアから一部変更を行ったソフトウェアについては、信頼性技術情報を発行し、以下の事項について注意を喚起する。
| i) | 回転動作によるタイミング信号を使用するコンポーネント試験では、公差の最大/最小値で試験を実施する。 |
| ii) | 回転動作によるタイミング信号に基づいて、モード遷移制御を行う場合には、タイミング信号の公差を考慮し、タイミングチャート等を用いてソフトウェア仕様書を記述する。 |
3.3.3 その他(留意事項)
飛行実績があるカタログ品でも、人工衛星開発メーカーでの使用実績が無い場合は、意図した使用方法に適するか十分検討する様に、信頼性技術情報を発行し、再度、注意を促す。
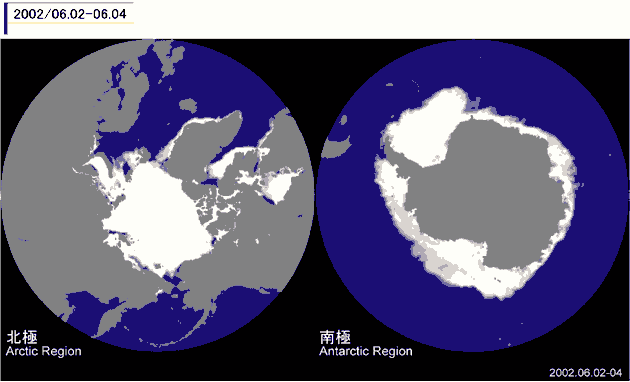
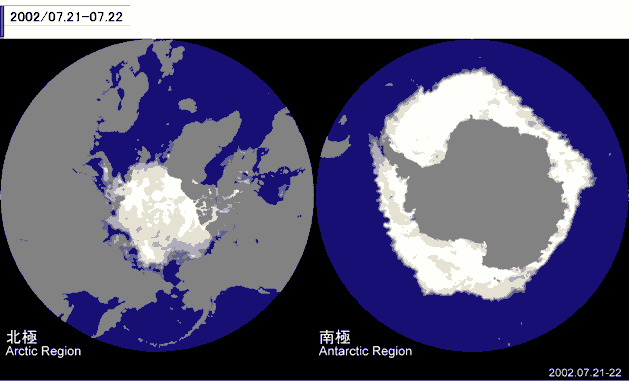
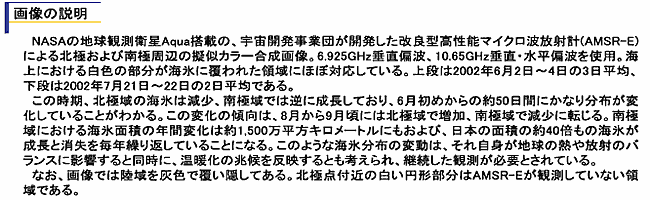
|
|