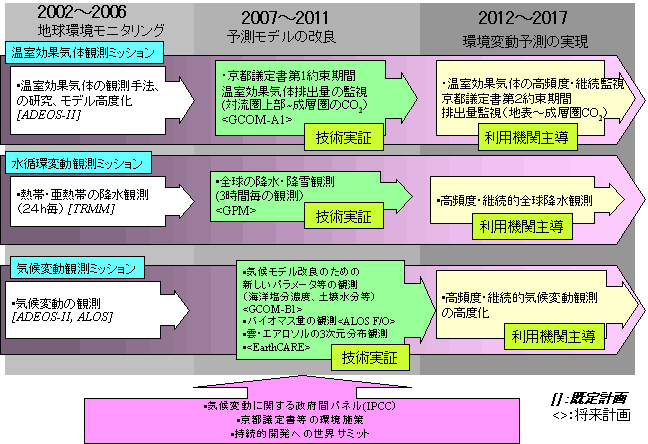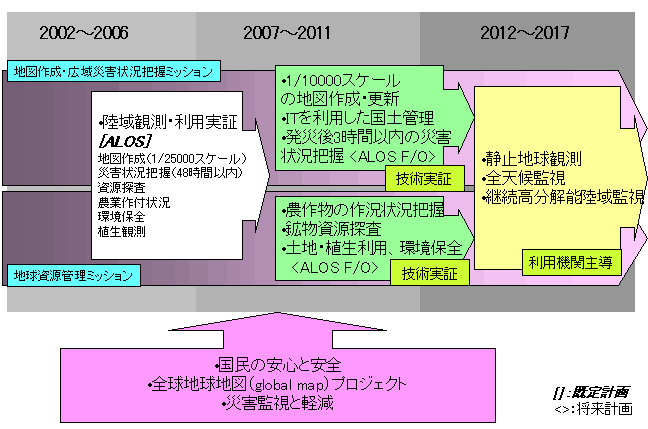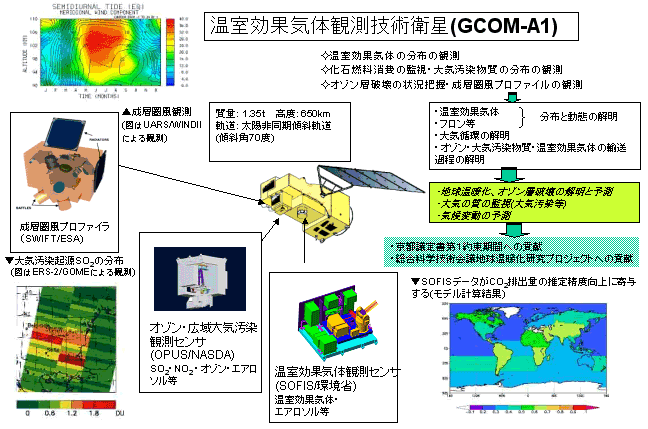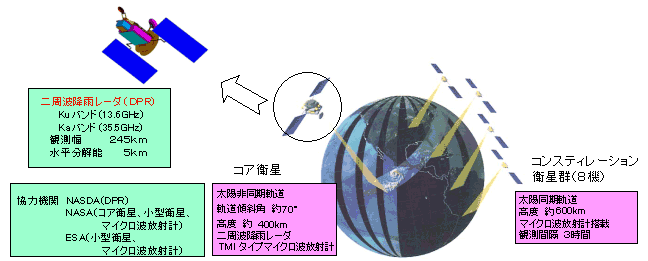本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
1. 10年後の地球観測の目標
(1)地球環境監視
- 緊急性・必要性の高い『地球温暖化問題』に重点的に対応。
- 国際的な協力体制のもと10年後に高頻度・継続的観測システムを構築
- 衛星観測で得られたデータの利用を国際条約の遵守、環境行政、気象予報等への反映、国民の生活の質の向上に貢献
(2)災害監視・資源探査
- 衛星を用いた広域災害情報監視、地図作成、各種モニタリング(地球資源管理)手法等の確立を通して、国民生活の安心・安全に貢献
(3)環境整備
- 観測データの処理、提供、アーカイブ技術等利用しやすい環境の整備
| ※ |
5月15日に宇宙開発委員会資料「今後の衛星開発の進め方について」論点の取りまとめ(骨子案)より引用 |
2.研究開発の進め方
(1)地球環境監視ミッションの優先順位
- 温室効果気体観測ミッション(地球温暖化の原因物質の観測)
- 水循環変動観測ミッション(地球温暖化に伴う主たる影響の観測)
- 気候変動観測ミッション(地球温暖化の影響の観測)
(2)災害監視・資源探査ミッションの優先順位
- 衛星地図作成・広域災害状況把握ミッション
- 地球資源管理ミッション(農業、林業、地下資源、沿岸環境など)
| ※ |
5月15日に宇宙開発委員会資料「今後の衛星開発の進め方について」論点の取りまとめ(骨子案)等より引用 |
3.地球観測の実施にあたって考慮すべき事項
(1)宇宙利用の戦略的な拡大
計画策定にあたり、利用機関と研究開発段階から連携し、利用機関主導の定常利用へ向け橋渡しを段階的に実施。
(2)日本の得意技術を踏まえた地球環境観測等の促進
観測センサーとそのデータ処理、解析技術の開発への重点化。
(3)先進国の一員としての我が国の貢献
国際分担による全球観測システムの構築と運用。
(4)利用者が観測データを容易に利用できる環境(アーカイブ、処理、提供など)整備の推進。
| ※ |
5月15日に宇宙開発委員会資料「今後の衛星開発の進め方について」論点の取りまとめ(骨子案)等より引用 |
地球環境監視のミッションシナリオ
災害監視・資源探査観測のミッションシナリオ
4.NASDAと利用機関の役割分担
宇宙機関の研究開発資源を有効に活用し、利用先導の新しい研究開発を行うために、NASDAと利用機関との役割分担を以下の通りとすることとしたい。
(1)NASDAにおいては、次の業務を実施する。
- 先端性、汎用性の高いセンサとその処理技術、衛星バスの研究開発
- 技術実証プロジェクトの利用機関と適切な分担のもとでの実施。
- 観測データの処理システム、検索・保存システム等の研究開発
(2)利用機関に対しては、次の業務の分担を想定する。
- 定常観測システムの整備、利用
- 特定用途のセンサの開発
- 技術実証プロジェクトの適切な分担のもとでの実施
- 特定用途のための高次処理システムの開発、整備、運用
| (3) |
利用促進のための「データ・アーカイブ」の重要性は認識。利用者にとって利便性が高く、かつ効率的なシステムの構築を、利用機関の適切な役割分担のもと進めたい。 |
次期地球観測プロジェクト候補
GCOM(地球変動環境観測ミッション)-A1
-温室効果気体観測技術衛星-
| 1.目的・必要性 : |
温室効果気体排出量・吸収量の、実測値に基づいた亜大陸規模での的確な把握手法を開発し、京都議定書第1約束期間における評価に資するとともに、これを基礎として京都議定書第2約束期間以降の途上国を含めた国際的枠組み作りに寄与。 |
| 2.利用・協力機関 : |
環境省、ESA |
| 3.打上げ時期 : |
京都議定書の第1約束期間(2008-2012年)対応を考慮しつつ今後検討 |
| 4.分担(案) : |
| ・NASDA |
: |
衛星バス、オゾン・広域大気汚染観測センサ(OPUS)、地上システム、打上げ(今後要調整) |
| ・環境省 |
: |
温室効果気体観測センサ(SOFIS)、SOFIS地上システム |
| ・ESA |
: |
成層圏風プロファイル観測装置(SWIFT)、データ受信支援局、SWIFT地上システム |
|
| 5.今後の要調整・検討事項 : |
|
| ・ |
GCOM-A1後継機にむけて、A1の技術移転を考慮した衛星開発 |
| ・ |
打上げサービスの購入にあたっての環境省との応分負担 |
|
GPM(全球降水観測ミッション)
-水循環変動観測ミッション-
| 1.必要性 : |
地球温暖化に伴い最大の影響が出る全球水循環変動の観測と予測、台風、集中豪雨の予報精度の向上 |
| 2.利用・協力機関 : |
NASA、総務省(CRL)、ESA、国土交通省、気象庁など |
| 3.打上げ時期 : |
NASAの構想との整合性を配慮しつつ今後検討 |
| 4.分担(案) : |
| ・NASA |
: |
コア衛星バス、マイクロ波放射計、GPM副衛星、地上システム |
| ・NASDA/CRL |
: |
二周波降雨レーダ、DPR地上システム、コア衛星打上げ(今後要調整) |
| ・利用機関 |
: |
データ処理設備 |
|
| ・ESAなど: |
GPM副衛星(マイクロ波放射計衛星)、地上システム |
| 5.今後の要調整・検討事項 : |
|
| ・ |
打上げサービスの購入にあたっての利用機関との応分負担 |
| ・ |
GPMに対する日本の貢献内容 |
| ・ |
DPR研究開発におけるCRLとNASDAの役割分担・資金負担 |
|
全球降水の高精度、高頻度観測
TRMM(熱帯降雨観測ミッション)の高精度、高頻度化
| (1) |
全球化(熱帯・亜熱帯域のみから温帯・寒帯域まで) |
| (2) |
高頻度化(衛星群による3時間毎観測) |
| (3) |
| 高精度化= |
降雨強度推定精度向上、弱い雨の観測、
降雨/降雪の区分(DPRの活用) |
|
|
GPMの社会的貢献
天気予報精度向上、集中豪雨の予測
地球温暖化、気候変動の解明
水資源管理、河川管理、洪水予測
農業用水の確保、穀物生産高の予測 |
|
|
|