標準型以降のH-IIAロケット開発の在り方
平成14年5月10日
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
これまでの議論
標準型H-IIAロケットの在り方について、平成14年4月17日の宇宙開発委員会においてNASDAより以下のとおり報告し、審議いただいた。
- 標準型H-IIAロケットについては、情報収集衛星等我が国の重要な衛星打上げに対し、これまでの打上げと同様の万全の体制で取り組むことが肝要
- 一方で、標準型H-IIAロケットを我が国の「基幹ロケット」として捉え、 我が国の宇宙輸送の自在性を確保するとともに、信頼性向上等を図りつつ、基幹ロケット技術を成熟・維持させることが重要
- これらを効率的かつ着実に進めるためには、宇宙関連機関及び民間企業の総合的な取り組みによるべきであり、今後の打上げ実績を蓄積しつつ、打上げ事業について適切な時期に民営化することが望ましい
標準型H-IIAロケットのラインナップ
 |
 |
 |
 |
|
| 機 体 識 別 名 称 | H2A202 | H2A2022 | H2A2024 | H2A204 |
|---|---|---|---|---|
| 静止トランスファ軌道投入能力(ton) | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| 打上げ予定の衛星例 | ADEOS-II | MTSAT-1R | DRTS/USERS IGS | ETS-VIII |
現行の増強型開発の目的
 |
|
 |
||||||
|
||||||||
| 10 トン | 低軌道打上げ能力 | 17トン | ||||||
| 4 トン | 静止トランスファ軌道打上げ能力 | 7.5トン | ||||||
| 285 トン | 打上げ時総重量 | 410トン | ||||||
| H-IIAロケット 標準型 |
H-IIAロケット 増強型 |
|||||||
現行の増強型の開発状況
| ■ | 開発の状況
|
||||||||||||
| ■ | 検討の必要性 宇宙ステーション補給ミッション及び将来の大型ペイロード打上げに対する拡張性と輸送コストの改善 |
H-IIAロケット打上能力向上の検討案(一例)
| 現行の増強型 (H2A212) |
拡張型案 (H-IIA+) |
||
| 機体形態 |  |
 |
|
| 打上能力 | GTO HTV |
7.5 15 |
8 16 |
| LE-7Aエンジン数 | 3 | 2 | |
| 技術課題 | エンジン・クラスタ 非対称形態 - |
エンジン・クラスタ - 1段5mタンク |
|
検討の前提
| ■ | 国際宇宙ステーションへの補給
|
||||||||||||||||||
| ■ | 大型衛星への対応 大型衛星の動向として、商業静止衛星は年々大型化 |
||||||||||||||||||
| ■ | 打上げコストのさらなる低減 今後台頭が予想される新型ロケットは、いずれも複数衛星打上げにより衛星1機あたりの打上げコストを大幅に低減する方向。我が国の基幹ロケット民営化後の重要な課題。 |
今後の検討方針
| ■ | 標準型試験機の打上げ成功によって検証されたH-IIAロケット技術に基づき、標準型に続くH-IIAロケットについては、システム及び開発方式等について一年をかけて検討することとしたい。 | ||||||
|
【参考】今後予想されるロケット群とH-IIA
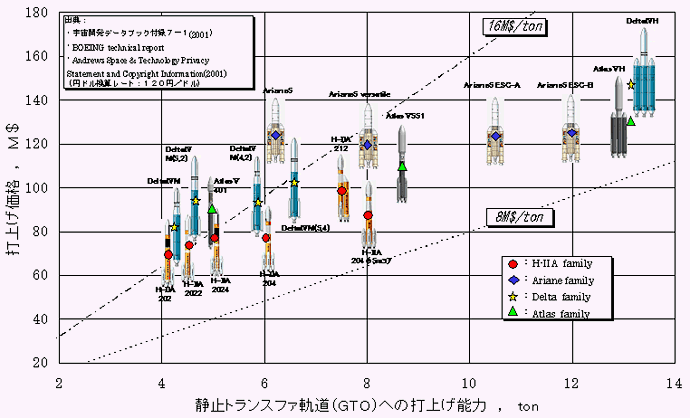
|
|