黒潮が日本周辺の気候へ与える影響を衛星観測データから発見
宇宙開発事業団
海洋科学技術センター
地球フロンティア研究システム(宇宙開発事業団と海洋科学技術センターとの共同プロジェクト)気候変動予測研究領域の谷本陽一研究員(北海道大学地球環境科学研究科助教授兼任)と、地球フロンティアとハワイ大学が共同で運営する国際太平洋研究センター(IPRC)の謝 尚平教授、野中正見研究員は、日本南岸の黒潮流域の海面水温の分布が、海上風の分布に影響することを衛星観測の解析から明らかにした。また、東シナ海・黄海では海底地形が冬季の水温分布に強く影響し、更には風や雲の分布や日本を通過する低気圧の発達にも寄与することも明らかにした。この成果は、12月28日発行の米国地球物理学連合の学会誌「Geophysical Research Letters(地球物理学研究レター)」と来年4月発行の米国気象学会の学術専門誌「Journal of Climate (気候学ジャーナル)」に掲載される。
背景
黒潮は日本付近の海況に多大な影響を持ち、水産、海運等に重要であるばかりでなく、大量の熱を熱帯から運ぶことで日本を含む広い地域の気候に影響している。従来の理論は太平洋スケールの風が黒潮を駆動するとしているが、逆に黒潮自身が風に影響を与えることも考えられる。しかし、黒潮から風への影響はこれまで明らかにされていなかった。また、冬季に日本の風上側にあたる東シナ海・黄海の水温分布も日本の気候に対して影響を持つことが考えられているが、その分布の形成原因には諸説あり決定的ではなかった。
成果
熱帯降雨観測衛星(TRMM)等を使った観測結果の解析から、日本南岸の黒潮の変動が大きな海面水温の変動を生み出し、それに伴い、温かい海の上では風が強く、冷たい海では風が弱い、という関係が見出された(図1、図2)。この風の変化は更に黒潮自身やそれに伴う漁場に影響すると考えられる。東シナ海・黄海では、冬季に吹く北風による海水の冷却効果が海の深さにより異なるため、海底地形を反映した特徴ある海面水温分布が形成され、さらに海上風や雲の分布にも影響する(資料1)。また、沖縄西方の暖かい黒潮と冷たい陸棚域との間の水温差は低気圧の発達にも強く影響することが数値モデルにより示された。
エルニーニョや地球温暖化の予測に使われる気候モデルは様々な不確定性を抱えており、特に、中高緯度海洋が気候に及ぼす影響がよく分かっていない。今回の成果を気候モデルに取り込むことで、気候変動予測の精確性向上に寄与することができる。
問合せ先
地球フロンティア研究システム合同推進事務局 担当:秋庭 Tel : 045-778-5684
宇宙開発事業団
広報室 Tel : 03-3438-6107〜9
海洋科学技術センター
総務部 普及・広報課 Tel : 0468-67-9066
|
|
図1:熱帯降雨観測衛星で観測された海面水温と海面風速
1998年(左図)と2001年(右図)4〜6月の海面水温(a)と海上風速(b)。黒潮沿いに温かい水が見られる。2001年には黒潮が東海地方で沖合いにあり、沿岸に冷たい水が分布する((a)矢印)。暖水の上で風が強く、冷たい水の上で風が弱い((b)矢印)。
(a)海面水温
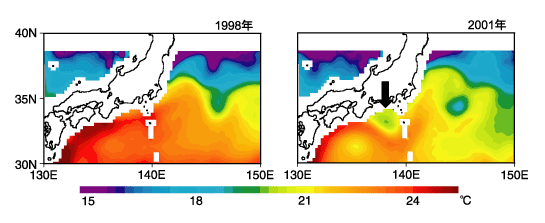
(b)海上風速
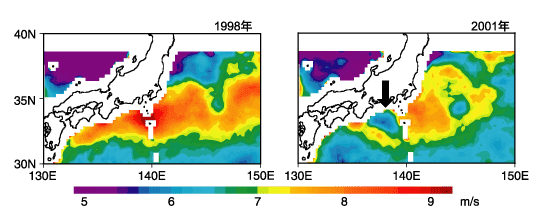
図2:黒潮が風に与える影響の模式図
黒潮によって運ばれてきた暖水上では風が強くなるのに対し、その本州側、北側の冷たい水の海域では風が弱い。
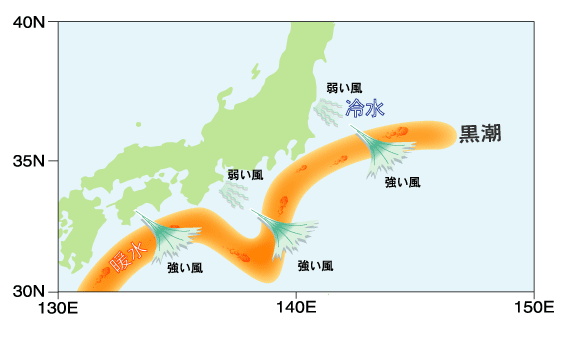
資料1:図1と同じ衛星で観測された気象要素(東シナ海・黄海)
海底地形の水温、風、雲の分布への影響。海が深い(浅い)ほど、水温は高く(低く)(a)、それに伴って風速(b)は速く(遅く)なる。海上風が減速(加速)を受ける風上で下層の空気が集まり(減少し)(c)、結果として雲の分布にも影響を与える(d)。
a)海底地形(色)と海面水温(線)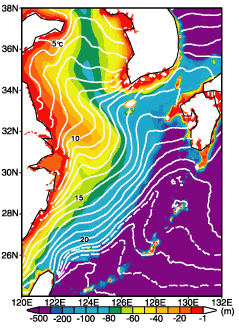 |
b)風速(色)と海面水温(線) |
|
c)風向・風速(↓)、下層大気の疎密(色)と海面水温(線)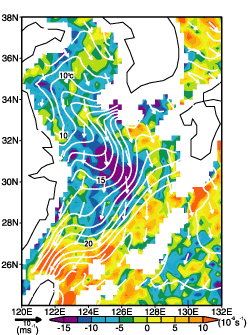 |
d)雲量(色)と海面水温(線)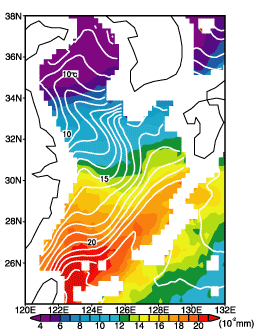 |
資料2:衛星観測の特質
海面水温や雲を捉える熱帯降雨観測衛星(TRMM)、海上風を捉えるQuikSCAT衛星による観測は高い時間空間分解能を持っている。今回の研究では、
- TRMM:緯度、経度とも0.25度間隔、週平均
- QuikSCAT:緯度、経度とも0.25度間隔、週平均
これに対し、従来の海洋観測は主に船舶に頼っており、海域と頻度に強い制約を受けているので、黒潮付近の詳細な構造を捉えることが困難であった。(下図)
12月14日に打ち上げられたADEOS-II(みどりII)では同様の観測が更に広範囲、高精度で行えるようになる。その成果を用いることで、今回のような気候学研究への応用が更に発展することが期待される。
図)最近の30年分の冬季のうちの船舶観測データのある年数
日本から台湾方面にかけての外航航路を外れる海域では観測頻度が極端に少なくなっている。
