LNG推進系飛行実証プロジェクトに係る計画の見直し要望
平成14年12月4日
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
はじめに
- プロジェクトの範囲を明確化
- 開発に係る体制を明確化
- ―NASDAと民間の役割分担を明確化
- 受託打上げに係る体制を明確化
- ―受託打上げの安全評価基準を作成
NASDAが、受託ロケットの打上げに係る安全評価基準を作成。評価体制を設定。 - ―米国企業からのGALEX社への技術輸出に係る協定が米国政府より認可
安全に関する技術の開示範囲が明確化。 - 打上げ時期の目標を設定
- 国としての自律性要求の整理
- ―国として自律性は要求しない
■前回の評価以降、検討・調整した事項等
プロジェクトの目的と実施形態
-
- NASDAは、将来の輸送系へ向けて計画的・段階的に研究開発を進めるLNG推進系プログラムの第1段階として 、本プロジェクトを実施。
- NASDAは、LNG推進系(LNGエンジン、複合材タンク)を開発し、その技術を修得。
- その飛行実証を早期にかつ効率的に行うため、民間が開発するGXロケットの打上げ機会を利用。そのため、NASDAはロケットシステムの要求にも合致したLNG推進系の開発を実施。
- 民間は、GXロケットのシステム全体の開発を責任を持って進め、この飛行実証に供する。
プロジェクトの範囲
-
- 本プロジェクトの範囲として、GXロケットの試験機を使用した飛行実証を2機まで実施する。
- 試験機終了時点で、NASDAは本プロジェクトの開発結果について実証データも踏まえ総合評価を受け、プロジェクトを終了。
- 開発・実証したLNG推進系については、この時点で民間に技術移転。
- 本プロジェクト完了後は、民間は独自の打上げ活動を実施する。(なお、国はH-IIAロケットの補完的手段としての検討を行う)
開発の体制
- プロジェクトの開発責任体制
開発から試験機による飛行実証までは、下図の体制により進める。
受託打上げの体制
- 受託打上げに係る安全評価体制
試験機打上げを含む運用段階での安全評価は、右図の体制により進める。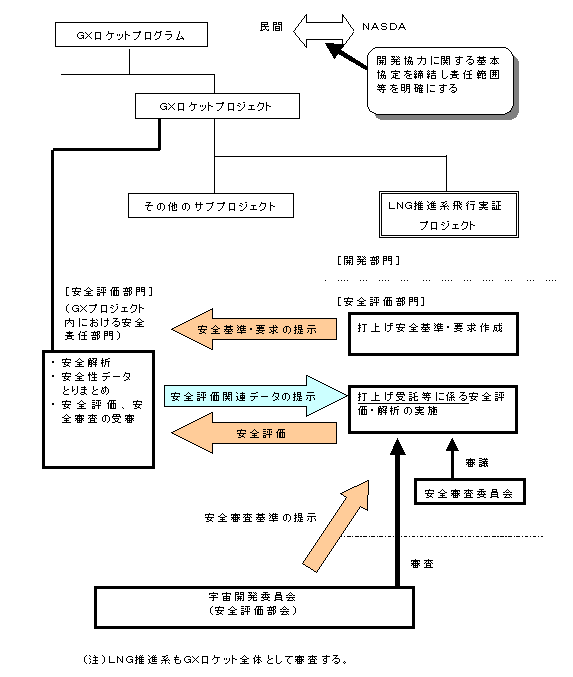
打上げ時期の目標
-
■平成17年度打上げ目標
- 平成17年度の試験機打上げは、民間の国内外市場予測による事業計画から来る目標.
- NASDAは、早期かつ効率的実証の観点から、この時期を目標とする
まとめ
- 前回評価で示された課題等に関連して、検討,調整等を実施し、結果をまとめた。
このため、LNG推進系飛行実証プロジェクトの課題等について評価をお願いしたい。
|
|