宇宙用部品の安定的確保について
平成14年6月5日
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
はじめに
宇宙開発の自在な展開に不可欠な宇宙用部品の安定的確保の方策検討のために、宇宙開発事業団内に設定された臨時組織「部品プログラム検討タスクチーム」の調査・検討の結果を以下報告する。
1.タスクチームの活動
|
|
NASDA認定部品の認定辞退が続出し、問題が顕在化 |
|
|
平成13年5月23日に臨時組織「部品プログラム検討タスクチーム」を編成 |
|
|
企業調査を実施、結果の分析、問題点、今後の対応策を検討 |
|
|
平成13年12月末に中間報告書を作成 |
|
|
関連機関、主要な企業に中間報告を説明し、追加検討などを実施 |
|
|
平成14年3月末に最終報告書を作成 |
報告書とりまとめの経緯
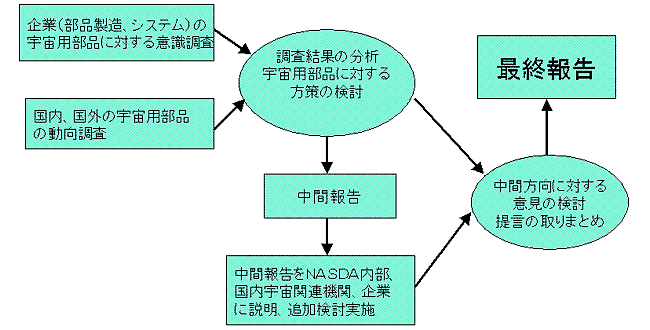
報告書の主な内容
|
|
部品プログラム30年の流れ |
|
|
現状の課題 |
|
|
現状の実態調査 |
|
|
調査結果の分析 |
|
|
今後の処置方針に対する検討 |
|
|
半導体製造ラインの検討 |
|
|
提言 |
2.部品にNASDAが何故、関与するか
部品の品質保証は本来は契約者の業務であるが、任せるだけでは解決出来ない構造となっている
|
|
宇宙機の品質は部品の品質から出発 |
|
|
宇宙用部品は量産品ではない(未成熟な市場) |
|
|
地上用部品と異なる要求と品質保証体系が必要 |
|
|
部品によるリスクを下げるためには、発注者の積極的な関与が不可欠 |
|
|
国産部品は品質確認が容易 |
3.NASDA-QPLに対する意見
部品ユーザ企業(21工場)
|
|
肯定的な意見
|
||||||
|
|
否定的な意見
|
||||||
|
|
課題
|
部品製造企業(電子部品、機構部品)(54工場)
|
|
肯定的な意見
|
||||||||||
|
|
否定的な意見
|
||||||||||
|
|
課題
|
4.NASDA認定部品の状況
|
|
1971年にNASDA認定部品(QPL部品)制度を開始 | ||||||
|
|
H-IIロケット部品の開発以降、組織的な部品開発は中断 | ||||||
|
|
約350品目の内、集積回路、半導体等が認定辞退 | ||||||
|
|
抵抗、コンデンサ、材料等約半数が認定継続 | ||||||
|
|
問題点
|
NASDA QPLの現状
| 部品数 | 継続 | 取消/予定 | |
|---|---|---|---|
| 集積回路 | 122 | 2 | 120 |
| 半導体、太陽電池 | 44 | 18 | 26 |
| リレー、配線部品 | 46 | 46 | 0 |
| 受動部品 | 78 | 58 | 20 |
| 機構部品、材料 | 56 | 34 | 18 |
| 346 | 158 | 184 |
5.NASDA認定部品の課題
|
|
「コスト高、部品開発に投資しない、新しいニーズに応えられない」のマイナス・スパイラル | ||||
|
|
国内の宇宙用部品供給体制の危機
|
||||
|
|
技術基盤の維持と経済性の矛盾 |
6.宇宙用部品に係わる方針の変化
|
|
H-II、ETS-VIの時代は米国技術からの脱却を目標、部品開発に資金を投入しNASDA-QPLを充実 | ||||||
|
|
その後、組織的な部品開発が行われなくなった
|
||||||
|
|
H-IIAロケットでは、独自の部品選定基準を設定 | ||||||
|
|
状況変化に対応した部品の方針を打ち出せなかった |
NASDAにおける部品開発費の推移
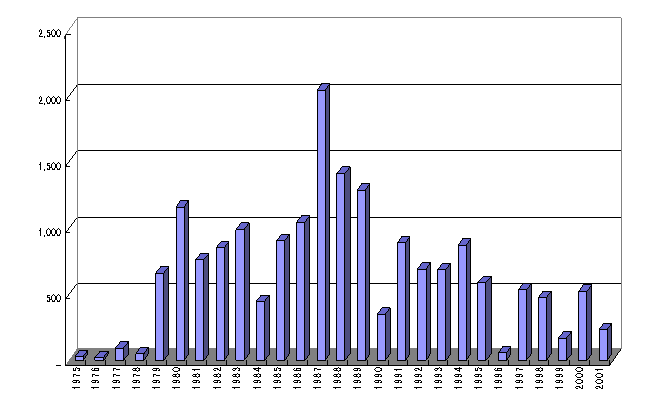
7.NASDA部品プログラムの課題
|
|
部品に対する方針が不明確 | ||||||
|
|
プロジェクト部品はプロジェクトが担当。結果として
|
||||||
|
|
部品グループは要請を受けてプロジェクトに寄与。この状態で
|
||||||
|
|
部品開発が内部の評価で進められ、NASDA外部の意見の反映が不十分 |
8.国産部品がなくなった場合、日本の宇宙開発はどうなるか
|
|
NASDA認定部品が国産部品の使用を支えており、NASDAの方針によっては国産宇宙用部品は壊滅 | ||||||||
|
|
NASDA以外の国内プロジェクトは外国部品が中心。 計画中のNASDAプロジェクトも同様。 短期的には影響は少ない |
||||||||
|
|
国産部品がなくなると次の問題が起きると考えられる
|
9.民生用部品の宇宙利用
|
|
民生用部品技術の利用は不可欠 | ||||||||
|
|
民生用部品の使用には問題がある
|
||||||||
|
|
使用するロットの評価が不可欠。後でコストが発生する | ||||||||
|
|
民生部品技術の利用方法として、ソフトウェア・パッケージの利用などが考えられるが、これらの研究開発が重要 |
システム会社がNASDAに期待するもの(合計点)
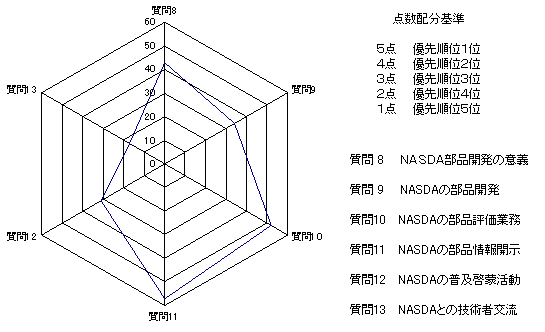
| 部品プログラム検討タスクチームの提言 |
提言事項のまとめ
|
|
部品はシステムの品質・信頼度の基本。高品質な宇宙開発を継続するためには、部品に係わる明確な部品プログラムを定め、プロジェクトを支援することが不可欠 | ||||
|
|
NASDA認定部品制度は受動部品及び機構部品を中心として企業の協力が得られる範囲で継続。 受動部品等の国産部品は品質的にも優れており部品製造企業が継続可能な方策を実行することが重要 | ||||
|
|
NASDAが宇宙開発に必要な部品を全て国産で開発することは不可能。プロジェクトに不可欠な部品、戦略的な部品に集中。国際間の競争と協調関係を維持 | ||||
|
|
民生部品の評価、研究を継続し宇宙用として使用可能な国産部品の増大をはかる | ||||
|
|
国内の宇宙開発の効率化のため次の施策を行う
|
||||
|
|
国際協力を推進し、国産部品の国際的な認知を高めると同時に、ギブアンドテイクの関係を構築し、外国の部品情報の積極的な入手に勉めプロジェクトを支援 |
10. 今後の対策(案)
|
|
我が国の宇宙活動の自在性確保のために不可欠な部品(戦略部品)を検討・選定し、国産開発
|
||||
|
|
民生用部品技術を宇宙利用するための評価、研究開発を進め、国産宇宙用部品を拡大 | ||||
|
|
国産部品の利用促進
|
||||
|
|
必要なリソースの投入 |
|
|