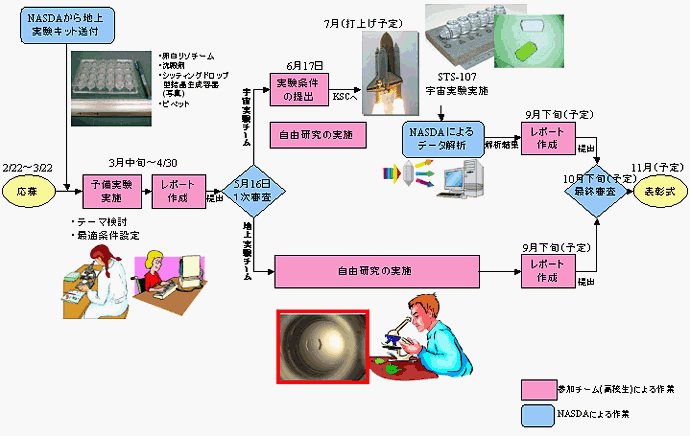宇宙実験に参加する高校生チームを選出
〜STS-107「チャレンジ!スペースシャトルで宇宙実験」第1次レポート審査結果〜
宇宙開発事業団
宇宙開発事業団(NASDA)では青少年の方々に宇宙開発や自然科学に対する関心を深めてもらうことを目的に、STS-107タンパク質結晶成長実験「チャレンジ!スペースシャトルで宇宙実験」を現在実施しております。2002年3月から4月にかけて各参加チームがおこなったタンパク質結晶成長の予備実験について、第1次レポート審査会を5月16日に実施し、独創性、論理性、レポートのまとめ方などの観点から、参加全149チームから宇宙実験に参加する6チームを選出しましたので、下記のとおりお知らせします。
| 宇宙実験チーム (順不同) | ||
| 北海道札幌啓成高等学校 | (生徒 2名、指導教諭:庄野和義) | |
| 茨城県・土浦日本大学高等学校 | (生徒 2名、指導教諭:野本正代) | |
| 茨城県・茗溪学園高等学校 | (生徒 7名、指導教諭:大竹隆夫、鈴木朋子) | |
| 埼玉県立浦和第一女子高等学校 | (生徒12名、指導教諭:岩田久道) | |
| 山口県立厚狭高等学校 | (生徒 6名、指導教諭:児玉伊智郎) | |
| 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 | (生徒 5名、指導教諭:児玉康裕) | |
上記6つの宇宙実験チームには、STS-107スペースシャトル「コロンビア号」(2002年7月打上げ予定)で行うタンパク質結晶成長実験のための実験条件(タンパク質溶液や沈殿剤溶液の濃度・pH、その他)を提出していただきます。地上実験チーム(宇宙実験チーム以外の全て)については、タンパク質や結晶などについて自由研究を行っていただき、双方のチームから提出された最終レポートを審査し、優秀チームを選定します。
| 添付1 | : | 第1次レポート審査委員名簿 |
| 添付2 | : | 第1次レポート審査講評 |
| 添付3 | : | 宇宙で行うタンパク質の結晶成長実験について |
| 添付4 | : | STS-107宇宙実験教育プログラムの流れ |
|
|
添付1
第1次レポート審査委員名簿
| 委員長 | : | 細矢 治夫 [ ほそや はるお ] | (お茶の水女子大学 名誉教授) |
| 委員 | : | 八木 達彦 [ やぎ たつひこ ] | (静岡大学 名誉教授) |
| 委員 | : | 安岡 則武 [ やすおか のりたけ ] | (姫路工業大学 名誉教授) |
| 委員 | : | 岩崎 不二子 [ いわさき ふじこ ] | (電気通信大学 電気通信学部 量子・物質工学科教授) |
| 委員 | : | 平山 大 [ ひらやま たい ] | (東京都立忠生高等学校 教諭) |
添付2
第1次レポート審査講評
| 北海道札幌啓成高等学校 (受付番号118) |
丁寧な実験を行っていて、ほとんどの実験で結晶を得ている。実験の経過をよく観察しており、結果に対する考察も妥当である。良好で大きな結晶を多くの実験で得ており、宇宙での結晶化実験への期待が持てる。
| 土浦日本大学高等学校 (受付番号95) |
長い期間にわたって忍耐強く丁寧に観察を続けたことは大変素晴らしい。また、実験道具、レポート構成など、さまざまの点で工夫と配慮が伺われる。
| 茗溪学園高等学校 (受付番号105) |
大変よく勉強され、実験が計画されている。実験条件の絞り込み、結果の整理、考察と、どれをとってもよくできた立派なレポートである。結晶の模型化もよいアイデアである。
| 埼玉県立浦和第一女子高等学校 (受付番号117) |
実験の目的、研究に取り組もうとしている動機がしっかりと記述されている。緩衝液理論も事前に調べており、シリカゲル法の開発をはじめ、数々の独創的な試みがなされている。考察のレベルも高く、微小重力下での実験についても触れている。膨大な内容を本文と資料に分離し、読みやすくしている。
| 山口県立厚狭高等学校 (受付番号61) |
酢酸ナトリウム系の緩衝溶液とは別に、鶏卵のpHに近い条件をリン酸緩衝溶液で試して、大きな結晶の成長条件を探したことは評価される。結晶の観察やレポートの書き方もきちんとしている。
| 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 (受付番号39) |
全体的にレポートのまとめ方がよい。結晶の大きさや実験条件の記載がきちんとしている。図と実験の対応も分かりやすい。最終レポートに対しても課題の提案がされている。
| 〜総評〜 |
非常に多数の応募があり驚いている。各チームともレベルが高く、評価について、紙一重の違いしかないものが多かった。その中でも宇宙実験チームとして選ばれたチームは与えられた条件以外に様々な考察を加えるなど、工夫が見られた。
使用した器材などについて、普段からの科学実験に対する学校の取り組みの差が一部ハンデになったかもしれないのは残念であるが、一方で装置の不足を工夫で補っていたチームもあり、評価に値する。
全体として、結晶の数や大きさなどについては、具体的な数値を挙げるなど定量的な観察・評価が不足していた。最終レポートでは定量的な観察・評価をお願いしたい。
今回の実験は、生物・物理・化学・数学など様々な要素を含むものである。これを機に理科離れ、科学離れのムードを変えるきっかけとなってほしい。宇宙実験チーム、地上実験チームとも最終レポートの作成に向けて引き続きがんばってほしい。
添付3
宇宙で行うタンパク質の結晶成長実験について
タンパク質にはいろいろな種類があり、生命を支える上で重要な、多種多様の役割を果たしています。タンパク質の種類や働きを理解することは"生命の仕組み"を理解することに大変役立ちます。
タンパク質は何千〜何万個もの原子で組み立てられた複雑で巨大な分子です。そして、そのタンパク質分子の形(立体構造)はそれぞれの種類によって厳密に決まっています。あるタンパク質の働きを決める重要な要素の一つは、そのタンパク質の立体構造です。複雑なタンパク質の立体構造を全ての原子の位置まで正確に明らかにできれば、生物学の研究だけでなく"医療や食糧生産"などさまざまな方面に役立ちます。
しかし、全てのタンパク質の構造が明らかになっているわけではありません。タンパク質の働きの秘密に迫るには、より多くのタンパク質の立体構造を調べる必要があります。タンパク質の立体構造が解れば、そのタンパク質の特定の部分にうまく当てはまる形の小さな分子を合成することもできます。
一例として、病気を起こすウイルスの増殖に必要な酵素の立体構造が明らかになりました。立体構造の情報をもとにして、この酵素の重要な部分に入り込んで働きを阻害する化合物が合成され、抗ウイルス薬として実用化されています。
何千個もの原子で構成されたタンパク質は分子としては巨大ですが、顕微鏡では内部の構造を見ることができない小ささです。小さなタンパク質分子の複雑な立体構造を調べるのは簡単ではありません。分子の立体構造を調べるにはエックス線の回折という現象を利用し、その結果をコンピュータで解析するのです。そのためにはタンパク質分子が規則正しく整列した結晶が必要です。
しかし、地上では重力があるために、物質が沈んでしまったり、密度や温度の差によって空気や液体に対流が生じたりして、結晶中のタンパク質の並び方に乱れができてしまいます。そこで、宇宙における微小重力環境が利用されるようになりました。わが国においても、1997年にスペースシャトルを利用して地上より品質のよい結晶を得ることに成功しています。宇宙の微小重力環境を利用した結晶化によって、数多くの重要なタンパク質の立体構造の解析が進むと期待されています。
添付4
STS-107宇宙実験教育プログラムの流れ