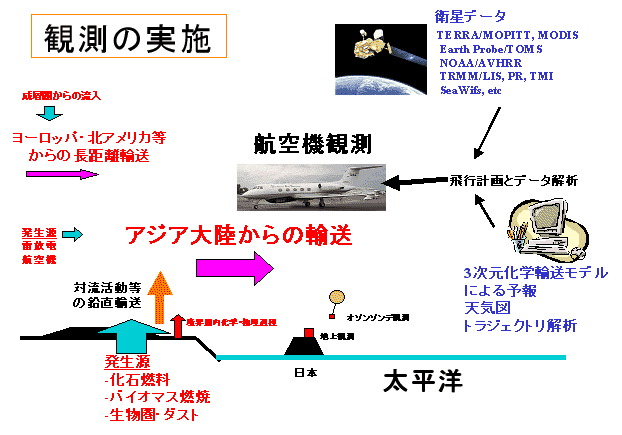広域大気汚染の航空機観測結果について
宇宙開発事業団
宇宙開発事業団は、地球規模の広域大気汚染の監視を行うリモートセンシング技術を研究・開発の一環として、航空機を用いたアジア・太平洋地域の観測を進めているところですが、別紙のとおり、今年1月6日から23日に実施した観測により冬の季節風によりアジア大陸を発生源とする大気汚染物質が日本上空にまで運ばれている様子が明らかとなりましたのでお知らせします。
今回得られたデータは、広域汚染等の実態を把握するとともに、日本付近の大気環境への影響評価を定量的に行うための基礎データとなり、人工衛星搭載観測器の設計等の開発に役立てることができます。今後このような観測を継続することにより、地球規模の広域大気汚染の常時監視および予測を可能にする技術システムが構築できるものと期待されます。
|
|
【観測結果ハイライト】
航空機観測では、オゾン、一酸化炭素、二酸化炭素、二酸化硫黄、酸化窒素類、炭化水素類、煤(エァロソル)、水蒸気など多数の大気微量成分を測定しました。ここでは、一次汚染物質として代表的な一酸化炭素についての結果を紹介します。一酸化炭素は、燃料の不完全燃焼で発生する有毒な気体です。大気中では他成分と化学反応を起し、オゾンを作るので注目される成分の一つです。
図1は、高度0.2〜2 kmの一酸化炭素の濃度分布を示しています。赤色の部分は、250 ppbv(1ppbvは体積比にして10億分の1を表す)以上の濃度域で、大気汚染の影響を強く受けた大気です。そのような大気では、酸化窒素類、二酸化硫黄、煤(エァロソル)なども高濃度になっています。
2002年1月7〜13日の観測によると、大陸からの大気汚染は東方に拡がり、日本海上空(北緯32〜38度)に達していることがわかりました。これは、寒冷前線の対流活動に伴い、大陸都市域を発生源とする汚染物質が上空へ上げられ、西風で運ばれて日本海上空にやって来たと考えられます。
2002年1月17〜21日の観測によると、高濃度の一酸化炭素を含む空気は、九州西南の海上(北緯26〜31度)に存在していました。この期間は西風が安定して強く、北緯30度付近に発生源をもつ大陸の大気汚染物質が東に運ばれやすい状況にありました。
発生源からの一次的な汚染物質である一酸化炭素、酸化窒素類、二酸化硫黄、煤(エァロソル)濃度は、日本海上空および九州西南海上において、それぞれ300±100 ppbv, 4±3 ppbv, 3±2 ppbv, 10±8 mg/m3 であり、同期間に観測を行なった高度2km以上の対流圏中層の値と比べ3-10倍の濃度になっていました。

図1 高度0.2〜2 kmの一酸化炭素の濃度分布。本州の日本海側と太平洋側の部分は、2002年1月7日〜13日の間の観測データに基づき、九州の西方および南方の部分は2002年1月17日〜21日の間の観測データに基づいています。
これまでも、本州日本海側で降水の酸性化が観測されるなど、大陸からの大気汚染の拡がりがいわれてきました。東アジア諸国の経済発展に伴い、大気汚染物質の放出量が増加し、日本の上空や太平洋上の大気環境に及ぼす影響度が増えることが心配されています。今回の観測においては、大気汚染物質の発生地域と上空への輸送が行なわれる対流発生地域を同定し、上空に運ばれた大気汚染物質が偏西風によって流される経路を特定し、航空機で観測した大気が日本上空へ移動途中の汚染大気であることを確認しました。
【今後の研究計画】
4〜5月には、大気の光化学作用と対流活動が活発になり、オゾンなどの反応生成物の濃度が増大します。アジア大陸からの大気汚染の影響がこれによって強まる可能性があり、日本列島もその影響下に入るおそれがあります。また、春は対流活動が盛んになり、大気汚染物質がより高い高度に運ばれ、その後偏西風にのって太平洋を横断し、アメリカ大陸まで到達する可能性もあります。2002年4〜5月にかけて、日本周辺とアメリカ西海岸で同時に航空機観測を実施し、太平洋を越えた大気汚染物質の輸送および化学的変質を日米共同で研究を行う計画です。
【観測の実施】
宇宙開発事業団 地球観測利用研究センターは、広域大気汚染を衛星から観測するシステムの実現を目指し、汚染の実態把握と衛星搭載観測器の研究を行なっています。その活動の一環として、2002年1月6〜23日の間に名古屋空港と鹿児島空港を基地として航空機観測キャンペーン「西太平洋域におけるアジア大陸から排出される人為起源物質の航空機観測」を実施しました。この観測では、(株)ダイアモンドエアサービスの保有するガルフストリームII型ジェット機を使用し、大気微量成分を測定する装置を機内および機外に搭載し、外部からの空気を測定装置に導入して直接計測を行いました(ただし、炭化水素類は大気採集後、実験室内で分析します)。
この観測は宇宙開発事業団 地球観測利用研究センター 小川利紘研究ディレクターおよび東京大学 先端科学技術研究センター 近藤豊教授をリーダーとし、東京大学先端科学技術研究センター、同理学部、国立環境研究所、カリフォルニア大学アーバイン校、ニュージーランド水圏・大気研究所、名古屋大学太陽地球環境研究所、北海道大学低温科学研究所、および宇宙開発事業団地球観測利用研究センターの研究者が参加しました。また、同時に行なった地上観測には、香港、韓国の研究機関、モデル解析研究には、京都大学理学部、地球フロンティア研究システムの研究者の参加を得ました。オゾンゾンデ観測は、気象庁の御協力を得ました。航空機運航に際しては国土交通省航空局の御理解と御協力を得ました。