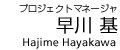近くて遠い星、月と火星の中間のサイズしかないにもかかわらず惑星固有の磁場を持っている惑星。惑星科学に関連する研究を行う科学者であれば一度は観測をしてみたいと思う惑星でありながら、その灼熱の環境、周回軌道投入に必要な燃料の多大さから直接観測がほとんどできなかった惑星、それが水星です。
固有磁場と磁気圏を持つ地球型惑星は地球と水星のみであり、初の水星の詳細探査は、「惑星の磁場・磁気圏の普遍性と特異性」の知見に大きな飛躍をもたらすと期待しています。また、磁場の存在と関係すると見られる巨大な中心核など水星の特異な内部・表層の全球観測は、太陽系形成、特に「地球型惑星の起源と進化」の解明に貢献します。これらはいずれも太陽系科学の根幹に関わるものです。
「BepiColombo(ベピコロンボ)」は、日本(JAXA)とヨーロッパ(ESA)の初の本格的共同プロジェクトであり、2機(ESA、JAXAがそれぞれ1機ずつ製作)の周回衛星を同時に水星へ持って行くことで、水星の磁場、磁気圏、内部、表層を初めて多角的・総合的に観測し、謎に満ちた惑星である水星の全貌を解明しようという野心的な計画です。
2001年から始まったESAや欧州各国の研究者との協力も6年を過ぎ、お互いに気心が知れてきました。衛星試作も終わりに近づき、来年度には熱構造モデルの試験を始めます。最大で地球の11倍の太陽光強度という灼熱環境に衛星が設計どおり耐えられるかを確認し、フライト品の設計・製作・試験へと続けるわけです。今まで要素モデルなどを製作し個別に確認してきましたが、いよいよ本格的な物作りが始まることになります。
打ち上げ後、月・地球・金星・水星のフライバイと電気推進を用いて6年後に水星に到着します。水星の周回軌道からは1〜2年の間観測を続ける予定です。データが出るまでにはまだまだ先の長い話ですが、水星での観測データが出る日を夢見てプロジェクトを進めています。
固有磁場と磁気圏を持つ地球型惑星は地球と水星のみであり、初の水星の詳細探査は、「惑星の磁場・磁気圏の普遍性と特異性」の知見に大きな飛躍をもたらすと期待しています。また、磁場の存在と関係すると見られる巨大な中心核など水星の特異な内部・表層の全球観測は、太陽系形成、特に「地球型惑星の起源と進化」の解明に貢献します。これらはいずれも太陽系科学の根幹に関わるものです。
「BepiColombo(ベピコロンボ)」は、日本(JAXA)とヨーロッパ(ESA)の初の本格的共同プロジェクトであり、2機(ESA、JAXAがそれぞれ1機ずつ製作)の周回衛星を同時に水星へ持って行くことで、水星の磁場、磁気圏、内部、表層を初めて多角的・総合的に観測し、謎に満ちた惑星である水星の全貌を解明しようという野心的な計画です。
2001年から始まったESAや欧州各国の研究者との協力も6年を過ぎ、お互いに気心が知れてきました。衛星試作も終わりに近づき、来年度には熱構造モデルの試験を始めます。最大で地球の11倍の太陽光強度という灼熱環境に衛星が設計どおり耐えられるかを確認し、フライト品の設計・製作・試験へと続けるわけです。今まで要素モデルなどを製作し個別に確認してきましたが、いよいよ本格的な物作りが始まることになります。
打ち上げ後、月・地球・金星・水星のフライバイと電気推進を用いて6年後に水星に到着します。水星の周回軌道からは1〜2年の間観測を続ける予定です。データが出るまでにはまだまだ先の長い話ですが、水星での観測データが出る日を夢見てプロジェクトを進めています。