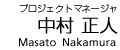我が国初の金星探査機「あかつき(PLANET-C)」は2010年5月21日早朝、種子島から打ち上げられ金星を目指しました。同年12月7日に金星に最接近しましたが、残念ながら金星をめぐる軌道への投入は失敗に終わりました。軌道投入、そして「あかつき」による金星観測を楽しみにしていたのはプロジェクトメンバーだけではなく、応援してくださっている皆さまもであろうと思うと、探査機開発の責任者として大変悔しく、また申し訳なく思います。
現在の「あかつき」の軌道は公転周期約203日です。金星の公転周期は約225日であるため、このままの軌道をとれば「あかつき」は約6年後に再び金星と会合する可能性があります。今後の長期にわたる運用での課題を整理し、再び金星に接近できるまで無事な状態を維持すべく検討を進めています。また、様々な想定される状況において、それぞれに対する軌道計画を検討しています。
幸い私たちはまだ「あかつき」を手の内にしています。ミッションは失われたわけではありません。まずは原因究明に全力を尽くし、続くミッションで同じ過ちを繰り返さないこと。そして、今の「あかつき」を無事に飛行させ、そして「あかつき」の弟、妹たちを宇宙に旅立たせ、人類の知識の獲得に向けて邁進すること。これが我々宇宙科学に携わる者の使命であるとプロジェクト一同考えています。
「あかつき」が目指す金星の探査は50年ほど前に始まり、アメリカ、旧ソビエト連邦が相次いで探査機を送り込んできました。失敗を重ね徐々に見えてきた金星の姿は、驚くほどに地球とは似ても似つかぬもので、分厚い熱い大気に覆われていました。海は存在せず、大気の組成も地球とは大きく異なっています。「あかつき」は紫外線から可視光、赤外線にいたる5台のカメラを積んでいて、それぞれのカメラが金星の異なる高度の雲の様子を捉えます。赤外線では一番表層の雲を透かして、もっと下の雲の様子まで見えるのです。これらのカメラで撮った写真を組み合わせると3次元的な雲の分布や各層の雲の動きがわかります。データを蓄積して統計的な処理をすることにより、金星の大気が物理的にどのような力によって動かされているかを調べることが出来るのです。
金星探査の意義は今も決して失われてはいません。金星の謎を解く日まで我々とともに歩んでいただけますようお願い申し上げます。
現在の「あかつき」の軌道は公転周期約203日です。金星の公転周期は約225日であるため、このままの軌道をとれば「あかつき」は約6年後に再び金星と会合する可能性があります。今後の長期にわたる運用での課題を整理し、再び金星に接近できるまで無事な状態を維持すべく検討を進めています。また、様々な想定される状況において、それぞれに対する軌道計画を検討しています。
幸い私たちはまだ「あかつき」を手の内にしています。ミッションは失われたわけではありません。まずは原因究明に全力を尽くし、続くミッションで同じ過ちを繰り返さないこと。そして、今の「あかつき」を無事に飛行させ、そして「あかつき」の弟、妹たちを宇宙に旅立たせ、人類の知識の獲得に向けて邁進すること。これが我々宇宙科学に携わる者の使命であるとプロジェクト一同考えています。
「あかつき」が目指す金星の探査は50年ほど前に始まり、アメリカ、旧ソビエト連邦が相次いで探査機を送り込んできました。失敗を重ね徐々に見えてきた金星の姿は、驚くほどに地球とは似ても似つかぬもので、分厚い熱い大気に覆われていました。海は存在せず、大気の組成も地球とは大きく異なっています。「あかつき」は紫外線から可視光、赤外線にいたる5台のカメラを積んでいて、それぞれのカメラが金星の異なる高度の雲の様子を捉えます。赤外線では一番表層の雲を透かして、もっと下の雲の様子まで見えるのです。これらのカメラで撮った写真を組み合わせると3次元的な雲の分布や各層の雲の動きがわかります。データを蓄積して統計的な処理をすることにより、金星の大気が物理的にどのような力によって動かされているかを調べることが出来るのです。
金星探査の意義は今も決して失われてはいません。金星の謎を解く日まで我々とともに歩んでいただけますようお願い申し上げます。
(2011年4月 更新)