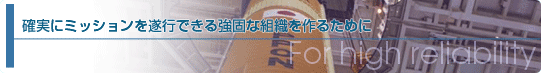
 宇宙航空研究開発機構 宇宙航空研究開発機構
安全・信頼性管理部部長
長谷川秀夫
モノ作りをする上で、安全や信頼性を考えるのは当たり前のことです。それを当然のこととして実施し、より確実な宇宙開発を進めるには、“意識改革”が重要なポイントとなります。
意識改革は「信頼性を重視する文化の熟成」とも言われ、「信頼性を重視する」意識をどのように植え付けていくかが課題であり、その実現は、個人が自覚するのを待つだけでなく、常に信頼性を意識し、重視しながら仕事を進めることができる仕組みをどのように作るかにかかっています。
相当のエキスパートでなければ信頼性をチェックすることはできませんが、エキスパートは「一日にして成らず」なのです。人材育成には時間がかかります。しかし、「相当のエキスパート」といえる人材がいないから信頼性の高いものは作れないと諦めず、個々の技術者の能力を正しく把握し、それを踏まえた上で「相当のエキスパートが実施したのと同じ」程度の「高い効果」を上げる仕組みを持つことが組織力だと思います。 信頼性を重視する仕組みの一つに、「独立の人間」による「日常的なチェック」の実施が考えられます。壊れやすいものを作ろうと思っている人は、一人もいません。プロジェクトの担当者は、設計や開発を進める際に、信頼性高く、より性能のよいものを作ろうと、最大限の努力をしていると思います。しかし、当事者ではなかなか気が付かないこともありますし、人間誰しも間違いはあるものです。そこで第三者によるチェックが重要になります。当事者であるがゆえに見落としてしまうことも、違う立場で少し離れて見ることで気がつくものです。つまり、「傍目八目(おかめはちもく)」効果です。信頼性確保という視点で、プロジェクトの活動を専門の人間がチェックするという仕組みの意義です。
塗られてしまった壁の内側は、外からは見ることはできません。内側を知るには、塗る前の段階から見ていなければならないように、プロジェクトの信頼性を確保するには、プロジェクトの中に入ってフェーズの早い段階から日常的にチェックすることが必要です。
以上のような考えのもと、プロジェクトと連携し、その進行とともにリアルタイムで、第三者が日常的に冷静な評価(サポート)を行える体制を強化していこうとしているところです。 宇宙開発の歴史を見ると、30年以上前の技術力で月に行くことができたのですから、技術力が低くとも、信頼性を維持する仕組みは作れるのです。「個々の技術者の技術力を高める」ことは、本質的な解決ではありますが、時間がかかる課題です。「個々の技術者の技術力」と「組織としての技術力」は、信頼性向上のための「車の両輪」だと考えています。組織の技術力の基礎となる「技術者の技術力向上」を図りつつ、現在の技術力を認識した上で、目的を達成するための仕組みを作ることが重要です。このことを念頭に置き、JAXAの信頼性向上を図っていきたいと思っています。
「組織の技術力」には、仕事を進める仕組みのほかに「豊富な技術情報/データ」や「手法の開発と応用」などがあります。「技術情報/データ」を蓄積するための仕組み(体制、蓄積/利用方法など)を構築し、それをもとにエキスパートが効果的な手法で評価することによって、信頼性の高いシステムの開発が可能になります。 「意識改革」「教育訓練」「技術データの蓄積」「信頼性評価手法の開発と応用」――これらを効果的に実施できる体制を築くことがJAXAの課題であると考え、段階的に鋭意取り組んでいるところです。
|

