第4回ライフサイエンス国際公募の宇宙実験候補テーマ選定結果について
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
1. 報告事項
平成13年5月から8月に募集を行った第4回ライフサイエンス(生物学・医学研究分野)国際公募における宇宙実験候補テーマの選定結果について。
2. ライフサイエンス国際公募について
2.1. 公募の目的等
ライフサイエンス国際公募は、日・米・欧・加・ウクライナが国際宇宙ステーション等における科学的研究に係るフライトテーマを国際的に選定するものであり、限られた実験装置及びリソースを効率的に利用し、最大限の科学的成果を得ることを目的としている。
今回の第4回国際公募は平成16年(2004年)から平成18年(2006年)の国際宇宙ステーションの初期利用段階を対象として行った。ただし、今回も第3回の公募同様にげっし類(ラット、マウス)を飼育する実験装置を使用するテーマについては、既に選定され準備中の実験が多く、今後追加の飛行実験機会の確保が困難であることから募集しないことが、参加各機関で取り決められた。
2.2. 参加の条件
| (1) | 参加機関による実験装置の提供(国際公募で選定された利用研究テーマに使用させるもの) |
| (2) | 利用研究テーマの各機関経由による募集 |
| (3) | 国際科学評価パネルへのパネリスト(当該分野の研究者)派遣、国際技術評価への参加 |
| (4) | 参加機関の独自の宇宙環境利用政策による再評価 |
| (5) | 国際ライフサイエンステーマ選定委員会への参加 |
| (6) | 各機関経由で提案され、選定されたテーマへのフライト準備・フライト・フライト後解析に亘る各機関によるサポート |
2.3. 第4回ライフサイエンス国際公募作業の流れ
 |
平成13年5月16日:募集開始 8月28日:締め切り |
 |
10月:7分野のパネルに分けて採点。 (米国にて実施) |
 |
11月:各宇宙機関担当者による実現性の評価。 (日本にて実施) |
 |
11月29日:宇宙環境利用研究委員会にて日本の通過テーマの科学評価を実施。 12月4日:NASDAとしてのプログラム評価 |
 |
12月11日:各機関での再評価を踏まえ、国際ライフサイエンステーマ選定委員会が、全体リソース、テーマ、研究の機会等を考慮し調整の上、宇宙実験候補テーマを選定。 |
| 平成14年1月:宇宙開発事業団理事会議にて候補テーマを承認。 |
3. 宇宙実験候補テーマ選定結果
日本からは以下の6テーマが選定された(別紙1の概要参照)。
| テーマ略称 | 提案者 | 試料 | 使用装置 |
|---|---|---|---|
| 宇宙環境因子のヒト培養細胞 への影響 |
谷田貝文夫* 理化学研究所 |
ヒト細胞 | 細胞培養装置 (NASDA) |
| オタマジャクシの発生異常と ストレス解析 |
内藤富夫* 島根大学 |
オタマジャクシ | 水棲生物実験装置 (CSA) |
| 破骨細胞の重力感受 | 高沖宗夫 宇宙開発事業団 |
マウス細胞 | 細胞培養装置 (NASDA) |
| 植物細胞壁の力学的強度への 重力影響 |
若林和幸* 大阪市立大学 |
コムギ種子 | 植物実験ユニット (NASDA) |
| 筋肉細胞を用いた筋萎縮の研究 | 二川 健* 徳島大学 |
ラット細胞 | 細胞培養装置 (NASDA) |
| 血管の形成と重力影響 | ピアーソン・ジェームズ 国立循環器センター |
鶏卵 | 恒温器(NASA) (一部NASDA卵ラック) |
* :本研究者は、宇宙環境利用に関する地上研究公募の代表研究者として参加している。
応募から国際ライフサイエンステーマ選定委員会までの各国のテーマ数の経緯を以下に示す。
| 日本 | 米国 | 欧州 | カナダ | ウクライナ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募テーマ数 | 15 | 52 | 39 | 3 | 11 | 120 |
| 国際科学評価通過テーマ | 6 | 26 | 15 | 1 | 0 | 48 |
| 国際技術評価通過テーマ | 6 | 21 | 11 | 1 | 0 | 39 |
| 各国の推薦テーマ | 6 | 10 | 11 | 1 | 0 | 28 |
| 国際テーマ選定委員会調整後の選定候補テーマ | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 24 |
4. 今後の予定
宇宙実験候補テーマについては、今後約1年間の実験計画設定作業を経た後、実験の実現性、リソースや準備計画等を評価し、また、国内外のISS計画の状況を踏まえつつ、フライトテーマとしての最終選定を行う。
5. その他、今回の日本テーマの国際評価結果について
第2回、3回ライフサイエンス国際公募とも日本のテーマの科学評価は他国に比べて平均点が最低であった。(第1回は日本は不参加であり、第3回まではウクライナは不参加である。)しかし、今回の公募では、日本のテーマの国際科学評価平均点は米国についで2番目となった。理由として想定されることは以下のとおり。
| (1) | 公募地上研究でのデータが出ており、その結果を基にした実験計画となっていることが評価された。 |
| (2) | 講習会、事前点検の結果、記述と主張方法が的確となった。 |
|
|
日本の選定候補6テーマの概要
テーマ:ヒト培養細胞におけるTK変異体のLOHパターン変化の検出
提案者:谷田貝 文夫
所属機関:理化学研究所 加速器基盤研究部 ラジオアイソトープ技術室
研究目的:この21世紀は宇宙の時代といってもよいでしょう。それは、宇宙という未知のものに対する人類の挑戦でもあります。宇宙での長期滞在にあたって、私たちが慣れ親しんだ地球上の環境から未知の宇宙環境に果たして適応していけるかどうか不安も生じてきます。こういった不安を除くためにも、宇宙環境の生物に与える影響を詳しく調べることはとても大切なことです。例えば、宇宙放射線の主な成分はイオン放射線と考えられており、その中でも原子番号の高いものは地上の生活環境にはなく、加速器を利用して得られる人工的なものだけです。そこで、宇宙放射線による遺伝的影響を調べてみることにしました。
研究方法・内容:国際宇宙ステーション内でマウスを飼育し発生する突然変異を調べるというアイディアのもとに、加速器からの放射線を利用してその予備的な研究をやってみました。突然変異の発生はがん化などと密接に関係していて、遺伝的影響の良い指標と考えられているからです。ところが、どうしても予測されるような低線量域で突然変異誘発を検出する手法の確立には至りませんでした。そこで、ヒト培養細胞を利用して染色体レベルで突然変異を高感度に検出する手法を開発することにしました。今までの研究でも、放射線は突然変異を引き起こすことはわかっていたのですが、低線領域で高感度に検出し、かつ自然発生のものと区別することが難しかったのです。DNA合成に関わるチミジンキナーゼ(TK)遺伝子座がヘテロ(一方は正常、一方は異常)に対合している細胞、ヒトリンパ芽球用細胞TK6を利用することにしました。このようなヘテロの細胞は、正常なTK遺伝子座に起こる様々なタイプの突然変異を検出することができます。実際に、極めて低線量のX線をこの細胞に照射し、放射線に特有な欠失型の突然変異((ヘテロ接合性の喪失;LOH)を検出することに成功しました。さらに、加速器による炭素イオンを同じ低線量照射すると、この特異的なLOHはもっと高頻度に出現し、その詳細パターン(欠失が染色体のどこの領域にまで及ぶか)がX 線照射の場合と異なることも明らかになりました。実際には、国際宇宙ステーション内では細胞を培養する操作だけにとどめ、その後地上に回収してから上述の遺伝解析を行なう計画です。
期待される研究成果:この放射線に鋭敏なLOH検出手法は、宇宙放射線の及ぼす遺伝的影響を明らかにすることに貢献するだけでなく、地上での高放射線バックグラウンド環境に対するリスク評価にも役立つことが期待されます。さらには、放射線によるDNA損傷の修復機構についての基礎研究にも利用できます。
ヒト培養細胞におけるTK変異体のLOHパターン変化の検出

テーマ:微小重力下における両生類オタマジャクシの生理学的研究
提案者:内藤富夫
所属機関:島根大学生物資源科学部生物科学科
研究目的:重力のない状態でカエルのオタマジャクシの呼吸や消化管そして心臓の運動を観察します。重力がこれらの内臓のはたらきにどのように影響しているか,オタマジャクシも宇宙酔いにかかるかを,自由におよぐオタマジャクシをつかって明らかにします。また,アフリカツメガエルのオタマジャクシは宇宙でうまく育ちませんでしたが,その理由について別の種類のオタマジャクシで詳しく調べます。
研究方法・内容:腹の皮膚や膜が透明で外から内臓がよく透けてみえるオタマジャクシ(宇宙実験をおこなう季節によってヤマアカガエル,アマミアオガエル,またはスズガエル)を用いて,呼吸,消化管,心臓の運動をビデオカメラで撮影します。カエルは乗り物酔いをするのがわかっていますが,オタマジャクシも宇宙酔いをするかどうかを内臓の運動の様子を解析して調べます。腹の透明なオタマジャクシを実験に用いることによって,自然な生活状態にある動物の内臓の活動を直接観察することができます。アフリカツメガエルのオタマジャクシを宇宙で飼育したときにみられた体のいくつかの異常の原因を,今回とりあげる別の種のオタマジャクシの呼吸や骨や筋,そして発生の様子を調べることにより明らかにします。
期待される成果:自然状態で動物の消化管や心臓の運動などを宇宙で観察することは今回が初めてです。また,動物が宇宙酔いをおこせば,心臓や消化管運動などに影響が表れると思われるので,内臓運動を調べることで宇宙酔いのメカニズムや無重力環境に適応していく様子をよく調べることができます。オタマジャクシの発生が宇宙で正常に進まない理由を明らかにすることにより,宇宙で動物を継世代する研究を進めることができます。

テーマ:破骨細胞分化因子(RANKL)遺伝子制御領域内の重力感受エレメントの同定
提案者:高沖宗夫
所属機関:宇宙開発事業団宇宙環境利用研究センター
研究目的:骨組織の細胞の働きを遺伝子レベルで調べ、宇宙飛行中に骨からカルシウムが溶け出る現象を防止する方法の開発に役立てる。
研究方法・内容:私たちの骨は古くなった部分を溶かす破骨細胞と新しい骨を作る骨芽細胞の働きが常にうまく釣合って健康な状態に維持されている。体重を支えたり運動することよって骨に加わる力の大きさが、破骨細胞と骨芽細胞の働きのバランスを保つために重要で、宇宙飛行や寝たきり状態などその力が減少すると骨を溶かす方に傾いてしまうと考えられている。骨芽細胞は自身が骨を作るだけでなく破骨細胞分化因子(RANKL)等の物質を作って破骨細胞の働きも調節しているらしいことが最近明らかにされた。骨に加わる力が減少したことを骨芽細胞がどのように感じ取ってRANKL遺伝子を発現させる(RANKLを作り出す)のかを探るために、RANKL遺伝子の発現を制御する領域にホタルの発光タンパクなど検出が容易な遺伝子を繋いだもの(レポーター遺伝子)を注入した培養骨芽細胞を宇宙ステーション上の無重量状態で培養して調べる。
期待される成果:この実験により、宇宙の無重量状態でRANKL遺伝子の発現が実際に高まっているのか否かが確認できる。さらに、遺伝子発現制御領域内で特に重要な働きをしている部分が明らかになる。これは、特に骨に加わる力をどのように感じ取って骨をバランス良く維持しているメカニズムを明らかにして、宇宙飛行士の健康だけでなく、骨粗しょう症等の予防や治療法の開発に役立つ情報になる。
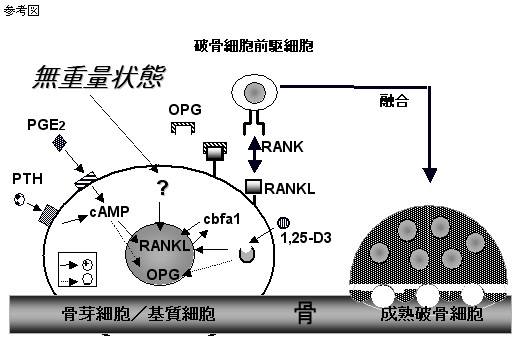
RANKL:破骨細胞分化因子
RANK:破骨細胞分化因子受容体
OPG:破骨細胞分化抑制因子
PGE2:プロスタグランジンE2
1,25-D3:活性型ビタミンD3
cAMP:環状アデノシン1リン酸
cbfa-1:転写因子の一種
骨芽細胞と破骨細胞のバランスには様々な因子が関与しているが、これまでの研究結果から宇宙の無重量状態での現象には破骨細胞分化因子(RANKL)が特に重要な働きをしていると考えられる。
テーマ:重力によるコムギ芽生え細胞壁のフェルラ酸形成の制御機構
提案者:若林 和幸
所属機関:大阪市立大学大学院理学研究科
研究目的:細胞壁は植物の細胞を取り囲み、その形や大きさを最も直接的に規定すると同時に、植物の成長や分化の過程にも深く関わっています。高等植物は地上の1gの重力下で誕生・進化したために、重力に抗しその体を支えるための丈夫な細胞壁を構築します。従って、細胞壁の強さは重力条件によって変化することが予想されます。
植物の細胞壁はその大半が複数種の多糖類から構成されています。多糖類の一部にはフェノール性化合物が結合しており、多糖類間のネットワーク(架橋構造)が形成されます。細胞壁多糖類の量やその分子サイズ、多糖類間での架橋形成は、細胞壁の強度(固さ)を規定する要因となっています。重力はこれら細胞壁成分の代謝系に影響し、その量や構造を変化させて細胞壁の強度を調節している可能性が考えられます。
本実験では、微小重力条件下で、植物の細胞壁多糖類の構造や多糖類間の架橋形成がどのように変化するのか、また、その変化に関わる代謝系の酵素活性やそれらの遺伝子の発現を調べることにより、重力による高等植物細胞壁の構築及びその強度の制御の仕組みを明らかにすることを目的とします。
研究方法・内容:乾燥状態のコムギの種子を保水性素材に固定し、これを容器にセットした状態で軌道上に運びます。軌道上で、この容器に水を加え発芽・成長させます。3?5日間、暗条件下で生育させた後、容器ごと冷凍保存し地上に持ち帰って細胞壁の物理的性質、構成成分、細胞壁代謝系酵素の活性とそれをコードする遺伝子の発現量、さらに、内生の植物ホルモン量等についての詳細な解析を行います。
期待される成果:微小重力条件では、特定の細胞壁多糖類のレベルや分子サイズ、多糖類間架橋構造のレベルが変化し、細胞壁の強度が変わることが期待されます。その成果は、高等植物の生活環の維持に必須である、細胞壁の構築過程の機構を解明する上での重要な知見をもたらすと考えられます。また、細胞壁の成分やその力学的性質に重力が与える影響を知ることは、将来の軌道上や地球に比べ重力の小さい星での植物の生育や生産に必要な基礎的データになると考えられます。


テーマ:筋蛋白質のユビキチン化を介した筋萎縮の新規メカニズム
提案者:二川 健
所属機関:徳島大学医学部栄養生理
研究目的:無重力による筋萎縮の新規メカニズムを実証し、その予防の可能性を探る。
研究方法・内容:長期間宇宙に滞在した宇宙飛行士の骨格筋は、帰還後自力で立てなくなるほど萎縮する。この無重力による筋萎縮は、今後人類が宇宙開発を進める上で必ず解決しなければならない重要な課題である。代表研究者らは、1998年に打ち上げられたスペースシャトルによる実験で、無重力により萎縮したネズミの骨格筋では特殊な蛋白質分解経路(ユビキチン-プロテアソーム経路)だけが活性化することを発見した。この蛋白質分解経路は分解しようとする蛋白質をユビキチンというペプチドで標識する(ユビキチン化)という特徴があり、この宇宙フライトネズミの骨格筋でも多くの蛋白質がユビキチン化され分解されていることがわかった。今回の研究では、宇宙ステーションで長時間培養したネズミの筋細胞は、細胞を増殖させる因子(増殖因子)を与えてもその信号を遺伝子 (核) まで伝達する蛋白質(情報伝達物質)が高度にユビキチン化され分解されているため、全く増殖しないことを実証する(図参照)。さらに、無重力によりユビキチン化されやすい情報伝達物質とその反応を誘導する酵素も同定し、無重力による筋萎縮の新規メカニズムの全容を解明する予定である。
期待される成果:無重力環境では筋蛋白質を分解するシステムが筋細胞の増殖も制御しているとする仮説はとても斬新である。また理論的には効果があると考えられてきた増殖因子がなぜ無重力による筋萎縮には無効であったかも明らかになる。さらに、現在においても筋力トレーニング以外に長期間の宇宙滞在による筋萎縮を予防する手段はない。しかし、本研究は、情報伝達物質のユビキチン化を抑制する薬剤や食事(宇宙食)を開発することが無重力による筋萎縮を防ぐ重要な手段になることを示している。これらの成果は、高齢化社会の我国の社会問題でもある寝たきりによる筋萎縮の予防にも応用できる。

テーマ:鶏胚の卵絨毛尿膜の血管新生を刺激するのは重力か?あるいは酸素濃度か?
提案者:ピァーソン・ジェームズ・トード
所属機関:国立循環器病センター研究所・心臓生理部
研究目的:鳥類卵は、卵殻孔を介した受動拡散により摂取する酸素以外は、成長に必要なものをすべて具備している。絨毛尿膜(CAM)は胚成長早期には卵殻内面を覆い、ガス交換の場を提供する。有効な酸素供給がCAMと胚の成長を促進させるが、他方、転卵もこれらの成長には不可欠な因子であり、その機序として、重力がCAMの血流分布に影響を与え血管新生を促進することが考えられる.しかし、この問題を重力のある地上実験のみで解明することは困難である。本研究の目的は、重力と転卵の相互作用がCAMの新生血管の形成と成長を刺激する重要な因子と考え(図参照)、CAMの発達が最も活発になる10日齢の鶏卵を用い、CAM辺縁への血流集積がシェアストレスを増し血管新生を促進させるか否かを検証することである。
研究方法・内容:有性鶏卵(0日齢)を(1)無処置群、(2)卵殻の一部に蝋を塗布した酸素摂取障害群、(3)卵殻の一部を削り、孔を作成した酸素摂取亢進群に分け、10日間恒温槽内に留置する.この際、各群において、i)卵を1Gで規則的に転卵させたもの(実験1)、及びii)無転卵のまま、1Gまたはスペースシャトルの微少重力下でインキュベートしたもの(実験2)を作成する。鶏卵回収後、CAMにおける血流・酸素飽和度の画像解析や血管の形態像、成長因子受容体の免疫組織学的分布などの組織学的検索を行う。
期待される成果:以上の実験により、鶏卵CAMの成長過程で血管新生がどのような局所機構で進み、それが胚形成にどのように関わるかが明らかにされるであろう。もし、血管内シェアーストレスの増大が血管成長因子の生成を促進させるとするならば、1G下で転卵した絨毛尿膜では、微少重力下と比較し、血管成長因子の受容体密度が高くなることが予想される。
