
Q. 衛星測位システムの整備は国の最重要課題に位置づけられていますが、JAXAとしてはどう貢献していくのでしょうか?

準天頂衛星初号機「みちびき」
GPSを搭載したカーナビや携帯・スマートフォンなどの普及により、位置情報は私たちの生活の中で欠かせないものになっています。現在、日本ではアメリカのGPSに100%依存していますが、さらにきめ細かなサービスが求められる中、アメリカのGPSだけでは限界があります。2010年に打ち上げた準天頂衛星初号機「みちびき」は、アメリカのGPSと組み合わせて使うことで測位精度を向上させるのが目的です。昨年の6月にはGPSを補完する測位信号の提供が始まり、技術実証および利用実証で成果をあげることができました。
その結果、準天頂衛星(国産の測位衛星)による測位システムの構築は国の基幹システムとして整備されることになったのです。国としては、当面はアメリカのGPSと協調しながら進めていき、将来的には独自システムとして構築していくこともあり得るという方針です。今後の測位衛星の打ち上げ計画も決めていただき、JAXAとしてはこれまで通り、システムの整備に向けて技術的に貢献していきたいと思います。「みちびき」の技術実証の成果を大いに活用していただき、海外の複数の衛星測位システムとの連携も含め、日本の準天頂衛星システムが有益なものとして整備されることを期待しています。
Q. 2010年にアメリカは、「2025年までに小惑星へ、2030年代半ばまでに火星への有人宇宙飛行を行う」という宇宙政策を発表しました。日本の今後の宇宙探査計画についてはいかがでしょうか?

小惑星探査機「はやぶさ2」
有人宇宙探査については、2011年8月に、国際宇宙探査コーディネーショングループ(ISECG:International Space Exploration Coordination Group)の第6回会合が京都で開催されました。ISECGはNASAやESA(ヨーロッパ宇宙機関)など世界14の宇宙機関が参加する任意団体で、宇宙探査活動に関する議論を行っています。JAXAも参加した昨年の会合では、将来の有人宇宙探査に向けた今後25年間のロードマップを2案作りました。火星探査の前に「月へ行く」か「小惑星へ行く」かの2案ですが、これはアメリカの宇宙政策に影響されています。今後はこのロードマップをもとに、世界の宇宙機関がそれぞれどう対応していくかを、国として考えることになると思います。
また探査機による科学探査については、昨年度から小惑星探査機「はやぶさ2」の計画が開始されています。2014年から2015年の打ち上げを予定しており、今度は炭素質の小惑星に行き有機物のサンプルを持ち帰り、地球生命誕生の解明に貢献することを期待しています。また、ヨーロッパと共同で計画中の水星探査計画「BepiColombo(ベピコロンボ)」の開発も進められています。その先には木星や土星に行く探査が考えられますが、具体的にはまだ話が出ていません。ただ、2010年に打ち上げた小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」は、将来の木星圏の探査を視野に入れ開発されたものです。IKAROSは宇宙で帆を広げ、太陽光を受けて加速・航行できることを世界で初めて実証しました。
宇宙には探査したい対象がいくらでもありますので、世界各国が同じ場所に行くのではなく、ある程度分担して太陽系の探査ができればよいと思っています。
Q. APRSAF(アジア・太平洋地域宇宙機関会議)などを通じてアジア諸国との連携をとってきましたが、どのような成果があがっていますか?
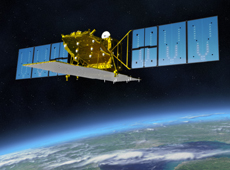
「だいち」の後継機として検討中の陸域観測技術衛星2号機
APRSAFは、日本が主導して開始したアジア・太平洋地域の宇宙機関の集まりです。年に1回年次会合を開催し、昨年の12月にシンガポールにおいて第18回目のAPRSAF年次会合を開催しました。単に意見交換だけで終わらないように、6年程前から具体的なプロジェクトをいくつか立ち上げています。そのひとつが衛星を活用した災害把握・災害管理に取り組む「センチネル・アジア」です。「センチネル・アジア」のステップ1では、陸域観測技術衛星「だいち」の観測画像を中心にインターネットで情報を提供し、現在のステップ2では日本以外の衛星の観測データも提供され、非常に良いシステムが構築できたと思います。
その他にも、宇宙技術を使い環境問題に取り組むプロジェクト「SAFE」や、衛星開発分野におけるアジア太平洋地域の人材育成を目的としたSTAR計画を立ち上げてきました。STAR計画は発展的に日本の大学の連合によるUNIFORM(大学国際フォーメーションミッション)へ移行中で、大学の先生たちにも協力していただき、実際に小型衛星を作ろうという段階まできています。
またオーストラリアから気候変動に関する新しいプロジェクトの提案がありましたので、今年はそのための新しいチームが発足されると思います。第18回目のAPRSAFでは、「きぼう」日本実験棟をアジア諸国でもっと活用していただくための「きぼう」利用プロジェクトの立ち上げを日本から提案し、賛同を得ました。
このように具体的な活動の場ができたことで、アジア・太平洋諸国においても宇宙利用への関心が強くなりAPRSAFへの参加国は年々増えています。それに伴い、アジア全体の連携をさらに高めるために、今後は日本が単独でAPRSAFを主導するのではなく、主要数カ国が主体となりAPRSAFを運営していく体制がとれたらよいと考えています。
Q. 日本の宇宙開発に関わる産業界や科学者などからのニーズについて、JAXAはどのように把握しているのでしょうか? またそれに対してどう応えていきたいと考えていますか?

JAXAは日本で唯一の宇宙研究開発機関ですから、国民のニーズをいかに把握して進めていくかが重要です。産業界に対してはJAXA産業連携センターが窓口となり、例えば「きぼう」日本実験棟でのタンパク質生成実験や、宇宙に関連した新しいビジネスや新製品の開発などに協力するほか、ロケットや人工衛星を製造する宇宙機器産業との協力関係を築いています。また科学者に対しては、各分野の学会や大学研究機関との相互関係を維持しながらJAXA宇宙科学研究所の宇宙理学委員会や宇宙工学委員会が窓口となってニーズを取り込んでいます。またISSについては「きぼう」利用推進委員会を作り、科学者の方たちに参画していただき意見をもらっています。
このように産業界や科学者の現場の意見やビジョンを聴き、できるだけみなさんのご要望に応えられるようにしていますが、宇宙開発に関わることは最終的には日本の宇宙政策という形でまとまり、JAXAとしてはその政策に基づいて実行することになります。ですから、政府や国民への説明責任を果たし、みなさんからのニーズを国の宇宙政策に反映してもらえるよう努めたいと思います。
Q. 2012年の主要なミッションと抱負をお聞かせください。
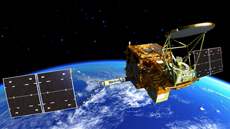
第一期水循環変動観測衛星「しずく」
今年は、第一期水循環変動観測衛星「しずく」と宇宙ステーション補給機「こうのとり」3号機の打ち上げのほか、星出彰彦宇宙飛行士による約6ヵ月間のISS長期滞在が予定されています。これらのミッションを確実に成功させ、みなさんの期待に応えたいと思います。「しずく」は地球上の降水を観測し水循環のメカニズムを解明し、水不足や洪水など水に関わる環境問題への対策に貢献することが期待される衛星です。地球環境監視を目的としたこのような衛星は、2009年に打ち上げられた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」に続き、2機目となります。この「いぶき」は世界で唯一の温室効果ガスを観測する衛星で、今年も大いに活躍してくれることでしょう。
JAXAにとって2012年は2008年4月から始まった5ヵ年の第2期中期計画の最終年です。今後も挑戦する気持ちを持ちながら、計画の達成に向けて気を引き締めていきたいと思います。