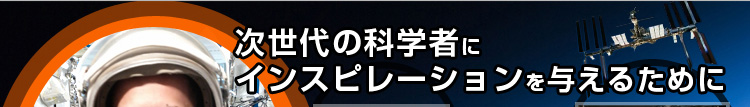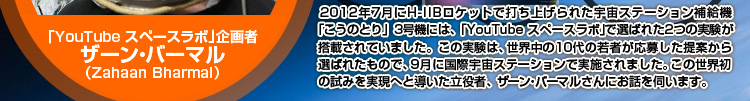
ザーン・バーマル(Zahaan Bharmal)
Google社 マーケティング・ストラテジック・コミュニケーション統括
1999年、オックスフォード大学にて物理学の学位取得。2007年、フルブライト奨学生としてスタンフォード大学ビジネススクールに学びMBA取得。2008年、Google社の欧州・中東・アフリカ部門 マーケティング・オペレーション統括。それ以前は主に英国政府の政策顧問とスピーチライターを務める。2012年より現職。宇宙空間で行う実験のアイデアを世界中の学生から募集したコンステト、「YouTube スペースラボ」を企画。
Q. 「YouTube スペースラボ」の概要を教えてください。

スペースラボの実験を搭載したH-IIBロケットの打ち上げ
「YouTube スペースラボ」は、世界中の14歳から18歳までの学生を対象に、宇宙実験のアイデアを2分間の映像にして応募してもらうコンテストで、2011年10月に募集を開始しました。審査員がその中から最も優秀な実験を2つ選び、それを実際に国際宇宙ステーションで行います。審査員には、私の子供時代のヒーローの一人であるスティーブン・ホーキング博士をはじめ、元・現役の宇宙飛行士、宇宙機関のスタッフ、教育者、科学者、思想家など大変素晴らしいメンバーを迎えました。JAXAの星出彰彦宇宙飛行士も審査員の一員です。
今年の3月には、地域別受賞者の6チームをアメリカのワシントンD.C.で開催されたスペシャルイベントに招待し、最優秀賞の2つの実験を発表しました。この受賞実験は、今年の7月に日本のH-IIBロケットで国際宇宙ステーションに向けて打ち上げられ、9月中旬に行われた実験の模様はYouTubeでライブ配信しました。 Q. 「スペースラボ」のアイデアはどこから生まれたのでしょうか? およそ20年前、10代の私は宇宙に強く興味を持ち始めました。宇宙に想像力を刺激されて学校の勉強に一所懸命取り組み、大学で物理を勉強したいとさえ思うようになりました。自分が実際に、宇宙が持つ非常に強い力に突き動かされるのを経験して以来ずっと、私が受けたようなインスピレーションを次世代の学生にも感じて欲しいという思いを漠然と抱いていました。
どうしたらそれを実現できるかがようやく分かったのは、4年前にGoogle社に入社した時です。誰もが新しいアイデアを提案できる社内コンペティションがあり、自分のアイデアを売り込んでみたのです。どのような反応が返ってくるか予想できませんでしたが、Googleの上級役員たちを相手に、国際宇宙ステーションに子供たちのアイデアによる科学実験を打ち上げる企画を発表したところ、非常に気に入られました。もともとGoogleは科学者によって設立された会社なので、次世代の科学者にインスピレーションを与えるという企画意図が評価されたのだと思います。
自分がかつてそうだったように、成長過程にある10代の若者たちは、興味の対象が何なのか、またこれから何を勉強しようか考えています。そのような若者たちが宇宙や科学によってワクワクし、楽しむことができたら素晴らしいと思ったのです。しかも、YouTubeというプラットフォームを使って、宇宙の驚異をコンテストに結びつけられるのは非常に魅力的です。
Q. 「YouTube スペースラボ」の成功の秘訣は何でしょうか?

動画チャンネル「YouTube Space Lab」
私たちは、宇宙に実験を打ち上げることについては専門外です。そのため最初の課題の1つは、それができる人材を世界中から集めてくることでした。まずは、重要なパートナーであるNASA、そして欧州宇宙機関(ESA)。それから、実際に実験を宇宙へ打ち上げるという非常に重要な役割を果たしてくれたJAXAです。彼らのロケットを使って宇宙ステーションへ実験を送りました。また、スペース・アドベンチャーズ社、国際宇宙ステーションで使われているノートパソコンを作っているレノボ社とも提携しました。大きなネットワークを持つパートナーの方たちの連携のおかげで、「スペースラボ」に正当性が与えられ、私たちのメッセージを世界により広く届けることができたのだと思います。
また主に告知は「YouTube Space Lab」というチャンネルで行いました。このチャンネルは、ウェブ上で宇宙と科学に関する動画を見られる専門サイトとしての役割を持っています。そこで紹介した「スペースラボ」のプロモーションビデオの再生回数は1300万回を超えました。また、パートナーたちのネットワークも、コンテストの存在を世界中に広めるのに役立ちました。例えば、審査員の1人、スティーブン・ホーキング博士は、プロモーションビデオの中で、人類の将来における宇宙の重要性について語ってくださいました。これは今でもインターネットで見ることができます。このように、私たちのチャンネルの存在と、素晴らしいパートナーたちのコンビネーションによって、この企画が成功したのだと思います。
関連リンク: YouTube Space Lab
Professor Stephen Hawking welcomes you to YouTube Space Lab Q. 企画を進めるにあたり、宇宙機関との共同作業はいかがでしたか? 率直に言って、彼らなしではこの企画は実現できませんでした。そのような意味で、宇宙機関と一緒に仕事をするのはいい刺激になりました。JAXA、ESA、NASAの人たちは驚くほど頭が良く、やる気と情熱に満ちていて、次世代の科学者、宇宙飛行士や探検家の育成について考えています。この20年の間、宇宙飛行士になりたくてもなれなかった私としては、宇宙機関との仕事はまさに夢が叶ったような素晴らしい体験でした。
Q. 「スペースラボ」には、どれくらいの数の応募がありましたか?
世界80ヵ国から2000以上の応募がありました。最も応募が多かったのはインドで、その次がアメリカです。日本からも約40通の応募がありました。これまで誰もこのような企画を実施したことがなかったので、正直なところ、最初はどれくらいの応募がくるか見当がつきませんでした。ですから、世界中からたくさんの応募があったことに大変驚きましたし、若者たちの見識や想像力、創造性にはとても感心しました。
応募の条件は、国際宇宙ステーションで実現可能な実験のアイデアを考えて、それを2分間の映像にまとめることですが、これは10代の若者にとって容易なことではありません。国際宇宙ステーションへの運搬にはさまざまな制約がありますが、それも考えなければならないのです。そういう意味でも、世界各国からたくさんの応募があったことに驚きました。
Q. 最優秀賞を受賞した2つの実験の内容を教えてください。

左からアム君、サラさん、ドロシーさん 
ショウジョウバエの死骸が見えるハエトリグモを入れた箱
14〜16歳を対象にしたグループから選ばれたのは、アメリカ・ミシガン州の2人の少女、ドロシーさんとサラさんによるアイデアで、細菌の特性に関するものです。NASAをはじめ他の宇宙機関の研究によると、「悪い」細菌を国際宇宙ステーションに送るとその細菌はさらに有害になるそうです。そこで彼女たちの素朴な疑問は、もし「良い」細菌、つまりプロバイオティクスを宇宙に送ったらどうなるのか、人間にとってさらに良い細菌になるのか、ということです。そこで、彼女たちは枯草菌というプロバイオティクスを宇宙へ送りました。実験の結果、細菌はより強力になりました。この類いの研究は、スーパーバグ(複数の抗生物質への耐性を持った細菌)の取り組みに道を開くので、大変興味深い実験だと思います。
17〜18歳のグループからは、エジプトのアレキサンドリア出身の少年、アム君の実験が選ばれました。彼の実験はハエトリグモを使います。クモの多くは巣を作り、そこにかかった獲物を捕まえますが、ハエトリグモは獲物に飛びついて捕まえます。ここで非常に興味深いのは、ジャンプには重力が必要なことです。そこで彼の実験テーマは、そのようなクモを微小重力空間に送ったらどうなるのか、どのように環境に適応していくのか、獲物を捕まえることができるのか、ということでした。宇宙で行われた実験のライブ配信を見たところ、クモを入れた箱の中には、獲物であるショウジョウバエがたくさん死んでいるのが映っていました。このことから、ハエトリグモが宇宙環境に適応できたことが分かります。
Q. 最優秀賞の選考の基準は何だったのでしょうか?

ロシアで宇宙飛行士訓練を体験するアム君 
種子島宇宙センターでロケットの打ち上げを見学するサラさんとドロシーさん

無重力飛行を体験する受賞者たち
まず第一に、私たちはグッドサイエンスを求めていました。学校の物理や生物の先生もいいと思えるような科学です。そのために、科学的方法に沿うことを応募の条件にしました。つまり、仮説を立て、検証し、その結果をどう解釈するか、2分間のビデオで説明しなければなりません。これが基本的なルールです。またそれ以外に、未知の要素も求めていました。創造性、想像力、そして既成概念にとらわれない考え方です。おそらくこの要素が、「スペースラボ」の特徴です。
例えば、ハエトリグモの実験が最優秀賞に選ばれた理由は2つあります。1つ目は、単純にすごく面白いテーマだということです。彼の実験テーマを聞いたら、誰でも、クモが宇宙でどうなるのか興味が湧きます。2つ目の理由は、もし人類が月を超えて火星、またはその先へ向かうことになったとき、長期の宇宙滞在が人体にどのような影響をもたらすかを理解していなければなりません。その答えを知るために、まず動物が微小重力環境にどう適応できるかを研究することは、とても大切なことです。そのような観点で見ると、この実験は、広範囲にわたって応用できる非常に興味深い内容だと思いました。 Q. 最優秀賞のほかにも、個人的に興味深い実験はありましたか? 私が特に興味をひかれた実験は、アメリカのマサチューセッツ出身の18歳の少女による実験で、テーマは宇宙における雪の結晶の成長です。私はこういったシンプルなテーマの実験が大好きですが、なぜ面白いかと言うと、雪の結晶の形状はガス状惑星にも見られるからです。例えば巨大ガス惑星の表面を観察すると、雪の結晶のような原子が生成しているのが分かります。そういう意味で、宇宙での雪の結晶の成長を理解することは、それと似た現象が見られるガス状の惑星や銀河の研究にも役立つ可能性があるのです。これはとても興味深いですね。 Q. 宇宙で実験を行う以外にも、入賞者には特典があったそうですね。 はい。最優秀賞を受賞した2チームに与えられる最高の特典は、自分の実験が国際宇宙ステーションで実施されるという感動と名誉です。そのほかの特典として、エジプト出身のアム君はロシアで実際の宇宙飛行士の訓練を体験しました。また、ミシガン出身のドロシーさんとサラさんは、自分たちの実験が宇宙へ届けられる様子を見るために、日本の種子島宇宙センターに行ってロケットの打ち上げを見学しました。また、最優秀賞を発表したワシントンD.C.に招待した地域別受賞者の6チームも、無重力飛行を体験しました。放物線飛行ができるジャンボジェットを使った無重力体験です。具合が悪くなった子は誰もいなくて、皆とても喜んでいました。このような経験は、きっと一生忘れられないことでしょう。彼らにとって、「スペースラボ」が、素晴らしいチャンスになったと願いたいですね。