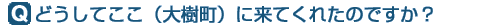
まず飛行船の発着のためには、気象が安定し広いスペースがあることが前提となります。ここ大樹町は年間を通じて比較的風が穏やかな土地で、飛行船の大きな機体をハンドリングするには格好の場所です。47万平方メートルの広大な「多目的航空公園」が整備され、1000mの滑走路も備えています。これだけのスペースをほぼ貸し切りに近い状態で使わせてもらうことができているのは非常にありがたいことです。
定期航空路からも離れていることもあり、以前から民間企業や研究機関が試作機の実験などに使ってきましたし、我々もNAL(航空宇宙技術研究所)時代からなじみ深い場所でした。こうした気象条件や広さなど地の利に加え、町役場をはじめとする地元の方々は航空宇宙分野に理解が深く、情熱を燃やし好意的に受け止めてくださる方々がたくさんいらっしゃる。それも、ここで実験を行ううえでの大きな、ひょっとしたら最大のメリットとなっています。
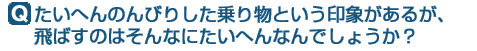
機体の投影面積が大きいので、風の影響も非常に強く受けます。風速1mで35kgf(kg重)の風圧が試験機に加わりますが、風速3mになると350kgfと約10倍になります。これを格納庫から馬のたづなを引くように、12〜16人のクルーで引き出し、放船します。「のんびりした乗り物」との印象を持たれるのは、おそらく商業広告用の飛行船をイメージされているのではないかと思いますが、あれはそもそも広告用ですからゆっくりのんびりと低空を飛ぶのが仕事。高度も数百メートルまでです。
しかし、成層圏プラットフォームではそれより2桁高い高度を目指すことになるわけで、膜材から構造、飛行制御の方法まで全く違ったものになってきます。「たいへんか?」と聞かれれば、正直、たいへんです。事故を起こさぬよう地上安全・飛行安全に全力を注ぎながら、未知の世界に挑み、実験の成果を挙げていかねばならないわけですので。