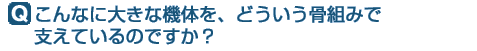
いえ、内部に骨組みはなく、内外の気圧差による膜材の張力で形状を保つ「軟式飛行船」と呼ばれるジャンルの機体です。カギとなるのは膜材の比強度です。NASAの火星探査機のエアバッグにも使われ有名になった「ベクトラン」繊維を全面的に採用しています。宇宙空間の長旅にも耐える、軽くて強靱なスーパー繊維です。機体の膜材はこのベクトラン繊維の織物と「エバール」という樹脂の膜をウレタンでサンドイッチする形となっています。
機体の内部にはヘリウムガスが詰まっていますが、ヘリウムガスは非常に分子の小さいガスなので、それを閉じこめておくために分子レベルで見てもスキマの少ない密な膜が必要となるわけです。
こうして作った膜材の厚みは0.2mm(官製はがきとほぼ同じ)ですが、幅1cmの短冊状にしても、70kgfの張力に耐えるほどの強さがあります。
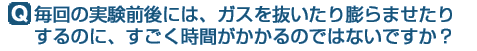
いえ、ガスはずっと入れたままなんです。骨組みがないのでガスを抜くとぺしゃんこになりまから、いったん注入したらまず抜くことはありません。内外の気圧差は地上では1000分の4ほどにすぎないのですが、それだけで、じゅうぶんに形状を保つことができます。たしか東京ドームなどでもその程度の気圧差だそうです。
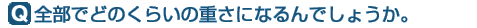
腹巻きにぶら下げるように推進機などを取り付けていますが、機体の重さは約半分が膜材で、合計で6.4トン。試験の際はヘリウムガスによる浮力と差し引きで100kgほどの重さになるよう、ガスの量を調整します。この機体を2機のプロペラを使って、上昇下降、旋回などを行わせ、飛行制御の実験をします。
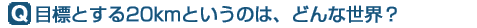
高度10kmから50km程度の所を成層圏、ストラトスフィアと呼んでおり、高度20kmは風が比較的おだやかな所です。一方、我々が住んでいる「対流圏」では、温かい空気が上昇し、冷たい空気が下降する「対流」が起こっています。雲が出来たり、雨が降ったりするのもこの世界での出来事です。しかし成層圏になると、温度が一定で、いわば空気は「層を成して」いる。だから対流もありません。風も穏やかで雲も雨もない世界です。気圧は地上の20分の1、空気の密度も15分の1になります。
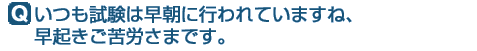
飛行船は、特に地上運用で風の影響を非常に強く受けるので、朝のなぎの時間帯に試験を実施する事が多くなっています。ですので、試験となると早起きというより、前日から徹夜での準備作業が必要となります。実験隊のメンバーは、ほんとうによくやってくれていると思います。