|
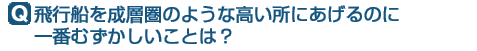
飛行プロファイルを決定するとき最も考えなければいけない部分が、外気温と内部のガスの温度の変化や、それによる膨張収縮で起きる浮力の変化がどう影響するか、なのです。
機体の内部のガスは冷えると縮み、暖まると膨らむのはおわかりだと思います。機体が冷えるファクターとしては、上昇に伴う外気温の低下がまず上げられます。上昇の速度が速いほど内外の差が大きくなり、浮力に効いてきます。
また、上昇するためには、飛行船内部バロネット(空気袋)の空気を外に排出しますが、そのときに「断熱膨張」で内部温度が下がり、これも浮力に影響します。さらに機体に風が当たることで無視できない量の熱が逃げていきます。機体表面での結露や蒸発がこれにからんでおり、もちろん対気速度も考え合わせなくてはなりません。
入熱のほうでは、太陽光による加熱が要因としてあり、これは天候や日射の強さ、日射にさらされた時間に左右されます。また下降する際には周囲温度の上昇や「断熱圧縮」など、上昇時とは逆のことが起こります。
このように、時々刻々と飛行船の内外の温度が変化し、それにともない複雑に浮力が変化します。その変化を適切にとらえ、機体を安定した高度や姿勢に保つところが、非常に技術のいる部分です。
|