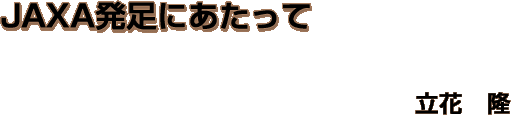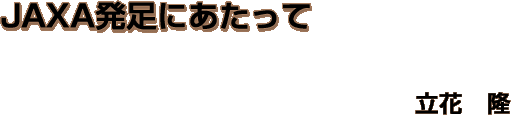|
―― JAXAが発足しましたが、JAXAに何を期待しますか?
立花 期待もありますが、期待より不安が先に立ちます。
―― といいますと?
立花 この組織、組織としてうまく機能するんだろうか? という組織論的不安もあれば、JAXAが生まれたことで、前よりも日本の宇宙開発はうまくいくようになるんだろうか? 宇宙科学はどうなんだろう? 航空のほうはどうなるんだろう? JAXAの母胎となった三研究機関がそれぞれカバーしていた技術とサイエンスの未来に対しての不安があります。
ぼくは、三研究機関とも、取材を通してその過去現在ともよく知っているんです。その上、宇宙研究所に関しては、しばらく評議員をやっていたこともあって、立ちいった内部事情も知っています。
三研究機関には、JAXA発足以前にもいろんないきさつがあって(東大航空宇宙研究所から、文部省宇宙研が生まれたときとか、東大系固体ロケット研究の流れと科技庁系液体ロケット研究の流れが争ったときとか、事業団が発足して、日本独自のロケット研究の流れに米国直輸入ブラックボックスロケット技術が継ぎ木されたときとか)、これまでもいろんな問題が度々生じて、そのたびにいろんなギクシャクがあったことを知っています。
今回も、科技庁系と文部省系、テクノロジー系とサイエンス系という、そもそも組織原則やカルチャーが全く異なる組織が合体するわけですから、いろいろ問題が起ることは目に見えています(事務処理上の原則問題から、基本的ものの考え方、価値観、組織のカルチャーなど)。しかし、それはまあ、大した問題ではないだろうと思っています。克服できないはずはないと思うからです。
もっと大きな問題は戦略問題にあると思っています。戦略問題というより、戦略の欠如問題です。
それはそもそもこの三研究機関合併が何なのかという問題でもあります。宇宙航空技術といえば、国家の戦略的技術です。それが三機関バラバラに研究が行われてきた。そこにたしかに無駄な側面や不合理な側面も多々あったでしょう。それを統合することによって無駄が省ける、そういう側面があることは否定しません。しかし、JAXAができる経緯を見ていると、そういう無駄を省くという行政改革的目的だけが先行していて、日本の国家戦略として、これから航空宇宙技術の研究育成をどうするのか、どういう方向にもっていくのか、そのためにそれを担い推進していく国家機関はどうあらねばならないのかという、本来先行してすましておくべき理念的考察がかけていたと思います。
 |
1/6 |
 |
|
 |