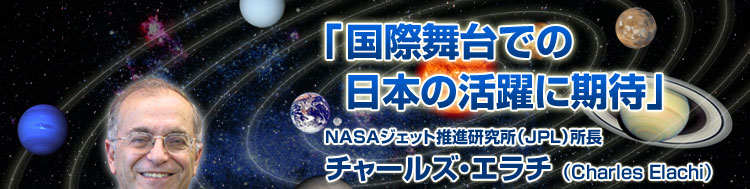
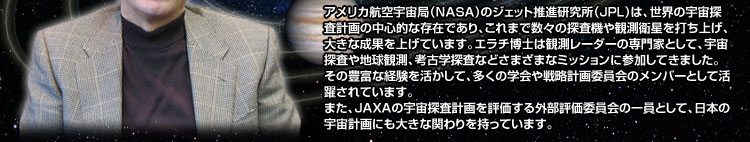
チャールズ・エラチ (Charles Elachi)
NASAジェット推進研究所(JPL)所長。カリフォルニア工科大学副学長。1968年、仏グルノーブル大学卒業(物理学)。1971年、カリフォルニア工科大学で電気科学の博士号取得。1979年、南カリフォルニア大学(USC)でMBA取得。1983年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で地質学の修士号取得。1970年よりジェット推進研究所勤務。1982年には、宇宙・地球科学プログラム部長となる。これまでに、金星探査機「マゼラン」や土星探査機「カッシーニ」、スペースシャトルの合成開口レーダーなど多くの宇宙探査ミッションに携わる。2001年より現職。また、カリフォルニア工科大学にて電気工学・惑星科学教授を務める。電気電子学会(IEEE)及び米国航空宇宙学会の特別研究員。米国工学アカデミー・国際宇宙航行学会会員。
エラチ博士は、人工衛星やスペースシャトルに搭載したレーダーによって地表面の詳細観測をする技術を確立。博士が開発した衛星搭載システムは、宇宙探査だけでなく、地球観測や災害監視など幅広い分野に応用されている。NASA戦略計画委員会委員長を務めるほか、20カ国以上で宇宙探査及び地球観測について講義を行う。エジプト、オマーン及び中国では多くの考古学探査にも参加。1989年には、惑星探査における功績が認められ、小惑星1982SUが4116エラチに改名される。
宇宙研究委員会ノードバーグ賞(1996年)、ドライデン賞(2000年)、ウェルナー・フォン・ブラウン賞(2002年)、武田賞(2002年)、ロンドン王立学会マッシー賞(2006年)のほか、NASAにおける数多くのメダル、IEEEの各賞など多数の賞を受賞している。
Q. エラチ博士はJAXA宇宙科学研究本部の外部評価委員会のメンバーですが、昨年の評価委員会ではどのような印象をお持ちになりましたか? 最も印象に残っている日本の宇宙科学ミッションは何ですか?
外部評価委員会では、JAXAのさまざまな宇宙科学プログラムやそのプログラムを実行する際の取り組み方について評価を行いますが、私は宇宙科学研究本部(ISAS)の努力に強い感銘を覚えました。特定のミッションというよりは、ISASが行っている惑星、天体物理学、宇宙物理学といった多岐にわたる活動や、科学者や技術者、そして彼らと研究を行っている学生たちの連携といったものが特に印象に残りました。それは、私にジェット推進研究所(JPL)の初期の頃を思い出させます。ISASはJPLよりも小規模ではありますが、宇宙探査の第一歩を見事に踏み出しているという印象を受けました。
Q. JAXAは海外でどのような点が評価されていますか?

月周回衛星「かぐや」

近年、JAXAは小惑星探査機「はやぶさ」による小惑星とのランデブー、着陸に成功しましたが、それはとても挑戦的なミッションでした。同じようなミッションをアメリカが行ったとしても、それは大きなチャレンジとなるでしょう。このような小惑星の探査や、現在月を周回している探査機「かぐや」による観測成果などから、日本が国際的にも惑星探査の分野でリーダーシップを発揮していることが見て取れます。
また、JAXAは惑星探査の分野だけではなく、地球科学の分野など多くのプログラムで国際的な活動を行っています。 これまでJPLは、日本の衛星を使った地球観測ミッションに数多く参加してきました。その一方で、日本の科学者も私たちのミッションに参加してきたわけですが、このような国際共同プロジェクトを通じて、科学的な関係だけでなく、強固な人間関係を築くことができました。国際的な関係を構築することは、宇宙科学の研究や探査を行っていくうえで非常に重要なことですが、JAXAはこの点で世界的にも高く評価されています。
Q. 世界から見て、日本の宇宙開発の役割は何だと思われますか?
日本は科学や工学の分野で非常に高い能力を持っています。ですから、東南アジアだけでなく、世界中に協力関係を拡大し、そういった国際共同プロジェクトにおいて、リーダー的な役割を果たしてほしいと思います。アメリカのNASAや欧州宇宙機関(ESA)などに加えて、日本は宇宙探査の主要参加国です。日本にはリーダーシップをとれる能力があると思いますし、これまで以上に広範囲の役割を果たしていくことが可能だと思います。日本は世界の宇宙探査で大きな役割を担っているのです。
Q. 今後、日本と国際協力したいミッションは何でしょうか?

小惑星探査機「はやぶさ」
最近の小惑星探査機「はやぶさ」の成果からも、日本は小惑星とのランデブーとサンプル採集に関しての技術を構築してきたことが分かります。将来的には、小惑星や彗星の研究、そのような小天体とのランデブーやサンプル採取など広範囲に渡るミッションを、日本と協力して進めていきたいと思います。こういった研究によって太陽系の多様性を理解することができますので、実現するのを非常に楽しみにしています。
さらに、私たちは地球の温暖化など、人類にかかわる問題を共有しているわけですから、地球科学の分野でも協力していくべきだと考えています。国民の税金を使った公共政策に従事する私たちが、地球がかかえる問題にどう対処していくかを決断するためには、地球に起こっている変化を観察するネットワークを構築していく必要があると思います。そのためには、宇宙開発で中心的な役割を担っている各国がすべて参加し、協力していかなければなりません。
Q. JAXAの活動についてご意見やアドバイスをいただけますか?
2つアドバイスさせていただきたいと思います。1つは、先ほど申し上げた、国際的な協力関係を拡大するということです。国際協力は非常に重要で、JPLが行うほとんどのミッションには海外の多くの科学者が参加しています。日本の場合は島国ですから他国と違うかもしれませんが、宇宙から地球を眺めた場合、国境は見えません。したがって、宇宙探査というのは全人類のためのものであり、国際的な活動であるべきだと思います。日本はすでに、いくつかの国際共同プロジェクトを行っているようですが、今後さらに活動範囲を広げるためには、例えば、「リサーチフェロー・プログラム」と呼ぶプログラムを実施し、世界各国の科学者をJAXAに定期的に迎え、1〜2年間受け入れていくなどしたらよいと思います。
2つ目は、リスクを恐れないということです。宇宙探査、特に惑星探査という分野では、前例のないミッションを多々行いますので、常に大きなリスクを抱えています。そのため、リスクを冒すことに対して寛容な態度を取ることが大切になってきます。これは、宇宙探査に限ったことではありません。北極探検であれ大洋横断であれ、300年前に探査を行う場合には非常に大きなリスクがありました。常に後退や失敗がつきまとってきたわけですが、人類がそこであきらめることはありませんでした。一般的に人間、特に大規模の組織は、リスクを避ける傾向にありますが、問題や失敗を恐れていてはリーダーシップを発揮することはできません。ですから、問題を避ける努力をしながらも、「問題は発生するものなのだ」という意識を持ち、発生した問題から学習をし、さらに宇宙探査というフロンティアを推し進めていくことが重要だと思います。JPLでは、成功したミッションもあれば、失敗に終わったミッションもありますので、何度もそのような経験をしてきました。しかし、常に私たちは失敗から学ぶことで新境地を開拓してきたのです。

火星探査機「マーズ・エクスプレス」
(提供:ESA)

Q. NASAとJAXA以外で、エラチ博士が注目しているミッションは何ですか?
まず注目するのは、欧州宇宙機関(ESA)の宇宙探査ミッションです。現在観測中の火星探査機「マーズ・エクスプレス」や金星探査機「ビーナス・エクスプレス」のほか、2014年の到着予定で彗星に向かっている探査機「ロゼッタ」があります。「ロゼッタ」は彗星とランデブーを行い、着陸機を彗星表面に投下します。このように、欧州宇宙機関は宇宙探査において、ますます大きな役割を担いつつあると思います。
次に、フランス国立宇宙研究センター(CNES)が行っている、宇宙から地球の海を観測するミッションです。このミッションにはJPLも参加し、フランスとアメリカの衛星が協力して観測を行います。日本もアメリカも太平洋に面していますから、海の熱変化から生じる気候の変化、エルニーニョ現象を観測することは、とても重要なことです。
Q. 有人宇宙飛行を成功させた中国の宇宙開発についてどう思われますか?
宇宙探査にはすべての人が参加するべきだと思います。平和利用で惑星探査や地球観測を行う場合には、人類全体の責任となってくるわけですから、常に協力体制をとっていく必要が出てきます。そのため、アメリカは非軍事的な国際協力を歓迎してきました。ですから、今後は更に中国との協力関係が構築されていけばよいと思います。現在の協力関係は非常に限られたものになっていますが、将来的には拡大していくことを望んでいます。
外部評価委員会では、JAXAのさまざまな宇宙科学プログラムやそのプログラムを実行する際の取り組み方について評価を行いますが、私は宇宙科学研究本部(ISAS)の努力に強い感銘を覚えました。特定のミッションというよりは、ISASが行っている惑星、天体物理学、宇宙物理学といった多岐にわたる活動や、科学者や技術者、そして彼らと研究を行っている学生たちの連携といったものが特に印象に残りました。それは、私にジェット推進研究所(JPL)の初期の頃を思い出させます。ISASはJPLよりも小規模ではありますが、宇宙探査の第一歩を見事に踏み出しているという印象を受けました。
Q. JAXAは海外でどのような点が評価されていますか?

月周回衛星「かぐや」
近年、JAXAは小惑星探査機「はやぶさ」による小惑星とのランデブー、着陸に成功しましたが、それはとても挑戦的なミッションでした。同じようなミッションをアメリカが行ったとしても、それは大きなチャレンジとなるでしょう。このような小惑星の探査や、現在月を周回している探査機「かぐや」による観測成果などから、日本が国際的にも惑星探査の分野でリーダーシップを発揮していることが見て取れます。
また、JAXAは惑星探査の分野だけではなく、地球科学の分野など多くのプログラムで国際的な活動を行っています。 これまでJPLは、日本の衛星を使った地球観測ミッションに数多く参加してきました。その一方で、日本の科学者も私たちのミッションに参加してきたわけですが、このような国際共同プロジェクトを通じて、科学的な関係だけでなく、強固な人間関係を築くことができました。国際的な関係を構築することは、宇宙科学の研究や探査を行っていくうえで非常に重要なことですが、JAXAはこの点で世界的にも高く評価されています。
Q. 世界から見て、日本の宇宙開発の役割は何だと思われますか?
日本は科学や工学の分野で非常に高い能力を持っています。ですから、東南アジアだけでなく、世界中に協力関係を拡大し、そういった国際共同プロジェクトにおいて、リーダー的な役割を果たしてほしいと思います。アメリカのNASAや欧州宇宙機関(ESA)などに加えて、日本は宇宙探査の主要参加国です。日本にはリーダーシップをとれる能力があると思いますし、これまで以上に広範囲の役割を果たしていくことが可能だと思います。日本は世界の宇宙探査で大きな役割を担っているのです。
Q. 今後、日本と国際協力したいミッションは何でしょうか?

小惑星探査機「はやぶさ」
さらに、私たちは地球の温暖化など、人類にかかわる問題を共有しているわけですから、地球科学の分野でも協力していくべきだと考えています。国民の税金を使った公共政策に従事する私たちが、地球がかかえる問題にどう対処していくかを決断するためには、地球に起こっている変化を観察するネットワークを構築していく必要があると思います。そのためには、宇宙開発で中心的な役割を担っている各国がすべて参加し、協力していかなければなりません。
Q. JAXAの活動についてご意見やアドバイスをいただけますか?
2つアドバイスさせていただきたいと思います。1つは、先ほど申し上げた、国際的な協力関係を拡大するということです。国際協力は非常に重要で、JPLが行うほとんどのミッションには海外の多くの科学者が参加しています。日本の場合は島国ですから他国と違うかもしれませんが、宇宙から地球を眺めた場合、国境は見えません。したがって、宇宙探査というのは全人類のためのものであり、国際的な活動であるべきだと思います。日本はすでに、いくつかの国際共同プロジェクトを行っているようですが、今後さらに活動範囲を広げるためには、例えば、「リサーチフェロー・プログラム」と呼ぶプログラムを実施し、世界各国の科学者をJAXAに定期的に迎え、1〜2年間受け入れていくなどしたらよいと思います。
2つ目は、リスクを恐れないということです。宇宙探査、特に惑星探査という分野では、前例のないミッションを多々行いますので、常に大きなリスクを抱えています。そのため、リスクを冒すことに対して寛容な態度を取ることが大切になってきます。これは、宇宙探査に限ったことではありません。北極探検であれ大洋横断であれ、300年前に探査を行う場合には非常に大きなリスクがありました。常に後退や失敗がつきまとってきたわけですが、人類がそこであきらめることはありませんでした。一般的に人間、特に大規模の組織は、リスクを避ける傾向にありますが、問題や失敗を恐れていてはリーダーシップを発揮することはできません。ですから、問題を避ける努力をしながらも、「問題は発生するものなのだ」という意識を持ち、発生した問題から学習をし、さらに宇宙探査というフロンティアを推し進めていくことが重要だと思います。JPLでは、成功したミッションもあれば、失敗に終わったミッションもありますので、何度もそのような経験をしてきました。しかし、常に私たちは失敗から学ぶことで新境地を開拓してきたのです。

火星探査機「マーズ・エクスプレス」
(提供:ESA)
Q. NASAとJAXA以外で、エラチ博士が注目しているミッションは何ですか?
まず注目するのは、欧州宇宙機関(ESA)の宇宙探査ミッションです。現在観測中の火星探査機「マーズ・エクスプレス」や金星探査機「ビーナス・エクスプレス」のほか、2014年の到着予定で彗星に向かっている探査機「ロゼッタ」があります。「ロゼッタ」は彗星とランデブーを行い、着陸機を彗星表面に投下します。このように、欧州宇宙機関は宇宙探査において、ますます大きな役割を担いつつあると思います。
次に、フランス国立宇宙研究センター(CNES)が行っている、宇宙から地球の海を観測するミッションです。このミッションにはJPLも参加し、フランスとアメリカの衛星が協力して観測を行います。日本もアメリカも太平洋に面していますから、海の熱変化から生じる気候の変化、エルニーニョ現象を観測することは、とても重要なことです。
Q. 有人宇宙飛行を成功させた中国の宇宙開発についてどう思われますか?
宇宙探査にはすべての人が参加するべきだと思います。平和利用で惑星探査や地球観測を行う場合には、人類全体の責任となってくるわけですから、常に協力体制をとっていく必要が出てきます。そのため、アメリカは非軍事的な国際協力を歓迎してきました。ですから、今後は更に中国との協力関係が構築されていけばよいと思います。現在の協力関係は非常に限られたものになっていますが、将来的には拡大していくことを望んでいます。