Q. エラチ博士が関わってきたミッションで特に印象に残っているものは何ですか?

火星探査機「マーズ・ローバー」
(提供:NASA)

学生時代からJPLで働き、参加したミッションはいろいろありますが、初めて作業に関わったミッションが特に思い出深いです。1989年にNASAが打ち上げた金星探査機「マゼラン」で、金星の地表をレーダーで観測するミッションでした。ただ、若い頃に参加したミッションが印象深いものになるのは容易に想像できますよね。私はその後も非常に興奮させられるミッションに多く参加してきました。火星探査機「マーズ・ローバー」、宇宙望遠鏡、スペースシャトルによる合成開口レーダーを使った観測ミッションなど、その中から1つ選ぶのは簡単なことではありません。私にとってミッションは我が子のようなものなのです。「自分の子供の中で誰がお気に入りですか?」と聞かれても、みんな同じくらい大切で、答えようがありません。どれも全く同じということではなく、同じように愛情を注いできたものばかりなのです。どのミッションからも何か新しいことを学べるわけですから、すべてのミッションに魅力的な側面が必ずあります。
Q. アメリカの惑星探査は今後どのようなことを目指していくのでしょうか?
アメリカの惑星探査プロジェクトの目標は、惑星の形成を理解することと、地球外で生命の進化の可能性を研究することです。ですから、かつて水があったと考えられる火星が大きなターゲットになってきます。私たちは2年ごとに火星へ探査機を送り、その歴史と生命の進化の可能性を理解するべく観測を行っているわけですが、他にも木星の衛星、エウロパに注目しています。氷で覆われたエウロパの表面下に、海が存在しているかもしれないからです。さらに、土星の衛星、タイタンには探査機「カッシーニ・ホイヘンス」を送り、現在も観測を続けています。タイタンには炭化水素を多く含む大気があり、かつて生命体が存在していた、あるいは現在も存在している可能性があります。このような惑星では、生命が進化した形跡があるかもしれないため、特に注目を集める研究対象になっています。
Q. 宇宙開発を国民に広報することの必要性をどう思われますか?
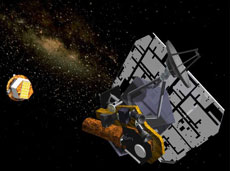
彗星探査機「ディープ・インパクト」
(提供:NASA)
宇宙開発プログラムは基本的に税金でまかなわれているものですから、国民に対して情報提供を行い、大きな関心を持ってもらうことが重要であると強く思います。
アメリカでは特に若者たちが宇宙探査に非常に興味を持ち、科学博物館の入場者数がスポーツ観戦に行く人数よりも多いと聞いています。毎年約2万人の学生がJPLを訪問していますし、彗星探査機「ディープ・インパクト」や火星探査機「マーズ・ローバー」など、探査機が目的地に着陸するような一大イベントがある場合には、JPLのウェブサイトに数週間で何十億ものアクセスがあります。そのことからも関心の高さが分かります。
私たちは、若い人たちを中心とした一般の方に、ウェブサイトや博物館での展示を通じて積極的に情報提供を行っています。展示といっても、何の変化もないような展示ではありません。着陸などのイベントがある場合には、JPLと全米の博物館をインターネットで接続して、リアルタイムで着陸の様子が見られるようにしています。
Q. 宇宙を題材にした教育についてどう思われますか?
宇宙探査や惑星などを題材にした学習が優れている点は、子供の心を開き、子供たちが「不可能なことは何もない」というような考えができるようになることです。自分の身近な環境に制限されることなく、夜空を見上げて美しい星を眺め、自分が将来その星を旅する姿を思い浮かべる。そうすることで、子供の想像力が広がり、夢が持て、それがどんな夢であっても叶えることができると思えるようになります。宇宙教育によって、子供たちが宇宙についての思いをめぐらせるだけでなく、宇宙が子供たちに「考える」チャンスを与えてくれるのです。月を見上げて月面旅行を夢見、実際に人間が月に向かって行くことで、子供たちは「不可能なことなどほとんどない」という考えを持てるようになり、励まされていくのです。このような前向きな気持ちになることは、人生で大事なことであり、それが基礎となって、探究心、発見、イノベーション(技術革新)、学習などにつながっていくのだと思います。
Q. 惑星探査の意義は何だと思われますか?

月周回衛星「かぐや」が撮影した月面と地球

私たちは太陽系に住んでいます。太陽系の中での地球の存在はどういうものなのか?これは、探査機「カッシーニ」が撮影した土星や、月から撮られた地球の画像を見ると分かってきます。「カッシーニ」の画像では、土星の輪の向こう側に小さな光の点が見えましたが、その小さな点こそが地球でした。また、最近、JAXAの月周回衛星「かぐや」が撮影した地球の写真を見ましたが、これを見ると、自分たちがいかに小さな存在であるかが分かります。人間は自己中心的に物事を考えがちであり、絶えず争い、国家は資源などを巡って戦争を行います。しかし、薄い大気に包まれた小さな星、地球を見た時に、この美しい星を共有している自分たちがいかに幸運であるかということ、そして、この小さくてか弱い星を守っていかなければならないということに気づかされます。このように、外から地球を見て初めて、太陽系の中で私たちがどれほど小さいか、その存在について考えさせられます。太陽系全体やその形成方法を調べることにより、その中での我々の位置づけを理解していくことが極めて重要なことだと思います。
また、かつては地球が宇宙の中心であると考えられていましたが、16世紀以降に、地球が太陽の周りを回っていることが分かりました。地球は、太陽という小さい星の周囲にある、微小な存在であることが発見されたのです。さらに、その太陽系の世界は小さな銀河の一部にすぎず、他に何十億という星雲があることも分かりました。このような広い世界で、人類をどのように位置づけることができるのか、それを理解するための第一歩が惑星探査であると考えています。
Q. これからの宇宙開発はどうあってほしいと思いますか?
 これまで宇宙開発はさまざまな分野で恩恵をもたらしてくれました。まずは、経済的なメリットが挙げられます。衛星放送や、衛星を使った通信、GPSを使って位置を把握できるのも宇宙開発があってのことです。また、我々は「セーブ&レスキュー」と呼んでいますが、ボートや山などで行方不明になった場合にも、衛星を使えば遭難者と連絡を取ることが可能になります。こういったことが、これまでの宇宙開発によってもたらされた成果ですが、将来的にはどうなっていくべきなのか?人間の想像力には限界がありますので、私たちの想像を遥かに超える形で応用されていくことになるかも知れません。現段階では宇宙旅行などが挙げられており、弾道飛行で宇宙を体験する人が出てくるなど実現に向かっています。また、宇宙ホテルの話をする人もいます。想像力を広げて、それを現実のものにしていくことで、特に新しい世代に新たなものが多く出てくることになるでしょう。たとえ、私たちが思い描いたものが全て現実化しなくても、いくつか実現するものがあれば、それは大きく人間の活動範囲を広げることになると思います。
これまで宇宙開発はさまざまな分野で恩恵をもたらしてくれました。まずは、経済的なメリットが挙げられます。衛星放送や、衛星を使った通信、GPSを使って位置を把握できるのも宇宙開発があってのことです。また、我々は「セーブ&レスキュー」と呼んでいますが、ボートや山などで行方不明になった場合にも、衛星を使えば遭難者と連絡を取ることが可能になります。こういったことが、これまでの宇宙開発によってもたらされた成果ですが、将来的にはどうなっていくべきなのか?人間の想像力には限界がありますので、私たちの想像を遥かに超える形で応用されていくことになるかも知れません。現段階では宇宙旅行などが挙げられており、弾道飛行で宇宙を体験する人が出てくるなど実現に向かっています。また、宇宙ホテルの話をする人もいます。想像力を広げて、それを現実のものにしていくことで、特に新しい世代に新たなものが多く出てくることになるでしょう。たとえ、私たちが思い描いたものが全て現実化しなくても、いくつか実現するものがあれば、それは大きく人間の活動範囲を広げることになると思います。

火星探査機「マーズ・ローバー」
(提供:NASA)
学生時代からJPLで働き、参加したミッションはいろいろありますが、初めて作業に関わったミッションが特に思い出深いです。1989年にNASAが打ち上げた金星探査機「マゼラン」で、金星の地表をレーダーで観測するミッションでした。ただ、若い頃に参加したミッションが印象深いものになるのは容易に想像できますよね。私はその後も非常に興奮させられるミッションに多く参加してきました。火星探査機「マーズ・ローバー」、宇宙望遠鏡、スペースシャトルによる合成開口レーダーを使った観測ミッションなど、その中から1つ選ぶのは簡単なことではありません。私にとってミッションは我が子のようなものなのです。「自分の子供の中で誰がお気に入りですか?」と聞かれても、みんな同じくらい大切で、答えようがありません。どれも全く同じということではなく、同じように愛情を注いできたものばかりなのです。どのミッションからも何か新しいことを学べるわけですから、すべてのミッションに魅力的な側面が必ずあります。
Q. アメリカの惑星探査は今後どのようなことを目指していくのでしょうか?
アメリカの惑星探査プロジェクトの目標は、惑星の形成を理解することと、地球外で生命の進化の可能性を研究することです。ですから、かつて水があったと考えられる火星が大きなターゲットになってきます。私たちは2年ごとに火星へ探査機を送り、その歴史と生命の進化の可能性を理解するべく観測を行っているわけですが、他にも木星の衛星、エウロパに注目しています。氷で覆われたエウロパの表面下に、海が存在しているかもしれないからです。さらに、土星の衛星、タイタンには探査機「カッシーニ・ホイヘンス」を送り、現在も観測を続けています。タイタンには炭化水素を多く含む大気があり、かつて生命体が存在していた、あるいは現在も存在している可能性があります。このような惑星では、生命が進化した形跡があるかもしれないため、特に注目を集める研究対象になっています。
Q. 宇宙開発を国民に広報することの必要性をどう思われますか?
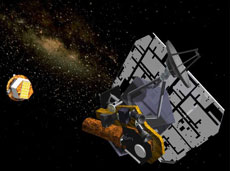
彗星探査機「ディープ・インパクト」
(提供:NASA)
アメリカでは特に若者たちが宇宙探査に非常に興味を持ち、科学博物館の入場者数がスポーツ観戦に行く人数よりも多いと聞いています。毎年約2万人の学生がJPLを訪問していますし、彗星探査機「ディープ・インパクト」や火星探査機「マーズ・ローバー」など、探査機が目的地に着陸するような一大イベントがある場合には、JPLのウェブサイトに数週間で何十億ものアクセスがあります。そのことからも関心の高さが分かります。
私たちは、若い人たちを中心とした一般の方に、ウェブサイトや博物館での展示を通じて積極的に情報提供を行っています。展示といっても、何の変化もないような展示ではありません。着陸などのイベントがある場合には、JPLと全米の博物館をインターネットで接続して、リアルタイムで着陸の様子が見られるようにしています。
Q. 宇宙を題材にした教育についてどう思われますか?
宇宙探査や惑星などを題材にした学習が優れている点は、子供の心を開き、子供たちが「不可能なことは何もない」というような考えができるようになることです。自分の身近な環境に制限されることなく、夜空を見上げて美しい星を眺め、自分が将来その星を旅する姿を思い浮かべる。そうすることで、子供の想像力が広がり、夢が持て、それがどんな夢であっても叶えることができると思えるようになります。宇宙教育によって、子供たちが宇宙についての思いをめぐらせるだけでなく、宇宙が子供たちに「考える」チャンスを与えてくれるのです。月を見上げて月面旅行を夢見、実際に人間が月に向かって行くことで、子供たちは「不可能なことなどほとんどない」という考えを持てるようになり、励まされていくのです。このような前向きな気持ちになることは、人生で大事なことであり、それが基礎となって、探究心、発見、イノベーション(技術革新)、学習などにつながっていくのだと思います。
Q. 惑星探査の意義は何だと思われますか?

月周回衛星「かぐや」が撮影した月面と地球
私たちは太陽系に住んでいます。太陽系の中での地球の存在はどういうものなのか?これは、探査機「カッシーニ」が撮影した土星や、月から撮られた地球の画像を見ると分かってきます。「カッシーニ」の画像では、土星の輪の向こう側に小さな光の点が見えましたが、その小さな点こそが地球でした。また、最近、JAXAの月周回衛星「かぐや」が撮影した地球の写真を見ましたが、これを見ると、自分たちがいかに小さな存在であるかが分かります。人間は自己中心的に物事を考えがちであり、絶えず争い、国家は資源などを巡って戦争を行います。しかし、薄い大気に包まれた小さな星、地球を見た時に、この美しい星を共有している自分たちがいかに幸運であるかということ、そして、この小さくてか弱い星を守っていかなければならないということに気づかされます。このように、外から地球を見て初めて、太陽系の中で私たちがどれほど小さいか、その存在について考えさせられます。太陽系全体やその形成方法を調べることにより、その中での我々の位置づけを理解していくことが極めて重要なことだと思います。
また、かつては地球が宇宙の中心であると考えられていましたが、16世紀以降に、地球が太陽の周りを回っていることが分かりました。地球は、太陽という小さい星の周囲にある、微小な存在であることが発見されたのです。さらに、その太陽系の世界は小さな銀河の一部にすぎず、他に何十億という星雲があることも分かりました。このような広い世界で、人類をどのように位置づけることができるのか、それを理解するための第一歩が惑星探査であると考えています。
Q. これからの宇宙開発はどうあってほしいと思いますか?
