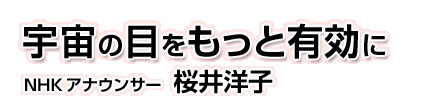
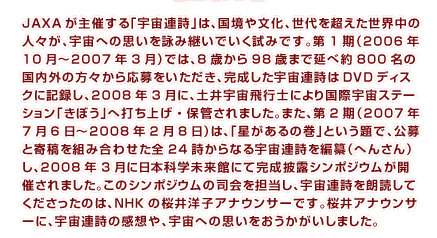
桜井 洋子(さくらい ようこ)
新潟県生まれ。明治大学を卒業後、1975年にNHKへ入局。東京アナウンス室に所属。主に報道・教養番組で活躍。2004年、新潟へ帰省中に新潟県中越地震に遭遇し、自身の震災体験を活かして、地震関連の特別番組の司会を担当するようになる。現在の出演番組は、「NHKアーカイブス」「ダーウィンが来た!生きもの新伝説」「ハートをつなごう」など。
Q.桜井アナウンサーは、昨年行われた第1期に引き続き、第2期の完成披露シンポジウムで詩を朗読なさいました。どのような印象を受けられましたか?
宇宙連詩のシンポジウムの司会を担当し、楽しく進行させていただきました。もともと私は文学が好きで、また、宇宙に対する関心も小さい頃からありましたので、わくわくしながら臨みました。今回は、JAXAが編纂したものだけでなく、甲府市立山城小学校や慶応義塾女子高等学校の生徒が作った宇宙連詩や、山梨県立科学館が中心となって公募した「星つむぎの歌」も披露され、子供たちや若い方たちに宇宙連詩が浸透しはじめたという印象を受けました。宇宙を題材にした新しい取り組みが始まっているんだということを実感でき、有意義な1日でした。
詩については、専門家ではありませんから講評するのは難しいのですが、今回のJAXAの宇宙連詩は外国の詩人の方などプロの方が参加されたことで、前回よりも内容のレベルは若干高かったように思います。ただ、年齢層が広かったと言う意味で、昨年の第1期の宇宙連詩の方が親しみやすさがあったように思います。今回、山梨の「星つむぎの歌」は、「みんなで星を見上げて、その想いを言葉としてつむいでいこう」という取り組みで、全国からの公募でできあがった詩を歌手の平原綾香さんが歌って披露しました。会場で平原さんの歌を聞いたときには、詩のフレーズを作った一人一人の気持ちが凝縮され、1つになれたように思います。そして、詩が歌になるという、宇宙連詩の大きな可能性が見えたと思いました。
Q.宇宙連詩のようなイベントから、宇宙へのイマジネーションが沸きますか?

地球(提供:NASA)

もちろんです。よりいっそう宇宙が近くなったという感じがします。私はもともと宇宙が好きで、「ぽかんと浮かんでいる地球をこの目で一度見てみたい」と小さい頃から夢見ていました。こういったイベントに参加させていただくと、そうした想いがますます強くなります。
1988年に出版された「地球/母なる星」(小学館発行)という写真集がありますが、私が初めて浮かんでいる地球の姿を見たのは、この写真集でした。各国の宇宙飛行士が撮った地球の写真と、彼らが感じたことを詩にした写真集ですが、私はその地球の写真を見て心が震えました。詩人の茨木のり子さんの作品に「水の星」(筑摩書房発行/詩集「倚りかからず」より)という詩があり、その一節に、「生まれてこのかたなにに驚いたかと言えば水一滴もこぼさす廻る地球の写真」とありますが、私もその浮かんでいる地球が脳裏に焼きついています。また、JAXAの月探査機「かぐや」に搭載されたハイビジョンカメラが撮った、月面越しに地球が昇ってくる「地球の出」の映像は、何度見ても引き込まれます。漆黒の宇宙に浮かぶ地球は、写真や映像で見ても感動的ですから、実際に自分の目で見ることができたらどんなに素晴らしいかと思いますね。

オリオン座
(提供:NASA, Matthew Spinelli)

Q.宇宙のどういうところがお好きですか?
好きというよりも、宇宙は、今自分が生きているところで、自分自身の基本的な場所ですから、そこをもっと知りたいという気持ちでしょうか。幼い頃は単なる宇宙への憧れで、星を見るのが大好きでした。新潟県の雪深いところで育った私の楽しみは、夜空に輝くオリオン座を見つけることだったんです。新潟の冬は、雪が降っていなくても雲に覆われていることが多かったため、たまに星を見つけるとまるで宝物を見つけたようで、とても嬉しかったのを覚えています。その後、NHKに入局して、「地球大紀行」という番組のナレーションを担当したときに、46億年前の地球の誕生から現在までを描き、地球がどのような進化を遂げてきたかを知りました。宇宙で地球が誕生して46億年経った今、そこに自分が存在しているという事実を実感しましたし、自分自身の位置を知る意味でも、ますます宇宙にひかれていきました。
宇宙連詩のシンポジウムの司会を担当し、楽しく進行させていただきました。もともと私は文学が好きで、また、宇宙に対する関心も小さい頃からありましたので、わくわくしながら臨みました。今回は、JAXAが編纂したものだけでなく、甲府市立山城小学校や慶応義塾女子高等学校の生徒が作った宇宙連詩や、山梨県立科学館が中心となって公募した「星つむぎの歌」も披露され、子供たちや若い方たちに宇宙連詩が浸透しはじめたという印象を受けました。宇宙を題材にした新しい取り組みが始まっているんだということを実感でき、有意義な1日でした。
詩については、専門家ではありませんから講評するのは難しいのですが、今回のJAXAの宇宙連詩は外国の詩人の方などプロの方が参加されたことで、前回よりも内容のレベルは若干高かったように思います。ただ、年齢層が広かったと言う意味で、昨年の第1期の宇宙連詩の方が親しみやすさがあったように思います。今回、山梨の「星つむぎの歌」は、「みんなで星を見上げて、その想いを言葉としてつむいでいこう」という取り組みで、全国からの公募でできあがった詩を歌手の平原綾香さんが歌って披露しました。会場で平原さんの歌を聞いたときには、詩のフレーズを作った一人一人の気持ちが凝縮され、1つになれたように思います。そして、詩が歌になるという、宇宙連詩の大きな可能性が見えたと思いました。
Q.宇宙連詩のようなイベントから、宇宙へのイマジネーションが沸きますか?

地球(提供:NASA)
もちろんです。よりいっそう宇宙が近くなったという感じがします。私はもともと宇宙が好きで、「ぽかんと浮かんでいる地球をこの目で一度見てみたい」と小さい頃から夢見ていました。こういったイベントに参加させていただくと、そうした想いがますます強くなります。
1988年に出版された「地球/母なる星」(小学館発行)という写真集がありますが、私が初めて浮かんでいる地球の姿を見たのは、この写真集でした。各国の宇宙飛行士が撮った地球の写真と、彼らが感じたことを詩にした写真集ですが、私はその地球の写真を見て心が震えました。詩人の茨木のり子さんの作品に「水の星」(筑摩書房発行/詩集「倚りかからず」より)という詩があり、その一節に、「生まれてこのかたなにに驚いたかと言えば水一滴もこぼさす廻る地球の写真」とありますが、私もその浮かんでいる地球が脳裏に焼きついています。また、JAXAの月探査機「かぐや」に搭載されたハイビジョンカメラが撮った、月面越しに地球が昇ってくる「地球の出」の映像は、何度見ても引き込まれます。漆黒の宇宙に浮かぶ地球は、写真や映像で見ても感動的ですから、実際に自分の目で見ることができたらどんなに素晴らしいかと思いますね。

オリオン座
(提供:NASA, Matthew Spinelli)
Q.宇宙のどういうところがお好きですか?
好きというよりも、宇宙は、今自分が生きているところで、自分自身の基本的な場所ですから、そこをもっと知りたいという気持ちでしょうか。幼い頃は単なる宇宙への憧れで、星を見るのが大好きでした。新潟県の雪深いところで育った私の楽しみは、夜空に輝くオリオン座を見つけることだったんです。新潟の冬は、雪が降っていなくても雲に覆われていることが多かったため、たまに星を見つけるとまるで宝物を見つけたようで、とても嬉しかったのを覚えています。その後、NHKに入局して、「地球大紀行」という番組のナレーションを担当したときに、46億年前の地球の誕生から現在までを描き、地球がどのような進化を遂げてきたかを知りました。宇宙で地球が誕生して46億年経った今、そこに自分が存在しているという事実を実感しましたし、自分自身の位置を知る意味でも、ますます宇宙にひかれていきました。