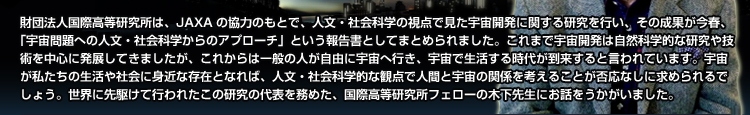
木下冨雄(きのしたとみお)
京都大学名誉教授。文学博士。
1954年、京都大学文学部心理学専攻卒業。1956年、京都大学大学院文学研究科修士課程修了。1979年、京都大学教授。京都大学教養部長、総合人間学部長を務める。1993年、京都大学名誉教授。1997年、甲子園大学学長。日本社会心理学会や日本リスク研究学会などの会長を歴任。2005年、財団法人国際高等研究所フェロー。2009年に国際高等研究所から発表された報告書「宇宙問題への人文・社会科学からのアプローチ」の研究代表。著書に「科学技術と人間の共生-リスクコミュニケーションの思想と技術」など。専門は社会心理学。
Q. どのようなきっかけで、人文・社会科学の視点で「人間と宇宙」を研究することになったのでしょうか?

国際宇宙ステーション(提供:NASA)
人類が宇宙へ初めて進出してから今年でおよそ50年です。1961年のガガーリンによる有人宇宙飛行に始まって、アメリカのアポロ計画による月面着陸、そして日本も参加している国際宇宙ステーション建設に至るまで、その輝かしい成果は私たちに大きな感動と誇りをもたらしました。私たちは「地球人」から「宇宙人」への第一歩を踏み出したと言えましょう。
ところが、これまでの宇宙開発における成果は、自然科学分野の研究や技術発展が中心で、人間の生活や社会、心理、文化などの理解を深める人文・社会科学分野での成果はほとんど見られませんでした。その原因は、宇宙ミッションを支える基盤が先端科学技術にあったからです。つまり優先される研究や技術は、宇宙での「生存」のためであり、「生活」のためではなかったのです。
しかし、近年になって宇宙技術が向上し、それに伴い宇宙飛行のリスクと費用が低くなったため、民間企業が宇宙旅行や宇宙ホテルを計画するなど、一般の人にとって宇宙がより身近なものになってきました。探検や冒険の時代がようやく過ぎ、宇宙が私たちの普通の生活に入り込んできたと言えるでしょう。
今はまだ民間の人が宇宙へ行くのには数十億円かかり、さらに6ヵ月以上の訓練も必要です。しかし10〜20年後には、数百万から1千万円くらいで、訓練もほとんど受けずに多くの一般市民が宇宙へ行ける日が来るかもしれません。そうなるとそこで、何が起こるでしょうか。
おそらくそこには、小さいながら「市民社会」が生まれると思います。社会が成立すると、そこから政治や文化が必然的に発生しますが、それに伴ってさまざまな問題が宇宙で発生するでしょう。例えば、宇宙で犯罪が起きたら、誰がどの法律で裁くのでしょうか?宇宙での市民社会を統治するための法整備を行うとしても、そもそも宇宙空間での生活がどのようなものかを理解していないと、制度そのものができません。しかも宇宙では、人間の価値観が地上とは違ってくると思いますので、地球上での常識概念で制度設計をしても、宇宙では通用しないと思うのです。ですから、宇宙での生活がどのようなもので、それによって私たち人間の価値観がいかに変化するかを理解したうえで、宇宙を統治するシステムを考える必要があります。
このような発想をもとに私たちは、宇宙の科学と技術を専門とするJAXAと協力し、人文・社会科学の視点で「人間と宇宙」に関する本格的な研究を行いました。2009年に発表した報告書は3部構成になっています。第1部では、宇宙空間の中で人類の価値観や認識形態、それに行動がどう変容するかについて、哲学、文学、宗教学、心理学の立場から論じています。第2部では、宇宙で人間がどのように生活するかについて、医学、心理学、工学の知見をもとに、その技術的可能性について予測しました。第3部では、宇宙のガバナンス(統治)システムの構築について、これまでの法制度や政治状況にビジネス的な視点も考慮に入れながら、いかなる制度設計が可能であるかを模索しています。このような宇宙問題への人文・社会科学からのアプローチは、世界で初めての試みではないでしょうか。
Q. この研究の成果は何だと思われますか?
今申しましたように、人文・社会科学の観点から宇宙問題を考える必要性を、世界に先駆けてアピールしたことが一番の成果だと思います。この研究は、未知の世界へのチャレンジであり、既存の資料が極めて乏しい状況のもとでの研究ですから、かなりの部分は思考シミュレーションに頼っています。もちろん内容がSFにならないように、これまでの科学的な知見に基づいた仮説を展開しましたが、まだどの仮説も検証されていませんから、まるで夢物語のようだと言われるかもしれません。しかし、世界で誰もやったことがなかった、人文・社会科学的な仮説を立てたということはとても意義あることだと思います。私たちが発表した報告書を基礎にして、すぐに制度設計をしようということにはなりませんが、将来、制度を作るときに、まず何に注意するべきかという論点の柱立てを提示できたと思います。私たちの仮説に基づいて、もっと理論展開を深めたり、検証しようとしてくださる方がいたら、これほど嬉しいことはありません。
Q. 人類が宇宙へ進出したことにより、私たち人間の価値観はどう変わったと思われますか?また、今後宇宙への進出を続けていくと、人類の価値観はどう変わると思われますか?

価値観は、判断の「基準系」に何を取るかによって大きく異なります。例えば人前で自分の意見を主張するという行動の是非は、日本文化を基準系に取るか西欧のそれを取るかによって価値判断が違います。
宇宙への進出も同じことで、これまで地球を基準系としていた判断が宇宙のそれへと変化するわけですから、価値観が大きく変化することは当然予想されます。一番大きな変化は地球を外部から見ることにより、地球を相対化する価値観が生まれることでしょう。
そして宇宙から冷静に地球を見ることができるようになれば、地上で起きている地域戦争や民族間の抗争、テロ、資源争奪といった争いが、いかにちっぽけでむなしいことかがきっと分かると思います。また、美しい地球の姿に素朴な感動を覚えたり、地球レベルで環境問題がどうなっているかが分かったり、国境の無意味さや、国際協調の重要性にも気づいたりするでしょう。このように地球を相対化できる価値観を持つ人が増えると、世界の平和や安全保障にも役立つかもしれません。最終的には、人間の価値観がそういう方向に変わっていくことを願っています。そのためにも一般市民だけでなく、多くの政治家が宇宙へ行ってほしいと思います。
国連総会や先進国サミットが、いつの日か宇宙で開催されるのを願ってやみません。
Q. これまでの宇宙への進出によって、人類は何を得て、何を失ったと思われますか?

ゴーギャン作「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」
失ったものは、科学的な知識がないまま空想の世界を膨らませて作り上げたイメージと夢の世界、文学的なロマンの世界だと思います。私たちの子ども時代には、月にはウサギがいて餅をついているという童話とか、作家ジュール・ヴェルヌの「月世界旅行」を読んで夢の世界を楽しむこともありました。しかし、科学技術が進歩して宇宙のリアルな情報が多く入るにつれて、想像の世界で遊べることが減ったように思います。
その一方で、宇宙へ進出したことにより、違ったロマンを得ることができました。それは、新しい発見をするという科学的なロマンです。科学が未発達のときは、何が分からないかが分からない状態ですが、科学的な知識が増えることによって、さらに新しい疑問がわいてきます。このように、永遠に未知の世界は拡大していくものですが、特に宇宙にはその魅力を感じます。画家ポール・ゴーギャンの晩年の大作に『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』という作品がありますが、近年、宇宙や生命、人類の成り立ちが少しずつ分かってきたことで、ゴーギャンのこの根源的な問いにも答えられる可能性が出てきました。これこそ壮大な科学的ロマンだと言えると思います。
