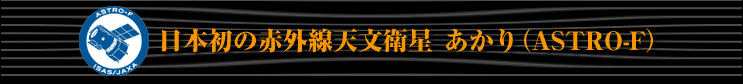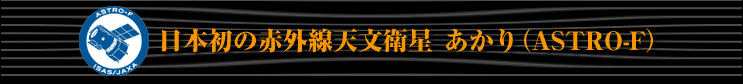|
 |
 |
 |
 |
|
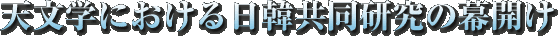

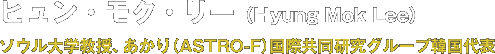
1999年、日本から3名の教授がソウル大学を訪れ、「あかり(ASTRO-F)」に関してプレゼンテーションをされました。データ処理などにマンパワーが必要なため、協力して欲しいと言われたのです。私たちはずっと日本の天文学者の方々と一緒に研究したいと思っていましたので、とても素晴しいチャンスだと思い、喜んでお引き受けしました。それが私と「あかり」の出会いです。
世界初の赤外線天文衛星IRASのデータは、解像度はそれほど高くありませんでしたが、とても有用性の高いものでした。「あかり」は、IRASのデータベースを高感度で鮮明なデータに更新する素晴らしいプロジェクトなので、ぜひとも日本と一緒に研究をしたいと思ったのです。
 |
|
|
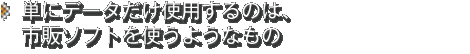

赤外線天文観測データは一般に公開されていますので、韓国の天文学者もデータを利用することには慣れています。しかしデータを使うだけで、誰も実際の観測やプロジェクトに関わったことはありませんでした。ただ単にデータを使用するのは、市販ソフトを使うようなものです。使い方は知っているが、応用の仕方は分からない。それでもいい研究もありますが、ほかの人と同じことしかできません。もっと先端的な研究をおこなうには、データについてさらに深く知る必要があります。実際にプロジェクトに関わり、どのようにデータが出てくるのか、そのデータにはどんな限界があるのかといったことを理解できるのはとても有意義なことです。
ソウル大学では、これまで教授5名と研究員3名、大学院生数名が「あかり」に参加してきました。現在は約10名が活動しています。今回の共同研究は、観測に必要な設計やトレーニングなどを含め、私たちに初めて本格的なプロジェクトに携わる機会を与えてくださったのです。これだけ多くの人が関わる大規模プロジェクトに参加できる経験は、韓国の将来のためにもとてもいい勉強になっています。
|
|
|
|
|


1983年にIRASが打ち上げられた時、私はとても興奮しました。なぜなら膨大なデータベースを提供してくれたからです。おそらく今までで最も多く使われている天文学のデータベースだと思います。当時私は大学院生で、宇宙塵に関する論文を書いていましたが、IRASの観測によって、それまで知られていた塵の成分よりもっと小さい塵が存在することが分かり、私の論文にも影響を与えました。1998年に公開されたIRASの全天マップ(宇宙の地図)の改良版は、これまでに全世界で3000編近くの論文に引用されている、天文学者にとっては最も刺激的な資料の1つです。全天マップを作ることは容易ではありませんが、世界の天文学者が待ち望んでいます。
ですから「あかり」の最も大きな使命は、これまで20年以上も使われているIRASのデータベースを高解像度なデータで更新することです。私の知る限りでは、「あかり」以降で赤外線を使った全天観測はしばらくありませんので、おそらく今後20年くらいは「あかり」のデータが世界的にかなり活用されると思います。また、現在、国際的に3つの大型赤外線宇宙望遠鏡計画が検討されていますが、どの計画も細部を観測するものです。「あかり」による全天観測は、天文学の将来のためにとても重要なのです。
|
|
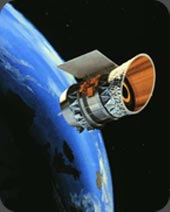

世界初の赤外線天文衛星IRAS(1983) |
|