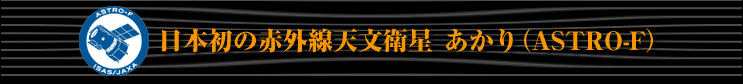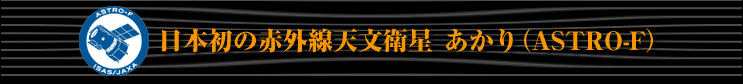|
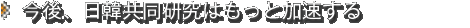

科学のほかの分野では日本と韓国の共同研究は盛んですが、天文分野ではこれまで遅れていました。韓国の天文学者の多くはアメリカに留学しているので、これまではアメリカの研究者と共同研究をおこなっていました。しかしアメリカはとても遠く、一方、日本は近くです。今まではお互いのことをあまりよく知りませんでしたが、「あかり」の共同研究を通じてお互いの理解が深まりました。最近、天文学における二国間の関係は急成長しています。赤外線のみならず、X線天文分野でも日本との共同研究をおこなおうとしています。光学観測関係者たちは、すばる望遠鏡を使いたいと願っていますし、日本側は、韓国の天文学者に観測装置開発に加わって欲しいようです。すでに「あかり」に続いて、電波天文観測分野では、韓国天文宇宙科学研究所と日本の国立天文台とのネットワークもはじまりました。多くの意味で「あかり」でのコラボレーションは、両国間の天文研究におけるパイオニアとしての役割を果たしていると思います。
私は現在、韓国の赤外線天文学研究グループの代表をしていますが、「あかり」の共同研究に触発されて、赤外線天文学プロジェクトについて多くの議論がおこなわれています。そして近い将来、韓国製の超小型赤外線衛星を開発したいと思います。「あかり」と比較するとかなり小さな衛星ですが、赤外線天文学では小さな衛星でも活躍できる分野があるのです。韓国ではいくつかの科学・技術衛星計画がありますが、その中の1つに赤外線観測装置を搭載できるように現在、提案しています。韓国の衛星の多くは超小型衛星です。ですからほかの衛星の打ち上げの時に相乗りして、ピギーバックで打ち上げています。これまでにロシアやヨーロッパ、インドのロケットを使用して計4機の超小型衛星を打ち上げました。一方、多目的衛星や商業衛星など大きな衛星は、全てアメリカによる打ち上げです。将来的には大型の通信衛星や気象衛星について、日本のロケットによる打ち上げの可能性もあるかもしれません。しかし私たちの計画する次の赤外線観測超小型衛星に関しては、韓国の実験ロケットで打ち上げたいと思っています。
さらに私たちは、韓国政府に日本が計画している次期赤外線宇宙望遠鏡SPICAに参加するように提案しています。SPICAでは、データ処理だけでなく、観測機器の提供など、「あかり」よりも一歩進んだ形で計画に参加したいと思っています。
|
|


日本が計画中の次期赤外線宇宙望遠鏡 SPICA
|
|