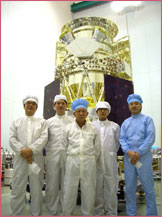今年、2006年2月22日、日本で初めての赤外線天文衛星ASTRO-FがM-Vロケット8号機により打上げられ、「あかり」と命名されました。「あかり」は銀河や恒星などが放射する赤外線を観測するための宇宙望遠鏡です。望遠鏡の口径は約70cmで、宇宙赤外線望遠鏡としては世界的にも一線級です。普通の天体望遠鏡と違うのは、望遠鏡と赤外線の観測装置が、液体ヘリウムと冷凍機を使ってマイナス270℃近くまで冷却されていることです。これによって非常に微弱な赤外線を検出することができます。「あかり」は全天をくまなく観測して数百万個にのぼる銀河や恒星のデータを集めます。現在の天文学の中心課題の一つは、銀河がどのように作られ、どのように現在の姿になったのかを調べること、そしてもう一つは、星や惑星系がどのように作られるのかを調べることです。「あかり」が集める膨大なデータを使って、私達はこのような課題に挑戦したいと思っています。
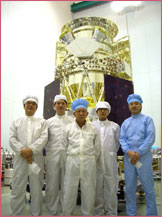
打ち上げ前の「あかり」と開発スタッフ |
「あかり」の開発は、幾つかの大学や研究機関の協力のもと、9年間かけて行われました。観測データの受信や解析には欧州宇宙機構(ESA)の協力も得ていますし、欧州や韓国の大学研究者もデータ解析ソフトウェアの開発に参加しています。また観測計画の議論には100名近い天文研究者が集まりました。「あかり」にはこれらの人々の期待がかかっています。それだけでなく、「あかり」が作る天体のリストは、世界中の天文研究者に公開され、利用されることになっています。もちろん新しい発見は一般の皆さんにもぜひお知らせしたいと思います。こんな期待を背負って、「あかり」は4月中旬には望遠鏡の蓋を開けて試験観測を開始する予定です。毎日夜明けと夕暮れに頭上を飛び過ぎて行く「あかり」に、空を見上げて「頑張れよ」と声をかける毎日です。
関連ページ >>

|