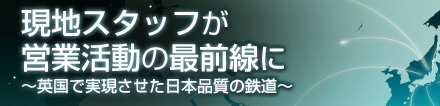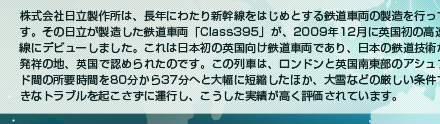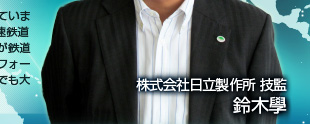Q. 鉄道の海外展開を決めたきっかけは何だったのでしょうか?

英国から受注を受けたアルミ合金製の高速鉄道車両「Class395」(提供:日立製作所)
日本は少子高齢化で輸送人員が伸び悩み、また国土のほぼ全域に鉄道網があるなど、国内市場は成熟化しています。それが海外展開の大きな要素ですが、1987年に国鉄が民営化されたことを契機に、国内で新しい鉄道技術が開発され、2000年頃までに世界に通用する製品ができつつあったという背景もあります。
新しい技術の代表的なものは、1992年にデビューした新幹線300系「のぞみ」に使われた、軽くて強いアルミ合金製の車両です。アルミは軽量素材で走行時のエネルギー消費を大幅に削減できるほか、リサイクルが容易で環境に優しいという利点があります。そのほかにも、ブレーキをかけた時に発生するエネルギーを電気に変えて、加速時に利用する技術(交流回生技術)。デジタル技術を用いた高精度の信号システムや、列車の走行や遅れを管理する運行管理システム等のIT技術。このような革新的な技術が開発され、世界でも十分競争力を発揮できる製品が確立されたことが、海外展開の大きなきっかけとなりました。 Q. 最初に英国市場に参入したのはなぜでしょうか? 1990年代に英国の鉄道が民営化されましたが、日本のように地域分割ではなく、線路と車両と運行会社がそれぞれ別々に分割されました。その結果、列車の事故やダイヤの乱れが多発するという問題が起きてしまったのです。一方、日本の鉄道は事故が少なく、新幹線の発着の遅れが1分以内だったり、東京の山手線が2〜3分間隔で運行されているなど、高い技術を持っていると世界的に評価されていました。
そこで英国運輸省が日本の鉄道品質を学びたいと希望し、日英の鉄道関連政府機関や鉄道事業者による「日英鉄道協力会議」が継続的に行われるようになり、テーマによっては私たちメーカーが会議に参加してプレゼンテーションを行いました。そして、この会議をきっかけに、英国運輸省が日本の品質を英国で実現したいと要請したのです。
当社はそれを受けて、英国市場に参入することを目的に、1999年に英国に駐在員を派遣しました。ところが、日本の鉄道品質がどんなに高く評価されても、それだけでは売れないということを実感したのです。英国市場に参入してから、実際に日立製の車両が英国を走るまでに、10年もかかりました。
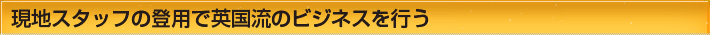
Q. 英国市場に参入し始めた頃には、どのようなご苦労を経験されたのでしょうか?

私自身、何度も英国に行って営業を試みたものの、最初の2年間は、英国の商習慣や車両受注のプロセスが全く分からず、契約がライバルメーカーに決まっていくのを悔しい思いで見ていました。
当時は日本人だけのスタッフでやっていたのですが、英語力に問題があるだけでなく、英国人はジェントルマンでイエス・ノーをはっきり言わないため、良いのか悪いのかが読み取れませんでした。それでは相手の心にも入れません。日本人だけの売り込みに2度挑戦して失敗したため、3度目からは英国人をフロントに出そうと決めました。車両の軽量化や信頼性といった技術を単にアピールするだけではダメで、どの部分をどのように訴求していくのか「見せ方」が重要であり、日本の方法では勝てないと思ったのです。
そこで私たちは、英国鉄道業界のビジネスルールや商習慣に精通した現地スタッフを中心に、チームを作ることにしました。日本人は技術的なサポートに徹し、商談は英国人に任せることにしたのです。また、車両のデザインも英国人の好みに合わせるため、現地の事情に詳しい世界的な工業デザイナー、アレクサンダー・ノイマイスター氏と連携しました。彼とは20年近くパートナーシップを結んでいて信頼関係があり、そのことも英国進出には大きく貢献したと思います。
Q. プレゼンテーションだけでなく営業活動も英国人スタッフが行ったんですね。
当然そうです。鉄道はインフラで地域に密着しているため、地域ごとに計画して進めることが多い事業です。ですから、最終決断は英国運輸省が行うものの、トップダウンで営業をすることはほとんどありません。むしろ、市や町で鉄道を管轄している交通局などと地道にコンタクトを取り、日本の鉄道の良さをプレゼンテーションしていくことが受注成功の早道です。
さらに、工場を建設して現地で雇用を確保したい場合は、現地メーカーとの協調が絶対に必要ですし、鉄道は技術の塊ですから、現地の技術者に理解してもらうことが何よりも大切です。そういう面でも、現地スタッフの人脈を活かした活動を行うことできましたので、英国人の優れた営業マンを積極的に登用して、本当に良かったと思います。「郷に入れば郷に従え」ということわざのように、英国のふところに潜り込むボトムアップの営業が、受注成功の秘訣だと思います。

Q. 英国からの高速鉄道受注の決め手となったことは何だと思われますか?

ロンドンのセントパンクラス駅。日本の品質を英国で実現した「Class395」(提供:日立製作所)
先ほど申し上げたように現地スタッフを登用したことと、日本の技術力、品質、信頼性を英国で証明できたことです。私たちは、「日本のインフラで日本の品質を出すのは分かるけれど、19世紀にできた英国のインフラで、日本の品質をどう実現するんだ」と絶えず問われていました。特に、車両に使われるモーターからのノイズが、信号装置に不具合を出し、踏み切りが誤作動をするのではないかと懸念されていました。
そこで、日立の駆動制御装置を既存の車両に載せて英国中を走り、問題がないことを長期間試験をして実証したのです。試験は約1年2ヵ月にわたって行われましたが、大きな問題は起きず、英国で日本の鉄道の安全性を証明することができました。このことが、2005年の高速列車「Class395」の受注へと結びついた大きな要因です。
それに加え、英国の鉄道で採用されている欧州規格への適合を立証できたことも勝因の1つです。欧州規格は日本の規格と異なり、例えば、レールの形が違います。鉄道車両は車輪とレールで支えられていますので、レールの形状が変わると車輪もそれに合わせなければなりません。日本のものをそのまま持っていくのではなく、欧州規格に適応させる必要がありました。