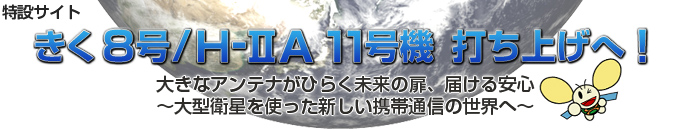山間部や海上など地上交換局がない場所での利用のほか、災害時の緊急車両の運行や被災者救援の迅速化など、私たちの暮らしの身近な場面で役立てられることが期待されています。
 ■ 超小型携帯端末
■ 超小型携帯端末
JAXAが開発した超小型携帯端末で、直接「きく8号」と通信をして、山や海、被災地等から情報を送ることができます。
■ ポータブル端末
 きく8号実験用の地上端末としてJAXAが開発した持ち運びが可能な端末です。B4サイズの大きさで、重さは約8.2kg、内蔵アンテナで512kbpsの通信が可能です。直径1.2mの外付けアンテナを使用することにより、通信速度は1.5Mbpsまで増加します。
きく8号実験用の地上端末としてJAXAが開発した持ち運びが可能な端末です。B4サイズの大きさで、重さは約8.2kg、内蔵アンテナで512kbpsの通信が可能です。直径1.2mの外付けアンテナを使用することにより、通信速度は1.5Mbpsまで増加します。

ウェアラブルカメラを装着した作業員が被災地から、ヘルメットに装着したビデオカメラの映像やスティックカメラの映像と、GPSアンテナで取得した位置情報を、地上無線アンテナで近くのポータブル端末へ伝送します。
ポータブル端末から「きく8号」を通して、災害対策本部や他の現場作業員へ映像や位置情報を送ることで、対策本部を中心とした迅速な対応が可能になります。

■ 携帯衛星端末(NICT開発)
情報通信研究機構(NICT)が開発した携帯衛星端末で、「きく8号」を介して、音声通話も可能です。
「きく8号」の巨大なアンテナにより、従来の衛星端末に比べ、小型化での開発が可能となりました。

■ 衛星通信システムデモンストレーション
これらのシステムを利用して、2006年9月3日、JAXAは高知県高知市と三重県尾鷲(おわせ)市を衛星通信で結んだ災害情報収集のデモンストレーションを行いました。このデモでは「きく8号」の通信環境を模擬し、高知市立御畳瀬(みませ)小学校と尾鷲市立尾鷲小学校にそれぞれ設置した仮の対策本部、避難所、被災現場間で情報を交換しました。
それぞれの市で実施された南海地震や津波を想定した防災訓練の後、「災害情報収集のデモンストレーション」として人工衛星通信システムを使った災害映像や文字情報の伝送を行い、各会場ともに150名を越える市民の方々に将来のシステムを使った防災訓練を体験していただきました。
また、10月23日には新潟県長岡市が主催する長岡市震災復興祈念行事に参加し、衛星通信システムのデモンストレーションを行いました。震災復興セレモニーでは、震災のあった17時56分に各会場で黙祷、18時には尺玉の追悼花火が打ちあがり、その様子をウェアラブルカメラで撮影し厚生会館から山古志支所前の会場に映し出しました。
■ 関連リンク
・i-Space
・情報通信研究機構(NICT)