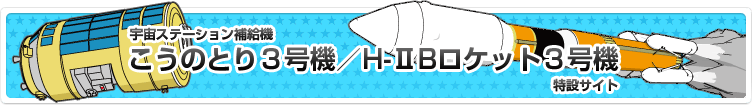H-IIBロケットの設計・開発から打ち上げまで、様々な立場でH-IIBロケットに携わるスタッフのコラムをお届けします。
宇治野 功 / H-IIBプロジェクトマネージャ(打上執行主任)

宇宙航空研究開発機構は我が国の安定した打ち上げ手段を確保することを重要な目的とし、基幹ロケットの信頼性を向上させ、技術の基盤を維持するための活動を行っております。H-IIAロケットの制御等をつかさどる電子機器についても、運用開始後10年以上が経過し、部品調達が困難となることから調達可能な置き換え部品を用いて再度開発を行っています。今回H-IIBロケット3号機に再開発した機器を集中的に搭載し全体性能を確認する試験を実施し、フライトで実証する計画です。
先日のH-IIAロケット21号機において、民間による初の海外衛星の打ち上げに成功し、民間事業の実績の評価が高まりつつあります。H-IIBロケット3号機の打ち上げを成功させ、開発とフライト結果の評価というサイクルを実施することで、技術基盤の充実をはかることにより、将来のロケットの性能・信頼性の改善のための技術蓄積が図れていくものと考えています。
打ち上げまで1ヶ月を切りましたが、打ち上げ成功に向けて、関係者一同、気を引き締めて、一丸となって着実に作業を遂行する所存です。試験機と同様に皆様の変わらぬご支援よろしくお願いいたします。
[2012年6月22日 更新]
新田 隆憲 / 三菱重工業株式会社 航空宇宙事業本部 宇宙事業部 宇宙システム技術部 試験・運用課(MILSET ロケット組立・設備グループ 推進系スタッフ/発射指揮者アシスタント(ALCDR))

機体が種子島に来てから、4ヶ月が経ちました。いよいよ、残りはカウントダウン作業のみです。私自身はブロックハウスに入るようになってH-IIA/H-IIBを通じて今号機が23機目となりました。H-IIBのALCDRは初めてですが、これまでのH-IIA/H-IIBの開発試験・打ち上げの経験を活かして、時間通りにロケットを飛び立たせてあげたいです。
[2012年7月20日 寄稿、 2012年8月3日 更新]
久保 方俊/ 三菱重工業株式会社 航空宇宙事業本部 民間航空機事業部 組立工作部 組立二課(MILSET ロケット組立・設備グループ 1段推進系担当)

ロケットの部品は、重量物且つ、構造が複雑で脆弱部も多く、何より高額であるために、取り扱いには非常に神経を使います。
今回のH-IIB3号機は、私が工場の組立作業に着手してから現在までに、1年と3ヶ月が経過しました。前工程を含めると、ロケットの製造には更に長い期間と、多くの作業者が関わっており、その最終工程に携わるのはプレッシャーもありますが、大きなやりがいも感じます。
今回は、H-IIB3号機を種子島に立ててから、先にH-IIA21号機を打ち上げる、2機同時整備ということもあり、通常よりも忙しく複雑なスケジュールですが、今までのところ大きなミスも無く、順調に作業を進めております。
H-IIAに引き続き、H-IIBの打ち上げ事業も近いうちに弊社へ移管されると言う話も聞いており、これより先の作業も今まで以上に飛行安全を強く意識し、正確にお安く軌道投入できるロケットの製作を目指し頑張っていきます。
[2012年7月20日 寄稿、 2012年8月3日 更新]
岩崎 知二 / 三菱重工業株式会社 航空宇宙事業本部 宇宙事業部 宇宙システム技術部 電子装備設計課 (MILSET 技術グループリーダ(技術GL))
佐藤 晃浩 / 三菱重工業株式会社 航空宇宙事業本部 宇宙事業部 宇宙システム技術部 装備設計課(MILSET 技術アシスタントグループリーダ(技術AGL))

同じくMILSET技術グループAGLの佐藤です。専門は推進系システムですが、ロケットシステム全体の技術に対して、GLとともに責任を負う立場にあります。ロケットシステムは大規模システムであり、地上設備、ロケット本体が適切に機能して初めてミッションの成功につながるものです。従って、技術グループには、視野の広さと緻密さの両面が求められます。
不適合、またはその兆候に対して、MHIや、パートナー各社の各専門技術者の知見を引き出し、束ねることによって解決に導くことが、我々技術GL, AGLの仕事です。(佐藤)
今回打ち上げるH-IIBロケット3号機には、技術GLになる前の3年半を掛けて担当してきた、新型のアビオニクス機器が搭載されていました。これまで開発試験、機能点検を通じて色々なことがありましたが、それらを解決し、いよいよ初フライトに臨めるところまで来ました。打ち上げが目前に迫り、緊張感が増してきていますが、打ち上げ成功を目指してJAXAさん共々一致団結して乗り切りたいと思います。
また、打上実績を積み重ね、いつかは左団扇で打上が眺められるように、専念していきたいと思います。(岩崎)
H-IIBロケットは、開発の立ち上げ時から携わった、特に思い入れの深いロケットです。私は推進系システムの開発を担当させていただきました。H-IIBでは、H-IIAのメインエンジン(LE-7A)2基を束ねる技術に挑戦し、技術獲得に成功しました。2号機からは、こうのとりを軌道に乗せた後の2段機体を、設定した海域(南太平洋)に制御落下させる機能を追加しました。また3号機からはアビオニクス機器を更新しました。このように、H-IIBは、常に進化するロケットなのです。変化には不適合がつきものですが、恐れず、確かな技術でひとつひとつ解決して来ました。打ち上げが目前に迫り、緊張感が増してきていますが、JAXAさん共々、関係者の総力を結集して、今回も定刻打ち上げ、規定軌道投入を達成したいと思います。(佐藤)
写真 左:岩崎 右:佐藤
[2012年7月20日 寄稿、 2012年7月31日 更新]
齊藤 靖博 / 宇宙輸送ミッション本部 宇宙輸送系システム技術研究開発センター 開発員(打上隊広報班 H-IIBロケット技術説明員)

3年前までは、毎号機の打上隊として飛行経路の再設定や飛行中の安全確保業務を行っていましたが、現在は、有人を狙った次の基幹ロケット・イプシロンロケット・軌道間輸送機など、宇宙輸送システムの将来について研究開発を行っています。
今回のH-IIB3号機は、技術を完成し次のロケット開発へ移行する重要な打ち上げであり、打ち上げ成功により、まずは、その1歩を踏み出せたことで大きな喜びを噛み締めつつ今後の研究開発に取り組んで行きます。
[2012年7月30日 更新]
杉本 伸一 / 鹿児島宇宙センター管理課総務担当

総務担当の主な仕事は打ち上げに関する地元の皆様への周知、音響・振動計測要員、通信機器保守要員及び医療支援要員の手配並びに関係部署との調整、打上隊員の使用する事務機器やレンタカーの手配など幅広く手掛けております。一言でいうと、縁の下の力持ちです。
例えば、日曜日の夕方に『笑点』というテレビ番組で大喜利というコーナーがあります。お題に面白く爽快な回答で視聴者を楽しませる笑点メンバーが打上隊の隊員であり、座布団を運ぶ山田君が私たち総務担当だと思います。山田君は笑点メンバーが良い仕事をするためになくてはならない存在であるように、私たち総務担当も打上隊員が良い仕事が出来て打ち上げが成功するように日々取り組んでいます。視聴者に愛される長寿番組のように、私たちのロケットも皆様の期待に応えられるように頑張ります。今後も皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。
[2012年7月30日 更新]
井田 恭太郎 / 有人宇宙環境利用ミッション本部 有人宇宙技術センター 開発員(打ち上げライブ中継 技術解説担当)

今回のH-IIBロケット3号機打ち上げの際には、筑波での打ち上げライブ中継の技術解説を担当しました。誰にでも理解できる言葉で技術解説する難しさを感じながらも、アナウンサーの司会進行の仕方など大変参考になり、良い経験ができました。そもそも今回の打ち上げ放送の技術解説を担当することになったのは、H-IIAロケット21号機打ち上げのライブ中継から新たに導入した、Google Earth上に3次元的にロケットの飛行経路を表示するシステムの企画から開発まで携わってきた経緯からです。JAXAの事業は国民の税金に基づいて成り立っているため、少しでもロケットの打ち上げを分かりやすく表示し、宇宙開発を身近に感じていただくことにより、国民に成果を還元したいという願いから、本システムを提案しました。
開発にあたり数々の課題に直面しました。特にロケットのアニメーション画像や飛行経路をどのように表示すればライブ中継をご覧の方々にとって分かりやすくなるかといったデザインに関して、普段技術の仕事をしている私にとってはあまり馴染みがなく苦労しました。アプリケーション製作をお願いした宇宙技術開発株式会社さんや中継映像でのコラボレーション使用を認めていただいたGoogle Earthさん、JAXA内では広報関係者、射場技術開発室の射場電気通信系/情報担当の協力を得ながら、一般の方々へのアンケート実施等、なるべく国民の視点に立って考えるよう努力することにより解決していきました。国民の方々が少しでもロケットの打ち上げを、宇宙開発を、身近に感じていただけたならば幸いです。
写真左:筆者(有人宇宙技術センター 井田 恭太郎)、写真中央:アナウンサー(林 暁代)、写真右:技術解説担当(HTVプロジェクトチーム 松田 貴史)
[2012年7月30日 更新]
小谷 勲 / 鹿児島宇宙センター射場技術開発室(つくば在勤)開発員(打上隊設備班係)

ロケット打ち上げの舞台裏、あまり目立つところではありませんが、今回の成功を支えた重要な役者だったことをぜひ知っておいて下さい。
写真下:ロケット打ち上げの後処置作業が一段落した後開催された、関係者慰労会の写真。
筆者左。
[2012年7月27日 更新]
大和田 陽一 / H-IIBプロジェクトチーム(資金管理担当)

これでH-IIBは3機連続での当初予定した時間での打ち上げ成功となり、成功率も100%。世界一の信頼性と言えると思います。
私はH-IIBロケットの民間移管について担当しており、3号機の打ち上げは、民間移管への最終的な判断としていることから、打ち上げ成功にまずは一安心です。これからフライト時のデータを詳細に評価して、ロケットに問題が無かったか? 民間に移管しても問題ないか? などじっくり評価して行きます。もうひと頑張りです。
[2012年7月27日 更新]
長福 紳太郎 / 宇宙輸送ミッション本部 射場技術開発室 開発員(打上隊:企画班気象係/企画係)

雨や風など数ある打ち上げ天候制約の中でも悩ませられることが多いのが“雷”です。ロケットが落雷を受けると、機体構造や搭載機器がダメージを受けてミッションが達成できない可能性があるため、雷は大敵です。雷がゴロゴロ鳴っているときは当然打ち上げはできないのですが、高速で飛ぶロケットの場合、雷雲まで発達していない、雨すら降らせていない雲でも、その中を突っ切ることで“誘雷”を招いてしまう可能性があります。そのため、この誘雷を発生し得る雲が打ち上げ時にロケットの通り道にないかを見定める必要があります。打ち上げ時には気象レーダ等による地上からの観測に加えて、打ち上げ前に航空機を飛ばして雲観測を行い、"氷結層を含む雲"の厚さがしきい値を超えていないかどうかで打ち上げの可否判断をしています。(打ち上げ前に射点上空を飛んでいる航空機はこれです)
この“ロケット誘雷を発生し得る雲”やそれを観測・予測する方法については、世界的にまだまだ研究の余地があるところで、JAXAとしても大学の先生方にご協力いただき現在研究を進めているところです。この研究によって打ち上げ延期を減らすことができる可能性もありますし、将来的には“雷に強い宇宙輸送機”の開発にもつながると思います。誰でも気軽に宇宙に行ける時代に向けて、鋭意研究を進めていきますので、こちらにもぜひご期待下さい。
写真下:航空機から見た雲
[2012年7月21日 更新]
入門 朋子 / 情報・計算工学センター (打上隊 ロケット班)

今回初めてH-IIBロケットに搭載されたRTOSは、JAXAの情報・計算工学センター(JEDI)と高田教授をはじめとした名古屋大学関係者との共同研究により開発されたものです。また、JEDIでは、ソフトウエアの信頼性を上げるための研究開発をしており、そこで開発したソフトウエアの検証手法(設計通りにソフトウエアができているか確認する方法)を適用しています。
このRTOSは、ロケットや衛星や探査機などに搭載するために、宇宙という高い信頼性が要求される環境でも使えるように対策を実施し、さらに想定通りに動くかどうか何回も繰り返し検証を行ってきました。
私たちRTOSの担当者は、筑波宇宙センターを拠点にしていますが、検証作業やユーザサポートにあたっては、日本電気通信システム株式会社(NCOS)の福岡事業所の方々に支援してもらっています。
打ち上げ当日、RTOSチームは種子島に行きませんが、つくばと福岡から“ワクワク、ドキドキ”しながら、RTOSの初フライトを見届けます。
[2012年7月21日 更新]
笹田 武志 / 宇宙輸送系要素技術研究開発センター 主任開発員(打上隊:ロケット班 電気系担当)

その中でも、ロケット内の各電子機器(アビオニクス)と結ばれてシステム全体を指令・制御する「誘導制御計算機」、自分がどこを飛行しているのかを算出する「慣性航法ユニット」は、それぞれロケットの頭脳と目に相当する重要な機器です。
今回のH-IIB3号機では、私が担当した誘導制御系機器も含め、アビオニクスの多くが一新されました。数年にわたる開発期間中はトラブルも多く苦労しましたが、いろいろな試験・分析を積み重ねて、最後は完全なものになったと思っています。大きなロケットから見れば小さな(高価な)箱ですが、応援よろしくお願いします。
[2012年7月20日 更新]
難波 秀治 / 宇宙輸送ミッション本部 宇宙輸送系要素技術研究開発センター 開発員(打上隊:ロケット班 電気系担当)

ロケットというと巨大な燃料タンクや迫力あるエンジンが印象的ですが、そのロケットを目的の軌道に向けて正確に飛行させるために内部で制御したり、機体の各種データを電波で地上に送信したりしているのがアビオニクス機器です。さまざまな点検項目があるため、その都度たくさんの人達が大型ロケット組立棟(VAB)や発射管制棟(ブロックハウス)で連携しながら、色々な装置や設備を駆使して点検していきます。もちろんエンジンや地上設備などの点検も並行して行われており、本当に多くの関係者が打ち上げ成功に向けて一丸となって作業していることを改めて実感しました。
そうやって一つ一つ準備が整いつつあるH-IIBロケット3号機、打ち上げまであと少しとなりましたが、無事に「こうのとり」をISSへ届けられるよう、皆さま応援お願いいたします!
[2012年7月20日 更新]
近藤 義典 / 宇宙輸送ミッション本部 宇宙輸送系要素技術研究開発センター 開発員(打上隊:ロケット班 電気系担当)

とはいえ、新たに開発したものが初めて飛ぶとなるとドキドキするものです。打ち上げまで残すところわずかとなった今では手ぬかりなく点検をし、最善を尽くすのみです。無事にこの射点から打ち上がり、打ち上げが成功することを祈りつつ、今後もその一端を担えるよう邁進していきます。
[2012年7月20日 更新]
大塚 淳子 / 宇宙輸送ミッション本部 H-IIBプロジェクトチーム 庶務業務担当

初代2009年の試験機から2011年の2号機、今回の3号機と、歴代のH-IIBロケットの打ち上げを筑波から見守ってきました。実物のH-IIBロケットを目の前で見たことがありますが、あんなに大きくて重いものが宇宙に数分で飛んでいくのは、本当不思議ですごい事ですよね。微力ではありますが、そんな仕事の一端に携われるのは、とてもすばらしい事だと思います。
打ち上げも目前に迫り、種子島では最後の調整作業で忙しい日々が続いている事と思います。
H-IIBロケット関係者の沢山の努力と思いを乗せて、どうか無事に打ち上げが成功しますように。
種子島の青く美しい海をバックに、立派に飛び立っていく姿を楽しみにしています。
皆さまもご声援の程、どうぞよろしくお願いいたします。
[2012年7月19日 更新]
小林 清 / H-IIBプロジェクトチーム主任開発員(打上隊ロケット班プロジェクト管理係主任)

[2012年7月19日 更新]
鈴木 雅夫、松井 孝弥 / 名古屋市科学館学芸課総務課 屋外展示担当
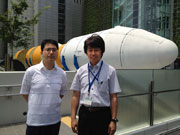
H-IIBロケットは皆さんご存じの通り、現在の日本で最大サイズ、最新のロケットです。当館の理工館・天文館の改築完了が2011年11月でしたが、設計当初から屋外の展示広場に名古屋近郊で製造されている国産ロケットを展示しようと、JAXAの皆さんと検討を重ねてきました。H-IIBの開発時期と、当館の改築時期が重なったことは本当にベストなタイミングでした。H-IIB試験1号機の打ち上げ成功の際は、我々も同じ気持ちで喜ばせていただきました。
展示してあるのは開発試験に用いられたフェアリング、段間アダプター、第1段中間部、第1段水素タンク、第1段エンジン部です。第2段部などは開発用供試体が製作されなかったため、当館で展示品として製作しました。
フェアリングは川崎重工播磨工場で2号機に向けた改良試験完了まで用いられた物です。船で名古屋港まで運び、夜間、特殊トレーラーで都市中心部にある当館まで運搬しました。公園内に入れる際は高く茂った木の上を超すため、都会の喧噪がおさまった夜間に、あのフェアリングが中空30メートルほどの高さに持ち上げられて圧巻の光景でした。第1段部は三菱重工飛島工場で製作されましたが、最大のロケットならではの悩みがありました。直径の5.2メートルのサイズは、低床トレーラーを使っても信号機や歩道橋のある街中を通ることはできません。そこで、タンクを半分に切断して運搬し、そのままアイソグリッド構造も見える様に展示してあります。
細かなところですが、フェアリングのスラスタカバーは、1号機・2号機の打ち上げ後、海上で回収した実機を用いています。開発試験段階でドーム形状でしたが流線型に変更された部分で、実物こだわったところです。建物内にはH-IIBロケット1号機回収フェアリングの一部もあり、ロケットについて多くの方に間近で見ていただいております。
長く言われ続けていることですが、資源の乏しい日本。これからはコンテンツやサービスなども重要でしょうが、やはり科学・技術への取り組み続けることは大切です。JAXAと当館は相互協力協定も締結しました。今後ますます科学技術の普及、宇宙開発への理解増進の一躍を担っていけたらと考えています。
屋外に展示したH-IIBロケットは開館時間中であればどなたでも近くでご覧いただけます。名古屋にお越しの際はぜひ当館にお立ち寄り下さい。
写真 左:松井 右:鈴木
[2012年7月18日 更新]
高田 広章 / TOPPERSプロジェクト会長、名古屋大学 大学院情報科学研究科教授

ロケットや人工衛星などの宇宙機の中には、数多くのコンピュータが使われています。今回、私たちが開発したOSが、H-IIA/Bロケットの新型の誘導制御コンピュータと慣性センサユニットに使用されることになりました。言うまでもなく、宇宙機の制御コンピュータには極めて高い信頼性が要求されており、今回、私たちが開発したOSが使用されることになったのは、数多くの技術者による信頼性確保のための努力のたまものです。
WindowsやMacOS、Andoroidなど、PCやスマートフォンホン向けのOSの分野では、海外で開発されたものが市場を席巻しています。一方で、組込みシステム向けのOSの分野では、1984年に開始されたTRONプロジェクトを出発点に、我が国の技術レベルは高く、数多くの組込みシステムに国産のOSが使われています。
今回採用されたOSも、TRONプロジェクトの成果の延長線上にあるものですが、我が国の独自技術で開発されたH-IIAロケット、H-IIBロケットに、国産のOSが採用されたことは、非常に意義深いことと考えています。
組込みシステムは、宇宙機のみならず、自動車や工作機械など、我が国の主要産業を支える重要な技術分野です。この分野で、我が国の技術レベルが世界のトップを維持できるよう、引き続き尽力していきたいと思います。
[2012年7月18日 更新]
泉 達司 / 宇宙輸送ミッション本部 宇宙輸送要素技術開発センター長

H-IIAロケットとH-IIBロケットはその名前や外見からも分かる通り基本的な設計が共通な、いわば兄弟ロケットです。その中でも電気系はほぼ同一の機器を用いており双子と言っても過言ではありません。
H-IIAロケットの電子機器は開発完了からすでに10年以上経過しているため設計も古くなっており、また部品も入手できなくなってきました。そのためここ数年かけてアップデートのための開発を行ってきております。今回、その新型機器の大部分を3号機に初めて搭載し飛行させることになりました。
今回初めて搭載するのは、ロケットの飛行を制御するためのコンピュータとそのソフトウエアをはじめ、ロケットの位置・速度・姿勢を計測する慣性センサユニットやロケットの姿勢制御に使用する電動アクチュエータコントローラ、そしてロケット機体内の状況をモニタするためのデータ収集装置及びそのデータを電波で地上に送るための送信機といった、いずれもロケットの打ち上げにとって大変重要な機器とソフトウエアです
。これらの開発においては十分な時間をかけて慎重な解析や多くの試験を行ってきました。開発中はそれぞれいろいろと難題に遭遇しましたが、いずれも関係者の一致団結した協力のもと解決することが出来ました。機器単体のみならず複数の機器をつないだ状態での試験でも十分な確認をしてきております。さらに機器の開発完了後もロケットに搭載した状態での地上試験や確認、そして開発結果の再点検を繰り返してきており、高い信頼性を持った状態に仕上がっていると考えております。
とは言うもののこれらの開発や試験、確認は人間が行っているものであり、100%完璧と言い切れるものではありません。これからも打ち上げが成功しペイロードを所定のところへ届けられるよう、気を抜かず人事を尽くして進めていきたいと思っております。
[2012年7月18日 更新]
杉森 大造 / 宇宙輸送ミッション本部 エンジン研究開発グループ 開発員(角田宇宙センター エンジン開発及び燃焼試験担当)

ロケットエンジンは、製造時のばらつきで性能が変わってしまう非常に繊細なものです。また、エンジンの作動不良は打ち上げ失敗に直結してしまうリスクの高いものでもあります。なので、エンジンは製造された後、打ち上げる前に、作動・性能確認試験を実施しています。
私は、H-IIBロケットの2段エンジンとしても使われているLE-5Bエンジンの開発と燃焼試験を担当しています。燃焼試験では、圧力、温度、流量など数百点の計測が行われ、エンジンが所定の性能を満たしているか、振動などのエンジン作動に対して有害な兆候が無いか等の確認をします。LE-5Bエンジンは、宇宙の真空環境で作動するエンジンなので、地上では真空環境を模擬できる試験設備で燃焼試験が行われています。この試験設備は、高空燃焼試験設備と呼ばれ、宮城県の角田宇宙センターにあります。
2011年3月、未曾有の大震災に見舞われた日本。角田宇宙センターも例外ではありませんでした。内陸に立地しているため、津波被害は免れたものの、試験設備は少なからずダメージを受けてしまいました。余震が続き、生活環境もおぼつかない中で、数か月にわたる復旧作業の後、初めて燃焼試験を実施できたのが今回打ち上げられるH-IIBロケット3号機用のLE-5Bエンジンでした。私にとっても特別な想いがつまったエンジンです。
こうして無事に角田宇宙センターでの試験を終えたH-IIBロケット3号機のLE-5Bエンジンは、復興の証として、「こうのとり」を無事に宇宙まで連れて行ってくれるはずです。皆様、応援よろしくお願いします!!
[2012年7月17日 更新]
佐藤 長未 / 宇宙輸送ミッション本部 宇宙輸送安全・ミッション保証室(打上執行主任付)

私は今まで、射場系の班長や主任を経験し現在に至っています。
今回の打ち上げでは、作業進行状況をひとつひとつ確認しながら、不具合による打ち上げ延期にならないよう頑張っていく所存です。
[2012年7月17日 更新]
岡田 修平 / 宇宙輸送ミッション本部 射場技術開発室 開発員(打上隊:設備班電気系担当・機体班電気系担当)

「地上設備って何?」と思われる方がほとんどだと思いますので、簡単にご説明いたします。地上設備というのは、打ち上げ前の準備期間と打ち上げ時に必要な地上で使う装置のことです。実はロケットの打ち上げ成功の為には、ロケットだけではなくてたくさんの地上設備が必要になるのです。
私が担当している地上設備には、「ロケットの打ち上げを自動制御するシステム」や「ロケットの状態をモニタするための受信装置」、「ロケットが本番通りに機能するか確認するための点検装置」などがあります。これらの地上設備に不具合があれば、ロケットの整備作業は止まってしまいますし、ロケットの状態が万全であるといえなくなってしまいます。だから、ロケットを打ち上げるためにはロケットだけではなくて、地上設備のコンディションも万全の状態にしておく必要があるのです。
ところが、地上設備ではつぎつぎに新しいトラブルが起きます。H-IIBロケット3号機が種子島に入ってきてからも、たくさんのトラブルが発生して、そのたびにJAXAと各メーカーさんは力をあわせて問題を解決してきました。そして、やっとの思いでH-IIBロケット3号機打ち上げを迎えることとなりました。打ち上げが成功する瞬間までまだまだ気は抜けませんが、地上設備が万全の状態でH-IIBロケットの打ち上げに臨めるようにJAXA・メーカーともに日々全力で頑張っています。
[2012年7月12日 更新]
藪崎 大輔 / 宇宙輸送ミッション本部 射場技術開発室 開発員(打上隊:ロケット班推進系担当、設備班推進系担当)

地上設備と言われてもあまりピンとこない方も多いかと思いますが、私の担当する推進系の主な設備はロケットの燃料(液化水素)や酸化剤(液化酸素)を貯蔵するためのタンク、打上前にロケットへ充填するための配管、バルブ等数多くの機器からなっており、当然ロケットの打ち上げには欠かせないものです。しかし毎回まっさらな新品を打ち上げるロケットとは異なり、古いもので20年以上使用している設備もあります。これらの設備は種子島の激しい気候、またロケット打ち上げ時の厳しい環境に晒されながら使用されていますが、ロケット打ち上げの瞬間に向けて最高の状態で使用できるようメンテナンスするのが我々の業務となっています。
さらにH-IIBロケット3号機の整備作業は、H-IIAロケット21号機の整備作業、及び打ち上げを間に挟むことで、非常に長い作業期間となっており、その間にも発生した数々のトラブルに対応しながらやっとの思いでH-IIBロケットの打ち上げを迎えることとなりました。まだこれからも最終的な点検・整備作業が残っており、今後もどんな事が起こるかわかりませんが、担当している設備が最高の状態で打ち上げを迎えられるよう祈りつつもJAXA、各メーカーが一丸となって打ち上げるH-IIBロケット3号機/「こうのとり」3号機(HTV3)の成功の一端を担えるよう日々の業務に取り組んでいきたいと思います。
[2012年7月10日 更新]
足立 寛和 / 宇宙輸送ミッション本部 射場技術開発室 開発員(打上隊:ロケット班/設備班HTV運用管制隊:HTV射場班)

7月に打ち上げるH-IIBロケット3号機は、多くの新しい技術を適用しているため、整備期間中に様々なトラブルがありましたが、打ち上げに係る多くの人々の協力により、確実に一つずつ乗り越えてきました。現在はロケット本体だけでなくHTVの全機組上げが完了しており、衛星フェアリング結合及びレイトアクセスを無事に完了すれば打ち上げ本番を残すのみとなります。
多くの人の思いが詰まったH-IIBロケットと「こうのとり」(HTV)を無事に打ち上げ、役目を果たせることを楽しみに、残りの作業を頑張っていきます!!
写真右:筆者(足立 寛和)、写真左:同室(道上 啓亮)
[2012年7月9日 更新]
谷山 孝二 / 宇宙輸送ミッション本部 射場技術開発室 主任開発員(打上隊設備班係主任)

[2012年7月6日 更新]
白石 紀子 / H-IIBプロジェクトチーム(プロジェクト管理係/発射指揮者)

3号機では新しくなったアビオニクス機器が搭載されます。H-IIBロケットプロジェクトチームの中でアビオニクスも担当している私は、新しく開発された機器がシステムの中に組み込まれてきちんと機能するのかに視点を置いて、一つ一つの開発状況を確認しながら、インタフェースの調整をしてきました。H-IIBロケットに使われているアビオニクス機器は、H-IIAロケットの開発時、または、その前のH-IIロケットの開発時に作られたものです。H-IIBロケット試験機の開発時にはその技術を流用したため、その詳細を学ぶ機会はありませんでしたが、今回の再開発を通じて、その技術の難しさと機器を開発して安定した供給を続けているアビオニクス機器メーカの方達の努力を知りました。アビオニクスはロケットの言わば頭脳の部分。構造や推進と違って形に見えにくくても小さな誤作動が全体に響きます。些細なことも見逃さず確実な打ち上げに臨むため、今もたくさんの人達が努力しています。中身が少し変わって、2号機よりも少し賢くなったH-IIBロケット3号機をみなさんも応援してください。
3号機でも発射指揮者を担当します。今回は一緒に仕事をする三菱重工業さんの発射指揮者のメンバーが新しくなりました。H-IIAロケットで発射指揮者を経験している方達なので大きな信頼を寄せると共にH-IIBロケットで3回目となる自分の経験を活かし、協力し合って良い仕事ができるよう頑張ります。開発や製造に携わった人達の思いを乗せたH-IIBロケット3号機を、みんなと力を合わせて宇宙に送り出せる日を今から楽しみにしています。
[2012年7月5日 更新]
佐藤 寿晃 / H-IIBプロジェクトチーム ファンクションマネージャ(打ち上執行主任代理、ロケット班長)

3号機ではロケットの頭脳にあたる搭載電子機器が一新されています。ロケットは打ち上げてしまったらあとは見守るしかないので、新しい機器に交換する際には、念には念を入れて機能などに問題がないかを確認しておく必要があります。このため、3号機では通常1ヶ月くらい前からの種子島での整備作業を3月から始め、じっくりと確認を行ってきています。ロケットも早くから射座の上に立てられ、後から来たH-IIAロケット21号機を見送っており、早く宇宙へ飛び立ちたいと思っているかもしれませんが、最後まで「慌てず、急がず、正確に!」の精神でいきたいと思います。
3号機が無事に飛行すれば、システムとしては完成の領域に達し、H-IIBも巣立ちの時期を迎えます。今後は「こうのとり」の打ち上げのみならず、H-IIAと合わせた日本の主力ロケットシリーズとして、大型の衛星の打ち上げにも展開されていくことが期待されます。きっちりと巣立っていけるよう最後まで頑張りますので、皆さま打ち上げ成功に向けて応援よろしくお願いします!
[2012年7月3日 更新]