第18号科学衛星(PLANET-B)「のぞみ」の火星周回軌道への
投入失敗の原因究明について
平成16年3月8日
宇宙航空研究開発機構
本日開催された宇宙開発委員会調査部会において、下記のとおり報告をいたしました。
概要説明
- 第18号科学衛星(PLANET-B)「のぞみ」のミッション概要及び経緯 資料番号:調査8−4−2
- 第18号科学衛星(PLANET-B)「のぞみ」の概要 資料番号:調査8−4−3 (PDF 496KB)
- 第18号科学衛星(PLANET-B)「のぞみ」の打上げからミッション終了までの経緯 資料番号:調査8−4−4 (PDF 1.8MB)
燃料供給系機能不具合(1998年12月20日)
- 不具合発生状況
- 現象把握
- 原因究明
- 今後の対策
通信系・熱制御系機能不具合(2002年4月25日)
- 不具合発生状況
- 現象把握
- 原因究明
- 今後の対策
[参考]
- 参考8-4 第18号科学衛星(PLANET-B)「のぞみ」に関する成果集 (PDF 424KB)
|
|
第18号科学衛星(PLANET−B)「のぞみ」のミッション概要及び経緯
1. 概要
火星探査機「のぞみ」(PLANET-B)は、2003年12月14日に火星周回軌道投入を予定していたが、搭載系の不具合により投入を果たすことができなかった。運用段階から「対策チーム」がJAXAの中につくられ、探査機の運用および不具合の原因究明に関して検討が行われてきた。次の2つの不具合に関する原因究明結果について述べていく。
- 火星周回軌道投入が当初予定より4年ほど遅れる原因となった、燃料供給系の不具合。これは1998年12月20日(地球軌道離脱時)に発生したものである。
- 火星周回軌道投入を不可能にした直接の原因となった、搭載電気系の不具合。これは2002年4月25日(惑星間空間巡航時)に発生したものである。
2. 「のぞみ」の経緯
打ち上げ(1998.7.4)宇宙科学研究所・鹿児島宇宙空間観測所(鹿児島県内之浦町)より、M-V-3号機にて打ち上げられた。
推進系トラブル(1998.12.20 地球軌道離脱時)
地球重力圏離脱時に燃料供給系に不具合が発生し、十分な推進力が発生できなかった。
- [原因]
酸化剤タンク下流にあるバルブが開ききらなかった為、十分な推力が発生出来ず結果として燃料を使い過ぎた。問題となったバルブは、米国の火星探査機マーズオブザーバーの失敗を受け、燃料・酸化剤の蒸気が上流に逆流しないように安全の為に追加した物である。 - [対処]
地球離脱オペレーション後の残燃料から、蒸気の逆流防止の為に上記バルブを閉じる必要が無い事が判明した。この為、1998年12月21日の可視運用中に上記バルブを開とし、その後は操作しない事とした。 - [影響]
当初予定した「1999年10月中旬の火星周回軌道投入」が不可能となった。しかし、2回の地球スイングバイを経ることで、4年遅れの2003年12月末〜2004年1月初頭に火星周回軌道投入が可能である軌道計画を発見し、計画変更を行った。変更後の軌道計画を図3-2に示す。
電気系トラブル(2002.4.25 惑星間空間にて)
通信系・熱制御系機能に不具合が発生し、最低限の通信しか機能せず、かつ、ヒーター制御ができない状態となった。
- [原因]
通信系および熱制御系の機能に影響を与える共通系電源が、ONできない状況に陥ったためである。原因としては、この電源が電力を供給している下流コンポーネントの一部に短絡モードが発生した可能性が最も高い。2002年4月22日の太陽フレアに伴って「のぞみ」として過去最大量の高エネルギー粒子に晒された事に関連している可能性がある。 - [影響]
共通系電源がオン出来なくなった為、データが送信できず、かつ熱制御回路が動作しない状況となった。 (2002年4月26日の時点では燃料が凍結していた事が4月末に判明。火星周回軌道への投入には主エンジンの噴射が必要だが、これには熱制御回路によるヒーター制御が不可欠である。) - [対処]
(1) 2002年5月3日: 観測機器をONして探査機温度の上昇を図った。熱解析の結果、9月ごろには衛星内部のタンク及び配管内の燃料が自然解凍することが判明。(2.3Nのスラスターは使用可能。但しメインスラスタへの配管の解凍にはヒーター制御回路の復活が必要) (2) 2002年5月15日: 事故が「短絡」に起因することを想定し、この箇所に電流を流す事で「焼ききる」復旧作業を試行したが、この作業中に送信電波がオフ状態となった。(コマンド配信部ICへの電源の不完全な立ち上がりによって不正コマンドが生じ、X帯送信機のリレーが誤動作したと考えられる。地上試験の結果、確率的に復旧しうる可能性が示唆された。) (3) 2002年7月: トラブルシュートの結果に基づき2ヶ月間通信系機能の復旧を試みた結果、最低限の通信が確保できる程度に通信系機能が復旧した。2003年6月に予定された地球スイングバイ・火星到達軌道への投入までは「復旧作業」を中断することと決定した。 (4) 2002年8月: 凍結していた燃料が解凍した。(「探査機−太陽間距離の短縮」および「観測機器の電源投入」によって探査機温度が上昇した事による。以後、姿勢を適切に保ち燃料凍結を防止。) (5) 2003年6月: 最低限の通信機能を使って地球スイングバイを実施、火星到達軌道への投入に成功した。 (6) 2003年7月: 通信系・熱制御系機能の回復を目指して、「短絡モードの不具合箇所に電流を流す事で焼ききる」復旧作業を再開した。その過程において、再び送信電波がオフ状態となり、最低限の通信も確保できない状態になった。 (7) 2003年12月まで: 復旧作業、具体的には共通電源を連続ONするコマンド [総計:約1億3千万回] を実施した。その後、搭載計算機の誤動作の可能性を排除するため、搭載ROM書き換えによる共通電源連続ONの実施。さらに、搭載ROMを初期値に戻して連続ON運用を実施した。 (9) 2003年12月9日: 復旧に至らなかったため、火星周回軌道への投入を断念し、衝突回避を確実にする*1為の軌道変更を9日夜に実施した。変更後の火星への衝突確率は約0.1%となった。
*1 火星における生命探査への影響を避けるために、宇宙科学関連の研究者組織である国際宇宙空間研究委員会(COSPAR)から 「特別な処置を施していない火星周回衛星に関しては打上げ後20年以内に火星に落ちる確率を1%以下にするという方針」 (COSPAR planetary protection policy)がでている。研究者として可能な限りその方針を遵守する道義的責任がある為、この措置を実施した。(10) 2003年12月14日: 火星表面から約1000kmのところを通過。12月16日には火星の重力圏を脱出したと思われる。
3. 「のぞみ」の概要
図3-1に「のぞみ」の外観図、図3-2に軌道図、図3-3に「のぞみ」ミッションの概要を示す。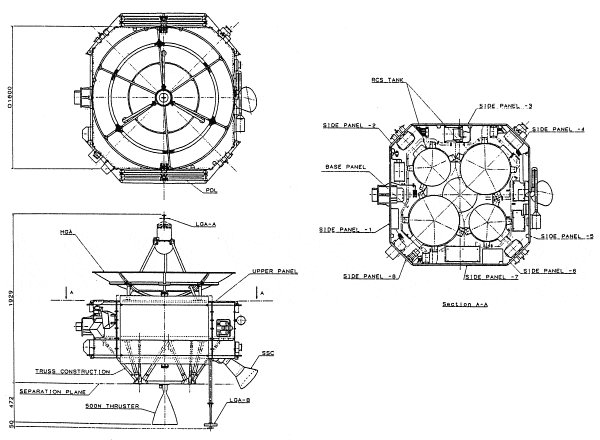
図3-1 「のぞみ」の外観図
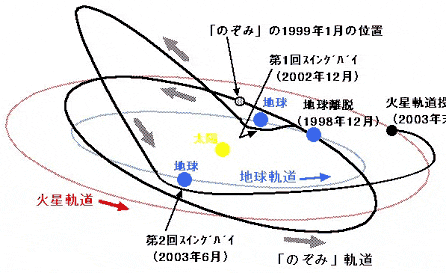
図3-2 火星探査機「のぞみ」の軌道

図3-3 火星探査機「のぞみ」の概要 *画像をクリックすると拡大画像が見られます。
宇宙航空研究開発機構 広報部
TEL:03-6266-6413〜6417
FAX:03-6266-6910