風計測ライダの飛行実験の開始について
航空宇宙技術研究所
航空機が突然の乱気流で揺れ、乗客・乗員が重軽傷を負う航空機事故が頻繁に発生しています。特に高々度における乱気流の存在は予測が難しいことから、航空会社ではシートベルトの常時着用を促進することで対応しているのが現状です。
独立行政法人航空宇宙技術研究所(NAL)では、こうした航空機事故を防ぐために、平成12年度から、レーザー光を用いて航空機の前方に存在する乱気流を検知する装置(風計測ライダ)の研究開発を進めています。この風計測ライダは、航空機が飛行中に前方の気流をリアルタイムに観測し、コックピット内の計器に表示できる装置で、実用化すれば、乱気流を避けて飛行したり、乗客等にシートベルト着用を指示するなどして事故を未然に防止することができ、飛行の安全性をより一層向上させることができます。
この風計測ライダの試験装置を開発し、本年9月、NALが所有する小型飛行機に搭載して3回の飛行実験を行い、航空機の前方約1キロメートルの気流が計測できることを確認しました。同様の実験は米国でも行われていますが、大型の装置をボーイング737型機に搭載して行ったものです。小型軽量化された装置を小型飛行機に搭載して実験を行った例は世界にもありません。従来は、小型化が難しく、それが実用化の障害になっていました。今回、小型化に成功したことにより実用化への目途が立ったと考えています。
今後は、新たに前方10キロメートル以上(乱気流を回避できる距離)の気流を観測できる装置を製作するとともにパイロットに対する警告表示方式に関する研究も進め、早期の実用化を目指した技術開発を進めて参ります。
なお、今回試作した風計測ライダは、眼球に対する影響が少ない波長のレーザー光を用いることで非常に高い安全性を備えています。新たに開発する装置もレーザーの出力を高くしても波長を変更せずに、充分な安全性を確保していきます。
風計測ライダについて
■風計測ライダの原理
風計測ライダとは、図1のように飛行中の機体から前方の大気中にレーザー光を放射し、大気中に浮遊するエアロゾル1)によるレーザー散乱光を機体側で受信して、ドップラー効果2)に基づき風速及び風向きを求める装置(計測可能距離:150m以上)である。
■風計測ライダ試験装置
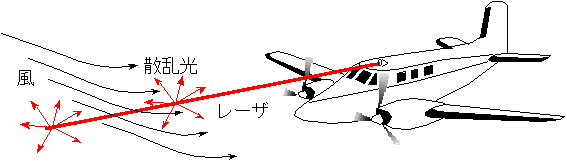
図1 風計測ライダ概念図
|
風計測ライダ試験装置は、本体部、送受信望遠鏡、計算機で構成されている。試験装置全体の外観を図2に示す。本体部はレーザ発振器、ライダ駆動部、光検出器からなり、送受信望遠鏡はフレキシブルな光ファイバで本体部に接続される。計算機は本体部の制御と信号処理用のための汎用計算機である。計算機の実際に飛行実験で得られた風速の計測結果の例を図3に示す。 |
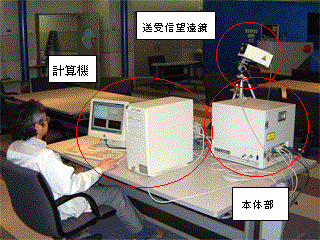 図2 風計測ライダ試験装置 |
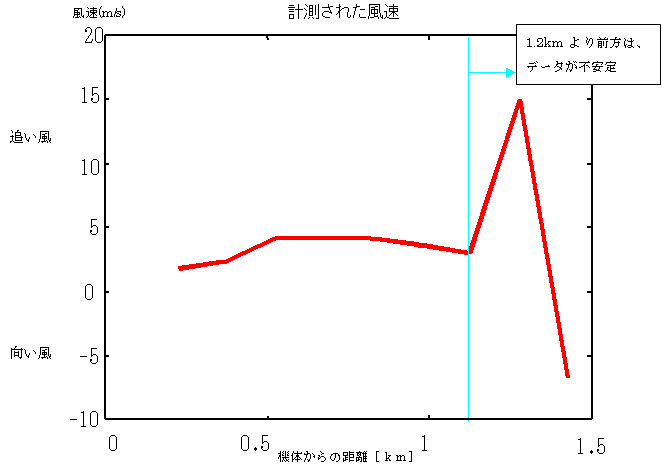
図3 風速の計測結果の例
| 本体部外寸 | 450×400×430 mm |
|---|---|
| 本体部重量 | 46 kg |
| 消費電力 | 420 W |
| レーザ波長 | 1.54μm |
| レーザ出力 | 平均1 W |
| パルス繰返し数 | 50 kHz |
| 送受信望遠鏡口径 | 60 mm |
| 送受信望遠鏡重量 | 5 kg |
■飛行実験
風計測ライダ試験装置は、当所所有の実験用航空機(ビーチクラフト式65型)に搭載した。本体および計算機はキャビン内のラック上に配置し、送受信望遠鏡も同じラックに上向きに取り付けた。レーザー光は胴体上部で反射鏡により前方に向けられる。機体に装置を取り付けた状態の外観を図4に示す。基本的な機能を確認する飛行実験は9月18日午前午後、9月20日午前の計3回行われた。図3の風速の計測結果の例では1.2kmまでのデータは比較的安定しており、良好に計測できたものと考えられる。
なお、最大測定距離に関しては天候の影響を強く受けるため、今後も継続して飛行実験を行い統計的なデータを取得する予定である。
■今後の予定
今後は、新たに前方10km以上(回避飛行が可能な距離)の気流を観測できる装置を製作するとともにパイロットに対する警告表示方式に関する研究も進め、早期の実用化を目指した技術開発を進めていく。
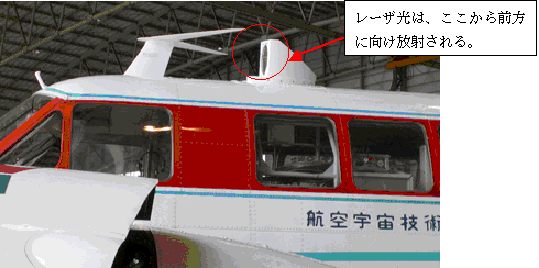
図4 搭載状態の外観
- 1)エアロゾル
- 大気中に浮遊する水滴や塵などの微小物体。
- 2)ドップラー効果
- 音波や光波などが、相対的に移動する物体から発せられたり反射したりしたときに、その波長が移動速度に比例して変化する現象。