衛星通信・放送分野ロードマップ
平成15年4月16日
宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
技術試験衛星VIII型(2004年度打上げ)や超高速インターネット衛星(2005年度打上げ)並びに準天頂衛星(2008年度頃打上げ)の次のミッション(実現時期:2010年頃)をターゲットに、さらに将来(今後15年程度)へ向けての目標と道筋を整理。
1.現状分析
- 現在、我が国の民間が保有する静止通信・放送衛星は16機。これらの衛星は現在外国からの調達。
- 高度情報化社会における、ユビキタス性(いつでも、どこでも、誰とでも)の要求は益々高まりつつある。
- 地上通信の目覚ましい発展により、衛星通信事業は衛星の特色(広域性・同報性・耐災害性)を活かした利用開拓が急務。
- 電波の利用が進むにつれ、周波数の獲得は、地上用/宇宙用、また、各国間での競争が激化し、事業の成否、システムの成立性に大きく影響。
2.今後の方向性
- 安全・安心な社会構築への貢献
衛星による通信・放送機能は、防災危機管理、地球環境モニタリング等、国レベルで構築するべき社会システムを支えるインフラとしての役割が増大する。様々な社会システムと融合した利用ミッションとして、特に安全・安心な社会構築への貢献が求められる。 - 国民生活の質の向上への貢献
高度情報化社会に対応し、情報格差の解消や、通信システムの信頼性、利便性の向上等、豊かな国民生活の構築への貢献が求められる。 - 社会経済への貢献
通信・放送分野は、これまで宇宙活動の中でも最も産業と深いかかわりを有してきた。今後、民間が実施するにはリスクの高い先端的技術の研究開発(利用開発を含む)を実施すること、タイムリーな宇宙実証を一層取り入れることで、研究開発から実用までの期間短縮に努め、国際競争力を確保する等、社会経済への貢献に努めることが重要。
3.新機関の役割と研究開発の進め方
新機関は、関係研究開発機関、産業界との連携をはかりつつ、国、社会が必要とする通信・放送分野のシステム(インフラ)等について、積極的に提案し、その構築に貢献する。この為に、民間では実施が困難な先端的な研究開発について、関係研究開発機関と連携・協力し推進するとともに、軌道上実証を実施する。○ 宇宙開発利用活動を支える宇宙通信インフラによる安全・安心な社会構築等へ貢献。
- 地球観測衛星データの効率的な送信や宇宙ステーション運用支援等、大容量・リアルタイム性を求められるデータ中継技術を光通信技術等の活用による高度化・軌道上実証。
○ 産業界等との連携をはかりつつ、高度情報化社会における、情報格差の解消や通信システムとしての信頼性、利便性の向上に資する先端的な衛星通信技術(利用開発を含む)の研究開発を行い、国民生活の質の向上等へ貢献。
- 新周波数帯域の開拓、アンテナ技術、搭載通信機器技術等の発展に応じた技術開発・軌道上実証。
○ 上記に対応した衛星システムを、IT等を導入し(開発期間短縮、信頼性向上等を目指した開発手法の改善・発展を含む)、機動的かつ柔軟性のあるシステム(例えば、フォーメーションフライト、コンステレーションフライト技術等)に関する研究開発の実施。
参考資料
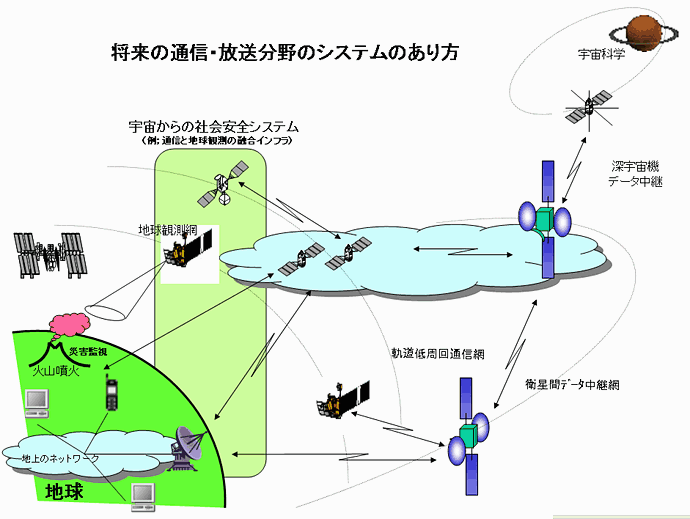
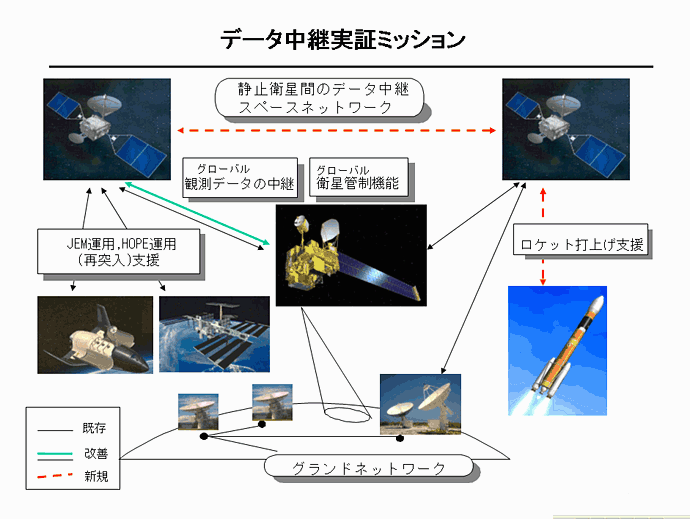
データ中継実証ミッション(-開発推進方策ー)
| フェーズ1 (〜2007) | フェーズ2 (2008目標〜2012) | フェーズ3 (2013〜2022) |
||
|---|---|---|---|---|
| 達 成 す べ き 目 標 値 | 通信速度の向上 | 〜6Mbps(S帯) 〜240Mbps(Ka帯) |
S帯,Ka帯については、 ほぼ左記同等 |
〜2Gpbs(光含む) S帯,Ka帯実運用 |
| 光通信の限定的な実験(*2) | ||||
| 利便性向上 (利用宇宙機の拡大) |
打ち上げ時のロケットのTLM(*1) データの中継は不可 |
ロケットTLMデータ中継実験(*3) | 左記に加えて、 |
|
| ユーザー機用フェーズドアレイシステム実証試験(*4) |
||||
| データ中継カバレッジの拡大 | グローバルな中継は不可 | 限定期間2機運用(カバレッジ拡大) | 同左システムの実運用 | |
| 光通信による静止衛星間通信実験 (*2) |
||||
| 備考 | (参考:伝送速度比較) 携帯電話(FOMA):384Kbps ISDN:64〜128Kbps BSデジタルハイビジョン:22Mbps/ch |
*1: TLM:テレメターデータ *2:光通信ミッション計画参照(中小型衛星で実証も検討) また、光・ミリ波等のトレードオフ検討が必要 *3:ロケットTLMデータ中継機能は140Kbps 程度の速度を想定、 小型衛星での事前実験も検討、コマンドデータの中継の可能性検討等が必要 *4:ユーザー機用無振動フェーズドアレイシステムについて、 中小型衛星での実証も検討 |
||
| 米国TDRSとほぼ同等の性能 | 米国TDRSよりも機能アップ |
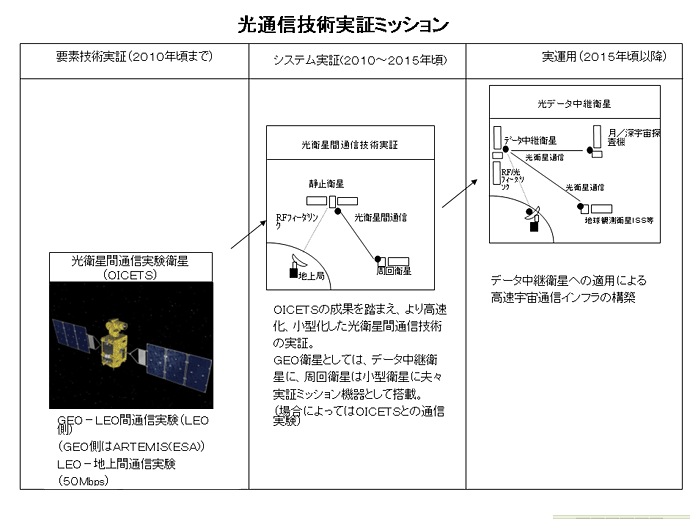
光通信技術実証ミッション (ー 開発推進方策 ー)
| フェーズ | フェーズ1(2002〜2007) OICETS | フェーズ2(2008〜2012) | フェーズ3(2013〜2022) |
|---|---|---|---|
| 行動計画/ 目標 |
・高精度捕捉追尾技術の習得
・高精度衛星搭載光学技術 ・GEO-LEO双方向光通信
・50 Mbps |
小型・軽量化 捕捉追尾方式の高度化・最適化
回線容量の向上 |
同左(より軽量化)
さまざまなミッションに |
|
|