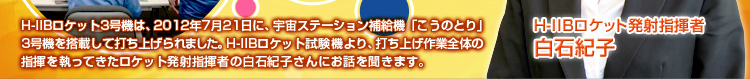Q. ロケット発射指揮者とはどのようなお仕事ですか?

発射管制室で仕事中の白石さん(中央)
ロケット発射指揮者(LCDR: Launch Conductor)の仕事は、打ち上げ4日前から行われる発射整備作業の指揮を執ることです。発射整備作業とは、組み立てられたロケットの最終点検の後、ロケットを発射台へ移動して推進薬を充填し、打ち上げを行うことです。これらの作業は多くの作業員の連携が必要となりますので、LCDRは作業がスムーズに進むよう全体を把握し、作業の開始指示や終了の確認を行います。また、打ち上げ270秒前から自動カウントダウンが始まりますが、その開始ボタンを押すのもLCDRの仕事です。さらに、打ち上げ直前に何か異常があった場合に、緊急停止ボタンを押すのも私たちの役目です。 Q. 同時に行われるさまざまな発射整備作業をどのように把握するのですか? LCDRは、射点から約500m離れた地点の地下12mにある発射管制室の中から、アシスタント3名と交替シフトを組んで作業全体を見渡します。並行して行われる多くの作業の進行状況はOIS(Operational Intercommunication System:構内通話運用システム)で知らされますが、ロケット、設備、射場系など作業部門ごとに分かれていて、その数は10チャンネル前後あります。10チャンネルの通話を同時に聞くと共に、大型モニタに写し出される射点の各地点の映像を見て、全体の進行状況を把握し、作業の進行度合いを調整します。
Q. 打ち上げまでのLCDRの具体的な作業を教えてください。

ドライラン実施中の発射管制室のようす
発射整備作業はY-3からY-0に分かれています。Y-3が打ち上げ4日前の作業で、Y-0は打ち上げ前日と当日の2日間に渡ります。このY-3作業の前日に行われるのが「ドライラン」です。これは、打ち上げ当日と同じオペレーションを行うリハーサルのことで、機体や通信回線の不具合などさまざまなトラブルが、これでもかというくらい次々と振りかかってきます。宇宙ステーション補給機「こうのとり」の場合は、国際宇宙ステーションとドッキングする関係で定刻に打ち上げなければならないため、打ち上げ時刻を変えられません。ですから、打ち上げ時刻が迫るなかでそのトラブルの性質を把握し、打ち上げに影響があるかないか、また、トラブルの対処が決められた時間内で終えられるかどうか、瞬時の判断が求められます。
それでは発射作業の内容を具体的にお話しましょう。Y-3(打ち上げ4日前)の主な作業は、推進系・電気系のクローズアップをして、打ち上げができるよう最終確認を行うことです。組み立てが終わったばかりのロケットには、点検用のケーブルがつながっていたり、足場が組んであったりしますが、それらを全部撤去して、打ち上げができる状態にすることを「クローズアウト」と言います。
Y-2(打ち上げ3日前)には、火工品の結線や、姿勢制御用ガスジェット装置へのヒトラジン充填など、危険作業が組まれています。火工品結線とは、火工品の導爆線に、着火の信号を伝える電気系のコネクターを取り付ける作業です。この2つの作業はどちらも他の作業との並行作業を禁止し、専門の作業員だけが防護服を着て作業します。このような危険作業を行う時は、機体へのアクセス制限が出てしまうため、ロケットの最終確認が済んでからでないと始められません。そういう意味で、この作業着手のタイミングは重要な判断になるわけです。それを最終的に決めるのは打ち上げ実施責任者ですが、その判断をするためにロケットの状況を伝えることもLCDRの仕事です。
Y-1(打ち上げ2日前)には、電気系系統の最終確認作業であるRFシステム点検から始まり、推進系の最終クローズアウト作業、機体アーミング(最終結線作業)など機体を射点に移動できる状態にする作業が行われます。また、並行して射点設備側の準備作業も実施されます。 Q. 次は Y-0。いよいよ打ち上げ当日を迎えますね。 Y-0の作業は打ち上げの約1日前から始まり、フェアリング内に搭載されている衛星への最終アクセスドアを閉めるところからスタートします。その後、機体を射点まで運ぶ機体移動の作業が行われ、打ち上げの約9時間半前には、射点周辺の半径3km以内が総員退避となります。それまではアシスタントがメインで指揮を執り、私はその様子を見守っていますが、総員退避以降は私がメインで指揮を執ります。一番気合いが入るところですね。そして、打ち上げに向けて推進薬の充填や電気系の点検など準備を整えていき、いよいよ打ち上げを迎えます。
実は、今回のH-IIBロケット3号機の打ち上げの日は天候が悪く、射場がある種子島の北部で雷が鳴ったり、雨雲が西から移動してきたりと、打ち上げ予定時刻に打ち上げられるかどうか不安な要素がありました。でも、「みんなの思いの詰まったロケットをなんとか定刻に打ち上げたい」と強く願いながら作業を進め、その気持ちが通じたのか、運良く発射場の天気がもちこたえました。天候の心配がある中、無事に予定通り打ち上げることができたときは、ほっとしました。
Q. 打ち上げ当日の緊迫した雰囲気の中で、特に心がけていることはありますか?

発射台へ移動されるH-IIBロケット
打ち上げに向けて働いているたくさんの人達の力を信じて、頼ることです。同時にいくつもの問題が起きたり、その解決にデータの確認が必要だったりと、打ち上げ当日はやるべきことがたくさんあります。そんな時、「みんなで打ち上げに向かって進んでいる」という一体感を感じると、自ずと各系統が連携して助け合って、効率よく問題を解決していく方法を考えられるんです。その一体感が大事だと思いますし、みんなの気持ちが一つになれるような雰囲気づくりを普段から心がけるようにしました。
例えば、些細なことにも耳を傾けるようにしたり、できるだけたくさんの人と顔見知りになり、良好なコミュニケーションが図れるよう努めました。現場に行って顔を合わせて話していると、最近どうですか?という話から始まって、時には現場の裏話を聞けることもあったりして(笑)。やはり、何か問題が起きたときに、みんなが情報を出し合える人間関係を普段から作っておくことって大事ですよね。それに、OIS(構内通話運用システム)で声を聞いたときに、話している人の顔が分かって聞いているのと知らないで聞いているのとでは、印象が全然違うんです。
また、発射管制室には150人近い人が作業をしていますが、私は部屋の空気を読むよう心がけていました。例えば、何か異常があるとざわつくなど、OISから入ってくる情報よりも前に、部屋の雰囲気から感じ取れるものがあるんです。そこはある意味、感覚に頼って仕事をしているのかもしれません。 Q. 無事にロケットが打ち上がると、LCDRの仕事は一段落ですか? はい。ただ、打ち上げ後にフライトデータを評価する仕事が待っていますので、ゆっくり休んでいる暇はありません。私はH-IIBプロジェクトチームの一員でもありますので、ロケットが飛んだ後も気が抜けません。打ち上げの成功を喜ぶだけでなく、フライト結果から不安要素をきちんと見つけ出し、必要に応じて追加の検討や解析をして、次のロケットをより確実でより安全に打ち上げられるようにすることも大切な仕事です。