 NASA[米国航空宇宙局]の米国内の教育機関を巻き込んだ、長年に亘る宇宙教育は国民に浸透している。周知のようにブッシュ大統領の発表した火星有人飛行などのように、宇宙が政治に使われるぐらい、国民の宇宙に関する関心は深い。多くの資料、教材が子供たちの学年ごとに開発されている: 観測ロケットの機器搭載空間の一部の高校生への提供、深宇宙用アンテナの高校生への貸与(アンテナ駆動操作と、受信データの解析など)。これらはごく一例であり、米国の宇宙教育を完全に網羅する事は不可能なほど多様である。
NASA[米国航空宇宙局]の米国内の教育機関を巻き込んだ、長年に亘る宇宙教育は国民に浸透している。周知のようにブッシュ大統領の発表した火星有人飛行などのように、宇宙が政治に使われるぐらい、国民の宇宙に関する関心は深い。多くの資料、教材が子供たちの学年ごとに開発されている: 観測ロケットの機器搭載空間の一部の高校生への提供、深宇宙用アンテナの高校生への貸与(アンテナ駆動操作と、受信データの解析など)。これらはごく一例であり、米国の宇宙教育を完全に網羅する事は不可能なほど多様である。
ESA(ヨーロッパ宇宙機関)は2000年全宇宙予算の1%を教育に計上することを理事会で承認した。スウェーデンのエスレンジ,ノルウェーのアンドヤロケット基地が教育実践の場としてESAの費用により提供されている。ここ数年のESAの課題は、全ヨーロッパ教師へESA教育プログラムの存在を周知させることにある。
画像右上:
NASAの教育ホームページ(http://education.nasa.gov/)
画像右下:
ESAの教育ホームページ(http://www.esa.int/esaED/index.html)
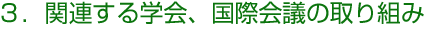
学会、国際シンポジウムで教育セッションが開かれるようになった。たとえば昨年スイスで開かれたESA主催の小型ロケットと気球のシンポジウムでは、4日のうち1日が宇宙教育に割かれ、本年7月にパリで開かれたコスパー総会(Committee on Space Research)でも1日半の教育セッションがもたれた。国内の学会でも天文学会をはじめ、いくつかの学会で教育セッションが持たれている。宇宙教育の必要性は世界的な理科離れの傾向がある中で急激に認識されつつある。

