 |
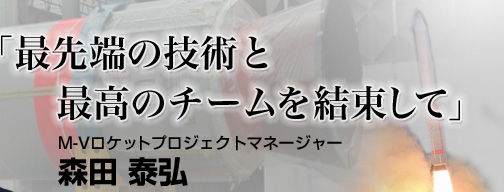 |
 |
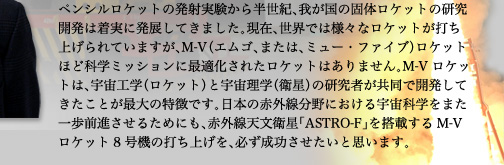 |
M-Vロケットは多段式の固体ロケットとしては世界最大級、かつ、最高性能のロケットです。惑星間軌道にまで探査機を打ち上げられる単独の固体ロケットは、世界でも他に例をみません。固体ロケットの最大の利点として、いつでも発射できる性質、すなわち、即射性があります。これは打ち上げウィンドウ(打ち上げ可能な時期)が短い科学衛星、特に惑星ミッションに適しています。例えば、火星探査の場合、火星も地球も異なる周期で公転しているため、うまく軌道にのるように打ち上げるチャンスは2年に1度くらい、しかも1週間という短いウィンドウしかないような場合も珍しくありません。さらに、打ち上げ可能な時間帯も数十秒だったりします。2003年に打ち上げた小惑星探査機「はやぶさ」の場合は30秒間しかありませんでした。液体ロケットの場合、燃料を入れたまま長期保存することが難しいため、何かの不具合で発射の直前に打ち上げが延期になった場合には燃料を入れ直す必要があります。そうすると数日間打ち上げることができません。一方、固体ロケットは燃料を入れたまま保管することができますので、万が一打ち上げが中止になったとしてもすぐさま翌日に打ち上げるという芸当ができるのです。一度チャンスを逃すと次のチャンスは数年後という科学ミッションにとって、即射性はとても重要です。 諸外国の例を見ると、固体ロケットは冷戦時代の名残りのミサイルを転用して打ち上げている場合が多く、探査機あるいは衛星の打ち上げを目的として専用に開発されているわけではないため、十分な性能を発揮していません。米国のタイタン・ロケットのサブブースタや、スペースシャトルの固体ロケット・ブースタのように、補助的な推進機関として利用されることはあっても、単独の多段式固体ロケットとして惑星探査にまで領域を広げて活躍しているのはM-Vロケットだけです。 これは、固体ロケットの誘導制御が難しいこともその原因のひとつでしょう。液体ロケットの場合には飛行中に推力の調節ができますが、固体ロケットは一度火をつけると途中で火を消したり再点火したりといった操作が自由にできません。自動車に例えると、液体ロケットはアクセルをたくさん踏むと推力が増し、途中でエンジンを止めることもできますが、固体ロケットは、アクセルを全開して燃料がなくなるまで突っ走るのと同じで、途中で推力を変えたり推力を止めることはできません。一旦火をつけたら燃料が燃え尽きるまで飛んでしまうのです。目標の軌道に到達できないと困るため、通常、燃料は少し多めに搭載しています。ですから、何もしないと目標の軌道に対して飛びすぎてしまいます。そうならないように途中でエネルギーを調整して、目標の軌道に到達するようロケットを誘導しなければなりません。しかも、科学衛星には観測のためにいつも特別な要求があって、目標の軌道は打ち上げごとに大きく異なります。ロケットのエネルギーがあらかじめ決まっているという制約条件の中で、科学衛星の厳しい要求に柔軟に対応する技術はとても難しいのです 赤外線望遠鏡を搭載した「ASTRO-F」の打ち上げでは、地球を南北にまわる太陽同期軌道で、しかも昼と夜の境界線上を飛ぶ特殊な軌道に誘導しなければならず、高度なテクニックが求められます。赤外線は温度が高いものから自然と出てきてしまうため、望遠鏡を太陽や地球から守らなければなりません。このため、「ASTRO-F」は昼と夜の境界線上をまわり、常に太陽を横に、地球を望遠鏡と反対側に見るような軌道をとるのです。 このように誘導の難しい固体ロケットを用いて、全段固体で惑星探査までやり遂げる日本のM-Vロケットは、世界でも最高性能の固体ロケットといえます。 |
|
||||
|
|||||
